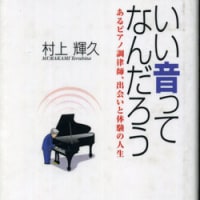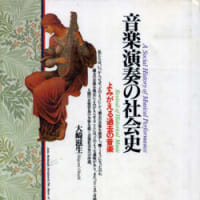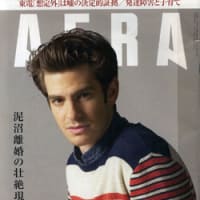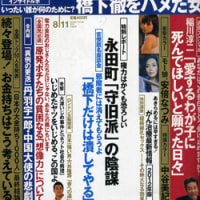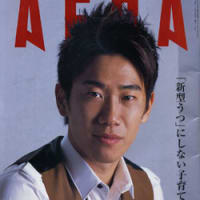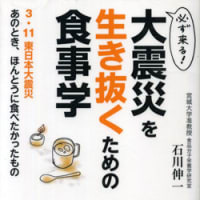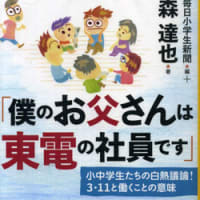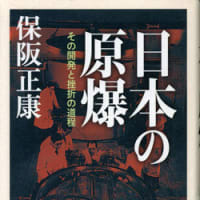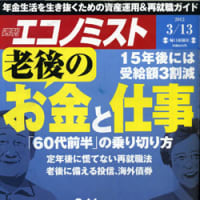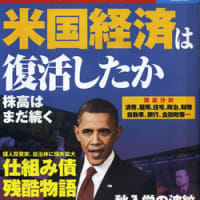『いまこそ私は原発に反対します。』
日本ペンクラブ・編/平凡社2012年
かつて川端康成が反核をされていて、ペンクラブを尊敬していた人たちもいます。
ところが、その後は人権さえ捨てたという人もいましたが、どうなんでしょうね?
「いまこそ」って遅すぎませんか? その反省もしていただきたい。
でも、ずっと反核のリーダーをしているような人たちが、意味あることも書かれています。
ペンクラブの人なんでしょうかね???

「【戯曲】老人と蛙--情報演劇一幕」中村敦夫・作。
いくいくは……と蛙。 下「」引用。
「老人「ただちに健康に影響はない……」
蛙「(怒って)そりゃ政府の答弁じゃねえか! ただちに影響はないってのは、行く行くはひどいことになるってことだろう?」
老人「その通りじゃ。当局は一切何も言わないが、理由の一つは、将来の賠償が恐いからだ。-略-」」
「老人と牛」吉岡忍・作。
「イラクと東京で掲げる「NO NUKES」」雨宮処凛。下「」引用。
「私が初めて「「NO NUKES」(反核・反原子力)という言葉を掲げてデモをしたのは、3.11ら遡ること八年、二○○三年のことだ。場所は、イラク・バクダッド。」
 index
index
国家=死の商人「フクシマで、あなたは何もみていない。」磯崎新。下「」引用。
「何しろ原発をこりずに輸出しようとしている。この三十年程で、国家は資本に乗っとられたといわれてきました。死の商人に姿をやつしたのですね。外交のきまり文句が国益にかなうことという基準だから、この人たちは首相や大臣の肩書きの名刺のうらを「日本K.K.」の手代や番頭に刷りかえてもらいたい。」
 index
index
「明日の神話」と悪意のある使徒岡本太郎。下「」引用。
「昨年が生誕百年だった岡本太郎はヒロシマを核爆発の十八年後に訪れて、『瞬間』という文章を書きました。(一九六三年八月三日・四日、朝日新聞)これは「原子雲を見た広島の人の素朴な言葉--……あの赤とも黄ともいえぬ綺麗な雲は何ともいえん綺麗でしたよ。」(蜂谷道彦『ヒロシマ日記』)の引用からはじまっています。そして、
「誇らしい、猛烈なエネルギーの爆発。夢幻のような美しさ。だがその時、逆に、同じ力でその直下に、不幸と屈辱が真黒くえぐられた。」
と自らの文章をはじめます。日常が回復し、平和記念公園にある慰霊碑に観光バスが訪れる有様をみて、「平和」という言葉にひっかかり、「何というニブサだろう。ナンセンスだ。明らかに筋がすりかわっている」と怒りはじめる。
数年後に太郎はメキシコに呼ばれ、いま渋谷駅に展示されている大壁画「明日の神話」(一九六九年)を制作します。「過去の事件としてではなく、純粋に、激しく、あの瞬間はわれわれの中に爆発しつづけている。」と記してあったものをそのまんま壁画に誇張していると私にはみえます。壁画の中央は爆発する人体です。作者本人も骸骨になるまでバラバラになったのでしょう。斜線の飛び散るむこう側に放射能を浴びてあえぐ群衆やビキニの灰をかぶった福竜丸らしい船も描かれているので、この壁画はヒロシマの爆発の瞬間をアレゴリカルに主題としたとみてとれます。さらに推測するならば、「芸術は爆発だ!」とその後四半世紀にわたってメディアのなかにみずからの身体を曝して演じつづけたのは、「夢幻のような美しさ」が同時に「不幸と屈辱」となったあの瞬間の惨劇を「平和」へとすりかえてしまったその後の世界のお目出度さを、悪意を抱きながら警告する使徒たろうとしたのだと私は考えます。」
 index
index
井伏と原発。下「」引用。
「事実は、短いものながら、「原発事故のこと」と「無常の風」という二つの文章を井伏は書いていて、この二つはほとんど同一の内容といってよいが、「原発事故のこと」は、『新潮』一九八六(昭和六十一)年七月号にエッセイとして書かれ、「無常の風」は、松本直治『原発死 一人息子を奪われた父親の手記』(一九七九年、潮出版社)の序文(厳密にはこの作品が『潮』に掲載された時の紹介文)として書かれたものだ。
文章にの趣意は、井伏の知人である松本直治の一人息子・勝信が北陸電力に入社し、東海村や敦賀の原発のかなり危険な現場で働き、そのためにガンに全身を蝕まれて死んだことを悼んだもので、「松本君の書いた『原発死』といふ題の手記は、謂はば息子さんへの鎮魂歌である。私は松本君に頼まれて、この手記に対し『まへがき』の意味で、怖るべき原発はこの地上から取り去つてしまはなくてはならない、といふことを書いた。『放射能』と書いて『無常の風』とルビを振りたいものだと書いた」と「原発事故のこと」には書いている。
井伏鱒二は、この松本直治の『原発死』に序文を書いただけでなく、内容や構成への助言や雑誌掲載の際の出版社との橋渡しなど、かなりの程度関与していたことが、松本宛ての書簡によって明らかになてっいる(『原発死 増補改訂版』「上田正行 新資料・松本直治宛 井伏鱒二書簡」)。-略-」
知見ではないが……。下「」引用。
「井伏鱒二の反原発の立場は、決して原子力についての科学的な知見や、社会学的な考察に基づいたものではない。それは友人の息子の死を悼むという、きわめて個人的で情緒的、人間的な感情に裏打ちされたものだ。-略-戦争や原爆投下という国家犯罪と同等である原発による事故や危険性を、本質的なところから指弾し、糾弾するものとして書かれている。
「原子力発電所は、その後ますます増設され、次々と日本列島を汚染の渦に巻き込んでゐると私思つてゐる。そのことは、かつて戦争の足音が国民の上に暗く覆ひかぶさつた暗い過去の思ひに繋がるのだが、一般にはその原発の持つ恐怖が意外にら知られてゐない。あたかも戦争への道の思ひに繋がるのだが、一版にその原発の持つ恐怖が意外に知られてゐない。あたかも戦争への道が、何も知らされてないうちにでき上つて行つたやうに--」。
この、松本直治の『原発死』のなかの一節を、井伏鱒二は共感を込めて、自分のエッセイのなかに引用している(「原発事故のこと」は、そのほとんどが、松本の著書の引用からできている。松本書の紹介にの意味で書いたものだろからだろう)。
松本直治は、息子の死をきっかけに、日本における原発の建設の政治的、社会的過程や放射能の対策を調べることによって、それが日本国民を悲惨のどん底に突き落とした戦争との類似性を持つことに気がついた。
国民の意志でも総意でもなく、密かにアメリカの原子力政策や原子力産業と結託して導入された日本の原発。それは核武装の底意を孕みながら、平和や安全というオブラートに包みこまれながら、原子力産業や原子力業界の権益を維持し、拡大させるためだけに遂行されてきたのである。戦争が、軍需産業や軍隊、軍国主義の体制そのものを守護し、その権益を拡張させるために展開されたように。-略-」
 index
index
「フクシマの子どもを護る」鶴田静。下「」引用。
「チェルノブイリ原発事故直後から今まで、日本は被曝者救護のために、各種の支援を行なってきた。それと連携しながら、これからは、フクシマ原発事故の被害にあった子どもたちの救援を行うことになる。集団移住や転地保養のために、国内外の各地であたたかい援助の手が求められることだろう。すでに国内外の種々の団体や個人が、夏休みや冬休み、休日のキャンプなどを非汚染地域で行い、子どもたちのからだと心のケアに努めている。政府が子どもたちの「集団疎開」を実施しないと、怒りに燃える多数の親たちと心を一つにして。
子どもたちから奪ってならないのは、生存権は元より、生きる希望である。被曝者としての恐怖を抱きつつ、混乱した社会で生きている子どもたが、生きる意味と可能性を見出せるように。子どもが夢や希望を持つことは、彼らの絶対的な権利である。それを奪う権利は誰にも、何者にもない。-略-」
 index
index
「大災害(カタストロィー)と表現者」広河隆一。下「」引用。
「二○一一年二月に私はチェルノブイリ取材を行った。ホットスポットについてのテレビ取材だった。日本に戻って一○日後に地震と津波と原発事故が起こった。三月一二日朝に現地に向かい、一三日朝には福島第一原発から数キロの双葉町役場前にいた。私が五○回のチェルノブイリ取材で一度も経験したことのないことが起こった。放射能測定器が振り切れたのである。放射線量は、一般人が一年間で浴びていいとされる限度以上を一時間弱の間に浴びてしまういう値だった。-略-」
「いまからでも疎開すべし」森詠。
あさのあつこの娘はいわき市に嫁ぎ、孫は8ヶ月……。
落合恵子さんの文章もありました。
「便奴(べんど)の岐路」森村誠一。
 index
index
 index
index
 目 次
目 次


日本ペンクラブ・編/平凡社2012年
かつて川端康成が反核をされていて、ペンクラブを尊敬していた人たちもいます。
ところが、その後は人権さえ捨てたという人もいましたが、どうなんでしょうね?
「いまこそ」って遅すぎませんか? その反省もしていただきたい。
でも、ずっと反核のリーダーをしているような人たちが、意味あることも書かれています。
ペンクラブの人なんでしょうかね???

「【戯曲】老人と蛙--情報演劇一幕」中村敦夫・作。
いくいくは……と蛙。 下「」引用。
「老人「ただちに健康に影響はない……」
蛙「(怒って)そりゃ政府の答弁じゃねえか! ただちに影響はないってのは、行く行くはひどいことになるってことだろう?」
老人「その通りじゃ。当局は一切何も言わないが、理由の一つは、将来の賠償が恐いからだ。-略-」」
「老人と牛」吉岡忍・作。
「イラクと東京で掲げる「NO NUKES」」雨宮処凛。下「」引用。
「私が初めて「「NO NUKES」(反核・反原子力)という言葉を掲げてデモをしたのは、3.11ら遡ること八年、二○○三年のことだ。場所は、イラク・バクダッド。」
 index
index国家=死の商人「フクシマで、あなたは何もみていない。」磯崎新。下「」引用。
「何しろ原発をこりずに輸出しようとしている。この三十年程で、国家は資本に乗っとられたといわれてきました。死の商人に姿をやつしたのですね。外交のきまり文句が国益にかなうことという基準だから、この人たちは首相や大臣の肩書きの名刺のうらを「日本K.K.」の手代や番頭に刷りかえてもらいたい。」
 index
index「明日の神話」と悪意のある使徒岡本太郎。下「」引用。
「昨年が生誕百年だった岡本太郎はヒロシマを核爆発の十八年後に訪れて、『瞬間』という文章を書きました。(一九六三年八月三日・四日、朝日新聞)これは「原子雲を見た広島の人の素朴な言葉--……あの赤とも黄ともいえぬ綺麗な雲は何ともいえん綺麗でしたよ。」(蜂谷道彦『ヒロシマ日記』)の引用からはじまっています。そして、
「誇らしい、猛烈なエネルギーの爆発。夢幻のような美しさ。だがその時、逆に、同じ力でその直下に、不幸と屈辱が真黒くえぐられた。」
と自らの文章をはじめます。日常が回復し、平和記念公園にある慰霊碑に観光バスが訪れる有様をみて、「平和」という言葉にひっかかり、「何というニブサだろう。ナンセンスだ。明らかに筋がすりかわっている」と怒りはじめる。
数年後に太郎はメキシコに呼ばれ、いま渋谷駅に展示されている大壁画「明日の神話」(一九六九年)を制作します。「過去の事件としてではなく、純粋に、激しく、あの瞬間はわれわれの中に爆発しつづけている。」と記してあったものをそのまんま壁画に誇張していると私にはみえます。壁画の中央は爆発する人体です。作者本人も骸骨になるまでバラバラになったのでしょう。斜線の飛び散るむこう側に放射能を浴びてあえぐ群衆やビキニの灰をかぶった福竜丸らしい船も描かれているので、この壁画はヒロシマの爆発の瞬間をアレゴリカルに主題としたとみてとれます。さらに推測するならば、「芸術は爆発だ!」とその後四半世紀にわたってメディアのなかにみずからの身体を曝して演じつづけたのは、「夢幻のような美しさ」が同時に「不幸と屈辱」となったあの瞬間の惨劇を「平和」へとすりかえてしまったその後の世界のお目出度さを、悪意を抱きながら警告する使徒たろうとしたのだと私は考えます。」
 index
index井伏と原発。下「」引用。
「事実は、短いものながら、「原発事故のこと」と「無常の風」という二つの文章を井伏は書いていて、この二つはほとんど同一の内容といってよいが、「原発事故のこと」は、『新潮』一九八六(昭和六十一)年七月号にエッセイとして書かれ、「無常の風」は、松本直治『原発死 一人息子を奪われた父親の手記』(一九七九年、潮出版社)の序文(厳密にはこの作品が『潮』に掲載された時の紹介文)として書かれたものだ。
文章にの趣意は、井伏の知人である松本直治の一人息子・勝信が北陸電力に入社し、東海村や敦賀の原発のかなり危険な現場で働き、そのためにガンに全身を蝕まれて死んだことを悼んだもので、「松本君の書いた『原発死』といふ題の手記は、謂はば息子さんへの鎮魂歌である。私は松本君に頼まれて、この手記に対し『まへがき』の意味で、怖るべき原発はこの地上から取り去つてしまはなくてはならない、といふことを書いた。『放射能』と書いて『無常の風』とルビを振りたいものだと書いた」と「原発事故のこと」には書いている。
井伏鱒二は、この松本直治の『原発死』に序文を書いただけでなく、内容や構成への助言や雑誌掲載の際の出版社との橋渡しなど、かなりの程度関与していたことが、松本宛ての書簡によって明らかになてっいる(『原発死 増補改訂版』「上田正行 新資料・松本直治宛 井伏鱒二書簡」)。-略-」
知見ではないが……。下「」引用。
「井伏鱒二の反原発の立場は、決して原子力についての科学的な知見や、社会学的な考察に基づいたものではない。それは友人の息子の死を悼むという、きわめて個人的で情緒的、人間的な感情に裏打ちされたものだ。-略-戦争や原爆投下という国家犯罪と同等である原発による事故や危険性を、本質的なところから指弾し、糾弾するものとして書かれている。
「原子力発電所は、その後ますます増設され、次々と日本列島を汚染の渦に巻き込んでゐると私思つてゐる。そのことは、かつて戦争の足音が国民の上に暗く覆ひかぶさつた暗い過去の思ひに繋がるのだが、一般にはその原発の持つ恐怖が意外にら知られてゐない。あたかも戦争への道の思ひに繋がるのだが、一版にその原発の持つ恐怖が意外に知られてゐない。あたかも戦争への道が、何も知らされてないうちにでき上つて行つたやうに--」。
この、松本直治の『原発死』のなかの一節を、井伏鱒二は共感を込めて、自分のエッセイのなかに引用している(「原発事故のこと」は、そのほとんどが、松本の著書の引用からできている。松本書の紹介にの意味で書いたものだろからだろう)。
松本直治は、息子の死をきっかけに、日本における原発の建設の政治的、社会的過程や放射能の対策を調べることによって、それが日本国民を悲惨のどん底に突き落とした戦争との類似性を持つことに気がついた。
国民の意志でも総意でもなく、密かにアメリカの原子力政策や原子力産業と結託して導入された日本の原発。それは核武装の底意を孕みながら、平和や安全というオブラートに包みこまれながら、原子力産業や原子力業界の権益を維持し、拡大させるためだけに遂行されてきたのである。戦争が、軍需産業や軍隊、軍国主義の体制そのものを守護し、その権益を拡張させるために展開されたように。-略-」
 index
index「フクシマの子どもを護る」鶴田静。下「」引用。
「チェルノブイリ原発事故直後から今まで、日本は被曝者救護のために、各種の支援を行なってきた。それと連携しながら、これからは、フクシマ原発事故の被害にあった子どもたちの救援を行うことになる。集団移住や転地保養のために、国内外の各地であたたかい援助の手が求められることだろう。すでに国内外の種々の団体や個人が、夏休みや冬休み、休日のキャンプなどを非汚染地域で行い、子どもたちのからだと心のケアに努めている。政府が子どもたちの「集団疎開」を実施しないと、怒りに燃える多数の親たちと心を一つにして。
子どもたちから奪ってならないのは、生存権は元より、生きる希望である。被曝者としての恐怖を抱きつつ、混乱した社会で生きている子どもたが、生きる意味と可能性を見出せるように。子どもが夢や希望を持つことは、彼らの絶対的な権利である。それを奪う権利は誰にも、何者にもない。-略-」
 index
index「大災害(カタストロィー)と表現者」広河隆一。下「」引用。
「二○一一年二月に私はチェルノブイリ取材を行った。ホットスポットについてのテレビ取材だった。日本に戻って一○日後に地震と津波と原発事故が起こった。三月一二日朝に現地に向かい、一三日朝には福島第一原発から数キロの双葉町役場前にいた。私が五○回のチェルノブイリ取材で一度も経験したことのないことが起こった。放射能測定器が振り切れたのである。放射線量は、一般人が一年間で浴びていいとされる限度以上を一時間弱の間に浴びてしまういう値だった。-略-」
「いまからでも疎開すべし」森詠。
あさのあつこの娘はいわき市に嫁ぎ、孫は8ヶ月……。
落合恵子さんの文章もありました。
「便奴(べんど)の岐路」森村誠一。
 index
index index
index 目 次
目 次