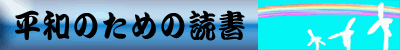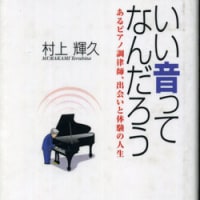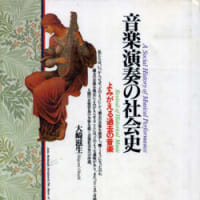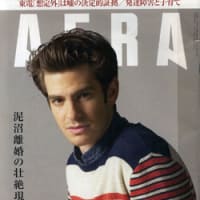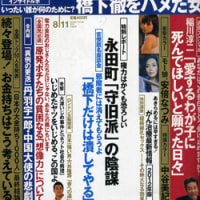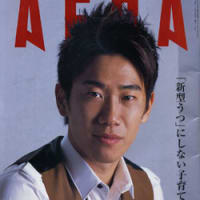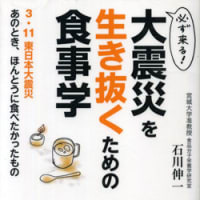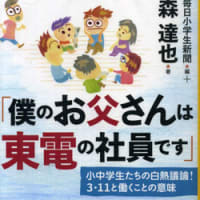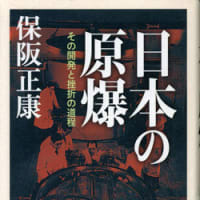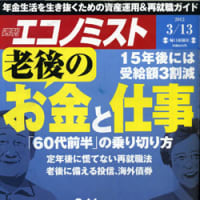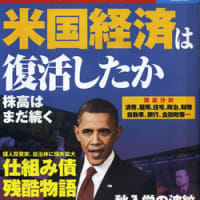『朝永振一郎著作集2 物理学と私』
朝永振一郎・著/小谷正雄・解説/みすず書房1982年、1985年4刷
ボーア、ハイゼンベルク、オッペンハイマーなど、やはり国際的な交流されていたようだ……。
そして、落語好きでもあったようです。あまり権威的な感じをうけない人物でもある……。

スコラ哲学というのも、困った面がありますね。下「」引用。
「たとえば当時のキリスト教の教会は一種の独自のスコラ哲学という考え方を持っていて、天体の運動は円でなければいけないという考え方もそこから出ているのでずが、そういうドグマ的な考え方を排斥したのがロジャー・ベーコンです。」
どっちもどっちだったという……。下「」引用。
「ケプラーはドイツ人でプロテスタントの信者-略-。プロテスタントも科学者をいじめた点ではローマ法王庁とどっちもどっちなのですが、幸か不幸かケプラーはガリレオほど派手に教会批判などはしていないという点で裁判にかけられたりすることはなかったようです。」
宗教裁判も神様が裁判したのではなく、俗っぽい人間性においておこなわれたようです……。
でも、ケプラーも宗教を恐怖していたでしょうね。下「」引用。
「ケプラーのお母さんは、当時魔女狩りというのが盛んに行われていて、魔女の嫌疑をかけられたらしいのです。とにかく当時はキリスト教会と科学とがまだ激しく対立していた時期です。」
ゲーテはニュートンの理論を『色彩論』で反駁。
--その理屈は、罵倒に近いものだったという。
科学もきれいごとですまされないという。下「」引用。
「それは科学ではなくて技術が悪いのだ、特に兵器をつくらせた政治家が悪いのだという言い方をすればすむわけです。しかし、物理学者が自然を知ることが、ケプラーの考えるように美しい調和を知ることだけであろうかということです。つまり非常に恐ろしいことも知る。知っていてそれを使わなければいいという見方もできるが、科学というものはとにかく昔の人やアインシュタインが考えたようなきれい事ではすまない面があるということです。」
「実験室のテロ」という人もいたようです。下「」引用。
「オルテガというスペインの哲学者がいるのですが、彼がやはり物理帝国主義という言葉を使っているのです。それから、もっとひどい言葉は「実験室のテロ」という言葉(笑)。つまり、物理学者は実験室で自然をおどかして、暴力をふるってい、自然に何か変な泥を吐かせる。そういうことをやって物理学の領土を拡げていくということらしいのです。」
「ハイゼンベルク博士を悼む」 (『朝日新聞」1976年2月2日)。下「」引用。
「ハイゼンベルク博士は、今世紀の最高級の天才だった。私が初めて博士にお会いしたのは、一九三七年から三九年にかけてドイツのライプチヒ大学に留学し、博士のゼミに参加したときだった。当時、博士は「不確定性原理」などの業績をあげた直後で非情に忙しく、研究の相談のためにお目にかかるのが大変だった。博士の部屋の前には、朝から行列ができた。深い思いやりがある半面、学問的には厳しく、わかないことをわかったようにいっていると、突っ込まれた。-略-
人間的にも大変幅の広い人で、ピアノがお上手だった。一九六七年、二度目の来日の際のお別れパーティーで、シューベルトのピアノ五重奏曲「ます」を日本の弦楽奏者として共演された。私にとってあの時が、最後のお別れになった。」
--錦林小学校のことがまた書かれてあった。
広い校区で、氏神様のお祭りには学校は休みになったという。
5月と10月には、もうたいへんなお休みが続いたそうです。
昭和24年に、一年たらず、オッペンハイマーの所へ行ったという。
--外国語をしゃべるのが窮屈だという。
 index
index
 index
index

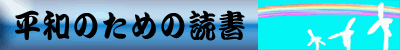

朝永振一郎・著/小谷正雄・解説/みすず書房1982年、1985年4刷
ボーア、ハイゼンベルク、オッペンハイマーなど、やはり国際的な交流されていたようだ……。
そして、落語好きでもあったようです。あまり権威的な感じをうけない人物でもある……。

スコラ哲学というのも、困った面がありますね。下「」引用。
「たとえば当時のキリスト教の教会は一種の独自のスコラ哲学という考え方を持っていて、天体の運動は円でなければいけないという考え方もそこから出ているのでずが、そういうドグマ的な考え方を排斥したのがロジャー・ベーコンです。」
どっちもどっちだったという……。下「」引用。
「ケプラーはドイツ人でプロテスタントの信者-略-。プロテスタントも科学者をいじめた点ではローマ法王庁とどっちもどっちなのですが、幸か不幸かケプラーはガリレオほど派手に教会批判などはしていないという点で裁判にかけられたりすることはなかったようです。」
宗教裁判も神様が裁判したのではなく、俗っぽい人間性においておこなわれたようです……。
でも、ケプラーも宗教を恐怖していたでしょうね。下「」引用。
「ケプラーのお母さんは、当時魔女狩りというのが盛んに行われていて、魔女の嫌疑をかけられたらしいのです。とにかく当時はキリスト教会と科学とがまだ激しく対立していた時期です。」
ゲーテはニュートンの理論を『色彩論』で反駁。
--その理屈は、罵倒に近いものだったという。
科学もきれいごとですまされないという。下「」引用。
「それは科学ではなくて技術が悪いのだ、特に兵器をつくらせた政治家が悪いのだという言い方をすればすむわけです。しかし、物理学者が自然を知ることが、ケプラーの考えるように美しい調和を知ることだけであろうかということです。つまり非常に恐ろしいことも知る。知っていてそれを使わなければいいという見方もできるが、科学というものはとにかく昔の人やアインシュタインが考えたようなきれい事ではすまない面があるということです。」
「実験室のテロ」という人もいたようです。下「」引用。
「オルテガというスペインの哲学者がいるのですが、彼がやはり物理帝国主義という言葉を使っているのです。それから、もっとひどい言葉は「実験室のテロ」という言葉(笑)。つまり、物理学者は実験室で自然をおどかして、暴力をふるってい、自然に何か変な泥を吐かせる。そういうことをやって物理学の領土を拡げていくということらしいのです。」
「ハイゼンベルク博士を悼む」 (『朝日新聞」1976年2月2日)。下「」引用。
「ハイゼンベルク博士は、今世紀の最高級の天才だった。私が初めて博士にお会いしたのは、一九三七年から三九年にかけてドイツのライプチヒ大学に留学し、博士のゼミに参加したときだった。当時、博士は「不確定性原理」などの業績をあげた直後で非情に忙しく、研究の相談のためにお目にかかるのが大変だった。博士の部屋の前には、朝から行列ができた。深い思いやりがある半面、学問的には厳しく、わかないことをわかったようにいっていると、突っ込まれた。-略-
人間的にも大変幅の広い人で、ピアノがお上手だった。一九六七年、二度目の来日の際のお別れパーティーで、シューベルトのピアノ五重奏曲「ます」を日本の弦楽奏者として共演された。私にとってあの時が、最後のお別れになった。」
--錦林小学校のことがまた書かれてあった。
広い校区で、氏神様のお祭りには学校は休みになったという。
5月と10月には、もうたいへんなお休みが続いたそうです。
昭和24年に、一年たらず、オッペンハイマーの所へ行ったという。
--外国語をしゃべるのが窮屈だという。
 index
index index
index