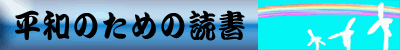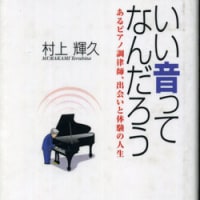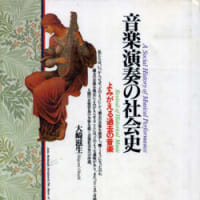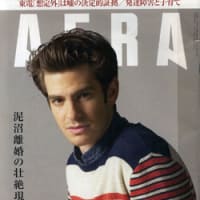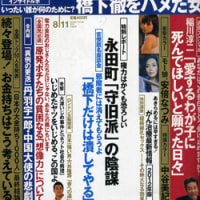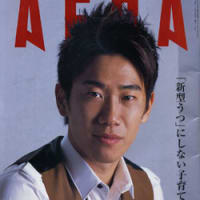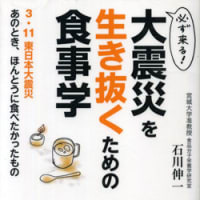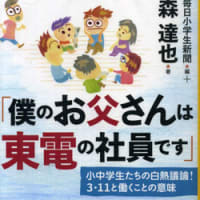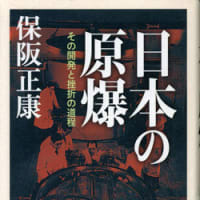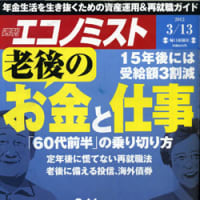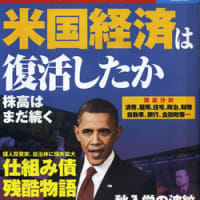『広島・原爆災害の爪跡』
中野清一・編著/蒼林社1982年
いろいろな本の部分をとりあげています。
体験もあります……。
--著者は広島大学名誉教授。

■目次・主なものだけ■
はじめに
第一部 原爆の体験記録
第二部 原爆第一号の調査記録
第三部 被爆者救済活動と原水禁運動
あとがき
国立民族研究所は疎開していたという。下「」引用。
「当時の私の勤務先は、一九四三年(昭和一八)年に創立された国立民族研究所であった。もともと研究所は東京の赤坂霊南坂の一角にあったのだが、東京空襲が激しくなったので、終戦の年の五月、滋賀県彦根市の今の滋賀大学経済学部の構内にあった同大学の研究所施設に疎開した。」
家族の住む岩国へ。下「」引用。
「明日は彦根に折り返そうと思っていた矢先に原爆が広島に落されたのである。落された頃、私も家内も庭先で、私は顔を洗っていたし、家内は洗濯をしていた。岩国は広島からおよそ四○キロほど離れているのだが、たらいに水を満たして洗いものをしていた家内は、水面にキラッと光るものを見たという。やがて庭の裏手の小さな山の上に黒ずんだ雲のようなものがもくもくと立ち登っていくのを家内も私も見た。日本陸軍が新型の爆弾を実験していたのだというのが、八月六日から七日にかけての岩国市民たちの噂であった。」
入市被爆したという……。下「」引用。
「原子爆弾が落ちてから二○日近く経っているのに、まさに「原子砂漠」ともいうべき姿がそこにあった。その状況が今もありありと念頭に浮んでくる。二時間ほど駅周辺を歩きまわったが、爆心地からどのくらいの巨利のところまで行ったのか記憶ははっきりしない。-略-被爆した人たちの「一体感」(連帯と呼んでもいい)は、八月二四日に根ざして始めていた、といえるかも知れない。」
1955(昭和30)年9月、「広島子供を守る会」が「被爆後十年間、自分たちはこうして生きてきた」の体験記手記を募集し、同年10月9日グループができ、タイトルなしで発行。1956年1月には「あゆみ」というタイトルがつく。
「第一部 原爆の体験記録」は、いろいろな本を取り上げられていた。
--例として。
「中沢啓治・共同映画宣伝部『はだしのゲン』(一九七六年)より」。下「」引用。
「私と次兄は、江波の小学校に編入した。ヨソ者である私達は、さんざんいじめ抜かれた。私は、ハゲハゲと馬鹿にされ本当にくやしかった。あっちでつつかれ、こっちでつつかれ、広島に原爆を投下したアメリカを、私は本当に呪った。」
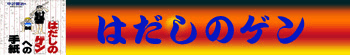 INDEX
INDEX
 index
index

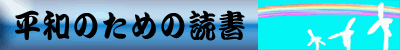

中野清一・編著/蒼林社1982年
いろいろな本の部分をとりあげています。
体験もあります……。
--著者は広島大学名誉教授。

■目次・主なものだけ■
はじめに
第一部 原爆の体験記録
第二部 原爆第一号の調査記録
第三部 被爆者救済活動と原水禁運動
あとがき
国立民族研究所は疎開していたという。下「」引用。
「当時の私の勤務先は、一九四三年(昭和一八)年に創立された国立民族研究所であった。もともと研究所は東京の赤坂霊南坂の一角にあったのだが、東京空襲が激しくなったので、終戦の年の五月、滋賀県彦根市の今の滋賀大学経済学部の構内にあった同大学の研究所施設に疎開した。」
家族の住む岩国へ。下「」引用。
「明日は彦根に折り返そうと思っていた矢先に原爆が広島に落されたのである。落された頃、私も家内も庭先で、私は顔を洗っていたし、家内は洗濯をしていた。岩国は広島からおよそ四○キロほど離れているのだが、たらいに水を満たして洗いものをしていた家内は、水面にキラッと光るものを見たという。やがて庭の裏手の小さな山の上に黒ずんだ雲のようなものがもくもくと立ち登っていくのを家内も私も見た。日本陸軍が新型の爆弾を実験していたのだというのが、八月六日から七日にかけての岩国市民たちの噂であった。」
入市被爆したという……。下「」引用。
「原子爆弾が落ちてから二○日近く経っているのに、まさに「原子砂漠」ともいうべき姿がそこにあった。その状況が今もありありと念頭に浮んでくる。二時間ほど駅周辺を歩きまわったが、爆心地からどのくらいの巨利のところまで行ったのか記憶ははっきりしない。-略-被爆した人たちの「一体感」(連帯と呼んでもいい)は、八月二四日に根ざして始めていた、といえるかも知れない。」
1955(昭和30)年9月、「広島子供を守る会」が「被爆後十年間、自分たちはこうして生きてきた」の体験記手記を募集し、同年10月9日グループができ、タイトルなしで発行。1956年1月には「あゆみ」というタイトルがつく。
「第一部 原爆の体験記録」は、いろいろな本を取り上げられていた。
--例として。
「中沢啓治・共同映画宣伝部『はだしのゲン』(一九七六年)より」。下「」引用。
「私と次兄は、江波の小学校に編入した。ヨソ者である私達は、さんざんいじめ抜かれた。私は、ハゲハゲと馬鹿にされ本当にくやしかった。あっちでつつかれ、こっちでつつかれ、広島に原爆を投下したアメリカを、私は本当に呪った。」
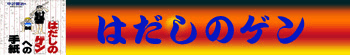 INDEX
INDEX index
index