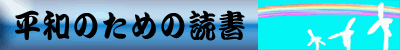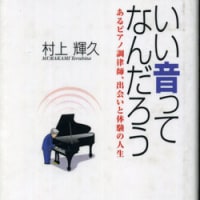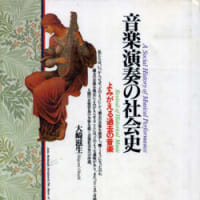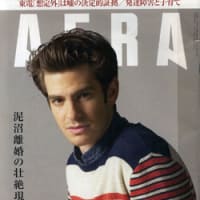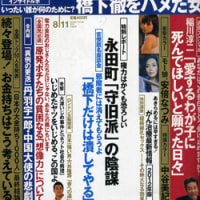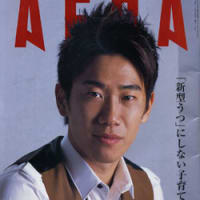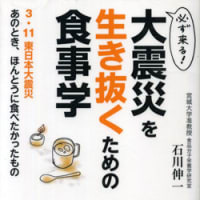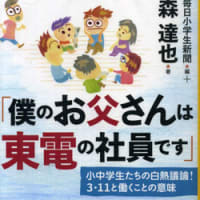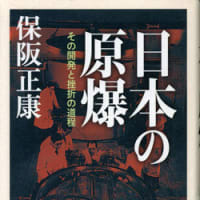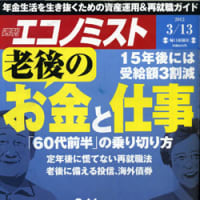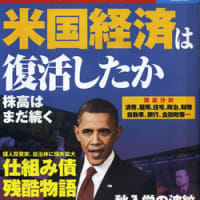『教科書に書かれなかった戦争Part6 先生、忘れないで!-「満州」に送られた子どもたち-』
陳野守正・著/梨の木舎1988年
満蒙開拓青少年義勇軍略年表:P234~235

立地場所……。下「」引用。
「現地訓練所の立地は「義勇隊の本質とその将来の発展を考慮し、国防的要請と義勇隊開拓団入植の背後地に重点を置いて」定めた(『満州開拓年鑑』昭和十九年版)。そのため、ソ連との国境地帯また一般開拓団よりも悪条件の地域に設置されることになった。したがって訓練所の多くが鉄道の最寄駅から遠くへだった地にあった。最寄駅からの距離は、たとば勃利訓練所は四○キロ、鉄嶺(てつれい)・嫩江(のんこう)大訓練所は四キロ。小訓練所になると三○-七○キロであった。興安訓練所などは一六○キロも離れていた。鉄道自警訓練所は、その性質上--二キロ程度であった。」
そして、とり残された子どもたち……。下「」引用。
「一九四五(昭和20)年八月九日未明、ヤルタ協定で連合側に対日参戦を約束していたソ連が、日ソ中立条約を破って参戦した。ソ連軍は満州各地で国境を越えて進攻して来た。
そのころ、一般開拓団・義勇隊は、無防備にひとしい北部満州に放置されていた。いざというとき必ず守ってくれるはずの関東軍は、戦略を理由にその主力部隊をすでに南満州に撤退させていたからである。しかも関東軍は、ソ連軍の進攻と同時に開拓団の男性たちを根こそぎ動員した。そのため開拓団は、老幼・女性・病弱者を残すだけとなり、崩壊寸前にあった。
一班開拓団・義勇隊訓練生たちは、不徹底な避難指示と混乱下にあって避難を開始した。しかし、攻め込むソ連軍機動部隊の足は速く、避難する側の動きは鈍い。追いつめられて進退きわまった人びとは、もはやこれまでと死を選び、北部満州の各地に凄惨な集団自決が相次いだ。避難途中、あるいはその後の収容所生活において、肉親や仲間との死別、別離に泣く子どもが続出した。この子どもたちが「中国残留日本人孤児」といわれている人びとである。子どもたちは、自ら残留したのでも、また孤児であったのでもない。
開拓団の苛酷な逃避行について、あるいは名ばかりの収容所における飢えと寒さと病気でつぎつぎと命を奪われていく悲惨な実状については、体験者によって記録されている。ここでは、一九四五年五月、すなわち、敗戦の三カ月前に渡満した京都中隊のソ連軍進攻以後の足どりを延吉収容所生活を中心に追ってみたい。-略-」
義勇軍募集……。下「」引用。
「義勇軍募集が開始された一九三八(昭和13)年ころの新聞各紙は、日中戦争大勝利のニュースを華々しく報じていた。国民は日本軍の大陸侵略に拍手を送っても、満州については「匪賊」や狼の出没するところといった認識しかもたかなかった。また「満州国」に対する認識も、他民族のの独立国というより、日本人が血を流して占領した聖地でありら、日本人が自由勝手にできる国であるといった程度であった。」
「強盗はどちらだったの?」
匪賊(東北抗日連軍の遊撃隊)か、日本人か? 下「」引用。
「「匪賊の方がまだよい、土地は奪わないから」と農民は語っている。中国人から見た日本人移民は、「匪賊」以上の「盗賊」であったわけである。」
「好成績超村名を公表した埼玉県」、「「国策非協力校」というレッテル」……
--国が圧力をかけていた……。
そして、こんな教師も……。下「」引用。
「「教師というものは、思い込んでしまったらどんな恐ろしいことでもするものである。国の命令といえば、殺人でもやりかねないということを、戦前の教育はわたしに教えてくれている」(広島平和教育研究所編『戦前の教育と私』朝日新聞社・一九七三年)」
反対の祖父……。下「」引用。
「「孫をだまして満州にやるとは、ひどい教員だ。あれは俺の孫だから君の言う通りにはさせぬぞ。第一、二十町歩の土地をどうして耕すのだ。一段の畑の草取りだって容易じゃない。それに寒い所だし医者もろくに居なくてどうする。孫はやらんから帰れか帰れ」と怒ります。
宮川寿幸「義勇軍教室-教へ子三十一名を送りて」より『新満州』一九三九(昭和14)年八月号所収」
「非協力の教師たち」もいたという……。圧力をかけられる……。下「」引用。
「広島県視学官であった小林哲一氏は、同県加茂郡下の校長会議の席で以下のような「烈々火を吐く」あいさつを行なった。
「そもそも教育というものは、国家の要請する線に沿うべきものであらねばならない。教育とはそれ以外のなにものでもない。-略-もし、私の方針が間違っていると思われる校長があるなれば、即刻、辞表を出して頂いても、敢えておとめは致しません」」
 もくじ
もくじ
そして、戦後も……。下「」引用。
「矢内原氏は、当時すでに行われていた、教育に対する政治の干渉や官僚統制の誤ちを指摘していたと厦う。ところが日本の為政者たちは、戦前はもちろん戦後も矢内原氏の言葉に聴く耳を持たなかったばかりでなく、矢内原氏の願いとは逆に平和憲法、教育基本法の精神を無視した政策、教育改革を押し進めてきたのである。」
 index
index
 もくじ
もくじ
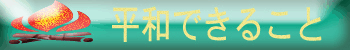 もくじ
もくじ
 index
index

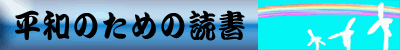

陳野守正・著/梨の木舎1988年
満蒙開拓青少年義勇軍略年表:P234~235

立地場所……。下「」引用。
「現地訓練所の立地は「義勇隊の本質とその将来の発展を考慮し、国防的要請と義勇隊開拓団入植の背後地に重点を置いて」定めた(『満州開拓年鑑』昭和十九年版)。そのため、ソ連との国境地帯また一般開拓団よりも悪条件の地域に設置されることになった。したがって訓練所の多くが鉄道の最寄駅から遠くへだった地にあった。最寄駅からの距離は、たとば勃利訓練所は四○キロ、鉄嶺(てつれい)・嫩江(のんこう)大訓練所は四キロ。小訓練所になると三○-七○キロであった。興安訓練所などは一六○キロも離れていた。鉄道自警訓練所は、その性質上--二キロ程度であった。」
そして、とり残された子どもたち……。下「」引用。
「一九四五(昭和20)年八月九日未明、ヤルタ協定で連合側に対日参戦を約束していたソ連が、日ソ中立条約を破って参戦した。ソ連軍は満州各地で国境を越えて進攻して来た。
そのころ、一般開拓団・義勇隊は、無防備にひとしい北部満州に放置されていた。いざというとき必ず守ってくれるはずの関東軍は、戦略を理由にその主力部隊をすでに南満州に撤退させていたからである。しかも関東軍は、ソ連軍の進攻と同時に開拓団の男性たちを根こそぎ動員した。そのため開拓団は、老幼・女性・病弱者を残すだけとなり、崩壊寸前にあった。
一班開拓団・義勇隊訓練生たちは、不徹底な避難指示と混乱下にあって避難を開始した。しかし、攻め込むソ連軍機動部隊の足は速く、避難する側の動きは鈍い。追いつめられて進退きわまった人びとは、もはやこれまでと死を選び、北部満州の各地に凄惨な集団自決が相次いだ。避難途中、あるいはその後の収容所生活において、肉親や仲間との死別、別離に泣く子どもが続出した。この子どもたちが「中国残留日本人孤児」といわれている人びとである。子どもたちは、自ら残留したのでも、また孤児であったのでもない。
開拓団の苛酷な逃避行について、あるいは名ばかりの収容所における飢えと寒さと病気でつぎつぎと命を奪われていく悲惨な実状については、体験者によって記録されている。ここでは、一九四五年五月、すなわち、敗戦の三カ月前に渡満した京都中隊のソ連軍進攻以後の足どりを延吉収容所生活を中心に追ってみたい。-略-」
義勇軍募集……。下「」引用。
「義勇軍募集が開始された一九三八(昭和13)年ころの新聞各紙は、日中戦争大勝利のニュースを華々しく報じていた。国民は日本軍の大陸侵略に拍手を送っても、満州については「匪賊」や狼の出没するところといった認識しかもたかなかった。また「満州国」に対する認識も、他民族のの独立国というより、日本人が血を流して占領した聖地でありら、日本人が自由勝手にできる国であるといった程度であった。」
「強盗はどちらだったの?」
匪賊(東北抗日連軍の遊撃隊)か、日本人か? 下「」引用。
「「匪賊の方がまだよい、土地は奪わないから」と農民は語っている。中国人から見た日本人移民は、「匪賊」以上の「盗賊」であったわけである。」
「好成績超村名を公表した埼玉県」、「「国策非協力校」というレッテル」……
--国が圧力をかけていた……。
そして、こんな教師も……。下「」引用。
「「教師というものは、思い込んでしまったらどんな恐ろしいことでもするものである。国の命令といえば、殺人でもやりかねないということを、戦前の教育はわたしに教えてくれている」(広島平和教育研究所編『戦前の教育と私』朝日新聞社・一九七三年)」
反対の祖父……。下「」引用。
「「孫をだまして満州にやるとは、ひどい教員だ。あれは俺の孫だから君の言う通りにはさせぬぞ。第一、二十町歩の土地をどうして耕すのだ。一段の畑の草取りだって容易じゃない。それに寒い所だし医者もろくに居なくてどうする。孫はやらんから帰れか帰れ」と怒ります。
宮川寿幸「義勇軍教室-教へ子三十一名を送りて」より『新満州』一九三九(昭和14)年八月号所収」
「非協力の教師たち」もいたという……。圧力をかけられる……。下「」引用。
「広島県視学官であった小林哲一氏は、同県加茂郡下の校長会議の席で以下のような「烈々火を吐く」あいさつを行なった。
「そもそも教育というものは、国家の要請する線に沿うべきものであらねばならない。教育とはそれ以外のなにものでもない。-略-もし、私の方針が間違っていると思われる校長があるなれば、即刻、辞表を出して頂いても、敢えておとめは致しません」」
 もくじ
もくじそして、戦後も……。下「」引用。
「矢内原氏は、当時すでに行われていた、教育に対する政治の干渉や官僚統制の誤ちを指摘していたと厦う。ところが日本の為政者たちは、戦前はもちろん戦後も矢内原氏の言葉に聴く耳を持たなかったばかりでなく、矢内原氏の願いとは逆に平和憲法、教育基本法の精神を無視した政策、教育改革を押し進めてきたのである。」
 index
index もくじ
もくじ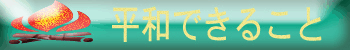 もくじ
もくじ index
index