拙ブログの記事「関税自主権喪失は長州藩の責任」のコメント欄で、薩長公英陰謀論者さんから宮崎市定氏の「幕末の攘夷論と開国論ー佐久間象山暗殺の背景ー」(『古代大和朝廷』ちくま学芸文庫所収、1995年、340-355頁)を紹介していただいた。不覚にも私は読んだことがなかったので、さっそく同書を購入して読んでみた。私も目からウロコが落ちるところが大きかったので紹介させていただきたい。東洋史の権威による全アジア史を俯瞰した広い視野に基づく「長州史観への挑戦」といってよい論考であった。薩長公英陰謀論者さん、ありがとうございました。
まず宮崎市定氏の主な論点を紹介したい。水色の字は宮崎氏の著作からの引用箇所である。
「日本の幕末維新史は、長い間、いわゆる明治の元勲たちの圧迫をうけて、非常にゆがんだ形で述べられてきた。戦後になって自由な研究が許されるようになったといっても、一度ゆがんだ形はなかなか真の姿が取り戻せない」 (宮崎、前掲書、340頁)
→ 長州閥の安倍政権下で長州=靖国史観のプロパガンダが行われようとしている。安倍政権の「日本を取り戻す」というスローガンは、長州藩閥政権時代の「ゆがんだ日本の形」を取り戻そうということなのだ。長州人の岸信介元首相がつくった岸派の流れを汲む自民党の清和会系の政治家は大なり小なり長州史観に染まっている。石原慎太郎氏にせよ、森喜朗氏にせよ、安倍晋三氏にせよ、清和会系の政治家たちが常軌を逸した発言をすることが多いのも、ゆがんだ歴史観に起因するところが大きいのだ。
「なにゆえに薩長二藩の財政が豊富であったかと言えば、皮肉にも、それは幕府の鎖国政策の結果であったのである。・・・経済統制は、きびしければきびしいほど、密貿易の利益はそれに比例して多くなるものである。この密貿易を挙藩一致して大々的に行ったのが、実に薩摩と長州とであった。…
…長州は朝鮮に近い。… 朝鮮貿易の実利をつかむのは長州であった。…
開国が実現されれば、彼らの密貿易の利益は当然なくなってしまう。
薩長を中心とする利己的な、きたない攘夷論であって、その本音は自分たちの密貿易の利益を温存するにあった。
…幕府の開国体制をくつがえさなければならない。これが薩摩と長州とに利害の共通した立場であり … 自明の理であったのである。… そこであらたな意味を持った攘夷運動は、薩長二藩によって、全力をあげて展開され、執拗に継続されたのである。さいわいに二藩は当分の間、幕府も及ばないほど財政面に余裕がある。そこで思い切って金銀をばらまき、自藩の脱走者にはもちろん、他藩の浮浪人をも誘って、尊王論を強調し、その蔭に攘夷論をしのばせて、徳川政権を揺り動かそうとしたのであった。… 」(前掲書、341-343頁)
→ 密貿易問題に関しては、「薩長公英陰謀論者」さんのコメントを読むまで全く認識していなかった。宮崎氏は、薩長の攘夷論がイデオロギーに基づくものではなく、自藩の密貿易の利益を温存するための「利己的」で「きたない」動機によるものであったと断言している。これは引き続き調べていきたい。読者の皆様には今後ともご教示いただければ幸いである。
密貿易を通しての長州と朝鮮の緊密な関係についての指摘も注目に値する。長州人の大村益次郎らがつくった東京招魂社(靖国神社)の「招魂祭」とは、日本の神道にも仏教にもない非日本的な儀式である。「招魂」という概念がどこから来たのか、コメント欄でりくにすさんからも指摘され、私もわからなかった。
調べてみると「招魂の儀」とは儒教を起源とする儀式である。朝鮮儒教の「招魂の儀」が長州に伝わり、それが靖国神社に取り入れられたという説もある。長州=靖国神社の「国家神道」は、日本古来の神道とは無縁なものなのである。
韓国「中央日報」紙のグ・ヒリョン記者は朝鮮儒教の「招魂」に関して、「招魂は儒教式礼法に基づくものだ。昔の人は人が一度息を引き取れば魂が肉体から抜けると考えた。魂が遠く離れる前につかまなければならなかった」と述べている。韓国で「招魂」は「皐復( コボク:고복)」とも呼ばれるそうである。以下の記事参照。
http://japanese.joins.com/article/348/128348.html
日本の自称「愛国者」たちは日本神道の伝統にはない朝鮮儒教の教義を礼賛しながら、ヘイトスピーチを垂れ流して韓国の批判を行っていることになる。皮肉なものである。
「佐久間象山の開国論に共鳴した吉田松陰が・・・長州に送り返されて蟄居を命ぜられると、今度は急に攘夷論に早替わりしたのはなぜか。これは長州という土地固有の利己的攘夷論に同化されたと考えなければ、何としても理解できない不思議である」(前掲書、343頁)
→ これは私も不思議であった。佐久間象山門下の頃はきわめて合理的な思考をしていた吉田松陰が、密航に失敗して国元蟄居になると、エキセントリックなエスノセントリズムに感染し、勝算も合理性も何もない排外主義的な攘夷論を唱えるようになる。この理由に関して私は、これまで納得できる説明を聞いたことがない。今後とも考えていきたい問題である。
「(象山は)河上彦斎のために、左脇を深く刺されて即死した。河上は久坂(玄瑞)と親しく、久坂は当時山崎まで進出した長州兵を指揮していたので、その使嗾によったものであろう。… 象山はきたない攘夷論者の手先にかかって倒れたのである」(前掲書、348頁)
→ 佐久間象山暗殺が、河上彦斎の単独犯行ではなく、長州藩の組織的犯行であることは歴史学的にも明らかであろう。しかしいまだに河上単独の犯行であるかのように言われることが多い。これも長州史観のバイアスなのである。
生前の松陰が命をかけても救いたいと願っていた象山を、あろうことか松陰の弟子たちが暗殺した。まさか松陰は、敬愛する恩師が自分の弟子たちの手にかかって殺されるなどとは夢にも思わなかったであろう。
孝明天皇を長州のテロから護ろうとして殺された佐久間象山は靖国神社には祀られていない。しかしあろうことか禁門の変で京都御所に向かって発砲した長州藩士の久坂玄瑞らは祀られている。この時点で靖国神社の教義の虚構性と、同神社が長州神社であるという本質は明らかであろう。長州の「英霊」たちの神社としたって、久坂はあの世で決して松陰には面会できないはずなのである。
薩摩藩は赤松小三郎という直接の恩師を斬殺した。長州藩の松下村塾党は佐久間象山という「師の師」を斬殺した。双方の暗殺事件とも、この上もなく卑怯な、武士道に反する凶行・テロリズムである。それ故、両事件ともその真相は闇の中に葬られてきたのである。
象山暗殺事件に関しては書き出すと長くなるので、稿をあらためて詳細に論じたい。
まず宮崎市定氏の主な論点を紹介したい。水色の字は宮崎氏の著作からの引用箇所である。
「日本の幕末維新史は、長い間、いわゆる明治の元勲たちの圧迫をうけて、非常にゆがんだ形で述べられてきた。戦後になって自由な研究が許されるようになったといっても、一度ゆがんだ形はなかなか真の姿が取り戻せない」 (宮崎、前掲書、340頁)
→ 長州閥の安倍政権下で長州=靖国史観のプロパガンダが行われようとしている。安倍政権の「日本を取り戻す」というスローガンは、長州藩閥政権時代の「ゆがんだ日本の形」を取り戻そうということなのだ。長州人の岸信介元首相がつくった岸派の流れを汲む自民党の清和会系の政治家は大なり小なり長州史観に染まっている。石原慎太郎氏にせよ、森喜朗氏にせよ、安倍晋三氏にせよ、清和会系の政治家たちが常軌を逸した発言をすることが多いのも、ゆがんだ歴史観に起因するところが大きいのだ。
「なにゆえに薩長二藩の財政が豊富であったかと言えば、皮肉にも、それは幕府の鎖国政策の結果であったのである。・・・経済統制は、きびしければきびしいほど、密貿易の利益はそれに比例して多くなるものである。この密貿易を挙藩一致して大々的に行ったのが、実に薩摩と長州とであった。…
…長州は朝鮮に近い。… 朝鮮貿易の実利をつかむのは長州であった。…
開国が実現されれば、彼らの密貿易の利益は当然なくなってしまう。
薩長を中心とする利己的な、きたない攘夷論であって、その本音は自分たちの密貿易の利益を温存するにあった。
…幕府の開国体制をくつがえさなければならない。これが薩摩と長州とに利害の共通した立場であり … 自明の理であったのである。… そこであらたな意味を持った攘夷運動は、薩長二藩によって、全力をあげて展開され、執拗に継続されたのである。さいわいに二藩は当分の間、幕府も及ばないほど財政面に余裕がある。そこで思い切って金銀をばらまき、自藩の脱走者にはもちろん、他藩の浮浪人をも誘って、尊王論を強調し、その蔭に攘夷論をしのばせて、徳川政権を揺り動かそうとしたのであった。… 」(前掲書、341-343頁)
→ 密貿易問題に関しては、「薩長公英陰謀論者」さんのコメントを読むまで全く認識していなかった。宮崎氏は、薩長の攘夷論がイデオロギーに基づくものではなく、自藩の密貿易の利益を温存するための「利己的」で「きたない」動機によるものであったと断言している。これは引き続き調べていきたい。読者の皆様には今後ともご教示いただければ幸いである。
密貿易を通しての長州と朝鮮の緊密な関係についての指摘も注目に値する。長州人の大村益次郎らがつくった東京招魂社(靖国神社)の「招魂祭」とは、日本の神道にも仏教にもない非日本的な儀式である。「招魂」という概念がどこから来たのか、コメント欄でりくにすさんからも指摘され、私もわからなかった。
調べてみると「招魂の儀」とは儒教を起源とする儀式である。朝鮮儒教の「招魂の儀」が長州に伝わり、それが靖国神社に取り入れられたという説もある。長州=靖国神社の「国家神道」は、日本古来の神道とは無縁なものなのである。
韓国「中央日報」紙のグ・ヒリョン記者は朝鮮儒教の「招魂」に関して、「招魂は儒教式礼法に基づくものだ。昔の人は人が一度息を引き取れば魂が肉体から抜けると考えた。魂が遠く離れる前につかまなければならなかった」と述べている。韓国で「招魂」は「皐復( コボク:고복)」とも呼ばれるそうである。以下の記事参照。
http://japanese.joins.com/article/348/128348.html
日本の自称「愛国者」たちは日本神道の伝統にはない朝鮮儒教の教義を礼賛しながら、ヘイトスピーチを垂れ流して韓国の批判を行っていることになる。皮肉なものである。
「佐久間象山の開国論に共鳴した吉田松陰が・・・長州に送り返されて蟄居を命ぜられると、今度は急に攘夷論に早替わりしたのはなぜか。これは長州という土地固有の利己的攘夷論に同化されたと考えなければ、何としても理解できない不思議である」(前掲書、343頁)
→ これは私も不思議であった。佐久間象山門下の頃はきわめて合理的な思考をしていた吉田松陰が、密航に失敗して国元蟄居になると、エキセントリックなエスノセントリズムに感染し、勝算も合理性も何もない排外主義的な攘夷論を唱えるようになる。この理由に関して私は、これまで納得できる説明を聞いたことがない。今後とも考えていきたい問題である。
「(象山は)河上彦斎のために、左脇を深く刺されて即死した。河上は久坂(玄瑞)と親しく、久坂は当時山崎まで進出した長州兵を指揮していたので、その使嗾によったものであろう。… 象山はきたない攘夷論者の手先にかかって倒れたのである」(前掲書、348頁)
→ 佐久間象山暗殺が、河上彦斎の単独犯行ではなく、長州藩の組織的犯行であることは歴史学的にも明らかであろう。しかしいまだに河上単独の犯行であるかのように言われることが多い。これも長州史観のバイアスなのである。
生前の松陰が命をかけても救いたいと願っていた象山を、あろうことか松陰の弟子たちが暗殺した。まさか松陰は、敬愛する恩師が自分の弟子たちの手にかかって殺されるなどとは夢にも思わなかったであろう。
孝明天皇を長州のテロから護ろうとして殺された佐久間象山は靖国神社には祀られていない。しかしあろうことか禁門の変で京都御所に向かって発砲した長州藩士の久坂玄瑞らは祀られている。この時点で靖国神社の教義の虚構性と、同神社が長州神社であるという本質は明らかであろう。長州の「英霊」たちの神社としたって、久坂はあの世で決して松陰には面会できないはずなのである。
薩摩藩は赤松小三郎という直接の恩師を斬殺した。長州藩の松下村塾党は佐久間象山という「師の師」を斬殺した。双方の暗殺事件とも、この上もなく卑怯な、武士道に反する凶行・テロリズムである。それ故、両事件ともその真相は闇の中に葬られてきたのである。
象山暗殺事件に関しては書き出すと長くなるので、稿をあらためて詳細に論じたい。










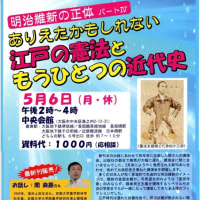









関さん、宮崎市定博士の紹介をしていただき、まことにありがとうございました。その『古代大和朝廷』(ちくま学芸文庫、1995年)所収の「東洋史の上の日本」の最後の章(近世の日本)にも、薩長の密貿易を含めて明治維新と近代化について述べてありますが、その中に「私の生国の信州・・」という表現があります(P280)。信州から京都に勉強にということ、宮崎市定博士は関さんの「大先輩」なのですね。
くだんの長州の対朝鮮密貿易から朝鮮の儒教の「招魂」の密輸入を引き出されたことに息をのみました。長州「招魂場」が靖国の起源であるということでとどまって、りくにすさんのように「招魂とはなんのことか」と思わなかったことを恥じます。
お話を勝手に敷衍してしまうこと忸怩たるものがありますが、長州の朝鮮との密貿易はおそらく、国際性がゆたかだったであろう清の物資を本命としたものではなかったかと推測します。ちなみに薩摩は琉球を介して清との交易(密貿易)を行っており、そのため「薩摩飛脚」の話で知られるように江戸からの密偵の潜入に対するきびしい防諜体制をひいていたと聞きます。
そこでさらに、Wikipedia「招魂祭」からの類推ですが、長州式招魂は朝鮮の儒教を経由した中国の道教の招魂の輸入だったということではないかとにらみます。中国古代の『楚辞』にあるという屈原の魂に対する招魂が道教の儀式としてなされており、これがなぜか朝鮮において儒教の儀式として成立していたのではないか、そこから長州に、と。
おそらく死者の魂云々というようなことはオリジナルの孔孟の教えにはないだろうと推測できますから。
ただし、儒教は徹底した現世主義であるがゆえにこそ招魂儀礼によって死者が現世に再生して子孫に命をつないでゆくということになるとか。「松岡正剛の千夜千冊」で込みいった紹介がなされている加地伸行『儒教とは何か』(中公新書、1990年)にその独特の儒教論があるとのことです( http://1000ya.isis.ne.jp/1205.html )。
ちなみに、Wikipediaによれば、日本の伝統的な招魂とされる陰陽道の招魂とは心身の衰弱により魂が身体から遊離してゆくのをもとに戻すためのもので、死者に対して行う鎮魂とはきびしく区別していたとのこと。
長州(大村益次郎)のことですから戦死者の「鎮魂」をするのではなく「招魂」で呼び戻してまた戦わせようというくらいの発想ではなかったのかと思います。農民から徴発された兵士たちがほんとうに可哀想です。
九段坂の旧招魂社(「靖国神社」)では、兵士だけではなく戦争の責任者を対象に含めて長州式招魂祭が継続して行われているのではないでしょうか。鎮魂ではなく招魂を!震えますね。
靖国式「招魂」は儒教の儀式、ということは、小島毅の『近代日本の陽明学』に示されているのですが、後期水戸学から三島由紀夫に話が行ってしまうし、朝鮮儒学の主流は陽明学ではないので相変わらずもやもやしっぱなしでした。朝鮮では自分の尊属以外は招魂しないと思うのでやはりユニークな存在と言えるでしょう。
京都では仏式葬を嫌う公家有志が神式葬を行う「霊明社」を創建し、やはり仏式葬を嫌う長州藩の神道葬を受け持つようになり、多くの勤皇志士がここに葬られました。wikipediaによるとここは維新後東山招魂社に「没収」され、後に霊山護国神社となります。神道が何かに乗っ取られてる?
ところで長州藩は「正義派」が実権を握る前は「航海遠略策」なる出貿易政策を提案していますが、これも密貿易説に従うと、一日の長のある長州は絶対損しないはずだ、ということでしょうか。幕末はみんな征韓論、と言われますが長州だけ朝鮮と特別な関係だったのでしょうか。
関さん、「(ブロック内)自由貿易」という名の、すでになりふりかまわぬ米国によるアジア構造改革=新植民地化の国際的制度統合が、さすがに米国内&外の状況によって難破しかねない事態になったとか。
それにかかわらず、ほとんど全銀行が外資化となったという韓国FTA体制のあとをひた走っている状況には目を蔽います。
「日本を韓国にするな」と、アベ総統に迫ったとして、そうトリッキーではないような気がしますが、韓国で苦しむ人々のことを考えるとやはり言葉を飲み込みます。
小学生のころに周囲の遊び友だちたちと「チョウセンチョウセンパカスルナ。オナジメシクテナゼワルイ」という口吻でかけっこをし、朝鮮が身近にあることを知りました。友だちのだれかがなぜか、韓国語の「アリラン」という歌をおしえてくれ、それから何十年経ちましたが、おしえられたそのままに口ずさむことができます。
さて、今をときめく総統の出自、長州の「招魂場」→「招魂社」→「靖国神社」と変身した「招魂」、りくにすさんが首をひねられるのはもっともで、理念や思想にさおさすものではなく、むりやり徴発した農民を兵士として死地に赴かせるための便宜、プラグマティックな浅知恵にすぎないのではないでしょうか。
目の先の利害や都合で走り回り大騒ぎする、そのための知恵はよくはたらくという、これはその後に長州を乗っ取り列島全体を乗っ取って現在にいたる「長州史観」派の一貫した特性では・・・かってに懸命、夢中になりながら、外からの狡猾なシナリオに無自覚に乗せられるので本当に迷惑ですが。
この人たちは、実質的に「対米戦争」であった太平洋戦争に敗北し、無条件降伏というあきれ果てることになったあげく、「米占領軍・GHQ」→「米駐留軍」に屈従して、露骨卑屈にすり寄ることとなりましたが、不思議なことに「対中戦争」に負けたとはまったく思っていないのではないかと思います。
それが親米右翼という奇矯な存在と、いまどき猖獗をきわめる中韓敵視の愛国小志士さんたちをふたたび生み出したのではないでしょうか。
りくにすさんの提起であわててWikipediaで見たのですが、尊攘派が長州の覇権を握る前の藩論であったという「航海遠略策」は、佐久間象山、それに変身前の吉田松陰の考え方と同一であるとのこと。見まして、密貿易利権を含む「藩益」という枠をおのずから乗り越えた、驚くべき思想といえるのではないかと思いました。それゆえに、長州藩権益をすべての上においた視野狭窄の「長州史観」派による政治的テロリズムにあったと・・・一夜にして長井時庸と彼を支持した長州の人たちのファンになりました。
しかし、あてにした日本史専門家によれば、けんもほろろなんです:
・・・長州藩の航海遠略策は、他藩から「自己航海の私論」と批判されたように、長州藩一藩が幕府に接近して産物交易策を拡張し、貿易にも参加するねらいであった。(井上勝生『シリーズ日本近現代史① 幕末・維新』岩波新書、2006年;P84)
・・・もし仮に、この策が実現すれば、現行の通商条約は、なし崩し的に追認され、それととともに締結主体としての幕府の地位も安定し、諸藩が参加して全国の国政を審議する体制作りの機会も失われてしまうだろう。それにまた、現行条約をいくら読み替えてても、外国側から見て貿易を朝貢と理解する可能性は皆無である。その意味からすれば、長井の論は、巧妙な議論のすり替えのうえに成り立っていた。天皇や正親町三条が賛同したのは、その点を理解できないまま、「五大州の貢」といった言葉を額面どおりに受け止めたためである。(青山忠正『日本近世の歴史⑥ 明治維新 』吉川弘文館、2012年;P75~76)
・・・「航海遠略策」は、・・長州藩の産物交易の展開を背景にした政論であった。・・・国是を開国に変えるのも「自然の時勢」という外交論は、・・・堀田正睦らの議論とほとんど同じである。・・・朝廷が、幕府の条約締結論と同じ長井の議論を受け入れたことがむしろ問題であった。翌年、朝廷は朝廷をないがしろにしたとして長井を批判し、長井は自害させられた。長州藩の周布や木戸、高杉の政治の原点は、この開国策「航海遠略策」にあるといえよう。ただし当時のそれは。幕政改革を否定した井伊政権を継承した安藤・久世政権を攻撃する策論ではなかった。朝廷に開国を説得する論であった。そのために失敗したのだった。(井上勝生『日本の歴史⑱ 開国と幕末変革 』講談社学術文庫、2009年;P262。原本は講談社、2002年)
と。りくにすさんが示唆された「長州の計算高さ」が裏目に出たものとして、ぼろかすに言われています。
長井さんを「姑息な策を弄する奸臣」と憎悪して犬猿の仲だった偉大な国民的英雄、吉田松陰大先生の目のくらむ輝きが翳らない限り、長井さんに日があたることはないのでしょう。
最後に・・・徳川期の「征韓論」というのはその中味はじつは「反徳川」で、豊臣に対する否定を含意した朝鮮との友好外交を重視した徳川公儀に対する反感から出てきたものだ、という説明があって妙に納得しましたが、いかがでしょうか。
毛利は反徳川の急先鋒だったわけで、長州は朝鮮を利用しているだけのつもりだったのでは。( http://members2.jcom.home.ne.jp/mgrmhosw/minaosushohan20.html )
詳しいことは忘れましたが、道教にも「招魂」ということはあったような気がして、「道教 招魂」で検索すると結構ヒットします。
Wikipediaにも「招魂祭」の項がありました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%9B%E9%AD%82%E7%A5%AD
三十年ほど前に図書館で読んだ本では、日本の神道には、天智、天武の時代から、中国の道教の影響がかなり入っていたと書いてありました。(どこかに一部をコピーしたはずなのですが、もし見つかれば本の題名もメモしたと思うので、お知らせしますが)以来、神道そのものが「まったくの日本のオリジナル」というのが、そもそも間違いなのでは?とずっと思ってきました。
私も安倍氏は「長州閥の生き残り」ではないかと思っていましたので、「長州史観」という考え方には興味があります。今後も拝読させていただきます。
それからこれは、やはりだいぶ前の、お笑い系(?)のTVドラマにこんなのがありました。(正月の「芸能人かくし芸大会」の中のドラマだったったような気もするのですが、はっきりは記憶していません)
高杉晋作等、吉田松陰の門下生が、刑死した松陰の遺体を引き取り、蘭学医村田蔵六(後の大村益次郎)の手で「フランケンシュタイン」のように蘇生させるという話です。しかし生き返った松陰は、以前にも増して純粋かつ、エキセントリックな人物になってしまったので、弟子たちも扱いに困ってしまって...というドタバタ劇でした。
私自身は若いころから司馬遼太郎の『世に棲む日日』や『花神』のファンであり、その二作を元に作られた中村梅之助が主役の村田蔵六を演じたNHK大河ドラマ、「花神」のファンでもありましたので、正直このおかしなドラマには不快でした。何故こんな奇妙でグロテスクな話を?と不可解にも思ったのですが、今になって「招魂」のことを考えてみると、妙に符合するところもあるような不思議なドラマでした。(大河ドラマの「花神」からは何年も経った頃なので、そのパロディというわけでもなかったようです)どういう人が考えたのかと思います。
なお孔子は「怪力乱神を語らず」「未だ人に事うること能わず、焉んぞ能く鬼に事えん」などと言ったとされており、死者の魂については語らぬことを決め込んでいました。「招魂」と儒教道徳は明らかに無関係です。
コメント欄に留めておくのはもったいないと思ったので、新しいエントリーで紹介させていただきました。
かなり核心的な議論になってきました。謎解きを楽しむ推理小説的なスリリングな気分も感じています。
ぜひ今後とも、皆様とともに謎解きを楽しんでいきたく思います。よろしくお願いいたします。
提案者が目論んでいたことと、周りの反応が私が予想したのと反対だったのですね。久坂玄随は最初から反対だったようです。
ところで『論語』だけが儒教だと思って加地伸行『儒教とは何か』を読むと、宗教的な面が強調されてたり太極や陰陽五行が出てきたりして面食らいます。儒教が仏教、道教や民間伝承を吸収して教えを強化していった結果です。中国や朝鮮では葬儀も儒式でやりますから、魂を扱う技術が必要です。(日本でも行われたが後が続かずその墓地は「儒者捨て場」と呼ばれた)
日本が平安時代だったころ、「朱子学」が登場してその後の儒教のスタンダードになります。それこそお釈迦様と鎌倉新仏教ぐらい隔たってしまうのです。
それにしても、日本人は『論語』が好きですよね。『本当は危ない論語』という本はあっても『本当は危ない「大学」』が売れるとは思いません。小倉紀蔵は『新しい論語』の中で、孔子と孟子以降の儒者はぜんぜん違うメンタリティーを持っていたと述べています。孔子は普遍的な一般法則を上から当てはめていくやり方を嫌い、人と人、物と物とが美しく調和することを尊んだ、というのです。
もちろん朱子学でも『論語』は尊重されていますが。
儒教の「孝」を、先祖の霊に仕えて招魂再生を行うこととする解釈が見られました。そうすると確かに儒教道徳と招魂再生がつながります。
これはどうやら、儒教・道教が成立する以前からの、中国の伝統的な死生観だったらしい。
言われてみれば確かに、「老子」にだって「招魂」をにおわせるような話は一言も書かれていない。道教の成立過程で、民間信仰を取り込んで結びついたと考えるのが妥当でしょう。
いずれにせよ儒教における「招魂再生」は、子孫が先祖に対して行うものであり、国家が戦死者の霊を一か所に招きよせて顕彰し利用するなどというものでないことは明らかです。
ちなみに陰陽道は、中国から渡来した儒教・道教などと日本の民間信仰が結びついてできたそうで、それも成立は7世紀後半以降だったそうです。
はじめまして。返信が遅れて、まことに申し訳ございませんでした。
ご高著『攘夷と憂国』は浅学にしてまだ読んでいないのですが、必ず拝読させていただきます。松陰のペリー暗殺計画に関しては、現在の時点で私に判断能力がありませんので磯川さまの著書で勉強させていただきます。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。