
船乗りマーロウはかつて、象牙交易で絶大な権力を握る人物クルツを救出するため、アフリカの奥地へ河を遡る旅に出た。募るクルツへの興味、森に潜む黒人たちとの遭遇、底知れぬ力を秘め沈黙する密林。ついに対面したクルツの最期の言葉と、そこでマーロウが発見した真実とは。
黒原敏行 訳
出版社:光文社(光文社古典新訳文庫)
『闇の奥』を最初に読んだきっかけは、村上春樹の小説(どれかは忘れた)に本書が登場したからだった。
当時の僕には難しすぎたのか、そのときはあまり感銘を受けなかったように記憶してる。
それから十年以上ぶりに読み返してみたが、思った以上におもしろかったので安心する。
おもしろいと思ったのは訳のおかげかもしれないが、物事の見方が変わってきたのも影響していよう。
具体的には、他者をどのように受け止め、認識するかという点だ。
僕は『闇の奥』を、自己防衛と認識に関する作品、と受け取ったのだが(もちろん誤読である)、上記の変化が、この小説に対する印象も変化させたように思う。
『闇の奥』の世界は十九世紀末である。
船乗りのマーロウはベルギーの植民地であるコンゴに入るが、その土地に住まう現地人の風習は、白人には理解の及ぶものではない。人肉をも好むあたりは典型だろう。
おかげで、白人側は現地人の生活習慣を理解しようという気持ちにすらならない始末。
逆に、アフリカ大陸に入植する理由として、「無知蒙昧な人たちを忌まわしい風習から引き離すため」、と言う人がいるくらいで、むしろその生活習慣を改善させるべきだと考えている。
いかにも白人至上主義らしい視点だ。
だが、白人は現地人を低く見ているけれど、文明を持っているという以外で、現地人より優れていると断言できる部分はどれだけあるのだろうか。
マーロウはほかの白人と違い、現地人に対する視点はニュートラルである。
むしろ彼は、文明人がとかく糊塗したがる人間の本質的な部分を、現地人を通して見ているように見える。
平たく言うならば、それは人間が、デフォルトで持っている獣性とも衝動とも言うべき、理性で抑えられないものなのだろう。この作品では、「闇」というメタファーで語られるものだ。
そしてそんなものにマーロウはとかく惹かれている。
「不可解なものは厭わしいもの」と彼は言っているが、「忌まわしきものの魅力」もそこには認めている。
そんな風に彼が感じるのは、それが理解できないからなのかもしれない。
わからないからこそ、理性で見えづらくなっているものに惹かれるのだ。
と同時に、それが人間誰しも持っているものだから、ということも大きいと思う。
現地人のことを「俺たちと同じように人間だと考える」とき、彼はぞっとすると言っている。
彼らが差別する現地人と、自分が大差ない、と考えるのはやはりそれなりにこわいらしい。
そういう点彼も、衝動や本能ではなく、理性でとかく物事を判断したがる白人の一人ということなのだろう。
だけど、マーロウはそれが忌まわしいものであろうと、それが人間の真実であるなら、それに肉薄したい人であるらしい。
言うなればそれは、自己認識、ひいては人間に対する認識を広げようとする、マーロウなりのチャレンジなのかもしれない。そんなことを思ってしまう。
だけど人は、そんな忌まわしいものに耐えられるとは限らない。その良い例がクルツだ。
クルツは森の中に住み、現地人と交流し、象牙交易で成果を上げている。
その過程で、白人として生きている自分の中にも品行方正とばかりはいられない、理性では片づけられない、深い闇があることに気付き、向き合っていく。
それは見ようによっては、とっても誠実な行為だ。
自分自身をしっかりつかみ、理性や何やらでごまかさないでいる。そこには偽善めいたものはなく、それがどこか好ましくもある。
だけど自分自身の醜い部分を、人はいつまでも見つめられるものではない。
脳の中には、自己防衛機能がある。
脳はとかく言い訳をしたがる、とよく言われるけれど、そうでもしなければ、自我を平静に保つことができないからだ。
クルツがしていることは、そんな脳の防衛機能を押さえつけているに等しい、と思う。
もちろん押さえつけているのは、理性の力だ。そういう点、彼はどこまでも白人的でしかないのだろう。
そして自己防衛をはばんでいるという時点で、それが敗北を前提にした戦いであることは明白なのだ。そんなものに人間の心は耐えられるわけがない。
そこまでして、人は自己認識を行なう必要性があるのだろうか。
最後の場面で、マーロウはクルツの婚約者に会い、クルツの最後を告げようとする。
だが彼の婚約者は、クルツに対して現実とはかけ離れた美しい認識を持っていた。
そのため、マーロウはクルツの真実を告げず、彼女の思いこみを尊重する。
たぶん彼女にとって、真実を話したところで、理解すらできなかっただろう。
しかしそんな思い込みが「闇の中でこの世のものとは思えない光を輝かせて人を救う」こともありうる。
少なくとも彼女の思い込みは、彼女の世界を救っているのだ。
そしてそれと同時に、他者が己に対して見る認識が、その程度のことでしかないと言っているように見える。
どれだけ自分が誠実に闇をのぞきこみ、心がズタズタになっても、他者の認識は変わらない。
結局、自己認識とは、自己満足のものであり、それを自分がどう受け入れるかという問題になってくる。そんな風に見えなくもない。
人は誠実でばかりいられるわけではない。ときにはごまかしながらも生きている。
そしてそれが人間のありのままの姿かもしれない。
そんな誤読たっぷりなことを読み終えた後に感じた次第だ。
評価:★★★★(満点は★★★★★)










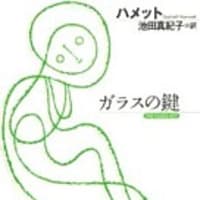

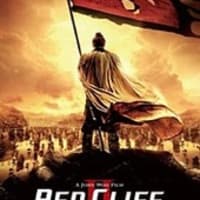
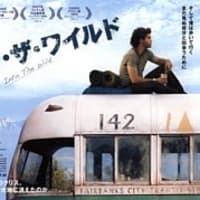
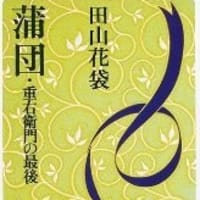
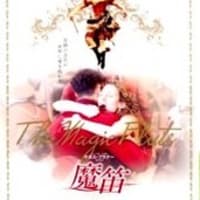
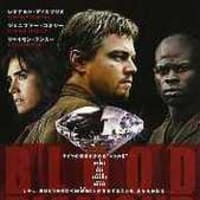
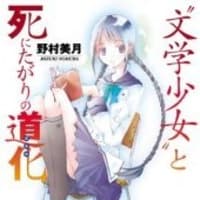
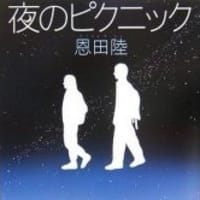

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます