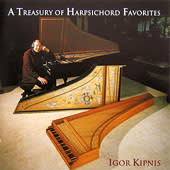
A Treasury of Harpsichord Favorites
Music & Arts Programs of America, Inc CD-243
演奏:Igor Kipnis (Harpsichords)
チェンバロ(独:Cembalo、英:Harpsichord、仏:Clavecin、伊:Clavicembalo)は、中世の終わり頃に誕生し、16世紀にはイタリアで軽量で弦の張力の弱い楽器が作られていた。16世紀には、フランドル地方に於いてこのイタリアのチェンバロをもとに、より強固な構造で豊かな響きを持つ楽器が作られるようになった。特にリュッカース一族の工房は、多くのチェンバロを産み出し、広く周辺の国にも拡がっていった。イギリスやドイツに於いてもそれぞれ独自のチェンバロが製作されたが、中でもフランスに於いては、当初はリュッカースをはじめとしたフランドルのチェンバロの改造を行い、次第にその経験をもとに独自のチェンバロを製作するようになって行った。そして18世紀の後半に、タスカンの工房などのチェンバロが最後の花を咲かせ、次第にフォルテピアノにその座を譲ることになった。
今回紹介するCDには、イタリアン、フレミッシュ、フレンチの三種類のチェンバロで演奏された16世紀中頃から18世紀終わりまでの35曲が収められている。使用されている楽器は、イタリアンは、1697年、メッシーナのカルロ・グリマルディ作、フレミッシュは、1768年、ベルギー、トゥルナイのアルベール・ダリン作、フレンチは、1707年、パリのニコラ・デュモン作のチェンバロをもとに、アメリカ、カリフォルニア州、バークレーのジョン・フィリップスが製作した複製楽器である。
このCDのもう一つの特徴は、それぞれの曲の作曲された時期や国に応じて、異なった音律を使い分けていることである。収録されている曲と使用楽器、音律のリストは以下の通り:
1 - 3 作者不詳(16世紀中頃、イタリア):3曲のイタリア舞曲
イタリアン、中全音律
4 作者不詳(16世紀中頃、イギリス):私のレディー・キャリーのドムペ
フレミッシュ、中全音律
5 ウィリアム・バード(1543 - 1623):ウォルシーのワイルド
イタリアン、中全音律
6 ジョン・ブル(c. 1563 - 1628):ギグ;ドクター・ブルのマイ・セルフ
フレミッシュ、中全音律
7 オルランド・ギッボンズ(1583 - 1625):クイーンのコマンド
イタリアン、中全音律
8 マーティン・ピーアソン(c. 1572 - 1650):落ち葉
イタリアン、中全音律
9 ヤン・ピーテルスゾーン・スウェーリンク(1562 - 1621):Ballo del granduca
フレミッシュ、中全音律
10 - 12 ジロラーモ・フレスコバルディ(1583 - 1643):Balletto I
イタリアン、中全音律
13 ルイ・クープラン(c. 1626 - 1661):パヴァーヌ変ホ
フレミッシュ、修正中全音律
14 ヨハン・ヤーコプ・フローベルガー(1616 - 1667):ブランクロシエ氏のパリでの死へのトンボー
フレンチ、中全音律
15 作者不詳(17世紀、イギリス):ナイチンゲール
イタリアン、中全音律
16 ヘンリー・パーセル(1659 - 1795):ラウンド 0(Z. T684)
フレミッシュ、1/5コンマ中全音律
17 ジェレミア・クラーク(c. 1674 - 1707):デンマーク王子のマーチ
イタリアン、ヴェルクマイスター III
18 ウィリアム・クロフト(1678 - 1727):グラウンドハ短調(Z. D221)
フレミッシュ、1/5コンマ中全音律
19 - 21 ベルナルド・パスクィーニ(1637 ―1710):3つのアリア
イタリアン、キルンベルガー III
22 フランソア・クープラン(1668 - 1733):神秘の障壁
フレンチ、1/5コンマ中全音律
23 ジャン・フランソア・ダンドリュー(1684 - 1740):オルフェのリラ
フレンチ、1/5コンマ中全音律
24 ジャン=フィリップ・ラモー(1683 - 1764):タムブーラン
フレンチ、1/5コンマ中全音律
25 ルイ=クロード・ダカン(1694 - 1772):カッコウ
フレンチ、1/5コンマ中全音律
26 ゲオルク・フリートリヒ・ヘンデル(1685 - 1759):パッサカリア
フレンチ、1/5コンマ中全音律
27 ゲオルク・フィリップ・テレマン(1681 - 1767):ブレー I & II
フレンチ、バーンズ/バッハ
28 クリスティアン・ペーツォルト(1677 - 1733):メヌエットト長調とト短調
フレミッシュ、1/5コンマ中全音律
29 - 30 ヨハン・ゼバスティアン・バッハ(1685 - 1750):前奏曲とフーガハ長調(BWV 846:1)
フレミッシュ、バーンズ/バッハ
31 ジオヴァンニ・バッティスタ・ペルゴレージ(1710 - 1736):ソナタイ長調
イタリアン、ヴァロッティ
32 ドメニコ・スカルラッティ(1685 - 1757):ソナタイ長調(K 9; L 413)
イタリアン、ヴァロッティ
33 ピエトロ・ドメニコ・パラディース(1707 - 1791):アレグロ
フレンチ、バーンズ/バッハ
34 フランツ・ヨーゼフ・ハイドン(1732 - 1809):アレグレットト長調
フレンチ、ヤング
35 ヴォルフガンク・アマデウス・モーツァルト(1756 - 1791):トルコ行進曲
フレンチ、ヤング
全体を通してみると、17世紀の曲は中全音律、17世紀の前半の曲になると主に1/5コンマ中全音律、それに曲によって、改良中全音律、ヴェルクマイスター第III、キルンベルガー第III、Barnes/Bach、Valottiなどの音律、そして古典派のハイドンやモーツアルトの曲はYoungの音律が用いられている。これらの音律についての概略は、「西洋音楽の音律についての簡単な説明」を参照されたい。ルイ・クープランの曲の演奏に採用されている「修正中全音律」については、何の説明もないが、中全音律におけるGis - Dis間の極端に広い完全五度を、他のいくつかの完全五度に割り振って、不快な唸り、いわゆる「ウルフ」を軽減させているのではないかと思われる*。また、1/5コンマ中全音律が、どのような音律かも説明されていないが、おそらくこれは歴史的な音律ではなく、ピュタゴラス・コンマあるいはシントニック・コンマを5分割して、完全五度のいくつかに割り振り、さらに他のいくつかの完全五度の調整も行った、「巧みな音律」の一種と思われる。
このCDに収められている様々な調律法は、この調性の拡大過程に考案されたものがほとんどである。これらの異なった音律の違いを聞き分けるのは、決して容易ではないが、長調の三和音の純正さを重視する中全音律で調律されたチェンバロで演奏されている曲は、確かに和音が美しい。例えば、同じイタリアン・タイプのチェンバロで、1/4コンマ中全音調律で演奏されている曲と、ヴァロッティ音律で調律された曲とを続けて聞くと、その響きの違いを明瞭に感じることが出来る。一度体験されることをお勧めする。
イゴール・キプニス(1930 - 2002)は、アメリカのチェンバロ奏者、ピアノフォルテ奏者として幅広い活躍をしていた。また拠点としていたアメリカ、コネチカットでは1983年以来、ジョン・ソラムとともに、コネチカット・アーリーミュージック・フェスティバルを開催していた。
なお、発売元のMusic and Arts Programs of America, Inc.のサイトには、このCDはCD-4243(1)と言う番号で掲載されており、購入可能である。また、このCDの他にもオリジナルのチェンバロによる演奏のCDは、数多くあるので、輸入のマイナーレーベルを多くそろえている店で探してみてはいかがだろうか?
発売元:Music and Arts Programs of America, Inc.
* この点に関しては、REIKOさんのブログ「 ヘンデルと(戦慄の右脳改革)音楽箱」の「F.クープラン「神秘の障壁」と音律 http://handel.at.webry.info/201101/article_3.html 」をはじめとして、曲に応じて中全音律のウルフを回避する様々な試みが紹介されているので、興味のある方は参照されたい。また、REIKOさんは最近、「音律の右脳改革鍵盤館♪ http://onritsu.blog.shinobi.jp/ 」と言うブログを始められて、もっぱら音律についての記事を投稿しておられるので、興味ある方は参考にされることをおすすめする。

クラシック音楽鑑賞をテーマとするブログを、ランキング形式で紹介するサイト。
興味ある人はこのアイコンをクリックしてください。
| Trackback ( 0 )
|
|
発売元のサイトからあっさり購入できました。
ミーントーンの和音は綺麗ですね。
楽器の違いも楽しいです。
ご紹介頂きありがとうございました。
日本の音楽教育はなぜ調律を無視なんでしょう。
これからも頑張ります。
これは大サービスのCDですね。
楽器はともかく、各曲の音律まで明記してあるのは珍しいと思います。
それで1/5コンマ中全音律ですが、ピタゴラスコンマまたはシントニックコンマの1/5だけ狭くした五度を五度圏にぐるりと並べ、最後に残った五度がウルフ・・・というものではないでしょうか?
前者は約+28セント、後者は約+24セント広い五度が残るので、ここは五度としては使えません。
しかし通常の1/4コンマ中全音律よりは、ウルフをまたいだ長・短三度などの音程が多少良くなっています。
(純正長三度はもう無いですけど)
ウルフの位置は通常G#-E♭ですが、動かして演奏する人もいます。
「神秘の障壁」で、A♭音がかなり低く聴こえたならウルフは通常位置、ちょうど良く聴こえたらG#がA♭になるように動かしているはずです。
1/5シントニック・コンマ・ミーントーンは、確かにGis - Es間に+11/15 skと言うウルフが来るようですが、私が参考にしている128の音律を紹介しているサイトでも、歴史的な記述はなく、Josef Ratteと言う人のイタリアとフランスのオルガンの調律に関する本(1991年刊)を紹介しながら、Wolfgang Th. Meisterは、「均質中全音律(Homogene Mitteltoenigkeit)」を表現しています。1/6コンマ狭い完全五度を配する音律は、ヴァロッティやヤングの音律に見られますが、これは11の完全五度すべてを1/6コンマ狭くするのではなく、いわゆる「巧みな音律」に属するものですね。
この様に歴史的に実用化されていたという確かな根拠がないため、今回の投稿のような記述にしたわけです。