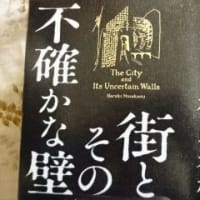藤本義一が10月30日、亡くなった。79歳だった。
藤本義一は、作家というよりテレビ番組「11PM」の司会者として知っている人が多いかもしれない。
「11PM」(イレブン・ピーエム)は、1965(昭和40)年から始まり1990(平成2)年まで25年間続いた、夜11時(23時)からの放映のテレビ番組だった。夜型人間が増え、若者が深夜族になる時代だった。
コンビニエンス・ストアの「セブン-イレブン」が日本で開店したのが1974(昭和49)年で、翌年から24時間オープンの店が出てきた。僕は、24時間店が開いていても、そんな夜中に買いものに行く人間がいるのかなと疑問に思った記憶がある。
当時、夜開いている店といえば飲み屋かラーメン屋ぐらいであった。普通の人は、夜、買い物に行ったり、意味もなく街を歩いたりなんてことはしなかった。だいたい夜は家で静かにし、日が変わる頃には寝ていたのである。盛り場以外、街は静かだった。
しかし、コンビニが24時間営業は当たり前となるにつれ、夜遅くまで営業する店も増え、深夜に活動する人間は増えていったのである。
その象徴的な現象ともいえるのが、「11PM」の登場ではなかったろうか。
「11PM」は、日本テレビと読売テレビの交互製作による、月・水・金曜日の東京局が大橋巨泉、愛川欣也で(途中から)、火・木曜日の大阪局が藤本義一の司会によるワイドショーで、深夜の番組にちょっとしたお色気を入れて人気があった。
藤本義一の横に座る女性アシスタントの初代が元京都芸妓の安藤孝子であったのも、新しい試みだったといえる。藤本のよどみない話に相槌を打つ安藤はしっとりと艶っぽく、番組全体に関西の風味が漂い、藤本とはいいコンビであった。
一方東京の大橋巨泉の相手は曜日によって変わり、当初は應蘭芳(オウ・ランファン)、ジューン・アダムス、朝丘雪路で、こちらも個性が違った色っぽい女性が座った。
應蘭芳は女性週刊誌による発言から「失神女優」などと呼ばれて話題になったが、「11PM」出演期間は短く、そのあとを受けたのは松岡きっこだった。
ジューン・アダムスは、ハーフのモデルで、カメラマンの篠山紀信とお互い最初の結婚をした。
朝丘雪路は父が日本画家の伊東深水というお嬢さん女優で、今でいう巨乳であった。朝丘は現在も健在で活躍中なので、過去形ではなく巨乳であると進行形で言わないといけない。巨泉はこのことを揶揄って「ボイン」と言ったことから、この言葉は流行語にもなった。
「11PM」のカバーガールを見てみると、ジューン・アダムス以下、沢知美、池島ルリ子、樹れい子、秋川リサなど、いわゆる当時のグラビア・ガールが見てとれる。現在も活動している、かたせ梨乃、飯島直子、岡本夏生なども出演していた。
大阪では、安藤孝子のあとアシスタントに、真理アンヌ、東てる美、横山エミー、松居一代などが見てとれる。
藤本義一は、このテレビの司会を続けながら小説を書き続け、1969(昭和44)年以来何度も直木賞候補となり、1974(昭和49)年に上方落語家の半生を描いた「鬼の詩」で第71回直木賞を受賞した。
当時の文壇は、タレント性の強い作家が小説だけでなくその行動や発言でマスコミを賑わしていた。
ルックスがよく「顔文一致」などと言われた五木寛之は、1967(昭和42)年に「蒼ざめた馬を見よ」で、翌年にはサングラス姿で何かと発言がマスコミを賑わしていた野坂昭如は、「火垂るの墓」「アメリカひじき」で直木賞を受賞し、小説家としてもその実力を示していた。
野坂は、歌手としてもデビューし、「黒の舟歌」や「マリリンモンローノーリターン」などのヒット曲も飛ばした。僕も「野坂昭如 不条理の唄」と「野坂昭如ライヴ総集篇Vol.1」のレコード・アルバムを持っている。
なかでも、「不条理の唄」に収められている「「野坂昭如新古今集より」は、いい歌だ。このアルバムのライナーノーツには、「野阪昭如誌上猥褻リサイタル」として、巻頭に雑誌「面白半分」に掲載した「四畳半襖の下張」の猥褻文書裁判の起訴状が載っているという個性的なものだ。
1971(昭和46)年創刊の「面白半分」は、代々作家が半年ずつ編集長を務めるという雑誌だった。初代が吉行淳之介で、2代目が野阪昭如であった。そのあと、開高健、五木寛之と続いて、5代目に藤本義一がなっている。
また、当時、佐々木久子が編集する「酒」という雑誌があった。この雑誌には、毎年「文壇酒徒番附」なるものが掲載されていて、それで作家の酒豪、酒好きがわかった。
毎年少しは顔ぶれ、順列が変わったが、1972(昭和47)年は、東西横綱に立原正秋、梶原季之、野坂昭如、黒岩重吾、大関に池波正太郎、三浦哲郎、吉行淳之介、瀬戸内晴美などが顔を並べたとある。
ある年は、東の横綱が吉村昭で、西が藤本義一のときがあったというほど、藤本も酒が好きだった。しかし、乱れることのない紳士的な飲み方だった。
*
藤本義一には多くの出版物がある。
その作家、藤本義一と会ったことがある。という言い方は少し違うが、僕が出版社の編集者のときに彼の単行本を1冊作った。西宮市の家に足を運んだこともあった。
編集したのは「巷の奇人たち」という本で、1978(昭和53)年発行だから、「11PM」司会の真っ只中の頃である。
とても丁寧な対応で、いつも紳士的な人であった。おそらく、誰にでも変わらない対応であっただろう。大阪を愛した人だが、大阪人というより東京の粋人のような印象を与える人だった。
本は、「事実は小説よりも奇なり!一つのことに憑かれた人間たち」と帯に書いたように、常識から逸脱した人間を描いたノンフィクション風小説である。
この本で取り上げたように彼は、市井の有名ではないが個性豊かな人物たちを丁寧に掘り起こした。
藤本義一は、人を愛し、酒を愛し、大阪を愛した。彼の旺盛な好奇心が、数多くの小説を生んだ。
藤本義一は、作家というよりテレビ番組「11PM」の司会者として知っている人が多いかもしれない。
「11PM」(イレブン・ピーエム)は、1965(昭和40)年から始まり1990(平成2)年まで25年間続いた、夜11時(23時)からの放映のテレビ番組だった。夜型人間が増え、若者が深夜族になる時代だった。
コンビニエンス・ストアの「セブン-イレブン」が日本で開店したのが1974(昭和49)年で、翌年から24時間オープンの店が出てきた。僕は、24時間店が開いていても、そんな夜中に買いものに行く人間がいるのかなと疑問に思った記憶がある。
当時、夜開いている店といえば飲み屋かラーメン屋ぐらいであった。普通の人は、夜、買い物に行ったり、意味もなく街を歩いたりなんてことはしなかった。だいたい夜は家で静かにし、日が変わる頃には寝ていたのである。盛り場以外、街は静かだった。
しかし、コンビニが24時間営業は当たり前となるにつれ、夜遅くまで営業する店も増え、深夜に活動する人間は増えていったのである。
その象徴的な現象ともいえるのが、「11PM」の登場ではなかったろうか。
「11PM」は、日本テレビと読売テレビの交互製作による、月・水・金曜日の東京局が大橋巨泉、愛川欣也で(途中から)、火・木曜日の大阪局が藤本義一の司会によるワイドショーで、深夜の番組にちょっとしたお色気を入れて人気があった。
藤本義一の横に座る女性アシスタントの初代が元京都芸妓の安藤孝子であったのも、新しい試みだったといえる。藤本のよどみない話に相槌を打つ安藤はしっとりと艶っぽく、番組全体に関西の風味が漂い、藤本とはいいコンビであった。
一方東京の大橋巨泉の相手は曜日によって変わり、当初は應蘭芳(オウ・ランファン)、ジューン・アダムス、朝丘雪路で、こちらも個性が違った色っぽい女性が座った。
應蘭芳は女性週刊誌による発言から「失神女優」などと呼ばれて話題になったが、「11PM」出演期間は短く、そのあとを受けたのは松岡きっこだった。
ジューン・アダムスは、ハーフのモデルで、カメラマンの篠山紀信とお互い最初の結婚をした。
朝丘雪路は父が日本画家の伊東深水というお嬢さん女優で、今でいう巨乳であった。朝丘は現在も健在で活躍中なので、過去形ではなく巨乳であると進行形で言わないといけない。巨泉はこのことを揶揄って「ボイン」と言ったことから、この言葉は流行語にもなった。
「11PM」のカバーガールを見てみると、ジューン・アダムス以下、沢知美、池島ルリ子、樹れい子、秋川リサなど、いわゆる当時のグラビア・ガールが見てとれる。現在も活動している、かたせ梨乃、飯島直子、岡本夏生なども出演していた。
大阪では、安藤孝子のあとアシスタントに、真理アンヌ、東てる美、横山エミー、松居一代などが見てとれる。
藤本義一は、このテレビの司会を続けながら小説を書き続け、1969(昭和44)年以来何度も直木賞候補となり、1974(昭和49)年に上方落語家の半生を描いた「鬼の詩」で第71回直木賞を受賞した。
当時の文壇は、タレント性の強い作家が小説だけでなくその行動や発言でマスコミを賑わしていた。
ルックスがよく「顔文一致」などと言われた五木寛之は、1967(昭和42)年に「蒼ざめた馬を見よ」で、翌年にはサングラス姿で何かと発言がマスコミを賑わしていた野坂昭如は、「火垂るの墓」「アメリカひじき」で直木賞を受賞し、小説家としてもその実力を示していた。
野坂は、歌手としてもデビューし、「黒の舟歌」や「マリリンモンローノーリターン」などのヒット曲も飛ばした。僕も「野坂昭如 不条理の唄」と「野坂昭如ライヴ総集篇Vol.1」のレコード・アルバムを持っている。
なかでも、「不条理の唄」に収められている「「野坂昭如新古今集より」は、いい歌だ。このアルバムのライナーノーツには、「野阪昭如誌上猥褻リサイタル」として、巻頭に雑誌「面白半分」に掲載した「四畳半襖の下張」の猥褻文書裁判の起訴状が載っているという個性的なものだ。
1971(昭和46)年創刊の「面白半分」は、代々作家が半年ずつ編集長を務めるという雑誌だった。初代が吉行淳之介で、2代目が野阪昭如であった。そのあと、開高健、五木寛之と続いて、5代目に藤本義一がなっている。
また、当時、佐々木久子が編集する「酒」という雑誌があった。この雑誌には、毎年「文壇酒徒番附」なるものが掲載されていて、それで作家の酒豪、酒好きがわかった。
毎年少しは顔ぶれ、順列が変わったが、1972(昭和47)年は、東西横綱に立原正秋、梶原季之、野坂昭如、黒岩重吾、大関に池波正太郎、三浦哲郎、吉行淳之介、瀬戸内晴美などが顔を並べたとある。
ある年は、東の横綱が吉村昭で、西が藤本義一のときがあったというほど、藤本も酒が好きだった。しかし、乱れることのない紳士的な飲み方だった。
*
藤本義一には多くの出版物がある。
その作家、藤本義一と会ったことがある。という言い方は少し違うが、僕が出版社の編集者のときに彼の単行本を1冊作った。西宮市の家に足を運んだこともあった。
編集したのは「巷の奇人たち」という本で、1978(昭和53)年発行だから、「11PM」司会の真っ只中の頃である。
とても丁寧な対応で、いつも紳士的な人であった。おそらく、誰にでも変わらない対応であっただろう。大阪を愛した人だが、大阪人というより東京の粋人のような印象を与える人だった。
本は、「事実は小説よりも奇なり!一つのことに憑かれた人間たち」と帯に書いたように、常識から逸脱した人間を描いたノンフィクション風小説である。
この本で取り上げたように彼は、市井の有名ではないが個性豊かな人物たちを丁寧に掘り起こした。
藤本義一は、人を愛し、酒を愛し、大阪を愛した。彼の旺盛な好奇心が、数多くの小説を生んだ。