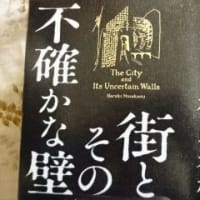毎年ゴールデンウィークに開催される、フランス発の音楽祭「ラ・フォル・ジュルネ」(熱狂の日々)が、今年も東京国際フォーラムで行われた。
毎年テーマが掲げられ、去年は「ベートーヴェン」だった。
今年のテーマは、「ORIGINES(オリジン) ――すべてはここからはじまった」である。
クラシック音楽のルーツ、最初に生みだされた音楽というだけでなく、幾世紀にもわたり、世界のあらゆる国々の作曲家たちをインスパイアしてきた様々な音楽の伝統にスポットライトを当てる、ということである。
*クラシック音楽の「オリジン」とは?
ラ・フォル・ジュルネのアーティスティック・ディレクターであるルネ・マルタンの言葉から、その内容を記しておこう。
クラシック音楽といえば、「音楽の父」と称されているJ.S.バッハがあげられるが、彼もまた、悠久の時と文明のるつぼに深く根を下ろした長い音楽の伝統を受け継いでいた。そして、彼以後の作曲家たちは皆、どの大陸、どの国の出身であれ、古くからの遺産をよりどころとして自分たちの音楽言語を練り上げ、作品を生み出してきた。
その「オリジン」として、次の例をあげている。
19世紀半ば以降、音楽を通して「オリジン」が探求されて、ロシア、ハンガリー、チェコスロバキア、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フランス、スペインなどで花開いたのが「国民楽派」である。
各国の限りなく豊かな大衆音楽から想を得、名曲を残した、ムソルグスキー、チャイコフスキー、スメタナ、ドヴォルザーク、コダーイ、バルトーク、さらにはグリーグ、シベリウス、アルベニス、ラヴェル、ビゼーらの作曲家をあげる。
音楽の「オリジン」をめぐるテーマとしては、「楽曲形式の変遷」をあげる。時代を超えて多くの傑作を生み出してきたソナタ、四重奏曲、協奏曲といった形式は、どのように誕生したのか?
そして、「楽器の起源」にも視点を置く。今日の私たちが知る楽器は、どのように生まれ、時とともにどのような変化を遂げたのであろう?
人間の息は、あらゆる音楽の起源であった。竪琴とともに世界最古の楽器の一つとされる笛以上に、息を、すなわち世界の起源を体現する楽器があるであろうか?
さらに、「パイオニア的作品」といえる、その法外な革新性によって新たな道を切り拓き、音楽史の流れを変えた作品も取りあげる。
例えば、ヴィヴァルディの〈四季〉、ストラヴィンスキーの〈春の祭典〉、バーンスタインの〈ウエスト・サイド物語〉などをあげている。
つまり、ラ・フォル・ジュルネにおいてのオリジンは、音楽のこと初めである歌声から、楽器、楽曲の形式、民族の特色など、その時代を彩った音楽、作曲家たちを取りあげる、クラシック音楽のパノラマということである。
*
私は、あらゆるジャンルの音楽を聴いてきた。
歌謡曲、シャンソンやファド、ロック、ジャズ、クラシックなど、時代の流れとともにあった気がする。
現在聴くのはクラシック音楽が最も多いが、現代音楽は苦手というか良いとは思わない。バロックからモーツァルト、ベートーヴェンなどの古典派が最も心地いいし、どうにかロマン派のブラームスあたりまでである。
坂本龍一がドビッシーの音楽を聴いたとき、それまでのベートーヴェンなどの古典派の、ソナタ形式などの構築された音楽から、和音にとらわれない水の流れのようだと形容し、音楽的衝撃を受けたと述べていた。
こう言われても私のなかでは、ドビッシーの良さは宙に浮いたままである。
現代の音楽家(作曲家や指揮者)の多くが称賛し、このラ・フォル・ジュルネのルネ・マルタンもオリジンとして取りあげているストラヴィンスキーの「春の祭典」も、皆なぜ絶賛するのかという疑問符は氷解することはない。
つまり、私はいまだベートーヴェンを敬愛した「ブラームスはお好き?」のままなのである。
*ラ・フォル・ジュルネ2024へ
ラ・フォル・ジュルネは、5月3~5日の間、朝から夜まで東京国際フォーラムの各ホールおよびその近辺で、数多くの公演が行われた。
5月4日、東京国際フォーラムに出向いた。
聴いた2公演は以下の通り。
・18:45 〜 19:30 ホールA
世界に新たな一歩を踏み出した霊妙のコンチェルト
[曲目]ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.61
[出演者]リヤ・ペトロヴァ(ヴァイオリン)
東京フィルハーモニー交響楽団
三ツ橋敬子(指揮者)
<リヤ・ペトロヴァ 略歴>
2016年ニールセン国際コンクール優勝者。ブルガリアの音楽一家に生まれ、エリーザベト王妃音楽院でデュメイに、アイスラー音楽大学でヴァイトハースに、ローザンヌ音楽院でカプソンに師事。パリ管、フランス放送フィル等と共演。2021年、「ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲ほか」をリリース。パリ在住。(ラ・フォル・ジュルネ広報より)
・20:00 〜 21:00 ホールB5(1) マスタークラス
[講師]アンヌ・ケフェレック(ピアノ)
[曲目]シューベルト: ピアノ・ソナタ第17番ニ長調 D850 から 第1楽章
公演ではなく、指定の曲を弾いた生徒(音大生)に対して、ピアニストの講師が指導、教授する催しであった。
*歴史を彩ったクラシック音楽家列像
会場で販売していたラ・フォル・ジュルネ音楽祭2024、30周年記念盤「オリジン~7世紀にわたる音楽の旅」と称したCD(2枚組)を購入した。
これまでの音楽祭に登場した、あるいは関連ある作曲家や作品を、「オリジン」のテーマに即した内容としている。
中世ノートルダム楽派のポリフォニー音楽の作曲家、ペロタン「祝福された胎児」(抜粋)から、バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、ドヴォルザーク、ブラームスの曲を含め、メキシコ人の現代音楽作曲家のA・マルケス「ダンソンno.2」までを、摘まみ選択したものである。
そのジャケットには、その時代を彩った作曲家、その関係者の肖像画を羅列してある。音楽の教科書や関連書で見たことのあるモーツァルトやベートーヴェンなど有名な人物もいるが、まったく見たこともない(聞いたこともない)人物もいる。(写真)
さて、何人知っているだろうか?
参考までに、以下にその解答を記しておく(名前の順は、左から右へ)。
①アントニオ・ヴィヴァルディ
②ヨハン・セバンチャン・バッハ
③ヨーゼフ・ハイドン
④ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
⑤ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
⑥ルイーズ・ファランク
⑦フランツ・シューベルト
⑧ファニー・メンデルスゾーン
⑨フレデリック・ショパン
⑩クララ・シューマン
⑪モーリス・ラヴェル
⑫ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー
⑬セルゲイ・ラフマニノフ
⑭メラニー・ボニス
⑮イーゴリ・ストラヴィンスキー
⑯ヨハネス・ブラームス
⑰ガブリエル・フォーレ
⑱ジョージ・ガーシュウィン
⑲ジェルメーヌ・タイユフェール
⑳フランツ・リスト
㉑ナディア・ブーランジェ
㉒フィリップ・グラス
毎年テーマが掲げられ、去年は「ベートーヴェン」だった。
今年のテーマは、「ORIGINES(オリジン) ――すべてはここからはじまった」である。
クラシック音楽のルーツ、最初に生みだされた音楽というだけでなく、幾世紀にもわたり、世界のあらゆる国々の作曲家たちをインスパイアしてきた様々な音楽の伝統にスポットライトを当てる、ということである。
*クラシック音楽の「オリジン」とは?
ラ・フォル・ジュルネのアーティスティック・ディレクターであるルネ・マルタンの言葉から、その内容を記しておこう。
クラシック音楽といえば、「音楽の父」と称されているJ.S.バッハがあげられるが、彼もまた、悠久の時と文明のるつぼに深く根を下ろした長い音楽の伝統を受け継いでいた。そして、彼以後の作曲家たちは皆、どの大陸、どの国の出身であれ、古くからの遺産をよりどころとして自分たちの音楽言語を練り上げ、作品を生み出してきた。
その「オリジン」として、次の例をあげている。
19世紀半ば以降、音楽を通して「オリジン」が探求されて、ロシア、ハンガリー、チェコスロバキア、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フランス、スペインなどで花開いたのが「国民楽派」である。
各国の限りなく豊かな大衆音楽から想を得、名曲を残した、ムソルグスキー、チャイコフスキー、スメタナ、ドヴォルザーク、コダーイ、バルトーク、さらにはグリーグ、シベリウス、アルベニス、ラヴェル、ビゼーらの作曲家をあげる。
音楽の「オリジン」をめぐるテーマとしては、「楽曲形式の変遷」をあげる。時代を超えて多くの傑作を生み出してきたソナタ、四重奏曲、協奏曲といった形式は、どのように誕生したのか?
そして、「楽器の起源」にも視点を置く。今日の私たちが知る楽器は、どのように生まれ、時とともにどのような変化を遂げたのであろう?
人間の息は、あらゆる音楽の起源であった。竪琴とともに世界最古の楽器の一つとされる笛以上に、息を、すなわち世界の起源を体現する楽器があるであろうか?
さらに、「パイオニア的作品」といえる、その法外な革新性によって新たな道を切り拓き、音楽史の流れを変えた作品も取りあげる。
例えば、ヴィヴァルディの〈四季〉、ストラヴィンスキーの〈春の祭典〉、バーンスタインの〈ウエスト・サイド物語〉などをあげている。
つまり、ラ・フォル・ジュルネにおいてのオリジンは、音楽のこと初めである歌声から、楽器、楽曲の形式、民族の特色など、その時代を彩った音楽、作曲家たちを取りあげる、クラシック音楽のパノラマということである。
*
私は、あらゆるジャンルの音楽を聴いてきた。
歌謡曲、シャンソンやファド、ロック、ジャズ、クラシックなど、時代の流れとともにあった気がする。
現在聴くのはクラシック音楽が最も多いが、現代音楽は苦手というか良いとは思わない。バロックからモーツァルト、ベートーヴェンなどの古典派が最も心地いいし、どうにかロマン派のブラームスあたりまでである。
坂本龍一がドビッシーの音楽を聴いたとき、それまでのベートーヴェンなどの古典派の、ソナタ形式などの構築された音楽から、和音にとらわれない水の流れのようだと形容し、音楽的衝撃を受けたと述べていた。
こう言われても私のなかでは、ドビッシーの良さは宙に浮いたままである。
現代の音楽家(作曲家や指揮者)の多くが称賛し、このラ・フォル・ジュルネのルネ・マルタンもオリジンとして取りあげているストラヴィンスキーの「春の祭典」も、皆なぜ絶賛するのかという疑問符は氷解することはない。
つまり、私はいまだベートーヴェンを敬愛した「ブラームスはお好き?」のままなのである。
*ラ・フォル・ジュルネ2024へ
ラ・フォル・ジュルネは、5月3~5日の間、朝から夜まで東京国際フォーラムの各ホールおよびその近辺で、数多くの公演が行われた。
5月4日、東京国際フォーラムに出向いた。
聴いた2公演は以下の通り。
・18:45 〜 19:30 ホールA
世界に新たな一歩を踏み出した霊妙のコンチェルト
[曲目]ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.61
[出演者]リヤ・ペトロヴァ(ヴァイオリン)
東京フィルハーモニー交響楽団
三ツ橋敬子(指揮者)
<リヤ・ペトロヴァ 略歴>
2016年ニールセン国際コンクール優勝者。ブルガリアの音楽一家に生まれ、エリーザベト王妃音楽院でデュメイに、アイスラー音楽大学でヴァイトハースに、ローザンヌ音楽院でカプソンに師事。パリ管、フランス放送フィル等と共演。2021年、「ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲ほか」をリリース。パリ在住。(ラ・フォル・ジュルネ広報より)
・20:00 〜 21:00 ホールB5(1) マスタークラス
[講師]アンヌ・ケフェレック(ピアノ)
[曲目]シューベルト: ピアノ・ソナタ第17番ニ長調 D850 から 第1楽章
公演ではなく、指定の曲を弾いた生徒(音大生)に対して、ピアニストの講師が指導、教授する催しであった。
*歴史を彩ったクラシック音楽家列像
会場で販売していたラ・フォル・ジュルネ音楽祭2024、30周年記念盤「オリジン~7世紀にわたる音楽の旅」と称したCD(2枚組)を購入した。
これまでの音楽祭に登場した、あるいは関連ある作曲家や作品を、「オリジン」のテーマに即した内容としている。
中世ノートルダム楽派のポリフォニー音楽の作曲家、ペロタン「祝福された胎児」(抜粋)から、バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、ドヴォルザーク、ブラームスの曲を含め、メキシコ人の現代音楽作曲家のA・マルケス「ダンソンno.2」までを、摘まみ選択したものである。
そのジャケットには、その時代を彩った作曲家、その関係者の肖像画を羅列してある。音楽の教科書や関連書で見たことのあるモーツァルトやベートーヴェンなど有名な人物もいるが、まったく見たこともない(聞いたこともない)人物もいる。(写真)
さて、何人知っているだろうか?
参考までに、以下にその解答を記しておく(名前の順は、左から右へ)。
①アントニオ・ヴィヴァルディ
②ヨハン・セバンチャン・バッハ
③ヨーゼフ・ハイドン
④ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
⑤ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
⑥ルイーズ・ファランク
⑦フランツ・シューベルト
⑧ファニー・メンデルスゾーン
⑨フレデリック・ショパン
⑩クララ・シューマン
⑪モーリス・ラヴェル
⑫ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー
⑬セルゲイ・ラフマニノフ
⑭メラニー・ボニス
⑮イーゴリ・ストラヴィンスキー
⑯ヨハネス・ブラームス
⑰ガブリエル・フォーレ
⑱ジョージ・ガーシュウィン
⑲ジェルメーヌ・タイユフェール
⑳フランツ・リスト
㉑ナディア・ブーランジェ
㉒フィリップ・グラス