「逝きし日の面影」(平凡社)という、2000年に和辻哲郎文化賞を得た興味深い本がある。明治以降の日本の近代化とともに、一つの文明が死んだと唱える、当時日本に滞在していた外国人の書いた述回を丹念に拾って構築した日本人論である。
この著者である渡辺京二による、その後の書が「黒船前夜」(洋泉社)で、第37回大佛次郎賞を得た。
ペリーが浦賀にやってきて開国を迫る100年ほども前から、ロシアの船がシベリアを越えて、しばしば樺太、千島、北海道近海に出没していた。当時は、蝦夷(えぞ)地といわれたこの方面は、幕府にとってもまだ不鮮明な領域であった。
その蝦夷地で、松前藩とアイヌとロシアの交流と軋轢があった。松前藩は幕府の了解を得て交渉・交流することになるが、アイヌと独自の交易も行っていた。
蝦夷地を通して、ロシアは日本に交易を求める。すなはち、開国である。
松前藩および幕府は、危機意識を持ちながらも、のらりくらりと結論を先延ばしにする。その時、蝦夷では何が行われていたのか?
もともと、蝦夷(えみし)という記述は、歴史には古くから表われている。7世紀から9世紀にかけて大和朝廷によってしばしば討伐された蝦夷とは、どういう人たちだったのか。
最初、「蝦夷」は「えみし」と呼んでいたが、のちに「えびす」となり、「えぞ」と呼ぶようになったのはなぜか。「えみし」は辺境の日本人だったのか、それともいわゆるアイヌの人だったのか、はっきりした記述はない。
本書は、アイヌ民族を梅原猛の説を用いて、日本人論にまで言及している。
話の本題は、ロシアが日本に交易を求めてきたことである。
しかし、双方警戒して話は進展しない。しかも舞台は、いまだ全体像が掴めていない蝦夷地である。樺太(サハリン)も、間宮林蔵の樺太・海峡航海まで大陸からの半島だと考えられていた時代である。
最大の障壁は、日本には長崎でのオランダ以外に、外国との交易を禁じているというネックがあったし、ロシアは日本の武力が不明で、リスクを犯してまで交易をするメリットがあるかどうかが不透明であった。
そのロシア人と日本人との克明なやりとりが、アイヌという媒体を通して、蝦夷の歴史を鮮明にさせている。
夥しい資料を基に、ロシア人の日本に対する見方や通訳の本音、ロシア人と日本人の庶民との接触など、歴史の表舞台に表われていない、興味深い内容となっている。
まだ、ロシアも日本も領土拡張を目論んでいない、帝国主義前夜の、ある意味では良き時代の蝦夷史である。
この著者である渡辺京二による、その後の書が「黒船前夜」(洋泉社)で、第37回大佛次郎賞を得た。
ペリーが浦賀にやってきて開国を迫る100年ほども前から、ロシアの船がシベリアを越えて、しばしば樺太、千島、北海道近海に出没していた。当時は、蝦夷(えぞ)地といわれたこの方面は、幕府にとってもまだ不鮮明な領域であった。
その蝦夷地で、松前藩とアイヌとロシアの交流と軋轢があった。松前藩は幕府の了解を得て交渉・交流することになるが、アイヌと独自の交易も行っていた。
蝦夷地を通して、ロシアは日本に交易を求める。すなはち、開国である。
松前藩および幕府は、危機意識を持ちながらも、のらりくらりと結論を先延ばしにする。その時、蝦夷では何が行われていたのか?
もともと、蝦夷(えみし)という記述は、歴史には古くから表われている。7世紀から9世紀にかけて大和朝廷によってしばしば討伐された蝦夷とは、どういう人たちだったのか。
最初、「蝦夷」は「えみし」と呼んでいたが、のちに「えびす」となり、「えぞ」と呼ぶようになったのはなぜか。「えみし」は辺境の日本人だったのか、それともいわゆるアイヌの人だったのか、はっきりした記述はない。
本書は、アイヌ民族を梅原猛の説を用いて、日本人論にまで言及している。
話の本題は、ロシアが日本に交易を求めてきたことである。
しかし、双方警戒して話は進展しない。しかも舞台は、いまだ全体像が掴めていない蝦夷地である。樺太(サハリン)も、間宮林蔵の樺太・海峡航海まで大陸からの半島だと考えられていた時代である。
最大の障壁は、日本には長崎でのオランダ以外に、外国との交易を禁じているというネックがあったし、ロシアは日本の武力が不明で、リスクを犯してまで交易をするメリットがあるかどうかが不透明であった。
そのロシア人と日本人との克明なやりとりが、アイヌという媒体を通して、蝦夷の歴史を鮮明にさせている。
夥しい資料を基に、ロシア人の日本に対する見方や通訳の本音、ロシア人と日本人の庶民との接触など、歴史の表舞台に表われていない、興味深い内容となっている。
まだ、ロシアも日本も領土拡張を目論んでいない、帝国主義前夜の、ある意味では良き時代の蝦夷史である。












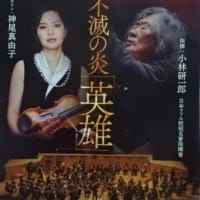

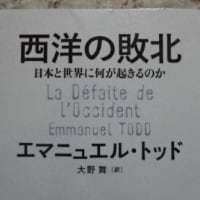










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます