2010.11.24(Wed) 両角 岳彦


毎年この時期になると、「カー・オブ・ザ・イヤー決定!」というニュースがメディアの片隅を賑わす。
しかし、こうした「イヤーカー」選びイベントは、今となってはその役割を自ら放棄した状況を続けている。したがって、黙殺していただいてかまわない。
かつて日本でこの催しを立ち上げた出版社の中で事務方を担当し、その後、自らも選考委員に名を連ねたことのある者として、今回はその内情を語っておきたい。「技術立国論」としては枝葉末節の話ではあるけれども、これもまた日本的な事象の一例、ということで。
【元々は「年男」「年女」を選ぶ内輪のお祭りだった】
元々日本で「カー・オブ・ザ・イヤー」というタイトルを与えるクルマを1年に1つだけ選ぼう、という催しを始めたのは、今はなき「モーターファン」誌(1995年休刊)であった。
その第1回は70年。この年の秋、東京モーターショーのシーズンまでに出た新型車を選考の対象とし、年が改まる頃までに決定・発表するので「1970-1971年次」とする、というのも、この最初の「イヤーカー選び」からの決まりごとだ。
当時は、モーターファン誌の「ロードテスト」(当時としては相当に緻密かつ広範な計測項目を網羅していた)を考案・実施していた大学の教授陣、そして執筆者の方々が選考にあたり、最終選考会議では投票の前に応援演説あり、討論ありで、和気あいあいと進められていたものである。
私自身は、その始まりから10年近く経とうという時期に、新米編集者として会議の裏方として採点の計算やら何やらのお手伝いをするところから関わりが始まった。当時の最終選考会議の会場は、まもなく姿を消す赤坂プリンスホテル旧館の一室が定例だった。
その当時、選考委員のリーダー格でもあった東京大学の平尾収教授が言われたことが今でも記憶に残っている。
「これはね、毎年いろいろなクルマに触れる機会がある我々が、言うならば『年男』『年女』を選ぶ、内輪の『お祭り』なんだよ」
そして、平尾先生発案の選考方法が「プラスマイナス5点法」。
単純に考えれば、「年男選びは選考委員が各自1票を投じて、その票数が最も多いものに決めればいいのでは」となる。しかし、単記1票方式では、人々と社会がクルマに求める多様な価値観が反映されにくい。
そこで平尾流思考法を駆使して、新たな採点法が考案された。それぞれの選考対象車に対して、「標準レベル」からどのくらい優れているか、あるいは逆に「これはちょっと・・・」と考えるかを、最大5点の範囲で表現して採点する。それを集計したところに、複数の価値観を反映した「年男」「年女」が現れるというわけだ。
ただし、「年男にマイナス点を付けるのは印象が悪いね」ということで、10点を基点にして15~5点の範囲で採点していた。選考委員が25人だとしたら(モーターファン時代は後期でもそのくらい)、最終選考に残ったクルマたちは250点に対して最大375点~最小125点の評点を与えられる形になる。
【モーターファン」の手を離れたことが「迷走」の始まり】
このモーターファン/カー・オブ・ザ・イヤーがちょうど10年を経過した時、モーターファンを発行する三栄書房の当時の社主、鈴木脩己氏が、「こうしたイベントは1雑誌が主催すべきものではない」と提唱し、その理念に沿って動き出した。
当時、主要な自動車雑誌のいくつかが、同様の年間賞を始めて、乱立の様相を見せ始めていたこともある。
モーターファン/カー・オブ・ザ・イヤーが元々ひな形にしたのは、欧州の「European Car of the Year」。この欧州版Car of the Yearは、63年にオランダの「Autovisie」誌が始め、その10年後に英独仏伊などの雑誌が参加して「汎ヨーロッパ」になった。モーターファンから汎日本へという思いが生まれた背景には、これも多分に意識されていた。
しかし、今振り返れば、これが「迷走」の始まりだった。
ある種、理想主義だった当時の三栄書房とモーターファンの手を離れたことで、そこに何らかの思惑を抱く人々が集まってくることになった。
自動車メディアに関わる「もの書き業」にとって、「試乗会に招待してもらえる」「試乗車を借りられる」、そして何より「カー・オブ・ザ・イヤー選考委員」という肩書を名乗れることをメリットだと考える人士が少なくないことは想像に難くないだろう。それ以上に、こうした賞典の主催者側に立つことで様々な権益を手にできると考える人々も決して少なくはない。
一応は「実行委員会」なるものがあり、それは雑誌、新聞、放送などの媒体によって構成されることになってはいるけれども、その中でも限られたメンバーが運営の方向を決めることになるのは世の常ではある。
例えば選考委員の人選ひとつ取っても「媒体からの推薦」によることになってはいるのだけれども、「汎日本」になってから数年を経ずして、「実行委員会」の投票による「過半数の信任」がないと選ばれない、という形に変えた。
これは実行委員が、各媒体から推薦された選考委員候補者に「○×」を付けるという行為を非公開で行ったところから始まっている。
つまり、カー・オブ・ザ・イヤー選考委員に「なりたい/あり続けたい」と思う人がいたとしたら、実行委員会の中核メンバーの「覚えがめでたい」ことに意を砕く必要がある、というわけだ。
それ以上に、毎年、「カー・オブ・ザ・イヤー」というタイトルを自動車メーカーに授与するという行為に隠然たる影響力を行使できる、ということの価値が大きい、と考える人士が現れる。これも、まあ、しかたのないことではある。
【新たな採点方法に潜む「トリック」とは】
数十名の選考委員による採点の合算なのだから、「そう簡単に選考結果を左右することはできないのでは?」と思われるかもしれない。しかし、その採点方式に鍵がある。
モーターファン/カー・オブ・ザ・イヤーが「プラスマイナス5点法」であったことの理念は、先ほども紹介したとおりだ。しかし、その理念も方法も俗人にはなかなか分かりにくい。
そこで「汎日本」体制に移行した後からは、10に絞った最終候補車を採点するにあたって・・・、
・選考委員各人の「持ち点」は25点
・どれか1車に必ず最高点10点を配する(現在は1車のみ)
・持ち点を5車に配分する
というルールが決められた。
この採点方法だと、まず「パーソナルベストカー」に10点を割り当てると、残りは15点。それを4車に振り分ける。ふつうに考えても、そこからの配点はかなり難しい。
さらに、ここにトリックを忍ばせることが可能なのだ。
例えば今年の「日本カー・オブ・ザ・イヤー2010-2011」で僅差のトップ争いとなったホンダ「CR-Z」とフォルクスワーゲン「ポロ」に、各委員がどんな採点をしたかを見わたしてみよう。
60人の選考委員の中でフルポイントの10点を投じた人数は、CR-Zが25人、ポロが20人。単記1票方式なら簡単にCR-Zで決まりだが、それぞれの獲得得点はCR-Zが406点、ポロが397点という僅差である。
ここはどうやら平尾流採点方式の名残りで、少なくとも現状の選考委員群の価値観が表現されたと見ることもできる。
さらに細かく見てゆくと、面白い傾向が浮かび上がる。CR-Zに10点を投じながらポロには4点以下しか入れなかった委員は11人。逆に、ポロに10点を投じながらCR-Zには4点以下しか入れなかった委員は8人。
しかもその中で、対抗車に「0点」を付けたのは、CR-Z満点組に2人、ポロ満点組では1人いた。この「マイナス点」の量で勝負が決まった、と言ってもいい。
もちろん価値観の差によって、「一方が優れていて、他方はマイナスの価値しかない」と判断する人がいるのは当然である。だが、今年の「年男」として、CR-Zとポロのどちらかが「標準レベル以下であった」と判定する評価基準はどこにあるのか、と首を傾げたくなる。
【今年の「CR-Z」は薄氷の勝利だった?】
以前は、採点内容だけを公表して、各選考委員の個人名は出なかったので、もっと露骨に「10点 or 0点」攻撃が行われた年もあった。
自動車メーカーの広報担当者たちがなんとかカー・オブ・ザ・イヤーを取りたいと考えれば、自社の車種に10点を入れつつ、対抗する存在になりそうな車種には「0点」と記入してくれる選考委員を数人確保すれば、「票読み」は相当に固いものになる。
さすがに誰がどういう採点をしたかが公表されるようになって、そこまで露骨な採点は見られなくはなった。だが、対抗する存在に配点はしつつ、1~2点に抑える委員を何人か確保すれば同様の効果は得られる。
その意味で今年のCR-Zは「薄氷の勝利」だったと見ることもできそうだ。いや、自動車メーカーがカー・オブ・ザ・イヤーのタイトルを手にすることにもはや価値を見出さなくなりつつあり、「軽くプッシュする程度で取れればよし」という感覚になっているのだろうと思う。
いずれにしても、こうした数字のトリックに気づき、そこに自らの影響力を投影することで、自動車メーカー広報との間で何らかの利益誘導を画策する人士が出てきても不思議はない。もちろん個々の選考委員の中でも、配点を決める時に何らかの思惑が交錯する人は少なくないはずだ。
私自身は、モーターファン誌を離れた後の80年代後半から何年間か、選考委員をさせていただいていた時期に、自らの評価内容を8分野に分け、特に「ものづくりのコンセプト」「移動空間としての資質の基本になるパッケージング(空間構成)」を2倍評点として、全体を100点満点で採点する方法を考案。その採点に基づいて配点を決めていた。
それが後に『本音のクルマ選び』というシリーズの核となる、市販車のほとんどを網羅した採点表へとつながっていったのだが。そうした何がしかの製品評価を行った結果から配点を決めている選考委員は、おそらくいないのではないかと思う。
そんなわけで、カー・オブ・ザ・イヤーというタイトルは、様々な価値観を集積して決まる「年男」「年女」とは言えないものへと、みるみる変質してしまった。
「広報オブ・ザ・イヤー」と言われても仕方がない状況
選考委員の多数に良い印象を与え、配点に何らかの影響をもたらすことを期待して(もっと露骨な意図と結果も含めて)、自動車メーカーの広報部門も様々に動く。
複数の候補車がある年に「ウチは今年○○でお願いします」とか、さらには「今年は諦めていますから、来年よろしく」などという「お願い」はざらのようである。幸いにして(?)、私が選考委員の時代にそういう言葉を直接言われたことはない。扱いにくい人、であるらしい。
バブル期には派手な接待が常態化し、海外試乗会、国内観光地への夫人同伴の試乗会招待なども実際に行われた。最近では逆に、仕事の舞台が縮小しつつある媒体・個人の方が自動車メーカー(広報)の思いを忖度(そんたく)する様子も感じられ、口さがない人々に「広報オブ・ザ・イヤー」じゃないか、と言われても仕方がないような状況が続く。
歴代の受賞車リストをながめても、スズキ、ダイハツの姿はなく、バブル崩壊から景気減退が続く中、自動車メーカーも経費削減を徹底する昨今では、多少なりとも体力を残すトヨタ自動車、ホンダの受賞が極端に増えている。
輸入車はもちろん論外である。日本カー・オブ・ザ・イヤーはもう10年近く前から、国産車と輸入車を分けずに選考対象としたにもかかわらず、まだ一度も輸入車の受賞車は出ていない。
こうした流れの中で、自動車メディアの衰勢も著しい。技術文明の進化、深化、変化に対応するだけの知識も努力もなく、クルマに乗った話さえすれば雑誌が売れていた時代の意識と方法論に頼ってきた。しかも、取材や編集に関わる人々の知的レベルは下がる一方。これは自動車専門メディアだけでなく、日本の出版界全体に広がる傾向だ。
自動車メーカーの広報部門は、新聞と放送関係、あるいは企業広報の担当と、専門誌を中心に対応する製品広報の2分野に分かれていることが多いのだが、当然のように会社内で彼らの業務とその成果に対する関心も薄れ、企業人としてモチベーションが低下するのもやむを得ない。
その中で、今「カー・オブ・ザ・イヤーを取る」ことが多少は意味を持つのかどうか。
【基本理念に立ちもどるためにRJCが設立されたが・・・】
話を日本カー・オブ・ザ・イヤーが始まって10年ほどが経過した頃に戻す。
実行委員会内外の様々な政治的駆け引きがあからさまに現われて来る一方で、タイトルの重みが増すにつれて、ホテルなどを借りた最終候補車両の試乗会、派手な授賞イベントなどを開催し、自動車メーカーにも多くの負担を求める「肥大化」の状況が関係者の目にも明らかに見えてきた。
その中で、前述の媒体推薦の選考委員を実行委員会がさらにふるいにかける、というやり方も始まった。そこで分裂が起こる。
日本カー・オブ・ザ・イヤーから「スピンオフ」した人々が再結集し、その中では、「カー・オブ・ザ・イヤーの基本理念に戻って手弁当で年男選びをしよう」「より幅広い人々を選考に加えよう」という方針が語られていた。
そのメンバーには、平尾先生や私の恩師を含めて、旧モーターファン/カー・オブ・ザ・イヤー時代からの学識経験者も加わっていたし、事務局が三栄書房の中に置かれたこともあって、私も発起人に誘われ、一度は名を連ねることにした。
しかし、いざ動き出すと、「日本自動車研究所のテストコースを借りて最終選考会をしよう。そこにメーカーの開発担当者にも出席してもらう」「授賞パーティーもやろう」「自動車メーカーには、選考メンバーに試乗してもらうなどの便宜を図ってもらおう」といった方向へと進み出してしまう。
ここで私は、初年次の実施前に離脱した。それ以後、この種の選考には関わることがないまま過ごしている。
結局、この「第2のカー・オブ・ザ・イヤー」は「日本自動車研究者・ジャーナリスト会議(RJC)」として活動を続け、今日に至る。
【スズキ「スイフト」はどうやって選ばれたのか?】
今年、2010-2011年次の「RJCカーオブザイヤー」はスズキ「スイフト」とのこと。こちらは最初から国産車に「カーオブザイヤー」、輸入車には「カーオブザイヤー(インポート)」を授与するという形を取っていて、そちらの受賞車はポロ。
先行した日本カー・オブ・ザ・イヤーの方も少し遅れてインポートカー部門を作って追従。前述のように2002-2003年次からはカー・オブ・ザ・イヤー選考対象にも加えている。
そういえば、RJCの採点方法が今はどうなっているか、私は知らない。今回、そのウェブサイトを少し見て回ったのだが、採点方法に対する記述、選考委員それぞれの採点内容を見つけることはできなかった。
とりあえず、この2つのカー・オブ・ザ・イヤーの歴代受賞車を本コラムの最終ページ(8ページ目)に表としてまとめておいたので、興味のある方は比較しつつご覧いただきたい。
ちょうど20年、オーバーラップしつつ続いてきた中で、両方の「ベスト」が一致したのは2回しかない。
ついでに、私自身の「パーソナルベストカー」も記しておいた。こちらは一応、私なりの基準に沿った選択であり、その多くは前述の「両角流」移動空間・工業製品としての資質採点に基づくものなので、見比べていただきたい。
もはや意味がない3つの「イヤーカー」
さらに業界内部の状況について説明を加えるなら、三栄書房は経営陣がすっかり入れ替わり、今や「日本カー・オブ・ザ・イヤー」の実行委員長に新経営陣の1人が就いている。
一方、RJCとは別に、そのメンバーの一部も含めて「日本自動車殿堂(JHAFA)」という組織が2001年に設立され、歴史的なクルマ・人を「殿堂」に加えて記憶に残すという活動に加え、カーオブザイヤー(国産車/輸入車)、デザイン、テクノロジーを顕彰している。
この「殿堂」の会員に名を連ねるのは錚々たる方々で、カーオブザイヤーの選考委員も、ほとんどが大学系の学識経験者である。そして選考方法も「客観化」をうたっている。
しかし、私も選考委員の過半は存じあげているが、この方々に、現実のクルマの開発を手がけたり、実車に触れて資質や技術を体感し、分析する経験を積んでいるのは、14名中2~3名しかいない。他の方々は机上論や自らの研究内容に照らして判断されるわけで、イヤーカー選びとしての妥当性はなかなか難しい、と言わざるを得ない。
かくして、日本で行われている「カー・オブ・ザ・イヤー」選びの結果は、もはや社会的に、あるいは自動車産業において意味のあるものではなく、黙殺していただいてかまわない、という最初の話に行き着くのである。
工業デザインや製品・サービスに対して評価・顕彰する様々な賞の多くも、ここまで混迷して無意味なものではないけれども、最近は同じように選考プロセスそのものが曖昧であったり、評価の軸がブレていたりする。
しかし、「最良のプロダクツ」を選ぶのではなく(それならば、明確な視点を持つ個人かグループによる判定の方が説得力を持つ)、「年男」「年女」を選ぶお祭りだと考えれば、それはそれでいいのかな、と思えるに違いない。そうやって納得できるようなものではあってほしいと思う。
そういえば、 モーターファン時代から数えて、「日本カー・オブ・ザ・イヤー」側だけを含めても6度のイヤーカータイトルを獲得したホンダ「シビック」という車名が、日本市場から消える、というニュースも伝えられている。
ホンダという自動車メーカーが考え、選んできた「世界企業としてのものづくりの道筋」が、一度は成功したものの、修正を怠った結果、次第に齟齬が現れ、それに対して最も安易な方策を採った、と見ることができる。そして、それは必ずしも「最適解」ではない、と私は考える。これについてはまた次の機会に。




毎年この時期になると、「カー・オブ・ザ・イヤー決定!」というニュースがメディアの片隅を賑わす。
しかし、こうした「イヤーカー」選びイベントは、今となってはその役割を自ら放棄した状況を続けている。したがって、黙殺していただいてかまわない。
かつて日本でこの催しを立ち上げた出版社の中で事務方を担当し、その後、自らも選考委員に名を連ねたことのある者として、今回はその内情を語っておきたい。「技術立国論」としては枝葉末節の話ではあるけれども、これもまた日本的な事象の一例、ということで。
【元々は「年男」「年女」を選ぶ内輪のお祭りだった】
元々日本で「カー・オブ・ザ・イヤー」というタイトルを与えるクルマを1年に1つだけ選ぼう、という催しを始めたのは、今はなき「モーターファン」誌(1995年休刊)であった。
その第1回は70年。この年の秋、東京モーターショーのシーズンまでに出た新型車を選考の対象とし、年が改まる頃までに決定・発表するので「1970-1971年次」とする、というのも、この最初の「イヤーカー選び」からの決まりごとだ。
当時は、モーターファン誌の「ロードテスト」(当時としては相当に緻密かつ広範な計測項目を網羅していた)を考案・実施していた大学の教授陣、そして執筆者の方々が選考にあたり、最終選考会議では投票の前に応援演説あり、討論ありで、和気あいあいと進められていたものである。
私自身は、その始まりから10年近く経とうという時期に、新米編集者として会議の裏方として採点の計算やら何やらのお手伝いをするところから関わりが始まった。当時の最終選考会議の会場は、まもなく姿を消す赤坂プリンスホテル旧館の一室が定例だった。
その当時、選考委員のリーダー格でもあった東京大学の平尾収教授が言われたことが今でも記憶に残っている。
「これはね、毎年いろいろなクルマに触れる機会がある我々が、言うならば『年男』『年女』を選ぶ、内輪の『お祭り』なんだよ」
そして、平尾先生発案の選考方法が「プラスマイナス5点法」。
単純に考えれば、「年男選びは選考委員が各自1票を投じて、その票数が最も多いものに決めればいいのでは」となる。しかし、単記1票方式では、人々と社会がクルマに求める多様な価値観が反映されにくい。
そこで平尾流思考法を駆使して、新たな採点法が考案された。それぞれの選考対象車に対して、「標準レベル」からどのくらい優れているか、あるいは逆に「これはちょっと・・・」と考えるかを、最大5点の範囲で表現して採点する。それを集計したところに、複数の価値観を反映した「年男」「年女」が現れるというわけだ。
ただし、「年男にマイナス点を付けるのは印象が悪いね」ということで、10点を基点にして15~5点の範囲で採点していた。選考委員が25人だとしたら(モーターファン時代は後期でもそのくらい)、最終選考に残ったクルマたちは250点に対して最大375点~最小125点の評点を与えられる形になる。
【モーターファン」の手を離れたことが「迷走」の始まり】
このモーターファン/カー・オブ・ザ・イヤーがちょうど10年を経過した時、モーターファンを発行する三栄書房の当時の社主、鈴木脩己氏が、「こうしたイベントは1雑誌が主催すべきものではない」と提唱し、その理念に沿って動き出した。
当時、主要な自動車雑誌のいくつかが、同様の年間賞を始めて、乱立の様相を見せ始めていたこともある。
モーターファン/カー・オブ・ザ・イヤーが元々ひな形にしたのは、欧州の「European Car of the Year」。この欧州版Car of the Yearは、63年にオランダの「Autovisie」誌が始め、その10年後に英独仏伊などの雑誌が参加して「汎ヨーロッパ」になった。モーターファンから汎日本へという思いが生まれた背景には、これも多分に意識されていた。
しかし、今振り返れば、これが「迷走」の始まりだった。
ある種、理想主義だった当時の三栄書房とモーターファンの手を離れたことで、そこに何らかの思惑を抱く人々が集まってくることになった。
自動車メディアに関わる「もの書き業」にとって、「試乗会に招待してもらえる」「試乗車を借りられる」、そして何より「カー・オブ・ザ・イヤー選考委員」という肩書を名乗れることをメリットだと考える人士が少なくないことは想像に難くないだろう。それ以上に、こうした賞典の主催者側に立つことで様々な権益を手にできると考える人々も決して少なくはない。
一応は「実行委員会」なるものがあり、それは雑誌、新聞、放送などの媒体によって構成されることになってはいるけれども、その中でも限られたメンバーが運営の方向を決めることになるのは世の常ではある。
例えば選考委員の人選ひとつ取っても「媒体からの推薦」によることになってはいるのだけれども、「汎日本」になってから数年を経ずして、「実行委員会」の投票による「過半数の信任」がないと選ばれない、という形に変えた。
これは実行委員が、各媒体から推薦された選考委員候補者に「○×」を付けるという行為を非公開で行ったところから始まっている。
つまり、カー・オブ・ザ・イヤー選考委員に「なりたい/あり続けたい」と思う人がいたとしたら、実行委員会の中核メンバーの「覚えがめでたい」ことに意を砕く必要がある、というわけだ。
それ以上に、毎年、「カー・オブ・ザ・イヤー」というタイトルを自動車メーカーに授与するという行為に隠然たる影響力を行使できる、ということの価値が大きい、と考える人士が現れる。これも、まあ、しかたのないことではある。
【新たな採点方法に潜む「トリック」とは】
数十名の選考委員による採点の合算なのだから、「そう簡単に選考結果を左右することはできないのでは?」と思われるかもしれない。しかし、その採点方式に鍵がある。
モーターファン/カー・オブ・ザ・イヤーが「プラスマイナス5点法」であったことの理念は、先ほども紹介したとおりだ。しかし、その理念も方法も俗人にはなかなか分かりにくい。
そこで「汎日本」体制に移行した後からは、10に絞った最終候補車を採点するにあたって・・・、
・選考委員各人の「持ち点」は25点
・どれか1車に必ず最高点10点を配する(現在は1車のみ)
・持ち点を5車に配分する
というルールが決められた。
この採点方法だと、まず「パーソナルベストカー」に10点を割り当てると、残りは15点。それを4車に振り分ける。ふつうに考えても、そこからの配点はかなり難しい。
さらに、ここにトリックを忍ばせることが可能なのだ。
例えば今年の「日本カー・オブ・ザ・イヤー2010-2011」で僅差のトップ争いとなったホンダ「CR-Z」とフォルクスワーゲン「ポロ」に、各委員がどんな採点をしたかを見わたしてみよう。
60人の選考委員の中でフルポイントの10点を投じた人数は、CR-Zが25人、ポロが20人。単記1票方式なら簡単にCR-Zで決まりだが、それぞれの獲得得点はCR-Zが406点、ポロが397点という僅差である。
ここはどうやら平尾流採点方式の名残りで、少なくとも現状の選考委員群の価値観が表現されたと見ることもできる。
さらに細かく見てゆくと、面白い傾向が浮かび上がる。CR-Zに10点を投じながらポロには4点以下しか入れなかった委員は11人。逆に、ポロに10点を投じながらCR-Zには4点以下しか入れなかった委員は8人。
しかもその中で、対抗車に「0点」を付けたのは、CR-Z満点組に2人、ポロ満点組では1人いた。この「マイナス点」の量で勝負が決まった、と言ってもいい。
もちろん価値観の差によって、「一方が優れていて、他方はマイナスの価値しかない」と判断する人がいるのは当然である。だが、今年の「年男」として、CR-Zとポロのどちらかが「標準レベル以下であった」と判定する評価基準はどこにあるのか、と首を傾げたくなる。
【今年の「CR-Z」は薄氷の勝利だった?】
以前は、採点内容だけを公表して、各選考委員の個人名は出なかったので、もっと露骨に「10点 or 0点」攻撃が行われた年もあった。
自動車メーカーの広報担当者たちがなんとかカー・オブ・ザ・イヤーを取りたいと考えれば、自社の車種に10点を入れつつ、対抗する存在になりそうな車種には「0点」と記入してくれる選考委員を数人確保すれば、「票読み」は相当に固いものになる。
さすがに誰がどういう採点をしたかが公表されるようになって、そこまで露骨な採点は見られなくはなった。だが、対抗する存在に配点はしつつ、1~2点に抑える委員を何人か確保すれば同様の効果は得られる。
その意味で今年のCR-Zは「薄氷の勝利」だったと見ることもできそうだ。いや、自動車メーカーがカー・オブ・ザ・イヤーのタイトルを手にすることにもはや価値を見出さなくなりつつあり、「軽くプッシュする程度で取れればよし」という感覚になっているのだろうと思う。
いずれにしても、こうした数字のトリックに気づき、そこに自らの影響力を投影することで、自動車メーカー広報との間で何らかの利益誘導を画策する人士が出てきても不思議はない。もちろん個々の選考委員の中でも、配点を決める時に何らかの思惑が交錯する人は少なくないはずだ。
私自身は、モーターファン誌を離れた後の80年代後半から何年間か、選考委員をさせていただいていた時期に、自らの評価内容を8分野に分け、特に「ものづくりのコンセプト」「移動空間としての資質の基本になるパッケージング(空間構成)」を2倍評点として、全体を100点満点で採点する方法を考案。その採点に基づいて配点を決めていた。
それが後に『本音のクルマ選び』というシリーズの核となる、市販車のほとんどを網羅した採点表へとつながっていったのだが。そうした何がしかの製品評価を行った結果から配点を決めている選考委員は、おそらくいないのではないかと思う。
そんなわけで、カー・オブ・ザ・イヤーというタイトルは、様々な価値観を集積して決まる「年男」「年女」とは言えないものへと、みるみる変質してしまった。
「広報オブ・ザ・イヤー」と言われても仕方がない状況
選考委員の多数に良い印象を与え、配点に何らかの影響をもたらすことを期待して(もっと露骨な意図と結果も含めて)、自動車メーカーの広報部門も様々に動く。
複数の候補車がある年に「ウチは今年○○でお願いします」とか、さらには「今年は諦めていますから、来年よろしく」などという「お願い」はざらのようである。幸いにして(?)、私が選考委員の時代にそういう言葉を直接言われたことはない。扱いにくい人、であるらしい。
バブル期には派手な接待が常態化し、海外試乗会、国内観光地への夫人同伴の試乗会招待なども実際に行われた。最近では逆に、仕事の舞台が縮小しつつある媒体・個人の方が自動車メーカー(広報)の思いを忖度(そんたく)する様子も感じられ、口さがない人々に「広報オブ・ザ・イヤー」じゃないか、と言われても仕方がないような状況が続く。
歴代の受賞車リストをながめても、スズキ、ダイハツの姿はなく、バブル崩壊から景気減退が続く中、自動車メーカーも経費削減を徹底する昨今では、多少なりとも体力を残すトヨタ自動車、ホンダの受賞が極端に増えている。
輸入車はもちろん論外である。日本カー・オブ・ザ・イヤーはもう10年近く前から、国産車と輸入車を分けずに選考対象としたにもかかわらず、まだ一度も輸入車の受賞車は出ていない。
こうした流れの中で、自動車メディアの衰勢も著しい。技術文明の進化、深化、変化に対応するだけの知識も努力もなく、クルマに乗った話さえすれば雑誌が売れていた時代の意識と方法論に頼ってきた。しかも、取材や編集に関わる人々の知的レベルは下がる一方。これは自動車専門メディアだけでなく、日本の出版界全体に広がる傾向だ。
自動車メーカーの広報部門は、新聞と放送関係、あるいは企業広報の担当と、専門誌を中心に対応する製品広報の2分野に分かれていることが多いのだが、当然のように会社内で彼らの業務とその成果に対する関心も薄れ、企業人としてモチベーションが低下するのもやむを得ない。
その中で、今「カー・オブ・ザ・イヤーを取る」ことが多少は意味を持つのかどうか。
【基本理念に立ちもどるためにRJCが設立されたが・・・】
話を日本カー・オブ・ザ・イヤーが始まって10年ほどが経過した頃に戻す。
実行委員会内外の様々な政治的駆け引きがあからさまに現われて来る一方で、タイトルの重みが増すにつれて、ホテルなどを借りた最終候補車両の試乗会、派手な授賞イベントなどを開催し、自動車メーカーにも多くの負担を求める「肥大化」の状況が関係者の目にも明らかに見えてきた。
その中で、前述の媒体推薦の選考委員を実行委員会がさらにふるいにかける、というやり方も始まった。そこで分裂が起こる。
日本カー・オブ・ザ・イヤーから「スピンオフ」した人々が再結集し、その中では、「カー・オブ・ザ・イヤーの基本理念に戻って手弁当で年男選びをしよう」「より幅広い人々を選考に加えよう」という方針が語られていた。
そのメンバーには、平尾先生や私の恩師を含めて、旧モーターファン/カー・オブ・ザ・イヤー時代からの学識経験者も加わっていたし、事務局が三栄書房の中に置かれたこともあって、私も発起人に誘われ、一度は名を連ねることにした。
しかし、いざ動き出すと、「日本自動車研究所のテストコースを借りて最終選考会をしよう。そこにメーカーの開発担当者にも出席してもらう」「授賞パーティーもやろう」「自動車メーカーには、選考メンバーに試乗してもらうなどの便宜を図ってもらおう」といった方向へと進み出してしまう。
ここで私は、初年次の実施前に離脱した。それ以後、この種の選考には関わることがないまま過ごしている。
結局、この「第2のカー・オブ・ザ・イヤー」は「日本自動車研究者・ジャーナリスト会議(RJC)」として活動を続け、今日に至る。
【スズキ「スイフト」はどうやって選ばれたのか?】
今年、2010-2011年次の「RJCカーオブザイヤー」はスズキ「スイフト」とのこと。こちらは最初から国産車に「カーオブザイヤー」、輸入車には「カーオブザイヤー(インポート)」を授与するという形を取っていて、そちらの受賞車はポロ。
先行した日本カー・オブ・ザ・イヤーの方も少し遅れてインポートカー部門を作って追従。前述のように2002-2003年次からはカー・オブ・ザ・イヤー選考対象にも加えている。
そういえば、RJCの採点方法が今はどうなっているか、私は知らない。今回、そのウェブサイトを少し見て回ったのだが、採点方法に対する記述、選考委員それぞれの採点内容を見つけることはできなかった。
とりあえず、この2つのカー・オブ・ザ・イヤーの歴代受賞車を本コラムの最終ページ(8ページ目)に表としてまとめておいたので、興味のある方は比較しつつご覧いただきたい。
ちょうど20年、オーバーラップしつつ続いてきた中で、両方の「ベスト」が一致したのは2回しかない。
ついでに、私自身の「パーソナルベストカー」も記しておいた。こちらは一応、私なりの基準に沿った選択であり、その多くは前述の「両角流」移動空間・工業製品としての資質採点に基づくものなので、見比べていただきたい。
もはや意味がない3つの「イヤーカー」
さらに業界内部の状況について説明を加えるなら、三栄書房は経営陣がすっかり入れ替わり、今や「日本カー・オブ・ザ・イヤー」の実行委員長に新経営陣の1人が就いている。
一方、RJCとは別に、そのメンバーの一部も含めて「日本自動車殿堂(JHAFA)」という組織が2001年に設立され、歴史的なクルマ・人を「殿堂」に加えて記憶に残すという活動に加え、カーオブザイヤー(国産車/輸入車)、デザイン、テクノロジーを顕彰している。
この「殿堂」の会員に名を連ねるのは錚々たる方々で、カーオブザイヤーの選考委員も、ほとんどが大学系の学識経験者である。そして選考方法も「客観化」をうたっている。
しかし、私も選考委員の過半は存じあげているが、この方々に、現実のクルマの開発を手がけたり、実車に触れて資質や技術を体感し、分析する経験を積んでいるのは、14名中2~3名しかいない。他の方々は机上論や自らの研究内容に照らして判断されるわけで、イヤーカー選びとしての妥当性はなかなか難しい、と言わざるを得ない。
かくして、日本で行われている「カー・オブ・ザ・イヤー」選びの結果は、もはや社会的に、あるいは自動車産業において意味のあるものではなく、黙殺していただいてかまわない、という最初の話に行き着くのである。
工業デザインや製品・サービスに対して評価・顕彰する様々な賞の多くも、ここまで混迷して無意味なものではないけれども、最近は同じように選考プロセスそのものが曖昧であったり、評価の軸がブレていたりする。
しかし、「最良のプロダクツ」を選ぶのではなく(それならば、明確な視点を持つ個人かグループによる判定の方が説得力を持つ)、「年男」「年女」を選ぶお祭りだと考えれば、それはそれでいいのかな、と思えるに違いない。そうやって納得できるようなものではあってほしいと思う。
そういえば、 モーターファン時代から数えて、「日本カー・オブ・ザ・イヤー」側だけを含めても6度のイヤーカータイトルを獲得したホンダ「シビック」という車名が、日本市場から消える、というニュースも伝えられている。
ホンダという自動車メーカーが考え、選んできた「世界企業としてのものづくりの道筋」が、一度は成功したものの、修正を怠った結果、次第に齟齬が現れ、それに対して最も安易な方策を採った、と見ることができる。そして、それは必ずしも「最適解」ではない、と私は考える。これについてはまた次の機会に。












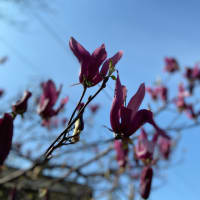









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます