
画像はコチラからお借りしました。
wedge 2010.4(リンク) 元上野動物園園長の中川志郎氏 インタビュー より引用
「今政権が、子育て支援や教育に力を入れています。それ自体は僕も賛成なんですが、どうもどうも親が働きやすくなったり、シュミの時間がとりやすくなったりすることが目的になっているように感じます。育てられる子供の側に立って政策がどういう意味を持つかという深い考察がないんじゃないか。生まれたばかりの子供が絶対的に必要としている母親を、遠ざける政策になっていないか」
子ども手当、保育所の増設、高校教育の無償化・・・。いずれの政策にも、子供を育てやすいとの大義があろうが、それらはおしなべて親にとって都合のよいものであり、むしろ子供にとってはマイナスになりかねないと、元上野動物園園長の中川志郎は危惧する。
中川はその半生を動物園に勤めて送り、数多くの動物の出産や育児に関わってきた。育児書も保育所もない動物たちの子育てからうかがえるのは、生物としての原点、言い換えれば個の成長や群れの安定を実現するために進化の過程で獲得してきた仕組みである。人間もまた動物の進化の結果として存在するのに、今はその原点を忘れつつある。
生物としての子育ての原点とは何だろうか。中川によれば、すべての生物には、どうしたら無益な争いを避けて共生できるかなど、長い歴史の中で積み重ねてきたノウハウが遺伝情報として記憶されている。それを発現させるには、生まれてからの、生物的学習、生態的学習という2段階の学習が必要になる。
「霊長類で言えば、絶対的な安心感があった子宮から生まれ出た子供に、子宮にいた時と同じような安心感を与えるのが、母親の抱擁や言葉かけです。その中で子供には自分を保護してくれるのが母親であり、自分は母親と同じ生き物であると刷り込まれます。こうした密着状態を通して、母親への絶対的な信頼感(原信頼)が生まれる。これが生物的学習です」
「原信頼があるから、母親の行動を真似たいという衝動が起きます。そうしていきる術を学んでいくのが生態的学習です。また、母親が一緒にいる人への信頼へと広がっていきます。信頼がなければ絆が生まれません。まず、母親への原信頼があり、次に父親へと絆を結び、祖父母や兄弟へと絆を結んでいきます。長じて集団に入るときも、母親という基地に帰れる安心感があるから踏み出せるんです」
「例えば、動物園の飼育係に育てられたサルは、どれだけ可愛がっても人間のやり方でしか育ちませんから、成長しても群れに入っていけなかったり、自分に子供が生まれた時にどう育てていいのかがわからなかったりして、トラブルを起こします」
母親がひたすらに抱いてくれることが子供に安心感を与え、それは保護する母への信頼を生む。原点ともいうべき信頼が、母親の行動を受け継ぐことにつながり、また家族や仲間との関係構築にもつながる。つまり、個体として生きるために必要な術、社会をつくるために必要な知恵の出発点が、生まれてすぐの母子の密着状態にあるということだ。
一方で父親は「そこにいることが重要です。存在そのものが安心感を与える」というのがその機能だという。「父親は母親よりも生物的にはつながりが細いので、母親が父親を頼っている、尊敬しているという2点がないと子供には伝わりません」と中川は言う。
考えてみれば、生物的学習から始まるプロセスは、子供がより安全に育ち、集団の中で生きていくために必要な仕組みとして、魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類という進化の過程で得られた最適解であったはずだ。なのに現代の人間は、子育てを「大人にとって」という視点から眺めようとしている。いきおい生物的学習や生態的学習に十分な時間を割くのは難しくなるだろう。
中川は、人間が他の動物と違うのは、生物的学習と生態的学習の先に体外脳があることだと言う。体外脳とは、個体が蓄えた知識や経験が、その個体の死とともにリセットされるのではなく、他の人に伝えるべく外部に集積していることを指す。人間は、書物や教育など自身の外にある”脳”から後付けで、「私はホモサピエンスである」「社会に出るためには相手との信頼関係が大事だ」と学ぶことだってできる。
だから、母子の接点は減ったとしても、子供には後で教育を与えればいい、何より親にとって仕事やシュミは大事だしと、考えるのも無理はない。
では体外脳で、生物としての本能的な部分はカバーできるのか?
「生物的学習と生態的学習が基盤となってはじめて、体外脳を正式に応用できます。今は最初の2つの段階を省略したまま、頭ばかり大きくなって、それを支える生物としての土壌が細まっていて、バランスが悪い状態です」
そもそも、教育によって大脳皮質に教え込まれたものを、大脳皮質で否定することは簡単だと、中川は指摘する。「殺すのはいけない」と教えても状況次第で真逆に振れることがある。一方、子供の頃に愛されたことで体に染み付いたものは、たやすくは変わらない。
「チンパンジーは4年おきに子供を生みます。子供は4歳になると、次に生まれてくる弟や妹を母親から借りて子守をします。弟や妹がいないときは、何も命じられていないのに、よその母親のところに行って頭を下げて、赤ちゃんを借りてくるんです。チンパンジーには育児書も道徳の時間もありません。道徳や倫理は頭で考えるものではなく、自然発生的な染み込んだものが表に出るということです」
両親に可愛がられた経験が、違う個体を慈しむ行動につながっている一例だろう。
「それに人間こそ、最初の密着状態を必要としているんですよ。人間の妊娠期間は霊長類の中でも一番長いし、赤ちゃんも相対的に大きい。ゴリラの赤ちゃんは1.5キロしかありませんから。しかも人間の赤ちゃんは、生まれてから1年はほとんど動けず泣くだけです。つまり、母親にはものすごい付加で、それがなんで進化なのか。実は、生まれた瞬間の視覚、聴覚、嗅覚、などの感覚は、人間は圧倒的に完成度が高いんです。発達した感覚で、ケアしてくれる母親のことを、1年間ですごい勢いで吸収し、母親を通じて父親や家族など絆を結んだ人が投影されて、子供が立ち、社会化していくんです」
それでも人間は、生物としての子育てを忘れてきている。その背景を中川は、テレビや携帯やパソコンによって巨大化する体外脳についていけないと人間ではないと言わんばかりの風潮があることを指摘する。あわせて、人間が長い進化の結果として存在することを忘れ、人間は動物とは別であるという傲慢さを抱いていることも大きな原因だと言う。
「チンパンジーから人間が分かれたのが、通説では600万年前です。私たちが本格的に道具を使うようになったのは1万年前の新石器時代からです。私たちが他の動物と違うと自覚しているのは文化を持っているからですが、それとて600万年のうちの1万年に過ぎません。私たちの文化は尻尾みたいなもので、それで巨大な過去をどうにかしようとしても無理です。それなのに尻尾で全体を振り回そうとしているんですから、理屈にあいません」
母親と父親の機能の違いが、奇妙な平等意識の中でないまぜになってきた感がある。また、自分が本来すべきことを、カネを払って誰かに委託することも当たり前になってきた。人間はそんな思想やシステムを生み出したことで、かえって子育てに悩み、汲々としてしまっているのではないだろうか。
動物の子育てはまた、親から子へという縦のつながりにおいて、大事なものが受け渡されることも示唆している。これも親の責任を学校や社会に丸投げしている風潮に対して、痛烈なアンチテーゼを投げかけている。中川の話にはドキッとさせられた。どうやら私たちは、ちょっと立ち止まって考えなければならないようである。(文中敬称略)
********************************************************************
生まれてきた子供にとって一番必要なことは母親の抱擁です。
今の「子育て政策」は、子と母を遠ざけることものになってないでしょうか?
大人たちの都合ではなく自然の摂理に立ち戻った制度を考えるべきだと想います。
wedge 2010.4(リンク) 元上野動物園園長の中川志郎氏 インタビュー より引用
「今政権が、子育て支援や教育に力を入れています。それ自体は僕も賛成なんですが、どうもどうも親が働きやすくなったり、シュミの時間がとりやすくなったりすることが目的になっているように感じます。育てられる子供の側に立って政策がどういう意味を持つかという深い考察がないんじゃないか。生まれたばかりの子供が絶対的に必要としている母親を、遠ざける政策になっていないか」
子ども手当、保育所の増設、高校教育の無償化・・・。いずれの政策にも、子供を育てやすいとの大義があろうが、それらはおしなべて親にとって都合のよいものであり、むしろ子供にとってはマイナスになりかねないと、元上野動物園園長の中川志郎は危惧する。
中川はその半生を動物園に勤めて送り、数多くの動物の出産や育児に関わってきた。育児書も保育所もない動物たちの子育てからうかがえるのは、生物としての原点、言い換えれば個の成長や群れの安定を実現するために進化の過程で獲得してきた仕組みである。人間もまた動物の進化の結果として存在するのに、今はその原点を忘れつつある。
生物としての子育ての原点とは何だろうか。中川によれば、すべての生物には、どうしたら無益な争いを避けて共生できるかなど、長い歴史の中で積み重ねてきたノウハウが遺伝情報として記憶されている。それを発現させるには、生まれてからの、生物的学習、生態的学習という2段階の学習が必要になる。
「霊長類で言えば、絶対的な安心感があった子宮から生まれ出た子供に、子宮にいた時と同じような安心感を与えるのが、母親の抱擁や言葉かけです。その中で子供には自分を保護してくれるのが母親であり、自分は母親と同じ生き物であると刷り込まれます。こうした密着状態を通して、母親への絶対的な信頼感(原信頼)が生まれる。これが生物的学習です」
「原信頼があるから、母親の行動を真似たいという衝動が起きます。そうしていきる術を学んでいくのが生態的学習です。また、母親が一緒にいる人への信頼へと広がっていきます。信頼がなければ絆が生まれません。まず、母親への原信頼があり、次に父親へと絆を結び、祖父母や兄弟へと絆を結んでいきます。長じて集団に入るときも、母親という基地に帰れる安心感があるから踏み出せるんです」
「例えば、動物園の飼育係に育てられたサルは、どれだけ可愛がっても人間のやり方でしか育ちませんから、成長しても群れに入っていけなかったり、自分に子供が生まれた時にどう育てていいのかがわからなかったりして、トラブルを起こします」
母親がひたすらに抱いてくれることが子供に安心感を与え、それは保護する母への信頼を生む。原点ともいうべき信頼が、母親の行動を受け継ぐことにつながり、また家族や仲間との関係構築にもつながる。つまり、個体として生きるために必要な術、社会をつくるために必要な知恵の出発点が、生まれてすぐの母子の密着状態にあるということだ。
一方で父親は「そこにいることが重要です。存在そのものが安心感を与える」というのがその機能だという。「父親は母親よりも生物的にはつながりが細いので、母親が父親を頼っている、尊敬しているという2点がないと子供には伝わりません」と中川は言う。
考えてみれば、生物的学習から始まるプロセスは、子供がより安全に育ち、集団の中で生きていくために必要な仕組みとして、魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類という進化の過程で得られた最適解であったはずだ。なのに現代の人間は、子育てを「大人にとって」という視点から眺めようとしている。いきおい生物的学習や生態的学習に十分な時間を割くのは難しくなるだろう。
中川は、人間が他の動物と違うのは、生物的学習と生態的学習の先に体外脳があることだと言う。体外脳とは、個体が蓄えた知識や経験が、その個体の死とともにリセットされるのではなく、他の人に伝えるべく外部に集積していることを指す。人間は、書物や教育など自身の外にある”脳”から後付けで、「私はホモサピエンスである」「社会に出るためには相手との信頼関係が大事だ」と学ぶことだってできる。
だから、母子の接点は減ったとしても、子供には後で教育を与えればいい、何より親にとって仕事やシュミは大事だしと、考えるのも無理はない。
では体外脳で、生物としての本能的な部分はカバーできるのか?
「生物的学習と生態的学習が基盤となってはじめて、体外脳を正式に応用できます。今は最初の2つの段階を省略したまま、頭ばかり大きくなって、それを支える生物としての土壌が細まっていて、バランスが悪い状態です」
そもそも、教育によって大脳皮質に教え込まれたものを、大脳皮質で否定することは簡単だと、中川は指摘する。「殺すのはいけない」と教えても状況次第で真逆に振れることがある。一方、子供の頃に愛されたことで体に染み付いたものは、たやすくは変わらない。
「チンパンジーは4年おきに子供を生みます。子供は4歳になると、次に生まれてくる弟や妹を母親から借りて子守をします。弟や妹がいないときは、何も命じられていないのに、よその母親のところに行って頭を下げて、赤ちゃんを借りてくるんです。チンパンジーには育児書も道徳の時間もありません。道徳や倫理は頭で考えるものではなく、自然発生的な染み込んだものが表に出るということです」
両親に可愛がられた経験が、違う個体を慈しむ行動につながっている一例だろう。
「それに人間こそ、最初の密着状態を必要としているんですよ。人間の妊娠期間は霊長類の中でも一番長いし、赤ちゃんも相対的に大きい。ゴリラの赤ちゃんは1.5キロしかありませんから。しかも人間の赤ちゃんは、生まれてから1年はほとんど動けず泣くだけです。つまり、母親にはものすごい付加で、それがなんで進化なのか。実は、生まれた瞬間の視覚、聴覚、嗅覚、などの感覚は、人間は圧倒的に完成度が高いんです。発達した感覚で、ケアしてくれる母親のことを、1年間ですごい勢いで吸収し、母親を通じて父親や家族など絆を結んだ人が投影されて、子供が立ち、社会化していくんです」
それでも人間は、生物としての子育てを忘れてきている。その背景を中川は、テレビや携帯やパソコンによって巨大化する体外脳についていけないと人間ではないと言わんばかりの風潮があることを指摘する。あわせて、人間が長い進化の結果として存在することを忘れ、人間は動物とは別であるという傲慢さを抱いていることも大きな原因だと言う。
「チンパンジーから人間が分かれたのが、通説では600万年前です。私たちが本格的に道具を使うようになったのは1万年前の新石器時代からです。私たちが他の動物と違うと自覚しているのは文化を持っているからですが、それとて600万年のうちの1万年に過ぎません。私たちの文化は尻尾みたいなもので、それで巨大な過去をどうにかしようとしても無理です。それなのに尻尾で全体を振り回そうとしているんですから、理屈にあいません」
母親と父親の機能の違いが、奇妙な平等意識の中でないまぜになってきた感がある。また、自分が本来すべきことを、カネを払って誰かに委託することも当たり前になってきた。人間はそんな思想やシステムを生み出したことで、かえって子育てに悩み、汲々としてしまっているのではないだろうか。
動物の子育てはまた、親から子へという縦のつながりにおいて、大事なものが受け渡されることも示唆している。これも親の責任を学校や社会に丸投げしている風潮に対して、痛烈なアンチテーゼを投げかけている。中川の話にはドキッとさせられた。どうやら私たちは、ちょっと立ち止まって考えなければならないようである。(文中敬称略)
********************************************************************
生まれてきた子供にとって一番必要なことは母親の抱擁です。
今の「子育て政策」は、子と母を遠ざけることものになってないでしょうか?
大人たちの都合ではなく自然の摂理に立ち戻った制度を考えるべきだと想います。












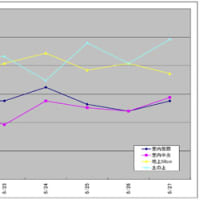
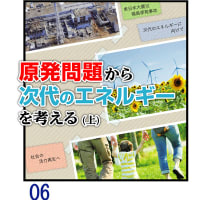




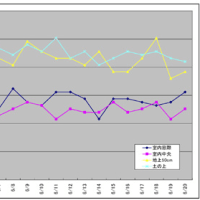
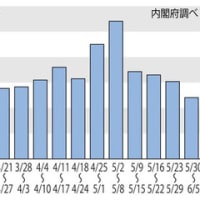
現実問題、食べたり育てたりするのに必要とは言え、なんかちょっと変ですね(-.-;
子供にも親にも必要な適した政策…これはみんなにとって大事な課題ですね!!!!!
食べたり育てたりが核家族の課題になっているのがそもそもの原因なんでしょうね。
なんであれ集団やチームでやるほうが安心だし効率もいい。
子にも親にも必要で適した政策は共同体を再生していくものだと想います。