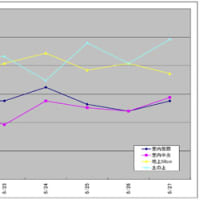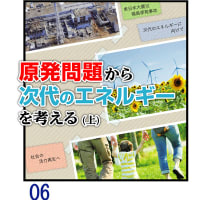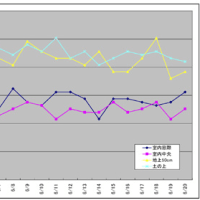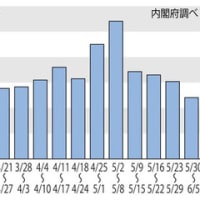試験制度の問題性はどこにあるのか?
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=214664より引用します。


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
・試験制度では、設問も、答えも、予め用意されている。つまり、問題も、正解も、所与のものである。出題、設問の元になる根拠は、絶対的なものである事が大前提である。なぜならば、問題の根拠があやふやでは、試験制度そのものが成り立たないからである。
・学校の試験は、一人で問題を解くのであるから、試験の結果に対しては、自分だけが責任を持つ。逆に言えば、自分の出した解答にだけ責任を持てばいい。それも点数にのみ責任を持つのであって、結果、全般に対して責任をとる必要はない。答えが間違っていてもそのままで良いのである。修正したり、ただす、必要はない。むろん謝る必要もない。つまり、やりっ放しである。
しかし、現実の社会で間違った答えを出したら、それを改めない限り許されない。場合によったら謝罪をしなければならない。
・学校では、試験中には設問以外、質問を受け付けてくれない。また、試験中に話をしてはならない。
しかし、現実の社会では逆である。問題が出されたら、まずその問題が正しいかどうかを確認しなければならない。つまり、設問以外に隠されていることを質問しなければならない。そのうえで、問題の真意や目的について出題者に質問をする。問題に取りかかったら、わからないことがあった場合、どんどん周囲の人間に相談をし、できれば、答案用紙を提出する前に答えを確認しておく必要がある。
・試験では、一定の時間内に解答を出すことを要求される。しかし、現実の社会ではありえない。一定の時間内で問題を解くのでは、受験者は創造力を発揮することができない。むろん、試験では創造力など要求していないし、要求できない。結果、学校教育に創造力が、入る込む余地がなくなる。創造力の強い子は、学校社会からはじき出されるのである。
学校は、閉ざされた社会であり、自分一人で、原則、教えられたことで解答が出される。一人でやるのだから、当然、自分以外の者の結果に対する、共感や共鳴はない。結果が、悪ければ指導者の教え方が、悪いと思うだけで、感謝の念、なんか、さらさらわかない。
それにたいし、現実の社会では、開かれた社会であり、自分一人ではわからない、できないことで大多数である。一人で責任のとれる仕事は少ない。逆に人の失敗の責任を問われることが多い。逆に、共同で仕事をするから、結果は、共有する。故に、結果に対し伴に泣き伴に笑うことになる。感動も共有する。指導した人に、感謝する念も生じる。
・試験では、教わった範囲内、教科書に載っていないことは、出題されない。教わっていない問題が出たら、それ教わっていませんですむ。それに対し、現実問題の、そのほとんどが、教室で、教えられたことだけでは、解決できない。教科書には書いてない事を使って解かなければならない。教わっていないなんて言ったら叱られる。しかも、現実の社会では、正解を出すまで何度でも、やり直さなければならない。できない、間違いましたでは許されない。そのうえ、きちんと、やり遂げないと、次がない。特に、同じ失敗を、繰り返すことは許されない。だから、常に問題を見直しておく必要がある。
だから、現実の社会では試験以前の準備や人間関係が大切なのである。要するに、試験には、現実の社会が、欠落しているのである。
・スポーツやクラブは、簡単なテストをするところもあるが、多くが、無審査か、実地テストである。ペーパーテストだけで、入団や入会、入社を決めるところは、少ない。なぜなら、実社会では、実力がものをいうからである。ペーパーテストで、人間の実力や人柄を測る事ができないことを実力の世界では、自明のように受け止めているからである。
・統一的試験制度のメリットは、管理しやすいという事にある。また、教える側にとっても都合がいい。というより、巧妙に責任を回避することができるうえ、教え方も標準化できるという点にある。つまり、生産性や効率が非常にいい仕組みだと言える。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
by kou
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=214664より引用します。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
・試験制度では、設問も、答えも、予め用意されている。つまり、問題も、正解も、所与のものである。出題、設問の元になる根拠は、絶対的なものである事が大前提である。なぜならば、問題の根拠があやふやでは、試験制度そのものが成り立たないからである。
・学校の試験は、一人で問題を解くのであるから、試験の結果に対しては、自分だけが責任を持つ。逆に言えば、自分の出した解答にだけ責任を持てばいい。それも点数にのみ責任を持つのであって、結果、全般に対して責任をとる必要はない。答えが間違っていてもそのままで良いのである。修正したり、ただす、必要はない。むろん謝る必要もない。つまり、やりっ放しである。
しかし、現実の社会で間違った答えを出したら、それを改めない限り許されない。場合によったら謝罪をしなければならない。
・学校では、試験中には設問以外、質問を受け付けてくれない。また、試験中に話をしてはならない。
しかし、現実の社会では逆である。問題が出されたら、まずその問題が正しいかどうかを確認しなければならない。つまり、設問以外に隠されていることを質問しなければならない。そのうえで、問題の真意や目的について出題者に質問をする。問題に取りかかったら、わからないことがあった場合、どんどん周囲の人間に相談をし、できれば、答案用紙を提出する前に答えを確認しておく必要がある。
・試験では、一定の時間内に解答を出すことを要求される。しかし、現実の社会ではありえない。一定の時間内で問題を解くのでは、受験者は創造力を発揮することができない。むろん、試験では創造力など要求していないし、要求できない。結果、学校教育に創造力が、入る込む余地がなくなる。創造力の強い子は、学校社会からはじき出されるのである。
学校は、閉ざされた社会であり、自分一人で、原則、教えられたことで解答が出される。一人でやるのだから、当然、自分以外の者の結果に対する、共感や共鳴はない。結果が、悪ければ指導者の教え方が、悪いと思うだけで、感謝の念、なんか、さらさらわかない。
それにたいし、現実の社会では、開かれた社会であり、自分一人ではわからない、できないことで大多数である。一人で責任のとれる仕事は少ない。逆に人の失敗の責任を問われることが多い。逆に、共同で仕事をするから、結果は、共有する。故に、結果に対し伴に泣き伴に笑うことになる。感動も共有する。指導した人に、感謝する念も生じる。
・試験では、教わった範囲内、教科書に載っていないことは、出題されない。教わっていない問題が出たら、それ教わっていませんですむ。それに対し、現実問題の、そのほとんどが、教室で、教えられたことだけでは、解決できない。教科書には書いてない事を使って解かなければならない。教わっていないなんて言ったら叱られる。しかも、現実の社会では、正解を出すまで何度でも、やり直さなければならない。できない、間違いましたでは許されない。そのうえ、きちんと、やり遂げないと、次がない。特に、同じ失敗を、繰り返すことは許されない。だから、常に問題を見直しておく必要がある。
だから、現実の社会では試験以前の準備や人間関係が大切なのである。要するに、試験には、現実の社会が、欠落しているのである。
・スポーツやクラブは、簡単なテストをするところもあるが、多くが、無審査か、実地テストである。ペーパーテストだけで、入団や入会、入社を決めるところは、少ない。なぜなら、実社会では、実力がものをいうからである。ペーパーテストで、人間の実力や人柄を測る事ができないことを実力の世界では、自明のように受け止めているからである。
・統一的試験制度のメリットは、管理しやすいという事にある。また、教える側にとっても都合がいい。というより、巧妙に責任を回避することができるうえ、教え方も標準化できるという点にある。つまり、生産性や効率が非常にいい仕組みだと言える。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
by kou