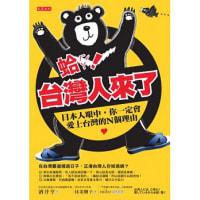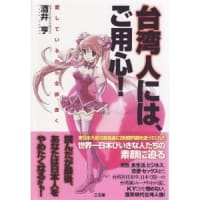9月9日に座り込みが始まり、9月15日に数十万人のデモを行ってピークを迎えた「倒扁(陳総統辞任要求)運動」。9月下旬になって急速に下火になっていったが、どうやらこの数日で完全に泡沫化し、失敗に終わったという評価がなされている。
10月16日付けの自由時報は、「新聞探索/藍營介入 路線分岐 紅軍陣營 無以為繼」(http://www.libertytimes.com.tw/2006/new/oct/16/today-p2.htm)と題する分析記事で、この運動が9月下旬から青陣営の急進派政治家の介入が目立ち、内部の路線対立も頻発し、「陳水扁辞任」ばかりが叫ばれて、本来求めたはずの「非暴力、反腐敗」はどこかに行ってしまって、自滅していった、と指摘している。
またそれと並行して、国民党および親民党陣営も混迷状態に陥っている。10月13日には二度目の陳総統罷免案の採決が立法院で行われたが、成立しなかったのはもちろんだが、現有総議席数220席、罷免成立に147票が必要なところ、賛成が116票と前回6月末の罷免案のときよりも3票も減るという、青陣営側の大失態に終わった。
これを受けて親民党と国民党の一部では「倒閣」に向けて動き始めたが、倒閣の結果、(1)内閣改造があった場合、王金平ら国民党本土派が国民党から脱走する可能性を馬英九が恐れている(自由時報16日「馬憂心第三勢力竄起」http://www.libertytimes.com.tw/2006/new/oct/16/today-fo4.htm)、(2)総統が内閣改造ではなく国会解散に踏み切れば、新たに定数半減となって改選が行われることを現職議員の多くが恐れている、という二つの可能性が考えられるため、国民党の大半が「倒閣」にしり込みしてしまっている。
1ヶ月前まで「陳水扁をやっつけ、民進党をつぶせ」とばかり意気軒昂だった国民党・親民党陣営は、打って変わった現在の状況に意気消沈している。年末の台北・高雄市長・議員選挙はもちろん、来年末の立法委員選挙、あるかわからないがあると仮定して08年3月の総統選挙と、青陣営が連敗する可能性が高まっている(自由時報16日、自由談・「變臉」http://www.libertytimes.com.tw/2006/new/oct/16/today-f1.htm)。
また、大きく傷ついたのが、馬英九だ。「倒扁」運動に密かに期待し、24時間集会を認めるという常識はずれの措置までして事実上支援してきたが、一方では「市長」としての立場も気になり、積極的に運動に参加することもできなかった。密かに支援している点では、緑陣営から「市長として中立的ではない」と批判され、かといって積極的に参加しない点で「倒扁」陣営から「それでも男か」などと攻撃される始末だった。
なまじ欲張って党主席と市長を兼務したために、本来役割が異なる両者の職務の矛盾に股裂きになった格好だ。それでも有能ならまだしも、馬英九は昔から優柔不断、八方美人で無能だと見られてきた。それが今回、赤裸々に示されたのである。
これで、馬英九の支持率とただでさえ実態がなかった「人気」は急落した。緑陣営は馬英九の大中国・反台湾主義者としての「本性を見たり」であり、青陣営の急進派から見てあまりにも軟弱だったのだ。
今日では、馬英九が08年3月の総統選挙に出て勝てると考える政界関係者や政界ウオッチャーはほとんどいなくなった。
08年に総統選挙が行われるかどうかもわからなくなっているし、それ以前にもし実施されたとしても、馬英九は泡沫化する「中国国民党」という泥舟とともに沈没することが予測されている。
ここで、潮目を変えたは何だったのかが気になるところだ。それは今思い起こせば、9月16日の台湾社による「陳水扁支援集会」だったのではないかという感じがする。
当時この集会は私自身は反対で、気が進まなかった。しかし、今になってみれば、あの時点で、急進独立派が中心となってあの集会を開いたことは、結果的に正解で、節目や潮目を変えたのだといえる。
そもそも台湾の民主化運動は、80年代末期以来、急進独立派が牽引役となって引っ張ってきたから達成されたのである。確かに急進独立派の思い通りの状態には台湾はなっていない。そこには大中国派の旧体制、台湾建国を望まない米国や日本や中国などの大国帝国主義の掣肘や圧迫、台湾人自身の性質そのものが国家というものにフィットしていないなどの理由が関係している。
しかし、だからといって、急進独立派や独立建国勢力の存在は無意味なのではない。そうした勢力があるからこそ、結果的には大中国派や米日中など帝国主義による圧迫との中和とバランス作用が生まれ、台湾が現在のように奇妙な形での独立状態を保てる契機やアクターとなっているといえるのである。
急進独立派もそれ自体としては決して過半数を超える多数派ではないのだけれども、やはり隠然かつ連綿として続き、台湾に活力を与える源になっているのである。
もちろん、今の私は、台湾が「せっかく」国民国家という19世紀西洋近代が生んだ陳腐かつ普遍性がない特殊なモデルに依存することなく、別の形態の社会や実体を示している点を評価し、独立建国論とは距離を置くようになっている。しかし、だからといって、強いて「統一か独立建国か」という選択肢から選べといわれたら、間違いなく独立建国のほうが良いというつもりだし、いかなる状況になろうとも大中国との「統一」などは絶対にありえないと断言したいし、それは死んでも阻止しようと思っている。
だから決して独立建国論という古臭い西欧近代のモデルに積極的に賛意を示さないのではあるが、それでも今回の一連の動きにおいて、独立建国論勢力が演じた積極的な役割は、素直に評価したい。9月16日に台湾社が行った集会は正しかった。あの時点で倒扁に対するカウンター勢力の声を大きく上げたことが、潮目を変えたという点は否定できないだろう。
そして、その根底にある真理とは「台湾は台湾人のものであり、台湾は中国のものではない」という考え方(それが国民国家を志向しようがしなかろうが)に分があるということである。もはや台湾において「台湾人は中国人、台湾は中国の一部」などという中華ナショナリズムは受け入れられない。それが時代の流れなのである。
この時代の潮流に逆らうことはできないし、逆らうものは必ず失敗する。それが今回の「倒扁」運動の破綻と、馬英九の急速な失墜に典型的に見られる。
ところが、こうした台湾社会の流れと真実に気づいていない自称台湾ウオッチャーが日本のマスコミ界に多いのは、どうしたことだろうか?
雑誌「世界」10月号で、中国残留孤児の家庭出身で、中国共産党系のフリーライター本田善彦氏が、台湾の民進党政権は失墜した。これまで台湾意識が伸張してきたという見方は、米中接近や台湾の中国への経済的依存で、通じなくなった--などとトンチンカンな見方を滔々と書いているが、誤りの典型例といってよい。台湾意識はますます強まっている。民進党も伸び悩んでいるのは事実が、国民党も一枚岩でもなく、馬英九に代表される大中国派国民党は低迷し、台湾土着派の勢力が強まっているのである。
そうした中国共産党流のデマに振り回されているのか知らないが、今年春あたりから、東京のほうでは「民進党は駄目で、08年は馬英九が総統になるのは確実」というデマがまことしやかに流れていたようだ。
しかし、それがいかに傲慢で、台湾人を馬鹿にしたものかということを、かつて台湾を植民地支配して、台湾人を二等国民として抑圧してきた日本人は、そろそろ気づき、謙虚に反省すべきだろう。日本人の多くはいまだに台湾を見下しているのではないか?台湾人が自らの尊厳と権利を求めていることについて、もっと虚心になって正視する必要がある。
台湾は、(本田氏や馬英九氏らのような)中国人のものでも、日本人のものでもない。ほかならぬ台湾人のものなのである。その基本を忘れて、台湾を語ることはできない。
10月16日付けの自由時報は、「新聞探索/藍營介入 路線分岐 紅軍陣營 無以為繼」(http://www.libertytimes.com.tw/2006/new/oct/16/today-p2.htm)と題する分析記事で、この運動が9月下旬から青陣営の急進派政治家の介入が目立ち、内部の路線対立も頻発し、「陳水扁辞任」ばかりが叫ばれて、本来求めたはずの「非暴力、反腐敗」はどこかに行ってしまって、自滅していった、と指摘している。
またそれと並行して、国民党および親民党陣営も混迷状態に陥っている。10月13日には二度目の陳総統罷免案の採決が立法院で行われたが、成立しなかったのはもちろんだが、現有総議席数220席、罷免成立に147票が必要なところ、賛成が116票と前回6月末の罷免案のときよりも3票も減るという、青陣営側の大失態に終わった。
これを受けて親民党と国民党の一部では「倒閣」に向けて動き始めたが、倒閣の結果、(1)内閣改造があった場合、王金平ら国民党本土派が国民党から脱走する可能性を馬英九が恐れている(自由時報16日「馬憂心第三勢力竄起」http://www.libertytimes.com.tw/2006/new/oct/16/today-fo4.htm)、(2)総統が内閣改造ではなく国会解散に踏み切れば、新たに定数半減となって改選が行われることを現職議員の多くが恐れている、という二つの可能性が考えられるため、国民党の大半が「倒閣」にしり込みしてしまっている。
1ヶ月前まで「陳水扁をやっつけ、民進党をつぶせ」とばかり意気軒昂だった国民党・親民党陣営は、打って変わった現在の状況に意気消沈している。年末の台北・高雄市長・議員選挙はもちろん、来年末の立法委員選挙、あるかわからないがあると仮定して08年3月の総統選挙と、青陣営が連敗する可能性が高まっている(自由時報16日、自由談・「變臉」http://www.libertytimes.com.tw/2006/new/oct/16/today-f1.htm)。
また、大きく傷ついたのが、馬英九だ。「倒扁」運動に密かに期待し、24時間集会を認めるという常識はずれの措置までして事実上支援してきたが、一方では「市長」としての立場も気になり、積極的に運動に参加することもできなかった。密かに支援している点では、緑陣営から「市長として中立的ではない」と批判され、かといって積極的に参加しない点で「倒扁」陣営から「それでも男か」などと攻撃される始末だった。
なまじ欲張って党主席と市長を兼務したために、本来役割が異なる両者の職務の矛盾に股裂きになった格好だ。それでも有能ならまだしも、馬英九は昔から優柔不断、八方美人で無能だと見られてきた。それが今回、赤裸々に示されたのである。
これで、馬英九の支持率とただでさえ実態がなかった「人気」は急落した。緑陣営は馬英九の大中国・反台湾主義者としての「本性を見たり」であり、青陣営の急進派から見てあまりにも軟弱だったのだ。
今日では、馬英九が08年3月の総統選挙に出て勝てると考える政界関係者や政界ウオッチャーはほとんどいなくなった。
08年に総統選挙が行われるかどうかもわからなくなっているし、それ以前にもし実施されたとしても、馬英九は泡沫化する「中国国民党」という泥舟とともに沈没することが予測されている。
ここで、潮目を変えたは何だったのかが気になるところだ。それは今思い起こせば、9月16日の台湾社による「陳水扁支援集会」だったのではないかという感じがする。
当時この集会は私自身は反対で、気が進まなかった。しかし、今になってみれば、あの時点で、急進独立派が中心となってあの集会を開いたことは、結果的に正解で、節目や潮目を変えたのだといえる。
そもそも台湾の民主化運動は、80年代末期以来、急進独立派が牽引役となって引っ張ってきたから達成されたのである。確かに急進独立派の思い通りの状態には台湾はなっていない。そこには大中国派の旧体制、台湾建国を望まない米国や日本や中国などの大国帝国主義の掣肘や圧迫、台湾人自身の性質そのものが国家というものにフィットしていないなどの理由が関係している。
しかし、だからといって、急進独立派や独立建国勢力の存在は無意味なのではない。そうした勢力があるからこそ、結果的には大中国派や米日中など帝国主義による圧迫との中和とバランス作用が生まれ、台湾が現在のように奇妙な形での独立状態を保てる契機やアクターとなっているといえるのである。
急進独立派もそれ自体としては決して過半数を超える多数派ではないのだけれども、やはり隠然かつ連綿として続き、台湾に活力を与える源になっているのである。
もちろん、今の私は、台湾が「せっかく」国民国家という19世紀西洋近代が生んだ陳腐かつ普遍性がない特殊なモデルに依存することなく、別の形態の社会や実体を示している点を評価し、独立建国論とは距離を置くようになっている。しかし、だからといって、強いて「統一か独立建国か」という選択肢から選べといわれたら、間違いなく独立建国のほうが良いというつもりだし、いかなる状況になろうとも大中国との「統一」などは絶対にありえないと断言したいし、それは死んでも阻止しようと思っている。
だから決して独立建国論という古臭い西欧近代のモデルに積極的に賛意を示さないのではあるが、それでも今回の一連の動きにおいて、独立建国論勢力が演じた積極的な役割は、素直に評価したい。9月16日に台湾社が行った集会は正しかった。あの時点で倒扁に対するカウンター勢力の声を大きく上げたことが、潮目を変えたという点は否定できないだろう。
そして、その根底にある真理とは「台湾は台湾人のものであり、台湾は中国のものではない」という考え方(それが国民国家を志向しようがしなかろうが)に分があるということである。もはや台湾において「台湾人は中国人、台湾は中国の一部」などという中華ナショナリズムは受け入れられない。それが時代の流れなのである。
この時代の潮流に逆らうことはできないし、逆らうものは必ず失敗する。それが今回の「倒扁」運動の破綻と、馬英九の急速な失墜に典型的に見られる。
ところが、こうした台湾社会の流れと真実に気づいていない自称台湾ウオッチャーが日本のマスコミ界に多いのは、どうしたことだろうか?
雑誌「世界」10月号で、中国残留孤児の家庭出身で、中国共産党系のフリーライター本田善彦氏が、台湾の民進党政権は失墜した。これまで台湾意識が伸張してきたという見方は、米中接近や台湾の中国への経済的依存で、通じなくなった--などとトンチンカンな見方を滔々と書いているが、誤りの典型例といってよい。台湾意識はますます強まっている。民進党も伸び悩んでいるのは事実が、国民党も一枚岩でもなく、馬英九に代表される大中国派国民党は低迷し、台湾土着派の勢力が強まっているのである。
そうした中国共産党流のデマに振り回されているのか知らないが、今年春あたりから、東京のほうでは「民進党は駄目で、08年は馬英九が総統になるのは確実」というデマがまことしやかに流れていたようだ。
しかし、それがいかに傲慢で、台湾人を馬鹿にしたものかということを、かつて台湾を植民地支配して、台湾人を二等国民として抑圧してきた日本人は、そろそろ気づき、謙虚に反省すべきだろう。日本人の多くはいまだに台湾を見下しているのではないか?台湾人が自らの尊厳と権利を求めていることについて、もっと虚心になって正視する必要がある。
台湾は、(本田氏や馬英九氏らのような)中国人のものでも、日本人のものでもない。ほかならぬ台湾人のものなのである。その基本を忘れて、台湾を語ることはできない。