さて記事の続きですが、カテドラルも見終わって、漸くこの日の最後の目的地、ピカソ美術館に向かう。
私はパリのポンピドーの現代美術館に行くまでは、ピカソってそんなに好きでもなかったが、
そこで衝撃的な作品に出くわして以来、結構好きだ。
でもこのピカソ美術館で受けた衝撃はもっとすごかったね。
「ピカソと春画」-特別展示で、ピカソが日本の春画にどのように影響を受けたか、というのをやっていたのだが、その展示内容もだけど、主張が前衛的過ぎて衝撃。
こーゆーの、美術館でやっちゃうんだ、スペインってすごい・・・と思ったし、同時に美術館の社会的役割について考えさせられた。
それから、観衆のスペイン人たちもすごいよ・・・。
結構恥ずかしい絵たちを、食い入るように鑑賞し、会話するスペイン人の男女。
R指定なんか無いから、子供まで入場して鑑賞しとるよ。
フランスがアムール(愛)の国なら、スペインはエロスの国なんだな、って思ったね。
詳細は後述するけど、今日はブログの内容も前衛的すぎるから、そーゆーのが好きじゃない人は読まないことを推奨。
または心の準備をして読むべし(笑)
まずはピカソ美術館の行き方から。
ピカソ美術館はカテドラルから歩いて10分ちょいのところにある。
大通りから、若干細めの道に入ってしばらく歩いて右折し、路地みたいなところをちょっと歩くと到着。
地図がなくても、標識が出てるのでたどり着けるはず。
こういうところで地図広げてるのは危険だからね。

なんか、普通の家みたいなところがそのまま美術館になってる感じ。

チケットオフィスから中に入ると、素敵な感じのカフェがあったので、そこに入る。
空腹と疲れが最高に達していたので、腹ごしらえをしようと思い、胡桃のケーキとエスプレッソを頂く。
エスプレッソがとても美味しくて、2杯も飲んでしまった。
アメリカから来た人間からすると、考えられないほどのコーヒーの美味しさ。
一杯1.5ユーロ(約2.2ドル)という、美術館コーヒーとしては考えられない安さも魅力。
そこで改めてパンフレットの表紙を見て、ぎょっとする。
このパンフ。(PDFに外部リンクされてます)
日本の春画が表紙になってるわけだけど、男と女のその器官が細かく描かれてるという。
何でこんなものが公共のパンフに・・・。
真面目なキモチで美術鑑賞しようとしてるときに、こんなものが出てくると、心の準備が出来て無さすぎて、通勤電車の中で、いきなり露出度の超高いヌードの中吊り広告に出くわした気分である。
ま、でも気分を取り直して、エスプレッソを飲み干し、鑑賞に備える。
最初は常設展示から、と思ったが、成り行きでこの特別展示から見る羽目になってしまった。
展示では、ピカソがいつから春画の影響を受け始めたか、どのように受けたか、ということを分かりやすく「検証」していた。
この「検証」の仕方が科学的なのも、とても面白いと思った。
1. ピカソが春画の影響を受けたのは、10代後半から20代前半のかなり若い時期らしい
これが、複数の証拠によって「検証」されてるのが面白かった。
20代前半のピカソの写真に、部屋の後ろに春画が写ってるものがあることから、この頃には既に所有していたと分かること。
ピカソの友人の日記で、ピカソに春画を買ってきて渡した、という記述があること。
青の時代のころのピカソの習作に、春画の影響を受けたとしか思えない作品がいくつかあること。
メッセージがあり、それを複数の証拠によって検証する、というピラミッドストラクチャー。
なんちゅー科学的な。
2. ピカソの絵の構図やアイディアには春画の影響を受けたものが多くある
影響を受けた、とされる春画と、対応するピカソの複数の絵が並べて検証されており、面白い。
最初は、春画の構図をそのままに、西洋風に書き換えただけの習作。
少し構図を変えたり、女の人数が増えたりする複数の絵。
女の胸とその部分だけが強調されていて、というか、それだけの絵、みたいなのもあって、ここまで来ると「何だこれ?」って感じで何のエロスも感じない。
それが最終的にピカソらしいキュービズムへとアレンジされていく。
こうやって見ていくと、確かに春画の影響を多大に受けてるのが分かる。
中でも面白かったのは、北斎が描いた、大きな蛸が複数の触手を使って裸の女性を犯している絵で、これはピカソだけでなく、当時の様々な画家に影響を与えたらしい。
(追記:葛飾北斎「蛸と海女」。Wikipediaにリンク。リンクには性的な記述が含まれます。)
北斎は全く狙ってなかったと思うが、蛸はキリスト教文化では、背徳の象徴。
その蛸が女性を犯す、という発想は、デカダンス全盛の当時の画家たちにはもうドンピシャだったことだろう。
北斎の絵は極めて日本的な絵だが、複数の画家がこれを西洋的なエロスに転換していて、それがいくつか展示されていた。
西洋のポルノ文化に慣れてる現代の日本人からみると、正直春画より西洋版の肉々しいほうがエロく思える。
が、元のアイディアは日本にあるわけだ。
ここである芸術家の言葉が引用されていた。
「春画は、全ての男の心の奥深くにある、暗い欲望を覚醒させ、それが芸術を新たな境地へいざなう」
(だったかな?細かい言葉は忘れたがそんな感じ)
他の国の人たちにそこまでの影響を与えられる大衆文化って、すごいと思うよ。
3. そもそもキュービズムという思考自体が春画の思考に発してるのではないか(仮説)
更に展示では、構図だけではなく、春画の「描きたいところだけ描くために自然法則を曲げる」という思想そのものが、ピカソに大きな影響を与えたのではないか、という仮説を披露。
(追記: 展示では、その検証を試みる書籍も展示されてました)
確かに春画って、背景や人物に比べて、女や男の目的の部分だけ精細に描かれていてすごく不自然。
また、人間の体はそのようには曲がらないだろうという不自然な構図のものがたくさんある。
「描きたい部分を描く」という目的を達成するために、多少の統一性や物理法則を無視してるわけだ。。
その考え方自体が、ピカソに大きな影響を与えたのではないか、と言われてみれば、確かにピカソのキュービズムってそういう考え方で描かれてるわけで、納得感がある。
でもその仮説はすごいよ。
もちろん「ゴッホの画風は浮世絵から来ている」という説も、今じゃ当たり前に受け入れてるけれど、最初はかなり抵抗があったと聞く。
もしかしたらそのうち「ピカソのキュービズムは日本の春画から来ている」なんて言われるようになるかも?
そしてピカソ美術館のこの展示が、そのきっかけになるかも?(若干飛躍気味)
こういう主張を、特別展示でやってしまうピカソ美術館ってすごい!と思ったね。
学会でもまだ全面的には受け入れられてない主張を、展示で主張し、科学的に検証してしまおうという美術館。
前衛的過ぎる。
4. 「見せる」だけじゃなく「メッセージを出す」美術館が面白い。
日本もそうだけど、現代の多くの美術館は、大衆の啓蒙を目的として建てられている。
もともと美術品コレクターなどが、所蔵してるだけじゃもったいない、ということで始めたのが美術館の始まりなわけだが、
その後大量に建てられた公共の美術館は「素晴らしい芸術に一般庶民が触れるための場」として設計されちゃってるし、展示の多くもそうだ。
例えば、「オルセー美術館展」みたいに西洋の美術館に所蔵されている美術品を拝むためのものなど。
もちろんパリに行かずしてオルセーを見れるのはすごいことだと思うけど、ただ海外の美術品を運んできて見せるストローのような役割を果たすだけいいのかねえ、と思うわけだ。
こういう美術館に慣れちゃった私たちには、「美術館って、すごい、ということになってる美術品を見るだけのところ」という何となくつまらないイメージが出来上がってしまっている。
そこにおいて、「見せる」から一歩先を行って、「メッセージを出す」「何らかの仮説を伝える」美術館って、新しいし、面白い。
美術館の新たな一形態になるかもしれない、と思った。
さて、ピカソ美術館には常設展示もあって、特に青の時代・赤の時代など若い頃の作品と、晩年の作品が所蔵されている。
一番活躍していた時代の作品は、ポンピドーを初めとして世界の美術館に分散してるからほとんど無いのだが。
でも、ピカソの若い頃の作品の軌跡を見るには、ここに来るしかないだろう。
あの特別展を見た後だと、どの作品も「このころから春画の影響を受けてるのか!」という気分でしか見られないんだけど(笑)
美術館がこんなに「面白い」経験は初めてでした。











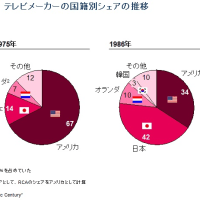
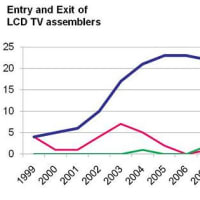
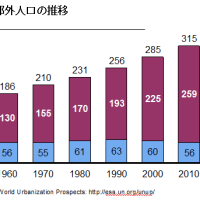
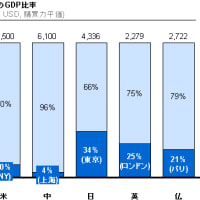

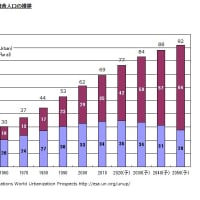
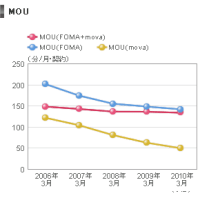
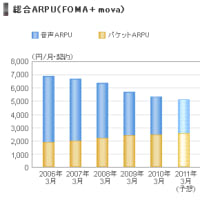
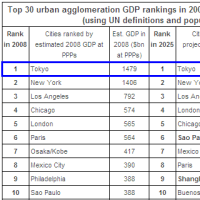
>そもそもキュービズムという思考自体が春画の思考に発してるのではないか(仮説)
これ、とても面白い考えですね。確かに西欧絵画はルネサンスで、平面のカンバスや板に立体的でリアリスティックな描写をする技術を取り戻して、以後、それを完璧にすべく努力してきたわけでしょうけど、ギリシャ・ローマ美術という手本を持たない日本画は、そもそも平面の素材に描くことを素直に受け入れた上で、線による抽象化(分析)やデフォルメで立体性を確保したように感じます。それが、西欧の画家からするととても前衛的に映ったのでしょう。でももともと線を基にやるほかない木版画の場合、そうするしか無かったのかもしれませんね。
>確かに春画って、背景や人物に比べて、女や男の目的の部分だけ精細に描かれていてすごく不自然。
おっしゃるように、ポルノは、体の一部などを拡大する必要があるので、浮世絵でも西欧絵画でもデフォルメが進むでしょうね。また、そもそも、性行為自体が、人間の日常活動の中では珍しい(?)姿勢を取るので(^_^)、他の姿態に比べ、そういう抽象化を喚起しやすい気がします。 Yoshi
>線による抽象化(分析)やデフォルメで立体性を確保
プラス、遠近法などの構図によっても立体性の確保を行ってますね。
北斎や広重などは遠近法の消失点を複数使いながら、これを隠す構図によって、不自然さをなくしおり、この構図が西洋美術に大きな影響を与えた、という話はよく言われていますし。
それから、色使いもゴッホやモネなど印象派画家に大きな影響を与えたとも。
オランダのゴッホ美術館にも行きましたが、ここには彼の浮世絵の習作が多く所蔵されていて、どんな影響を与えたかが分かるのが面白かったです。
音楽もですが、芸術が「誰/何にインスパイアされて出来上がったのか」を知るのは結構楽しいですね