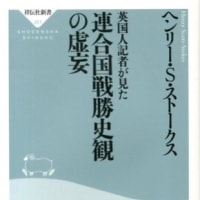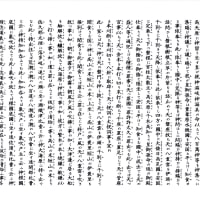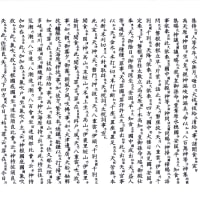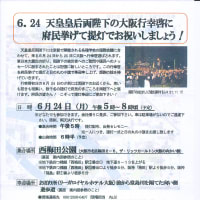六 被告人の責任
(1)叛逆性の誤つた類推
「何人も諸犯罪の発生した原因である日本の侵略政策について幾分でも責任があつたのでなければ、平和に対する罪、通常の戦争犯罪、又は人道に対する罪について起訴しなかつた」といふ。(K-三節)
これは戦争の蓋然性又はそれら犯罪の発生することを期待又は予見してゐなかつた場合でもなほさうである!
これが起訴状全部にしみ渉つてゐる誤つた全理論の秘密を開くためのマスター・キーである。そしてこれは国内法に対する叛逆罪の陰謀の設計図によつて示唆された観念である。
検察側はいつも「推定」をかうしたアナロジイの根拠とする。しかし生命をかけて裁判を受けてゐる被告はかうした安易な方法で有罪とされるべきではない。しかもなほ検察側も曖昧たることを免れえないのである。政策の形成に少しでも関与した者はその政策から派生したあらゆる結果にたいし責任を負ふといふ十六世紀的な奔放振りを発揮しつつ、なほ且つ更に進んで、一定の個人が政策形成に少しも関与してゐないのに、政策関与があつたかの如く責任を負はすのである。「事態の黙認」はこれが形成と「均しい」といふのである。
(2)検察側の理論は外交使節に関する全理論を壊滅せしめる。(K-四節)
この点については他の弁護人から詳論の予定であるから省略する。
(3)終局的権能を与へられた者の責任(K-六節)。この節は諸種の誤つた推定の下に立つてゐる。
第一に内閣と枢密院と内大臣は夫々(それぞれ)の権限内で政策の形成について最高の責任を附与されてゐるものとする。しかし枢密院は政策決定の義務はなく、単に之を批評する義務をもつだけである。内大臣の場合にはイニシアテイヴはさらに少ない。
第二に終局的権能を与へられてゐる者は部下の権力濫用にたいして責を負ふといふ、我々のつよく抗議する原則の存在を推定してゐる。英米法においてすら、ある人が使用人や代理人又は機関行為にたいして刑事責任を負ふのは、微罪の場合だけである。バーテンが時間外にビールを売つた場合旅館の主人が罰金を科せられるの類である。英国やスコツトランドでは、この原則適用はこの程度であると我々は理解する。検察側もその主張する提言についてなんら確信をもつてゐないらしい。けだしある箇所では、ある場合に「特にさう」であるといつてゐる。ある提言は正しいか正しくないか何れかでなければならぬ。時としては「特にさうである」といふのは、単純な真理としてそれが受け入れえないものであることを承認することとなるのである。
第三に同僚や部下の決定を黙認することは自らその権能を行使したのに「均しいものと見做しうる」と述べる。ポリス・コオトやジユージユ・ドウ・ペイ〔juge de paix〕の慣行以外に根拠となることのない代位刑事責任を死刑罪について推定するなどといふことは、心あるものにとつて堪ふべからざるところである。
(4)上官の責任(K-八節)
本節もおなじ刑事代位責任の理論の推定によつて議論を進めてゐる。事態によつては上官の匡正(きょうせい)的干渉が必要であり、事態を充分に知り、且つ匡正の機会をもちながらこれを怠つた場合国内法上責任を負ふことのあるべきはこれを否定しない。しかし国際的責任については我々は勿論全面的にこれを否定する。
(5)部下の責任
本節は下僚の責任を取扱つてゐるが、下僚はその主張する政策には行動が問違であることを明かにするに足る充分な情報を必ずしももつてゐないといふ事実を考慮に入れてゐない。しかもなほ検察側はかゝる官吏は非難の対象となつた行為に全然関与しないか、又はこれに反対し又はこれに反対の進言をしなければ刑事責任を負ふものとするのである。
(6)閣員の責任
本節もすこぶる大胆な推定をあへてする。
閣員はその同僚の主管する事項についてはその同僚の方が自分よりも熟知してゐるものとして、少くとも辞職するといふ程度まで自己の意見をつよく主張する丈の能力はないと思ふこともあらう。閣員は必ずしも外交関係や外交政策について、その職務上エキスパートである必要はない。或はある提案について疑をいだいて閣議で決を求めることもできる。しかし同僚殊に主管大臣の方が自分よりも事柄を良くわきまへてゐるものと推定しても少しも差支ないのである。
検察側が閣員は「悪いといふことについて完全な認識をもち」、「さう信じてゐる」とするのは著しく不当である。かれはそれが悪いなどとは考へてゐない。かれは内閣の同僚からそれは悪いことでない、君は心配しすぎてゐるといはれ、それを承認したとしても、少しも不当ではない。陸軍大臣と外務大臣とがそのよりすぐれた知識にもとづいて君は間違つてゐるといはれた場合、どうして農林大臣は侵略戦争について責任があるのか。現地を視察した取締役の報告にもとづいて、ニユー・ギネアのある財産について誤つた報告書を出すことに他の取締役が同意を与へたとしても、かれを犯罪人とすることができないのと同様である。
或は云ふであらう。「侵略戦争」は明々白々たる事柄で容易にこれを認識しうるから誰でもこれを拒絶せねばならぬといふ。それとは逆に、それは国家の性質とか物権的地役権の存在とその防衛とが、国家の利権にたいする脅威とか、又すこぶるつきの難問である自衛権の存否とかに依つてきまるのであつて、決定はすこぶる困難である。農林大臣は政策の皮相的面に動かされ、閣議で決を求めることもできよう。しかしかれは問題はきはめて難しく、自己は間違つてゐるだらうと想像しても少しも差支ないのである。かれは自己の主張にたいするうぬぼれの念にかられて、早急に辞職する必要は勿論ないのである。しかるに検察側はこのことを要求する。
勿論閣員が辞職を断行せねばならぬやうな場合もあるであらう。しかし本件の場合はさうした場合には該当しない。それは複雑且つ不確定な自衛権の問題であつて、自衛権の定義については、いかなる国家も満足な理論を与へえない種類の問題であるからである。
(7)統帥部と内閣
この節で検察側は統帥部の外交政策に及ぼす絶大の圧力を強調するにかかはらず、この圧力を制御しえない内閣に責任があるとする。内閣は辞職して国を政府なきままの状態に委すべきであつたのか、又財政的支出を拒否して国を軍隊なき状態に置くべきであつたのか。内閣が軍の意見に従つたからといつてそれは必ずしも非難さるべきではなく、又内閣又は閣員がその関与しえざるすべての計画について責任を負はさるべきでないことはきはめて明白である。検察側も亦(K-二九節)「ある行為にたいする責任は行為をなす力と義務に伴ふ」といつてゐる。そして内閣は統帥部を抑制する力はなかつたのではなかつたか。
(8)枢密院
枢密院は米国の上院とか英国の貴族院とは異つて、ただ一定の重要な事項について意見を開陳する丈(だけ)である。しかるにいはゆる「侵略政策」の形成に関与しえない枢密院を一定の事項についてのその行動が「侵略政策」の「形成に導いた」といふ理由で処罰すべしといふのである。かうした責任の負はせ方は、そのきはまるところを知らないであらう。すべての共産主義的著作者は「共産主義政策の形成に導いた」ともいへるであらう。
(9)内大臣
内大臣に関し「ある行為にたいする責任はその行為をなす力と義務とから流出するといふ通常の推定である」といふのはやや早計な推定である。
ここにいふいはゆる「推定」の意味は、A(日本皇帝又は日本の一般公衆)にたいし民事刑事の責任を追及されずに自由に進言をする義務的行動者は、B(訴追者たる聯合国)にたいして刑事責任を負ふといふ意味に外ならない。各国において自由な進言をなす義務あるものは、自由にではなく、その及ぼすべき影響の制約の下に、進言をなす義務があるといふなら、それなる「通常の推定」は通常どころか、不当なそして圧制的な推定なのである。さらに進んでは公衆を啓発することをその任務とする新聞記者は、その自由な言論に対し刑事責任を負はねばならぬと主張することになるであらう。これではフリー・プレツスはその姿を消すこととなるであらう。
内大臣は刑事責任の顧慮なく絶対自由に進言しうるのである。即ち内大臣は英米法にいはゆるアブソリユト・プリヴイリツヂ〔absolute privilege〕を享有する。そして検察側は英米において法律顧問の享有するこの特権を何等の理由なしに否定し去らうとするものである。
本節では検察側はその主張の基底をば全部くつがへして了ふやうな自認をしてゐる。元来検察側は被告の行為は法違反であると主張してゐるのである。しかるに内大臣が日本国内法上責任ある場合には、その責任は法によつて課せられるが、法によつて責任が課せられなければ引事実上の責任」があると検察側は明白に云つてゐる。かくして「事実上の責任」と「法によよって課せられた責任」とを同一視するのである。云ひかへれば、被告に義務と責任ありの検察側の主張は実は法にもとづくものではないことを示すのである。
一葉落ちて天下の秋を知る。検察側は不用意にも自らの主張する責任と法的責任とを鋭く対立せしむることによつて、自らの主張の基礎が空疎であることを曝露したのである。
本節は内大臣による総理大臣の推薦は日本慣習法の一部をなしてゐるとの推定をなしてゐるが、これは誤りであることの極めて明白な推定である。何人かがかゝる推薦をなす慣習はあつた。
それも英米における「憲法上の約束」と均しく慣習法ではない。かかる推薦が内大臣によつてなされるといふことは、憲法上の約束でさへなく、木戸侯爵がさうした意見を求められた最初の人であつたのである。
結語
裁判長並に裁判官各位。極東国際軍事裁判所は、技術的には「軍事」裁判所とよばれてゐる。しかしそれは敵国の報復のおそれを除いてはその放恣的傾向を抑制する何ものもない武力闘争の事態の下に、略式手続によつて戦争犯罪を処理する、法的な訓練も経験も、将又法的な公正や忍耐をも欠いてゐるお粗末な間に合せの軍事裁判所ではない。本裁判所は、敵対行動がすでに遥か以前に終了しそれが復活するおそれのいささかもないきはめて平和的な雰囲気のうちに裁判を行つてゐる。それ故全世界の人々は本裁判所が熟達した法律家から成る裁判所の機能を有つと共に世界政治一般特に極東政治の実際に精通した政治家、外交官、軍人、歴史家から成る特別陪審の資格を具へてゐることを期待する。被告人は通常の兇漢ではなく、高級の政治家軍人であつてその世界政治観は夫々異るとしても、総べてその知見に応じて、極東政治の荒波の中に国政を動かして来た人達である。しかもその極東政治は過去一世紀における東洋と西洋列強との政治的交渉に由来する歴史的所産であつた。極東に於ける安定勢力としての日本は既に過去のものとなつた。
そして極東における平和と秩序とを確保する責任は、他の指導的国民が担ふこととなつた。かうした事態の下において、被告人の面接した困難がいかなるものであつたかの真相は、正しく評価されることとなつたであらう。極東諸国民、いな全人類の視線は、すべて本裁判所の歴史的な判決に注がれてゐる。
本裁判の開始以前に、わが法曹界では、いはゆる裁判所条例なるものは、裁判所にたいし敵国の指導者を処罰する権限を与へ且つこれを命ずるために現行国際法の法則にお構ひなく包括的用語を以て規定せられた専断的な裁判指針にすぎないとか、いはゆる裁判所なるものは、司法的機関ではなく刑罰をふり当てる行政的機関にすぎぬとか、条例に表現された聯合国政府の政策と抵触する場合には国際法は当然無視されるであらうから今更むきになつて国際法の議論をしてもはじまらない、といつたやうな意見がしばしばささやかれたのであつた。
しかし一九四六年五月三日、本裁判の開廷に当つて裁判長が述べられた「本日ここに会合するに先立ち、各裁判官は、法に従つて恐れることなく、偏頗(へんぱ)の心をもつことなく、裁判を行ふ旨の合同誓約に署名した」、「われわれの大きな任務にたいして、われわれは事実についても法についても虚心坦懐にこれを考慮する」、「検察側は合理的な疑の存せぬ程度に有罪を証明すべき立証責任を負ふ」との言葉(英文記録二-二二頁)によつて右のやうな迷想は殆ど解消したのである。法に優越する何者をも認めない英米の法伝統を知る者にとつては、裁判長のこれらの言葉の意味は明々白々であつた。懐疑主義者はたしかにこれには面喰つたが、しかしなほ「法に従つて」とは「国際法に従つて」といふ意味に用ひられたのではなく、「条例に規定せられた法に従つて」といふ意味にすぎないのだと言ひ張つた。しかしさらに首席検察官がその壁頭陳述において、被告人達は国際法に関する行政府の決定によつてではなく、現行の国際法そのものによつて断罪せらるべきであり、本条例はかかる現行国際法を宣明せんとするものに過ぎないゆゑんを明白にされた。これによつてこの疑は完全に
解消した。
首席検察官自ら、コンモン・ロオに育まれた著名な法律家である。私人に対する政府の特権を何ら認むることなく、行政府の法解釈も公正な裁判所によつて排斥されることを認めるといふ英米司法裁判の特徴をなすフエア・プレイの精神を体得してをられるのである。そして政府の代表者も判決に於て自らの主張が全部排斥された場合にも、欣然としてこれに服するのである。
かるが故に弁護人側は、裁判所が被告人の有罪無罪を決定するに当つて、単なる条例の規定の字義通りの解釈によらず、(これによれば「戦争犯罪人」としての責任追及を免れうる日本人は殆どないことになる)被告人をも含めて万人周知の確立した国際法に依て裁判されるべきものと考へたのである。かくして弁護人側は検察側の挑戦に応じて、現行国際法の法則によれば、被告人は釈放せらるべきであることを証明せんと努力したのである。
かくして、検察側及び弁護人側の双方の共通信念によれば、本裁判は、被告人のみならず、全世界の政府が畏敬すべき国際法の尊厳を象徴すべきである。
バアラマーキ〔Burlamaqui〕が二百年前(一七四七年)にいつたやうに、国際法は諸国民又はこれを支配する主権者が服従すべき、それ自体において拘束力をもつ法である(バアラマーキ『自然法の原理』第二部第六章第六部)。本裁判は、一方検察官諸賢によつてきはめて有能に代表されてゐる戦勝国政府の政策と、他方敗れたりとはいへなほ自尊心を失はない国家の政治家及び軍人たる被告人の自由と生命―いな、より適切には国際面における基本的人権を争点としてゐる。かゝる基本的人権の擁護のためにこそ本裁判のアメリカ弁護人諸氏は来朝されたのである。
われわれはこの歴史に先例のない刑事裁判において、その画期的判決をなすにあたり確立した国際法のみに基づくべきことを裁判所にたいして強く要請する。法の認めない犯罪にたいして事後法に基き厳刑を科すがごとき正義にもとる処置は、必ずや来るべき世代の人々の心情のうちに遺恨を残し東西の友好関係と世界平和とにとって不可欠な欠くべからざる恒久の和睦を阻害する原因を作ることとなるであらうことは、賢明にして学識ある裁判所は万々御承知のことであらう。
来るべき世代の東洋の人々が―いな人類全体が―この画期的判決を広い歴史的視野か
らふり返つて眺めるとき、三世紀にわたる期間においで西洋の政治家や将軍がその行つた東洋地域の侵略について処罰をうけたことが一回もなかつたことを想起して、かれらは、東洋の一国の指導者にたいし事後法に基く処罰を行うたことについて大いなる不正が犯されたとの感想を抱くに至るかもしれない。
英国占領軍の厳格なる監視の下に審理された処刑を受けたオルレアンの一少女ジヤンヌ・ダルクは、後にはフランス国民から殉教者、聖女と見倣さるるやうになつた。
これと均しく、征服者の治下において、被告人の一人にたいし極刑が加へらるることがあるとすれば、それは平凡な一日本人をして、国民の殉教者、いなアジア解放の殉教者たらしむる危険を包蔵するものである。政治的又は宗教的指導者に科せられた死刑が、彼の罪科を浄めるだけでなく、さらに魔術的にその平凡なる生涯に光輝を添へることとなつた歴史的事例が多々存することは、裁判所の熟知される通りである。
かかる事後法的処罰は又、今や最高司令官の聡明な指導の下に、新憲法の厳格な遵守、従つて又その不可欠の一部をなす事後法による処罰禁止の規定の厳格な遵守を誓約してゐる日本国民にたいして、残酷な模範を示し、かれらの殊勝な熱意を冷却せしめることともなるであらう。かくしてそれはかれらに、勝利者の法と被征服者の法とは別物であるとの深い印象をあたへるであらう。かかる不正は、それは正しい法の支配なる一つの世界」の建設に役立つことのない権力政治のあらはれに過ぎぬものとみられるであらう。
そればかりでなくさらに、この歴史的なそして又劇的な裁判において、かやうな前例が設けられることは、本裁判所に代表せられてゐる戦勝諸国における刑事裁判の将来にも深刻な影響を与へることとなるかもしれない。さうした場合には、「血なまぐさい教訓は、必ずもとに戻つて教訓者を苦しめる」といふ格言が妥当することもあるからである。それ故厳格に法を遵守することこそは、司法的勇猛心の表現である許りでなく、裁判所のとるべき正しく且つ賢明な道である。周知のそして確立した国際法の原理を固守することによつて、又これによつてのみ、「文明」そのものの不可分の要因をなす法至上の灯光は、永久に国際社会を照らし、揺く灯としてでなく不動の灯明台として、嵐吹きすさむ世界に指標を与へることとなるのである。
東京裁判日本の弁明「却下未提出弁護側資料」小堀桂一郎編
「検察側の最終弁論中の法律論の反駁」高柳賢三
「検察側の最終弁論中の法律論の反駁Ⅱ」高柳賢三