四 殺人
(一)正当な理由なくして故意に人を殺した者を各国が殺人罪として取扱ふからそれは国際犯罪を構成すると云ふ検察側の議論(B-二一節)が正しいとすれば、場所と人とに関らず又は検察側の所謂「国際的性格」(その意味は不明である)の有無にかかはらず世界のいかなる場所でもそれは犯罪であることになる。これでは英国並に米国によつて終始支持され、又有名なロータス事件においてフランスも又強力に主張した「犯罪は地域的なり」といふ提言が全然消失して了(しま)ふことになる。これは到底認容することは許されないことであると弁護側は主張する。
更に殺人罪に対する免責事由は各国の法制上その軌を一にしない。死刑を廃止した国家は裁判所の命令をもつて免責事由とはせぬであらう。侮辱をうけた夫が間男を殺した場合、ある国では広い範囲の免責を認めるが他の国ではそれを認めない。如何にしてかうした雑多な法の状態をそのまま国際法規範としてこれを国際的に執行し得るであらうか。それによつてわれわれは自家撞着と変態的事態に堪へぬこととなるであらう。
A国ではXを殺人犯となし、B国ではXを死刑に処するのは殺人と考へるかも知れぬ。極刑を科する国際法上の殺人罪なるものはどうしても世界国家と世界法の存在を前提としてのみ成立する。斯かる世界国家は存在してゐない。又世界法は戦時における間に合せとして一般に行はれて居る戦争法規違反者の処罰等少数の場合以外には存在しない。「殺人」はペルシヤとフランスでは夫々異つた取扱を受ける。普遍的な要素丈を取つて国際法上の殺人を構成するといふことは事実にもとづかずして抽象を以てこれに代へることになる。しからば先づ抽象的国際的殺人罪を作つてそれに各国国内法の内容をこれに附着せんとする検察側の試みについては如何。
殺人罪の免責事由は各国まちまちである。検察側が殺人罪はいかなる場所でも同じであると言ひうるためには、すべての国家で侵略戦争の遂行は免責事由とならないことを立証する必要がある。各国裁判所はこれを免責事由とすべきではないことを立証してみても何等役に立たない。具体的に各国裁判所がこれを免責事由としないことを立証しない限り世界中何処でも侵略戦争は死刑に該当する犯罪として取扱はれて居るなど、推定することは許されない。そしてその証拠は少しも提出されてゐない。検察側の主張は全世界が彼等の見解と同様であることの立証を必要とする。スヰス国又はペルシヤ国の裁判所が無思慮に戦争を始めたと云ふ理由で総理大臣を殺人罪として処罰するであらうかどうか。
(二)B-二一節にある如く殺人罪は国際法の一部であると云ふのは単なる推定に過ぎない。
諸権威、特に一九二〇年の国際裁判所条例を起草した著名な法学者の国際法の広汎な法源理論は単に国家国民を拘束する国際法の法源に関するのである。
其の法源は(一)国際条約(二)国際慣習(三)文明国家問で認められた法の一般原則(四)判例(五)国際法学者の教説(六)正義、衡平法と信義誠実これである。
個人行為に関する原則が国際法の一部なりとする議論が提出されて居ると知つたら右の分類の起草者は恐らく驚倒するであらう。「文明国家が認むる法の一般原則」が掲げられたのは国家の行為に適用される意味で類推的に加へたのである。是れ以外の意味はありえないのである。
(三)国際法上に殺人罪が存在し―しかもそれは国際的性格をもたねばならぬと云ふ説明なき不明確な条件を附して―世界各国の裁判所が(夫々の原則に基きといふことらしいが)処理しうるといふ主張は全然不当である。はげしく論争された管轄権の問題はここでは不問に附せられてゐる。若しこの犯罪が国際法上の犯罪なのなら何故各裁判所がこれを取扱ひえないのであるか。検察側の論旨の全てが推定と架空の総合である。国内法、しかも蒸溜された国内法が国際法上に大量に移入されたと知つたら故フヰルモーア卿はその一九二〇年の同僚と共に仰天するであらう。
(四)戦争が殺人罪を阻却(そきゃく)するにはそれが合法的でなければならぬ、と云ふことは支持しえない提言である。けだし検察側の議論は正当なる理由がなければ殺人は死刑に該当する罪として各国によつて取扱はれるといふ絶対的同意に依拠するがゆゑである。なんとなれば、国家にとつて不法だとの意味に於いて、戦争行為が不法であるなら免責事由とはならないと、すべての国家が同意してゐることは立証されてゐないし、さうした蓋然性すらない。
そして検察側の論議の基底が、嬬るあやしい提言に対し各国が完全に同意してゐるといふことにあるからである。
(五)B-二五節(速記録三九〇三三頁)においては検察側は戦時中と戦争開始前に行はれた不法行為との間に何等差異なしとする。これは問題の論点を逸してゐる。論点は行為の違法性の軽重ではなく単にへーグ条約の適用範囲いかんの点にあるのである。戦争の遂行に何等関係なき行為にも及ぶものとすることはできない。
五 通常の戦争犯罪
通常の戦争犯罪は「俘虜摘要」(J-一-一六一節)中に論ぜられてゐる。これに関する法の問題は「被告の責任」(K)で取あつかひ「俘虜摘要」では単に事実の要約に止めるといふ趣旨である。しかし右の摘要中には法に関する一定の推定を前提としてゐるので、ここにはかかる推定の若干の面について批評を加へることに止める。
(一)ジェネヴァ条約の準用に関する所謂日本の約束(J-四六節)
検察側はそこに日本を拘束する国際的合意があつたものと推定してゐる。弁護側の見解によればこれは大きな誤りである。米国及び英国が一九四二年に云つたことは、自分達はジエネヴア条約に従ふつもりだから、日本もこれに従ふことを要望するといふのである。右両国のなしたその他の宣言もやはり同種のものであつて、やはり同じやうに理解せられねばならないのである。それはただ現在の態度に関する「ステートメント」であつて法的拘束力をもつ約束ではない。それらは日本の行動を条件としたものではなく、全然独立、自発的であつて約因のないものである。日本がこれを了承してもそれによつて米国及英国を拘束することにはならないのである。そこには「アグリーメント」とか「プロミス」(J-一六〇B節)
とかはないのであつて、日本の声明も両国の意向を了承し同様の意思を表明したのに過ぎないのである。この意思表示は前の意思の対価としてなされたのでなく、随意に行つたのである。従つてこの「カウンター・プロポーザル」を「約束」であるといふのは不正確である。これをなしたことが日本にとつて有益であつたとか、又「準用」の意味いかんとかの点は全然関聯性のない問題である。あたかも旅行者が他の旅行者にたいして「自分は明日歌舞伎座に行くつもりだが君はどうか」と云ひ、これにたいし「さう自分もやはりそのつもりでゐる」と答へた場合、そこには、道徳的にも法律的にも「合意」とか「引受」とかは全然ないのである。右の例が法の範囲外だといふなら他の例をとらう。株式所取引員は他の株式所取引員にたいして「自分は今週銅を出来値次第で売りに出るつもりだが君はどうか」と云ひ、これにたいし「左様自分もそのつもりだ」と答へた場合この二人のいづれもその思ふがまゝにふるまひうるので銅を売らうが売るまいが全然その自由である。
(二)ジエネヴア及びへーグ条約(J-六0B-一六一節)
検察側は「兎に角一九二九年ジエネヴア俘虜条約は一九〇七年へーグ条約のうちにすでに内在してゐたところを明示的に規定したものにすぎない」と云ふ。しかし、一九二九年の条約は単に現行法を成文化した丈でなく俘虜の状態を改善するために之を修正したのであることは明かである。へーグ条約前文の一般的宣言は予見すべからざる場合の処理について、軍司令官の不当な行為につき国家に賠償責任あることを示さんとしたのであること、以上のことをそれから引出すことは許されない。それは国家がこれらの場合を予見し軍司令官に命令を発することを国家に期待してはゐないのである。
前文の宣言は右の条約は網羅的ではなく、予期すべからざる事件が起つた場合に適用すべき法について軍司令官の判断が終局的だと国家が主張することは許されないことをいつてゐるにすぎないのである。
凡そ条約の前文なるものは、いかなることも制定することはできないのである。そしてこの前文はその次の本文の条項が網羅的でないことを宣言したのである。一九〇七年へーグ条約の主たる目的は国家の責任を確保するにあつたのである。伝統によつてみとめられた少数の場合にだけ認められる個人の責任については、殆んど注意がはらはれなかつたのである。況んや政府高官の責任などは全然考へてゐなかつたのである。前文における問題は将校のグループと他のグループ―軍指揮官と内閣の何れに責任を帰せしめるかといつたやうな問題ではなく、国家責任を確保するといふ問題であつたのである。かるが故に署名国は軍指揮官の専断的な判断にかくれて責任を免れることをえないものとしたのである。かゝる宣言―その次に違反国は賠償を支払ふべきことを規定し、大臣の責任などには少しもふれてゐない―をゆがめて、政府高官に個人責任があるといふやうな解釈がなされるとすれば、それは将来の政治家にたいし英国の「チヤンサリ、バリスタ〔Chancery barrister〕」〔や不動産専門の批評家〕が払ふやうな細心の注意を以て起草しないと国際条約は危険極まるものであることの警戒となるであらう。しかし、従来国際条約は同様な思想的背景をもつ友人間の協約であつて寛大な精神で起草されたものであることを忘れてはならない。
最後に検察側はへーグ条約中のガヴアメントと云ふ字句の使用から条約遵守についての閣員その他の個人責任を引き出してゐる。
へーグ条約に於けるガヴアメントといふのは色々の資格でその時々に統治をいとなんでゐる個人をいふのではない。この言葉はステイトのシノニムとして用ひられる。最近の慣行によれば条約はガヴアメント間に締結されるといふ風に書かれてゐる。然し何人も大臣の職務を行つてゐる個人、いはんやその下僚が条約の当事者であるなどとは考へないのである。英国におけるドイツ俘虜はアトリ氏やモリスン氏やミス・ウイルキンスンによつて個人的に管理されてゐるとは誰も考へない。それは国家を意味するのである。何人もサア・スタフオド・クリツプスやジオセフ・ウエストウツドやジョイス卿が俘虜扶養の費用を支払ふ義務があるなどとは考へない。しかしへーグ条約第七条は俘虜をその権力内にもつに至つたガヴアメントは俘虜の扶養のための費用を支払ふ義務があるものとしてゐるのである。
検察側の議論はガヴアメントの二つの意味即ち、
(1)「統治を行つてゐる人」と(2)「国家主権の非人格的権化」との間の混乱にもとづいた誤魔かしであること一目瞭然たるものがあるのである。条約の条項違反に対して青任があるのは国家なのである。へーグ条約のいかなる個所をみても大臣その他の文官が交戦行為を監督し抑制する義務があるとか、又いはんや交戦規則違反の罪を分つ責任があるとかのことを示唆するものは絶無なのである。へーグ条約はかかる義務と責任とを課することによつて、全統治機関を軍法の下に置くこと殊謙可能であつたのである。然しその制定者は、さうしたことをしないだけの聡明さをもつてゐたのである。そして驚くべき解釈によつて条約制定者が明示的にさけたところを試みないことが賢明であること勿論である。
(三)検察側の思想は「一般的断定には欺瞞(ぎまん)が隠されてゐる」といふ格言を無視してゐるやうである。それは「共同計画」又は「中央官憲から発した命令」の証拠としての「共通の型」の理論に特に顕著に現はれてゐる。
検察側は「日本人の行つた犯罪は、日本及び日本人の占領した多くの場所においてその性質についても又手口についても同一であつた事実は、犯罪が各々の犯行者の思ひつきで行はれたのではなく〈共同計画の〉一部として行はれたといふ殆んど不可避的な推論に導くものである。又それら犯罪はそのための〔特〕別訓練又は少くもある中央官憲から発した命令の結果であることをつよく証明するものである」といふ。
これでは重大な刑事的訴追の基礎とするには余りにも漠然としてゐる。
けだし検察側は所謂「型」なるものが到るところで画一的に存在するとさへも云つてゐない。ある場合にはさうでないことを自認するのである。それは「その目的の為の特別訓練」或は「少くもある中央官憲から発した命令」の推定を打破してゐることになるのだ。それだけでなく検察側のかゝるいはゆる各「型」を熟視するならば逆にそれはその犯罪なるものは突発的なものであること、且つ「共通の計画」も、またある「中央官憲からの命令」なるものも全然存在しないことを立証することとなつてゐるのである。
(1)逃亡せざる宣誓又は約束(J三一乃至三九節)これ等各節の叙述は真に強制のあつた事件を示さんとする趣旨である。そしてシンガポール(三件)香港(二件)ボルネオ、ジヤヴア、善通寺及び台湾以外の場所に関して、なんら事件が掲げられてゐない点は重要である。印度ビルマ及び比島に関しては何もいつてゐない。従つてこの型は大きなギヤツプを示してゐる。又事実上所謂強制行為のやり方について共通なるものはない。あるときは脅迫、あるときは熱、あるときはその結合である。どこに共通の型があるのか。勿論そこには宣誓の要求といふ共通の特徴はある。
然しこれは厳格な監視を免れるがための公正な対価として許さるべく且つ正当な拠置である。又これらの事件はみな一九四二年の最初の九ケ月に起つてゐる。このことは反つて不法な強制をやる公的政策のなかつたことの有力な証拠ではないのか。若しこれらの残酷な処置がとられたとすればそれは各地の下級将校の偶発的行為であつたのである。
(2)殺戮(J一四一-一四四節)
(イ)色々な方法で行はれたとされてゐる所謂殺戮について「型」を発見することは困難である。検察側もそこに型を発見することができないのである。それをある動機で結びつけることを躊躇してゐるからである。厄介を避ける為であるとか、住民に恐怖心を起させるためだとかのあて推量はしてゐる。然しそこに型があるとは主張してゐない。そこに述べられた事件が仮に証明されたとしてもそれは一九四二年の三ケ月問に一定数の殺戮事件が起つたといふことである。たとへかかる事件が起つたとしてもそれは「ある中央官憲から発した命令によつた」といふよりも寧ろそれは直ちに抑止されたことを示すものである。
(ロ)(J-一四五節)この節に叙述されてゐる殺戮事件は仮にそれがあつたとしても殆んど総て一九四三年にボルネオで行はれたものであつて地方的な叛乱の抑圧の際に起つたもののやうである。武力による反乱鎮定は仲々なまやさしい方法でできるものではない。暴力、いはゆる「戦争叛逆者」を前にしての軍事的処刑はあらかじめ裁判の方法を必要とする場合には該当しないのである。
(ハ)J-一四六、七、八節の叙述は何等の「型」を示してはをらない。
それらが仮りに証明されたとしても、それは敵の侵入が近づいた際、時として俘虜が殺されたと云ふことを示すのに過ぎない。検察側は、それは俘虜による幣助の供与を防止する為であつたらうとその動機について推量するが、それは検察側が自認する如く、一つの推量に過ぎない。
「推量」によつて「型」を証明することは出来ないのである。かかる場合における俘虜の殺戮は時としては適当且つ許さるべき軍事的予防手段であるかもしれないのだ。次に検察側は侵入を「予見的」事件として取扱ふといひながら、直ちに「空襲後起つた」殺数事件(タラワ)を引用してゐるのは矛盾である。とにかくこの「予見的」型の事件の発生は極めて少数しか主張されてをらない。それらの事件から何等の「型」を見出すことは出来ないのである。俘虜による脅迫の話や、書記による密令の話などは「強い傍証」ではなくして、それは極めて薄弱な証拠に過ぎないのである。もしも「中央」「最高」の日本の政策なるものが存在したのであつたならば、それは少数の場所においてではなく、劃一的に、常に如何なる場所に於ても適用されたことであらう。
とにかく、仮想された「最高の政策」を「日本の」として表示することは不十分であつてこれについて、如何なる日本人が責任があるのかを特記することが必要である。
日本軍隊のとる原則は、俘虜に対する義務は日本将兵の生命の保持に優先せずといふにあつたことは有りうべきことである。又、個々の場合に於て、指揮官がこの原則を不当に拡大したこともあり得べきことである。然しそれは、それら指揮官がさうした命令を受けたことを意味しない。そして右の原則そのものは、へーグ条約及び未批准の一九二九年のジエネヴア条約に反するものではないのである。
憲兵隊の使用した拷問に関して、J-一五六節は次の如くいふ。「その画一性に照しそれらは偶然に発生したはずはない。それは共通の訓練の結果であつたに相違ない。然しもしもかかる共通の訓練が与へられたとするならば、それは政府の政策事項であつたに違いない」。
右の「共通訓練」の推論は常識上ありえないことである。又拷問といふことは或る職業にともなふ共通の職業心理に起因するのかも知れないからである。更に進んでなされた右の訓練は「政府の政策事項」であつたといふ推論は、訓練は「軍事訓練」を意味することになるので、これ又誤つた推論である。軍事訓練の詳細を監視することは政府の任務ではないからである。
(四)検察側がこの摘要を通じて広汎且つ不分化の「日本政府」といふ字句を使用したことは検察側の責任理論に照応するのであるかもしれない。「日本政府」といふのは「閣員のみならず、陸海軍将校、大使及び高級官吏を包含した広い意味で」使用されてゐると云ふ。且つ日本政府といふ言葉はこのサメーシヨン〔Summation・最終弁論〕を通じ観察すると、この簡単らしく見える定義に更に「又はそれらの或るもの又は全部」といふ言葉をそつと附け加へたかの如くに使用されてゐるのであることを発見する。かうした特記なくして概括的字句を用ひて刑事責任の存在を主張することが個人としての被告人に対する刑事裁判に於て、きはめて不当であることは明白である。かうした技術は国内裁判所に於ては許容されないところであらう。例へば、或る戦争犯罪その他の事項が「日本政府」に知られて居つたといふ場合には、実際は少数の者しか知らなかつたに拘らず、以上の定義に包含せられる者全部が知つてをつたといふ誤つた推論に導きやすいのである。又一定の政策が「政府の」政策であると云ふ場合には、実は単に軍の軍略的政策にすぎないので、他の閣僚や、大使や、高級官吏は何等それに関係しなかつた場合でも、彼等すべてがそれに対して責任があるかの如
く響くのである。
通常の戦争犯罪に関する訴追についても、推定に基いて被告人に極刑を科すべきではなく、若し仮りに被告に罪ありとすれば、それは個人的犯罪の立証に基かねばならない。我々は、賢明なる裁判所が本摘要に充満する「推定」によつて誤られないことを要望するものである。
(五)J-六節において次の如くいはれてゐる。
「他方本部門では検察側において証拠を提出しなかつた俘虜収容所員の他の場所に関する弁護側の証拠を無視している。これは裁判長の弁護側に向けた言葉“チャージ〔charge・問責〕がなされた事項にたいして答弁しなさい。チャージがなされて居ない場合、そこに欠点がなかつたことを立証しようと試みてはいけない”によつたのである」。
検察側が弁護側のさうした証拠を無視することは明白に不公正であるが、これは検察側の推測を基礎とする責任理論と関聯するものであらう。弁護側はよい状態の証拠を提出してはならない、悪い状態のチャージに対応せねばならないといふのが裁判長の見解であるとするなら、このことはそれら特定の場所における将校に対するチヤージに対して尤もである。より高級の将校に関してはその管理下の他の場所おいて、状態がよかつたことの立証は関聯性あること明白である。それは非難をうけた場合においても状態は良かつたとの推論に導くからである。監督の欠陥があつたとされる被告の場合には、そのチヤージにたいしてかれの監督が一般的に効果的であつたことの立証は関聯性があるものとせねばならない。反カトリツク暴動に関与したことで起訴された場合、被告が法王の侍従長であつたことを立証することは関聯性がある。
続く
東京裁判日本の弁明「却下未提出弁護側資料」小堀桂一郎編
「検察側の最終弁論中の法律論の反駁」高柳賢三
「検察側の最終弁論中の法律論の反駁Ⅲ」高柳賢三
















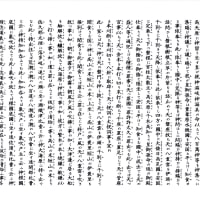

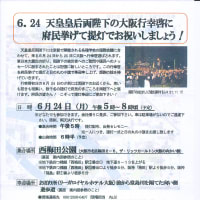

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます