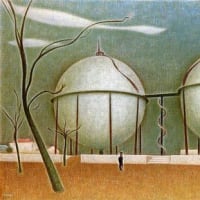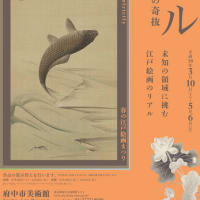遅い夏休みを取って新潟県の八海山に登ってきました。
八海山は、標高1778m。
山頂は、八ツ峰と呼ばれる岩峰群があり、垂直に近い鎖場が連続する難所となっています。

新開道から見た八ツ峰

稜線は切り立った岩場が続く

鎖場は高度感があってスリル満点
実は登り始め、頭を蜂に刺されるアクシデントもあり、引き返そうとも思ったのですが、登ってみれば、なかなかスリルがあってかなり楽しめました。
鎖場が延々と続き、高度感もあって、難しいといわれている剱岳のカニノタテバイと呼ばれる岩場よりずっとリスキーです。
そんな山なのに、地元の人などでけっこう賑わっていてちょっとびっくり。
中には長靴で登っている人もいました。
また元々、信仰の山なので、八ツ峰のそれぞれの山頂にはお地蔵さんや不動明王の像などが祭ってあったりしてそんなところも興味深かったです。
紅葉には少し早かったのですが、これで紅葉していたら本当に最高だろうと思います。
それほど有名ではない山ですが、わざわざ新幹線に乗っていく価値がある楽しい山行となりました。
で、今回、この八海山に来たもうひとつの理由が、八海山醸造。
新潟の銘酒として有名ですが、縁あって蔵の見学や美味しいご馳走をいただくことが出来ました。

普段、日本酒をよく飲みますが、八海山というお酒は、名前は知っていても、あまり積極的に飲んではきませんでした。
でも、今回、蔵を見せてもらい、社長さんやスタッフの方から、話を聞くことで印象がずいぶん変わりました。
社長さんからは、「八海山というお酒は、日常のお酒として飲んでもらうために造っている。だから飲み飽きないように、華やか過ぎる香りなどは付けずに醸している」と聞きました。
また、「自分たちの蔵の使命は、日本酒のレベルを上げること。そのための規模拡大や機械化も積極的に進めている。趣味的に小さな規模で美味しいお酒を造るより、自分たちが理想とする高い水準の日本酒を安定的に供給することが、日本酒という文化を守る唯一の方法だと思う」とも話してくれました。
実際、新しい工場は規模も大きく、機械化も進んでいましたが、人の手をかけたほうが良い部分、例えば麹造りなどの重要な作業はほとんど機械化せず、蔵人達の手で丁寧に行われています。
工場や売店などもみんな新しく、そこで働く人たちもきびきびしていて、八海山で働く誇りや喜びを感じさせます。
今回、八海山という名前の山と酒蔵を訪ねましたが、どちらも味わい深いものでした。
季節を変えてまた行きたいものです。
八海山は、標高1778m。
山頂は、八ツ峰と呼ばれる岩峰群があり、垂直に近い鎖場が連続する難所となっています。

新開道から見た八ツ峰

稜線は切り立った岩場が続く

鎖場は高度感があってスリル満点
実は登り始め、頭を蜂に刺されるアクシデントもあり、引き返そうとも思ったのですが、登ってみれば、なかなかスリルがあってかなり楽しめました。
鎖場が延々と続き、高度感もあって、難しいといわれている剱岳のカニノタテバイと呼ばれる岩場よりずっとリスキーです。
そんな山なのに、地元の人などでけっこう賑わっていてちょっとびっくり。
中には長靴で登っている人もいました。
また元々、信仰の山なので、八ツ峰のそれぞれの山頂にはお地蔵さんや不動明王の像などが祭ってあったりしてそんなところも興味深かったです。
紅葉には少し早かったのですが、これで紅葉していたら本当に最高だろうと思います。
それほど有名ではない山ですが、わざわざ新幹線に乗っていく価値がある楽しい山行となりました。
で、今回、この八海山に来たもうひとつの理由が、八海山醸造。
新潟の銘酒として有名ですが、縁あって蔵の見学や美味しいご馳走をいただくことが出来ました。

普段、日本酒をよく飲みますが、八海山というお酒は、名前は知っていても、あまり積極的に飲んではきませんでした。
でも、今回、蔵を見せてもらい、社長さんやスタッフの方から、話を聞くことで印象がずいぶん変わりました。
社長さんからは、「八海山というお酒は、日常のお酒として飲んでもらうために造っている。だから飲み飽きないように、華やか過ぎる香りなどは付けずに醸している」と聞きました。
また、「自分たちの蔵の使命は、日本酒のレベルを上げること。そのための規模拡大や機械化も積極的に進めている。趣味的に小さな規模で美味しいお酒を造るより、自分たちが理想とする高い水準の日本酒を安定的に供給することが、日本酒という文化を守る唯一の方法だと思う」とも話してくれました。
実際、新しい工場は規模も大きく、機械化も進んでいましたが、人の手をかけたほうが良い部分、例えば麹造りなどの重要な作業はほとんど機械化せず、蔵人達の手で丁寧に行われています。
工場や売店などもみんな新しく、そこで働く人たちもきびきびしていて、八海山で働く誇りや喜びを感じさせます。
今回、八海山という名前の山と酒蔵を訪ねましたが、どちらも味わい深いものでした。
季節を変えてまた行きたいものです。