米国ベストセラー著書にみる「思慮あるしつけ」の日常実践例
『No Drama Discipline: the whole-brain way to calm the chaos and nurture your child's developing mind』
by Daniel J. Siegel, M.D. and Tina Payne Bryson, Ph.D.
のp.66-68に紹介されている事例です。
ーーーーー意訳始まりーーーーー
お父さんはバスケットボールの試合中継を見るためテレビの前。
コマーシャルになったら、上の階の子ども達の様子を見に行こうと決めています。
8歳のお兄ちゃんとお友達と5歳の弟君が、レゴの整理に取り組んでいます。
お兄ちゃんはこの日のためにお小遣いをはたいて、「釣り道具を小分けにして収納する入れ物」を購入。
レゴフィギュアの頭、胴、剣や弓矢など持ち物まで細かく分類していきます。
分類のアイデアも次々飛び出し、夢中になってレゴを整えるお兄ちゃんとお友達。
次第に、5歳の弟君には、複雑過ぎて、よく分からなくなっていきます。
お兄ちゃん達は、弟君にはまだ難し過ぎるからと、弟君が参加することを拒み始めます。
怒りがこみ上げる弟君。
整理整頓済みの入れ物をつかみ、床に投げつけたああああ!!!!
何百ものレゴが、音を立ててハードフロアに散らかり、入り口のドアから部屋のすみずみまで広がります。
階下で音を聞きつけ、何事かと部屋へ現れるお父さん。
「○○(弟君)が全部むちゃくちゃにしたー!」
泣叫びながら部屋を走り出るお兄ちゃん。お友達も居心地悪そうについていきます。
真っ赤になって鼻息荒く立ちすくむ弟君。
さて、お兄ちゃん達が一生懸命分類したレゴがめちゃくちゃになっただけでなく、
部屋中に散らばったレゴも片付けなくてはなりません。
おまけに、バスケットボールの試合も見逃すことになってしまい。
弟君に指をつきつけ、
「なんでこんなことをするんだ!
だから○○(兄)達がおまえにレゴを触らせたくないのが分かるか!
二度と○○(兄)達の遊びに参加するなああああ!」
と、思わず叫びたくなります。
そこへ、「“考える” 脳の箇所(階上)」が発動。
「全脳に働きかける」アプローチを試してみます。
弟君が今まず必要なのは、
「お前みたいなちびっ子には理解できないよ」と仲間はずれにされ、
傷ついた気持ち、悲しみ、怒りを落ち着けること。
「してよいこと/ よくないこと」を「教え・学ぶ」よりも、まずは、「コネクト」。
お父さんは、膝をついて腕を広げます。
お父さんの胸に顔をうずめる弟君。
お父さんは、嗚咽する弟君の背中をなぜ、
時折「I know, buddy, I know(分かるよ、○○(名前)」とだけ言います。
少しすると、弟君はお父さんを見上げ、涙目で「レゴ、こぼしちゃった」といいます。
お父さんは少し笑って、「“こぼしちゃった”よりも、随分ものすごいけどね!」
弟君も少しふき出し。
ここで、お父さんは「教え・学ぶ」ことのできる状態になったなと思います。
そうして話し始めます。
お兄ちゃんがどう感じたか。
自分たちの行動というのは、しばしば他の人々に大きな影響を与えること。
強い感情をどう表すのが適切なのか。
弟君も、今では、お父さんの言うことを聞き、考え、お兄ちゃんの気持ちを想像し、
今度はどうしたらいいか?と思うことができるようになっています。
ーーーーー意訳終わりーーーーー
まずは、気持ちを落ち着けること。
感情が高まっている時とは、脳の「階下の(大脳辺縁系)」が活発になっている状態。
考え、想像し、共感し、記憶するといった前頭野を含む「階上(大脳皮質)」は、
うまく機能してない状態といいます。
その感情の高まりを落ち着けるのが、著書曰く、「コネクト」なんですね。
子どもにとっては、気持ちを認めてもらい、大好きなパパやママの温もりに包まれること。
感情が落ち着けば、考え、想像し、共感しと、「教え・学ぶ」こともできるようになります。
実生活での実感
私自身振り返り、
このお父さんが、立ちすくむ弟君に向け、思わず指をつきつけて叫びそうになった言葉、
「なんでこんなことをするんだ!だからお兄ちゃん達はおまえにレゴを触らせたくないのが分かるか!二度とおにいちゃんとお友達の遊びに参加するな!」
何度こみ上げ、実際投げつけたこともあったか・・・。
でも、そうして繰り返すうちに、
この「まずはコネクト、それからリディレクト(導く)」という方法が、
結局は、最も近道で効果的だと、今では心の底から実感しています。
こちらは、当時4歳だった次男とのやりとりをまとめたものです:
全部飲む!「条件づけ」と「無条件の愛情」
冷蔵庫にひとつだけ残ったヨーグルトドリンクを飲みたい!
→他の子も飲みたい!
→皆で分けてね。
→分けたら一人お猪口にちょっとぐらいの量になる。
→癇癪。
→抱っこゆらゆら。次第に気持ちが落ち着く。
→落ち着いたら、自分から皆に分け始める。
といった出来事。
当時私自身は、
「ああこれが、無条件の愛情をひっこめることなく、それでも『リミット』は教えていくということなんだな」
と自分なりにイメージしていました。(成長には、無条件の愛情と条件付けの両方が必要)
それは「より力の入る利き手で抱き、もう片方の手で押しやる」
といったイメージともいえるなあ、と。
そこへ、この著書『No Drama Discipline』に出合い、
「脳の機能」からの説明を学び、よりすとんと整理でき、
「新しい言葉」を与えてもらった!というような気持ちでした。
無条件に感情面を包み込みつつ、
してよいこと・よくないことの「リミット」も「教え・学び」としていく。
「考え、想像し、記憶する」ことのままならない脳の状態にあるときに、
いくら教えようとしても伝わりやしません。
目の前の「好ましくない行為」の「よし悪し」はひとまず横に置き、
まずはコネクトし落ち着く。
是非、実生活でお試しください!
結局、近道で最も有効なのだと実感されると思います。
メモ:
・「良心」とはリミットが内在化したものなのか?
それとも、本来元々備わるものなのか?
それは分かりませんが、
大きくなるにつれ、「コネクト」で気持ちを落ち着けるにつれ
自ずと、この「良心」が表れる場合があるとも感じています。
すると「教え・学ぶ」とする必要もなく、自ら動き始めます。
・また、「大脳辺縁系」(強烈な感情、反射、不安恐怖)と
「大脳皮質」(考え、想像し、共感し、全体像を観られる)のバランスについて、
エレイン・アーロン氏も、「敏感な子は前頭野(考える箇所)が活発」というようなことを言っているんですが、
「敏感な子」って、周りの人々の期待や状況を読み(過ぎ)、
期待にこたえようと本来の年齢の脳の発達には不自然なほど「考える部分」に偏りすぎ、
「大脳辺縁系」(強烈な感情、反射、不安恐怖)が爆発して癇癪などを起こしてしたりと、
バランスを壊しやすいのかな、と感じたりします。
著書『No Drama Discipline』には、
「脳の考える部分に働きかける繋げる」ということがよく書かれているんですが、
「敏感な子」の場合はバランス的に、
「原始的な機能(感情など)」をのびのびと発揮できるような場を整えることが大切だなあと感じています。
あくまでも、脳科学についての素人が、日頃「敏感な子」達に接する中で感じていることです。
「良心」の表れや、「敏感な子」への働きかけについて思うこと、またまとめたいです!
さて、怒涛の週末が始まります!4連休!
それでは皆さん、楽しい週末を!










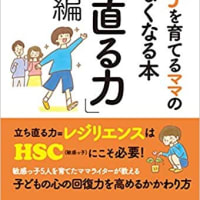





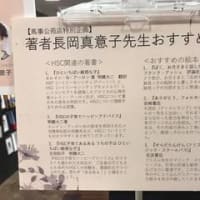

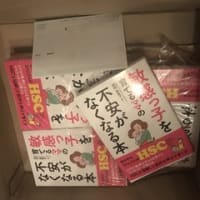

これからも楽しみにしています
ありがとうございます、励みになります!