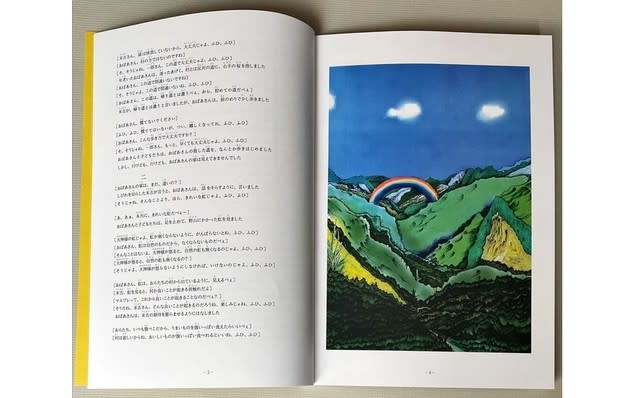1.ムラサキカタバミ

和名:ムラサキカタバミ (紫片喰、紫酢漿草)
別名:キキョウカタバミ
分類:カタバミ科カタバミ属
原産地:南米
以下はGKZ植物辞典の引用です。
地下に褐色の鱗茎があり、たくさんの小鱗茎ができるので、繁殖力は強い。葉はみな根性葉で、長い柄の先に3枚のハート形の小葉が着く。花は淡紅色の弁花。
わが国へは18世紀頃渡来しているが、現在では帰化植物状態に野生化している。
2.オトメギキョウ

和名:オトメギキョウ(乙女桔梗)
学名:Campanula portenschlagiana
別名:ベルフラワー
科名 / 属名:キキョウ科 / ホタルブクロ属
以下は「趣味の園芸」の引用です
オトメギキョウは初夏に花を咲かせる、ベルフラワーの名でよく知られた常緑性の小型多年草です。3月ごろから促成栽培されたものが出回り始め、4月から5月に最も多く流通し、花屋の店先を飾ります。
草丈は10~15cmほどで、小さな濃い緑色の葉を多数つけ、茎は根元から密に枝分かれして直径30~40cmほどのクッション状の茂みになります。それぞれの枝先に1~数輪の花をつけます。花は青紫色で直径2cm前後、釣り鐘形で上向き、あるいは斜め上向きに咲きます。
3.ヤマモモソウ

和名:ヤマモモソウ(山桃草)
学名:Gaura lindheimeri
別名:ハクチョウソウ(白蝶草)、ガウラ
分類:アカバナ科 / ヤマモモソウ属(ガウラ属)
以下は「趣味の園芸」の引用です。
ガウラの穂状に咲く小花が風に揺れる様子は、白い蝶が群れて飛んでいるようで、やさしい風情が感じられます。性質は強健で耐暑性もあり、初夏から晩秋まで次々と花を咲かせながら株が大きく成長していきます。花弁は4枚で、長い雄しべがよく目立ちます。1つの花は短命で3日ほどで散りますが、花つきがよく、ほとんど途切れることなく咲き続けます。日本へは明治時代中ごろに入ったといわれています。以前は、草丈1m以上に伸び、白花だけでしたが、近年、濃いピンクの‘シスキューピンク’の育成に始まり、複色、草丈の低いものなど、多くの園芸品種が育成され、利用されるようになりました。

和名:ムラサキカタバミ (紫片喰、紫酢漿草)
別名:キキョウカタバミ
分類:カタバミ科カタバミ属
原産地:南米
以下はGKZ植物辞典の引用です。
地下に褐色の鱗茎があり、たくさんの小鱗茎ができるので、繁殖力は強い。葉はみな根性葉で、長い柄の先に3枚のハート形の小葉が着く。花は淡紅色の弁花。
わが国へは18世紀頃渡来しているが、現在では帰化植物状態に野生化している。
2.オトメギキョウ

和名:オトメギキョウ(乙女桔梗)
学名:Campanula portenschlagiana
別名:ベルフラワー
科名 / 属名:キキョウ科 / ホタルブクロ属
以下は「趣味の園芸」の引用です
オトメギキョウは初夏に花を咲かせる、ベルフラワーの名でよく知られた常緑性の小型多年草です。3月ごろから促成栽培されたものが出回り始め、4月から5月に最も多く流通し、花屋の店先を飾ります。
草丈は10~15cmほどで、小さな濃い緑色の葉を多数つけ、茎は根元から密に枝分かれして直径30~40cmほどのクッション状の茂みになります。それぞれの枝先に1~数輪の花をつけます。花は青紫色で直径2cm前後、釣り鐘形で上向き、あるいは斜め上向きに咲きます。
3.ヤマモモソウ

和名:ヤマモモソウ(山桃草)
学名:Gaura lindheimeri
別名:ハクチョウソウ(白蝶草)、ガウラ
分類:アカバナ科 / ヤマモモソウ属(ガウラ属)
以下は「趣味の園芸」の引用です。
ガウラの穂状に咲く小花が風に揺れる様子は、白い蝶が群れて飛んでいるようで、やさしい風情が感じられます。性質は強健で耐暑性もあり、初夏から晩秋まで次々と花を咲かせながら株が大きく成長していきます。花弁は4枚で、長い雄しべがよく目立ちます。1つの花は短命で3日ほどで散りますが、花つきがよく、ほとんど途切れることなく咲き続けます。日本へは明治時代中ごろに入ったといわれています。以前は、草丈1m以上に伸び、白花だけでしたが、近年、濃いピンクの‘シスキューピンク’の育成に始まり、複色、草丈の低いものなど、多くの園芸品種が育成され、利用されるようになりました。