
それはまだレゲという音楽をレゲと呼ぶのが正しいかレガエと呼ぶのが正しいか、なんてのどかな議論がなされていた頃の話であるが。あっと、”レガエ派”の急先鋒は中村とうよう氏であったのだけれども。で、もちろん、アナログ盤の時代の話ね。
あの頃、「世の中にはレゲ(レガエ)などという音楽があって」という”紹介もの”としていくつかコンピレーションもののアルバムが出されていた。まだ出す側もあんまりレゲという音楽の何たるかも。まあ、分かってはいたかも知れないが、どのように売って行ったら良いのかに関しては手探り状態であったはずだ。
その辺のアルバムに入っていた音楽って、ちょっと好きだったなあ。ジャケには椰子の木なんかがあしらわれ、まだラスタがどうの、といった影も見えず、なんだかハワイアンのアルバムと見た目は変わらない。音楽自体は軽いノリのR&B曲カヴァーが主体だった気がする。
気がする、というのは、もうそれらは手元には残っていないからなのだが。その後に出された”本格もの”を聞くにつけても、それらはいかにも入門用のサンプルっぽい匂いがして、もう持っている必要がない、というか持っているのが格好悪く思え、さっさと始末してしまったのだ。
これはつまらない選択だったなあ。あれってなかなか良い雰囲気の音楽だったぞ。いま思えば。実にシンプルにアメリカのR&Bのカヴァーであり、その安易さ、腰の軽さが、いかにも大衆音楽の楽しさを伝えていた。大衆の甘やかでいい加減な夢の集積としての愛しきポップ・ミュージックの顔をしていた。
後に知ることとなるジャマイカの現実、それを伝える音楽としての重い手触りなどとはずいぶん様相の違う代物。
あのようなものをレゲの入門用に持ち出したことを、紹介者側は”レゲという音楽に誤解をもたらす反省すべき選択だった”とか考えているんではないかなあ。その後の”日本のレゲ・シーン”が辿ったシリアス路線を思えば。
その背後に控えるシリアスなメッセージなど語るほうが、そりゃカッコイイし、ワカモノたちにも話題として売り易いんだろうけど。でも、”偉大な芸術家の高貴な芸術音楽”よりも”庶民の低レベルな娯楽”の中に瞬間宿る輝き、そんなものに心引かれる性分の私としては、あの”軽レゲ”路線がそのまま続いていたら、今ごろ結構なレゲ好きでいられたのではないかなどと思ったりもするのだ。
なんて事を言うと、本格派のレゲファンに叱られてしまうのかも知れないが、あの”椰子の木陰のお調子者の娯楽音楽”が、今となってはいとおしい私なのであった。
それにしても、あれらのアルバムに収められていたミュージシャンって、誰だったのか。調べれば分かることでもあるんだろうけど、そうせず放ってある。
それらを手放してこれだけ時間が経ってしまうと、思い出の中でイメージが増殖して、いざ本物を聞いてみたら「なーんだ」ってなことになる場合も往々にしてあるからね、思い出のままに置いておく方がいいのかも、とか思って。
微妙なものであります、音楽との出会い方、付き合い方も。










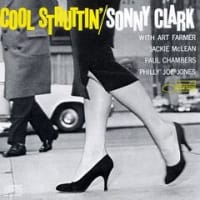


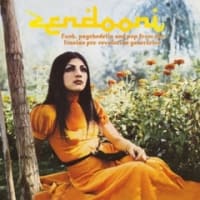
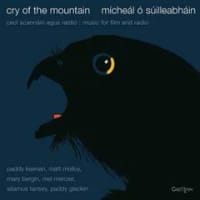
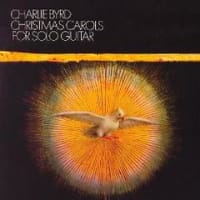
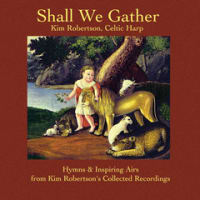
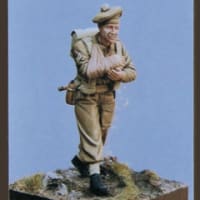

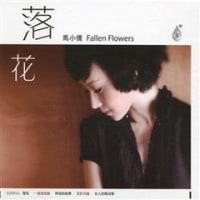
何かが生まれている瞬間を体験できるのってすごくうらやましいです。レゲエでもロックでも、カリプソでもジャズでも、大きなうねりが今まさに始まろうとしている瞬間を見てみたかったなぁと思います。そんなうねりを作り出す中心になればいいのですけどね。
では。
ONE LOVE/Iyahkie
「陽気な南国の音楽」から、「不正を告発するシリアスな音楽」へと変わって行った。
それをどちらが正しい解釈とか言っても仕方ないけど、「日本のレゲエの曙」につかの間見た、あの軽い明るさが妙に懐かしくてならない私なのであります。