【言い張り可能な世界(1)】
http://blog.goo.ne.jp/ldtsugane/e/1d78cda9dd4bffd2aced1dfc281eafb1
(↑)このエントリーの続きです。(1)から先に読んで下さい。
■言い張り可能な世界
さて、いよいよ「言い張り可能な世界」の話をするんですが、その例示として、ちょっと「ファクト(事実)」っぽい話(?)をつついてみたいと思います。
【批評について「カレーとショートケーキ」編】
http://blog.goo.ne.jp/ldtsugane/e/73615fd946ea584e3587eaaea30ba727
この項の話なんですが。作品を批評するには、まずその作品がどういう“料理”か分らないとはじめられないよね。それを怠るとカレーをショートケーキとして批評しちゃうような恥をかくよね…ってたとえ話ですね。個人的にけっこう気に入っていて、よく人にする話なんですが…ある作品(物語)に接する時、その作品が何を描こうとしているか?は、僕は間違いなく真っ先に始める事ですね。そうそう、この一連のエントリーの元になっているペトロニウスさんの発言でも…
【物語三昧:物語の主題と各エピソードによるガジェットの比率とは?】
http://d.hatena.ne.jp/Gaius_Petronius/20090526/p2
…とありますが、僕もこれはそうです。少なくとも最初に取り掛かる「分析」ですし、仮説でもいいのでその作品の全体像を掴んで、そこから「読んで」行く事は、物語を理解する事ひいては「愉楽する事」に対して、かなり効率の良い吸収をしていける事は経験から言っても間違いありません。
…しかし、ですね。“何の料理”か見極める事はそうそう簡単な事じゃないんですよねwなんの料理か…?つまりテーマという物は「言い張り可能な世界」の領域に属していて、そう簡単に実相を掴ませないんですよね。…ちょっと、ここでハッキリ分けましょう。「何の料理を作ろうとしたか?」…これは「作り手」がその答えを持っている事でしょうね。しかし、出来上がった料理が「実際に何の料理になったか?」は「作り手」さえも預かり知れない事だと「物語愉楽論」では考えます。そして、どういう料理か考えるこの場は「言い張り可能な世界」なんですwう~わ~ww (`>ω<´)←嫌そう
「作り手」が「可愛い女の子を描きました」と言っても「受け手」が「可愛くない」と言い張れば“その人”にとって可愛くないのは(暫定ながらも)確定と言えるでしょう。たとえば「作り手」がこのカレーにはハッカを入れましたと言ったとして…「ハッカなんか入っていない。全然ハッカの風味が出てないもの」→「いや、でも作者は入れたと言っているよ?」→「それは、そいつがその気になっているだけ。シソとハッカを勘違いしているんだよ。シソなら分る」→「いや、でもスースーするけどな?」→「俺はしない!」←これだ!これが“言い張り”だ!そして、ここが「言い張り可能な世界」なんだ!w……いや、なんかちょっと誤解されちゃいそうなんでアレですけど(汗)「作り手」が何を入れたか?なんてかなり「ファクト(事実)」っぽい所も、やり方次第で相当な所まで「言い張り可能な世界」に巻き込める事が言いたかったんです。【絶対視思考と相対視思考】で触れましたが、ここはズブズブの「相対視思考」を使うのに最適な場所なんですね。「ファクト(事実)の世界」はこうは行きません。あたなの思いや解釈がどうであろうと否応なく「ファクト(事実)」を突きつけるし、間違っていようがいなかろうが、ともかく結論を出し、それによって返ってくる結果「ファクト(事実)」を否応なく受け止めなければなりません。
じゃあ、むしろ「ファクト(事実)」の考え方を取り入れた方がいいんじゃないか?とか。たとえば「作り手」がハッカを入れたと言っているのだからその証言を持ってきて、それとそれに近い見解が“正解”で、それから遠ければ“不正解”という具合に割り切りましょうか。……ダメです。「物語愉楽論」はその考え方には組みしません。
「ファクト(事実)の世界」というのは“確かな事”、“説明がつく事”、“皆が納得できる事”などで構成されていて、そうでないものは削ぎ落として行く傾向があります。あなたが“そう感じているだけ”の話はファクト(事実)を示さない限り吹き飛ばされて行きます。(※とはいえ言葉や文章に顕せば、一つ小さな「ファクト(事実)」を手に入れますね)でも「物語を楽しむ」と言う事は、それを大事に扱う事なんだという話は前項でしました。
「物語」というものの基盤の所に「ファクト(事実)」がある事は確かだとしても、僕は“その方向”に「愉楽する事」を積み上げて行くつもりはありません。森羅万象の在り様、それを模した「物語を楽しむ事」が、たかだか“皆が納得できる事”なんて小さな考え方に収まるものだとは思っていないからです。
「言い張り可能な世界」は、相対視思考を低いレベルで使うドロドロの価値溶解者をのさばらせているような、智恵ある人には嫌な世界でしょうね。そいつらを「ファクト(事実)の世界」に引っ張り出して「お前は間違っている!」とやれたら、それは痛快でしょうね。でも「愉楽する事」を価値観に置く限り、「面白い」とは何か?僕が感じる「面白い」とは何か?それはそう簡単に白黒はっきりつけられる話じゃない。「言い張り可能」とは、常に可能性が残されているという事であり、すぐに結論が出るなんて考えで「楽しむ」範囲を狭める選択をしたくはない。……大丈夫です。この世界は(最終)結論を出さなくていいという事が、短所であり長所なんです。…つまり、時間だけは死ぬまで目一杯あります!!(`・ω・´)
え~っと。いろいろ回りくどく前振りしましたが、要するに僕はどんな楽しみ方でも、その人が真実楽しんでいる限り肯定されるという話をしています。他の人の作品批評や、作品分析は違うかもしれません。しかし「物語愉楽論」は「楽しい」、「面白い」が引き出せればそれでよく、基本的に間違った楽しみ方、間違った面白さという考え方をしません。
…これだけだと納得いかないというか、反論したくなる人がいるのではないかと思いますので、補足…というか話を続けると、(その人が真実「楽しんで」いる限り)間違った楽しみ方はありません。ただし「小さな楽しみ方」はありますね。ある作品の一部分だけを楽しむ…みたいな感じでしょうか。対して「大きな楽しみ方」、「深い愉しみ方」というものもあります。そしてより大きく、より深く、楽しむ事を目的としていますので「小さな楽しみ方」に留まる事は「是」としていません。故に…ちょっとどういう状態かイメージないですけど概念として「楽しむ世界を狭めてしまう楽しみ方」は、真実楽しんでいてもダメですね。まあ、あとね。一応言うと犯罪絡みとかもダメですねw文字通り“論外”でダメ出しですよね。「ファクト(事実)の世界」からの干渉として(汗)w(←でも、こういう極端な反論をしかける人がいる)
「楽しみ」を拡げて行くのは他者との意見交換が一番効率いいと僕は思っています。それ故、意見交換の「伝達効率」を上げるために、この論を書いたり「言葉」の整備をしたりしようとしているわけですね。
ものすご~~っく、作品からかけ離れた所で楽しんでいたとしたら、それは“おかしい”のではないか?みたいな意見の人もいると思うんですけどね…。それは「そこに留まる事」は肯定していないから、いずれあなたが納得できる「楽しみ方」にも来るでしょう…という返しになるかな?また、普通は、皆と大体同じような楽しみ方をした方が、楽に「楽しめ」ますし(←笑)連鎖や共鳴もあってより大きく、深く行き易いんですよね。それにも関わらず、何かちょっとずれた所で真実「楽しんで」いるのだとしたら、少なくともその人にとっては何かあるのでしょう。それを非常識とかそういう観点で云々言ってもしょうがない事だと思います。
ただし、くどいようだけど、そこだけに留まらない事。また、「言葉」を磨いて、そういった部分も「言葉」で伝達して行く努力をする事は必要ですね。
【観客として】
http://blog.goo.ne.jp/ldtsugane/e/099a5770473f38a2a6d6276784366ba1
むか~し、書いた決意文なんですけど、まあ「物語愉楽論」の出発点そのものが書かれています。「群盲象を撫でる」のたとえは、今、上で話していた事を、たとえ話にまとめたものという事になると思います。
そして最後に「『つまらない』と感じたりすることに嘘をつかない。」という話をしてこの項を終わります。僕は「物語愉楽論」の目的として、最終的に全ての「面白さ」を理解する事(「愉楽」する事/体感する事)と述べています。そして、それを実現させる、その場所が「言い張り可能な世界」である事を説明しました。……それはどういう事かというと、外面だけでいいなら、その目的は今すぐにでも達成できてしまう事なんですよね。「全てを楽しむ」なんて、大仰でご大層な事は、口だけで「うんうん、その『面白さ』も分かるよ」と言えば達成されてしまう。「ファクト(事実)」に晒され続けても、その言葉が言えるならそれはそれで“本物”と言えるかもしれない。…でも、ここは「言い張り可能な世界」で、口だけなら何とでも言える世界なんです。
口で上手く「伝達」できない事は、口で上手く「伝達」できない事以上のものではない。本人が「面白く」感じてはいない事の証明にはならない。…結局、本人が真実「楽しんで」いるか?「楽しみ」を分っているか?は、本人以外誰にも分るはずがない。だからこそ嘘をついてはいけない。もともと口では何とでも言える世界だから。「言い張り可能な世界」だからこそ、言い張ってはいけない。謙虚でなければ、こんな目的、最初っから無いも同然なのだ。
というのが僕の価値観の話ですね。ここ、すっごく足場悪い事分かってるけど僕がんばる…みたいな?………まあ、これを他者にどうこうというつもりは無いのですが、僕と意見交換する時とか、ああ、こういう事を考えている人なんだなあ…と思ってもらえると「伝達効率」がいいかなと。あと、断片的にでも、この話を何かの“足し”にしてもらえると幸いです。
※「言葉の位相」の話もほどなくしようと思います。
http://blog.goo.ne.jp/ldtsugane/e/1d78cda9dd4bffd2aced1dfc281eafb1
(↑)このエントリーの続きです。(1)から先に読んで下さい。
■言い張り可能な世界
さて、いよいよ「言い張り可能な世界」の話をするんですが、その例示として、ちょっと「ファクト(事実)」っぽい話(?)をつついてみたいと思います。
【批評について「カレーとショートケーキ」編】
http://blog.goo.ne.jp/ldtsugane/e/73615fd946ea584e3587eaaea30ba727
まあ、それはそれとして簡単な事のようで意外にこれ(何を作ったかを汲み取る努力)ができていない。あるいは意識できずに批評をする人が多いようです。その原因は「ショートケーキの味わい方しか知らない」か「とにかくショートケーキ“だけ”が大好き!」という事があるのでしょうけどね。しかしだからと言ってカレーライスに対し…「何だこれは?全然、甘くないじゃないか!?液化してしかも茶色で汚らしい!第一、いちごが乗っていないじゃないかぁ!!!」……とショートケーキとしての批評をするのはかなり的外れである事は分かると思います(笑)こういう事って、よく見かけるし、自分の心当たりも無きにしも有らずじゃないでしょうか?(笑)
この項の話なんですが。作品を批評するには、まずその作品がどういう“料理”か分らないとはじめられないよね。それを怠るとカレーをショートケーキとして批評しちゃうような恥をかくよね…ってたとえ話ですね。個人的にけっこう気に入っていて、よく人にする話なんですが…ある作品(物語)に接する時、その作品が何を描こうとしているか?は、僕は間違いなく真っ先に始める事ですね。そうそう、この一連のエントリーの元になっているペトロニウスさんの発言でも…
【物語三昧:物語の主題と各エピソードによるガジェットの比率とは?】
http://d.hatena.ne.jp/Gaius_Petronius/20090526/p2
「主題の本質の理解」を最も優先順位の高い価値を置くというのは、僕は、物事の正しさを考えるべき重要な選択基準だと思います。
…とありますが、僕もこれはそうです。少なくとも最初に取り掛かる「分析」ですし、仮説でもいいのでその作品の全体像を掴んで、そこから「読んで」行く事は、物語を理解する事ひいては「愉楽する事」に対して、かなり効率の良い吸収をしていける事は経験から言っても間違いありません。
…しかし、ですね。“何の料理”か見極める事はそうそう簡単な事じゃないんですよねwなんの料理か…?つまりテーマという物は「言い張り可能な世界」の領域に属していて、そう簡単に実相を掴ませないんですよね。…ちょっと、ここでハッキリ分けましょう。「何の料理を作ろうとしたか?」…これは「作り手」がその答えを持っている事でしょうね。しかし、出来上がった料理が「実際に何の料理になったか?」は「作り手」さえも預かり知れない事だと「物語愉楽論」では考えます。そして、どういう料理か考えるこの場は「言い張り可能な世界」なんですwう~わ~ww (`>ω<´)←嫌そう
「作り手」が「可愛い女の子を描きました」と言っても「受け手」が「可愛くない」と言い張れば“その人”にとって可愛くないのは(暫定ながらも)確定と言えるでしょう。たとえば「作り手」がこのカレーにはハッカを入れましたと言ったとして…「ハッカなんか入っていない。全然ハッカの風味が出てないもの」→「いや、でも作者は入れたと言っているよ?」→「それは、そいつがその気になっているだけ。シソとハッカを勘違いしているんだよ。シソなら分る」→「いや、でもスースーするけどな?」→「俺はしない!」←これだ!これが“言い張り”だ!そして、ここが「言い張り可能な世界」なんだ!w……いや、なんかちょっと誤解されちゃいそうなんでアレですけど(汗)「作り手」が何を入れたか?なんてかなり「ファクト(事実)」っぽい所も、やり方次第で相当な所まで「言い張り可能な世界」に巻き込める事が言いたかったんです。【絶対視思考と相対視思考】で触れましたが、ここはズブズブの「相対視思考」を使うのに最適な場所なんですね。「ファクト(事実)の世界」はこうは行きません。あたなの思いや解釈がどうであろうと否応なく「ファクト(事実)」を突きつけるし、間違っていようがいなかろうが、ともかく結論を出し、それによって返ってくる結果「ファクト(事実)」を否応なく受け止めなければなりません。
じゃあ、むしろ「ファクト(事実)」の考え方を取り入れた方がいいんじゃないか?とか。たとえば「作り手」がハッカを入れたと言っているのだからその証言を持ってきて、それとそれに近い見解が“正解”で、それから遠ければ“不正解”という具合に割り切りましょうか。……ダメです。「物語愉楽論」はその考え方には組みしません。
「ファクト(事実)の世界」というのは“確かな事”、“説明がつく事”、“皆が納得できる事”などで構成されていて、そうでないものは削ぎ落として行く傾向があります。あなたが“そう感じているだけ”の話はファクト(事実)を示さない限り吹き飛ばされて行きます。(※とはいえ言葉や文章に顕せば、一つ小さな「ファクト(事実)」を手に入れますね)でも「物語を楽しむ」と言う事は、それを大事に扱う事なんだという話は前項でしました。
「物語」というものの基盤の所に「ファクト(事実)」がある事は確かだとしても、僕は“その方向”に「愉楽する事」を積み上げて行くつもりはありません。森羅万象の在り様、それを模した「物語を楽しむ事」が、たかだか“皆が納得できる事”なんて小さな考え方に収まるものだとは思っていないからです。
「言い張り可能な世界」は、相対視思考を低いレベルで使うドロドロの価値溶解者をのさばらせているような、智恵ある人には嫌な世界でしょうね。そいつらを「ファクト(事実)の世界」に引っ張り出して「お前は間違っている!」とやれたら、それは痛快でしょうね。でも「愉楽する事」を価値観に置く限り、「面白い」とは何か?僕が感じる「面白い」とは何か?それはそう簡単に白黒はっきりつけられる話じゃない。「言い張り可能」とは、常に可能性が残されているという事であり、すぐに結論が出るなんて考えで「楽しむ」範囲を狭める選択をしたくはない。……大丈夫です。この世界は(最終)結論を出さなくていいという事が、短所であり長所なんです。…つまり、時間だけは死ぬまで目一杯あります!!(`・ω・´)
え~っと。いろいろ回りくどく前振りしましたが、要するに僕はどんな楽しみ方でも、その人が真実楽しんでいる限り肯定されるという話をしています。他の人の作品批評や、作品分析は違うかもしれません。しかし「物語愉楽論」は「楽しい」、「面白い」が引き出せればそれでよく、基本的に間違った楽しみ方、間違った面白さという考え方をしません。
…これだけだと納得いかないというか、反論したくなる人がいるのではないかと思いますので、補足…というか話を続けると、(その人が真実「楽しんで」いる限り)間違った楽しみ方はありません。ただし「小さな楽しみ方」はありますね。ある作品の一部分だけを楽しむ…みたいな感じでしょうか。対して「大きな楽しみ方」、「深い愉しみ方」というものもあります。そしてより大きく、より深く、楽しむ事を目的としていますので「小さな楽しみ方」に留まる事は「是」としていません。故に…ちょっとどういう状態かイメージないですけど概念として「楽しむ世界を狭めてしまう楽しみ方」は、真実楽しんでいてもダメですね。まあ、あとね。一応言うと犯罪絡みとかもダメですねw文字通り“論外”でダメ出しですよね。「ファクト(事実)の世界」からの干渉として(汗)w(←でも、こういう極端な反論をしかける人がいる)
「楽しみ」を拡げて行くのは他者との意見交換が一番効率いいと僕は思っています。それ故、意見交換の「伝達効率」を上げるために、この論を書いたり「言葉」の整備をしたりしようとしているわけですね。
ものすご~~っく、作品からかけ離れた所で楽しんでいたとしたら、それは“おかしい”のではないか?みたいな意見の人もいると思うんですけどね…。それは「そこに留まる事」は肯定していないから、いずれあなたが納得できる「楽しみ方」にも来るでしょう…という返しになるかな?また、普通は、皆と大体同じような楽しみ方をした方が、楽に「楽しめ」ますし(←笑)連鎖や共鳴もあってより大きく、深く行き易いんですよね。それにも関わらず、何かちょっとずれた所で真実「楽しんで」いるのだとしたら、少なくともその人にとっては何かあるのでしょう。それを非常識とかそういう観点で云々言ってもしょうがない事だと思います。
ただし、くどいようだけど、そこだけに留まらない事。また、「言葉」を磨いて、そういった部分も「言葉」で伝達して行く努力をする事は必要ですね。
【観客として】
http://blog.goo.ne.jp/ldtsugane/e/099a5770473f38a2a6d6276784366ba1
「群盲象を撫でる」ということわざがある。これは「巨大なる者を測ろうとする愚かさ」を喩えたものだが、それでも“象”を知ろうと思ったら、他者の意見を聞き、自らも発言して、情報を構築していくしかない。そして自分一人でより多くの部分をカバーできる自分を目指し、いずれは“象”一匹全て己のみで理解できるようになりたい。
でも、今は駄目(←笑)今は全然そのレベルじゃない。だから『面白い』と感じたり、『つまらない』と感じたりすることに嘘をつかない。「うんうん、その『面白さ』も分かるよ」と分ってるフリをしない。そしていずれは、あらゆる『面白さ』を理解できるようになりたい。その為に今は『面白い』ことと『つまらない』ことを徹底的に考える。観客として。
むか~し、書いた決意文なんですけど、まあ「物語愉楽論」の出発点そのものが書かれています。「群盲象を撫でる」のたとえは、今、上で話していた事を、たとえ話にまとめたものという事になると思います。
そして最後に「『つまらない』と感じたりすることに嘘をつかない。」という話をしてこの項を終わります。僕は「物語愉楽論」の目的として、最終的に全ての「面白さ」を理解する事(「愉楽」する事/体感する事)と述べています。そして、それを実現させる、その場所が「言い張り可能な世界」である事を説明しました。……それはどういう事かというと、外面だけでいいなら、その目的は今すぐにでも達成できてしまう事なんですよね。「全てを楽しむ」なんて、大仰でご大層な事は、口だけで「うんうん、その『面白さ』も分かるよ」と言えば達成されてしまう。「ファクト(事実)」に晒され続けても、その言葉が言えるならそれはそれで“本物”と言えるかもしれない。…でも、ここは「言い張り可能な世界」で、口だけなら何とでも言える世界なんです。
口で上手く「伝達」できない事は、口で上手く「伝達」できない事以上のものではない。本人が「面白く」感じてはいない事の証明にはならない。…結局、本人が真実「楽しんで」いるか?「楽しみ」を分っているか?は、本人以外誰にも分るはずがない。だからこそ嘘をついてはいけない。もともと口では何とでも言える世界だから。「言い張り可能な世界」だからこそ、言い張ってはいけない。謙虚でなければ、こんな目的、最初っから無いも同然なのだ。
というのが僕の価値観の話ですね。ここ、すっごく足場悪い事分かってるけど僕がんばる…みたいな?………まあ、これを他者にどうこうというつもりは無いのですが、僕と意見交換する時とか、ああ、こういう事を考えている人なんだなあ…と思ってもらえると「伝達効率」がいいかなと。あと、断片的にでも、この話を何かの“足し”にしてもらえると幸いです。
※「言葉の位相」の話もほどなくしようと思います。










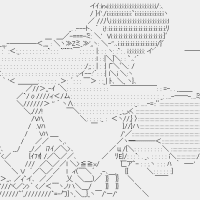
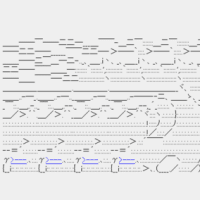
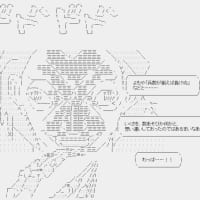
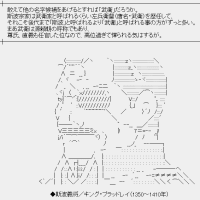
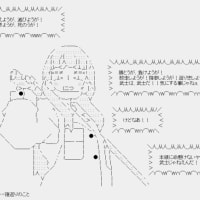
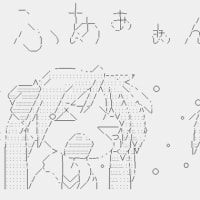

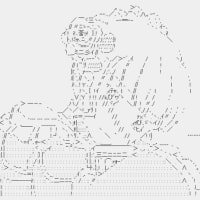

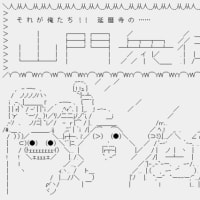
「面白い」が主観である以上、他者がどう言おうが、事実(ふぁくと)がどれだけ並ぼうが、「俺が面白い/面白くない」に帰着してしまうのは、間違いないでしょう。
では、逆に、なぜ「面白い」を客観にしにくいのか? を考えてみました。
客観の王道たる「実験」について百科事典をひいてみますと次の文章があります。
>人為的に特別の条件をつくり,考慮に入れるべき条件の数をできるだけ限定したうえで〈仮説を検証するため〉にインプットとアウトプットとの関係を調べる操作を〈実験 experiment〉と呼ぶのである。(平凡社世界大百科事典より)
「考慮に入れるべき条件の数をできるだけ限定」――コレが面白いを分析し、客観視するときのネックであろうと思います。あるものを読んだ時、人はその作品だけを見ているわけではありません。かつて読んだ作品が、自分の経験が、脳の中から引き出され、目の前の作品と融合し、反応し、たくさんの思いを生み出します。そしてそれが、最終的に「面白い/面白くない」に大きく切り分けられるわけです。
もし「面白い」を客観にしようとすれば、「考慮に入れるべき条件の数をできるだけ限定」するため、実験に投入する読者を選ぶ必要があります。過去に同じような作品を読み、同じような人生を送り、同じような境遇にある人間を集めるわけです。
過去に同じような作品を読んだ、という条件は、漫画やアニメだけに限れば二十年前、三十年前であれば、ある程度は可能だったかもしれません。作品そのものの数が少なく、おそらくマニアと呼べる人であれば、ほぼ同じような「共通体験」を持ち、条件がそろったのではないでしょうか。厳密な科学実験ほどではないにしても、話は通じるし、評価も近くなりそうです。ズレるとしても、それは個人の嗜好によるものであることが、互いに納得できたと思います。
しかし、それは今では望むべくもありません。『ガンダム』について語り合う場合でも、「平成生まれで、最初に見たのがSEEDで、ガンダムが面白いから初代の『機動戦士ガンダム』を見た」という人と、「昭和生まれで、『マジンガーZ』のおもちゃで遊び、同じ時間帯で放映されていた『ザンボット3』や『ダイターン3』を見た後の流れで『機動戦士ガンダム』に触れた」という人では、同じものを見ても、条件が違いすぎます。
では、両者は分かり合えないかというと、そうでもないと思います。
互いの「主観」に寄り添う、つまりは相手という「個人」を理解する、共感することで、その人の視点をエミュレートできるのではないでしょうか。そしてそれには、相手への尊敬や愛情が必要不可欠であるようにも思います。「老害だ」「若造だ」「ゆとりだ」「オタクだ」と相手への侮蔑がベースにあると、たとえ相手を正しく理解したとしても、得られる結果は誰にとっても得にならぬ、殺伐としたものになりそうです。
そうですね。僕としてはその中で自分の知らなかった面白さに出会う/気付くといった経験を繰り返す内に~それは、今まで狭かった自分の視野が広がるという事ですが~どうやったら、自分の視野(主観)を広げてより多くの「面白い」に気付く事ができるのか?と考えはじめて、この話があります。
>互いの「主観」に寄り添う、つまりは相手という「個人」を理解する、共感することで、その人の視点をエミュレートできるのではないでしょうか。
その方法はやはり、これが一番効率いいように思います。そしてその伝達ツールとして「言葉」は相当な役割を果たすんですよね。故に、このブログでは「言葉はツール」と言った「言葉」とはどういう物か?を考察するエントリーがあります。
「尊敬や愛情が必要」…というと少し大仰な気もしますが、とにかく相手の「言葉」と真摯に向かい合う事が必要なのは間違いありませんね。相手の言葉を真面目に受け取ろうとすれば、正直、侮蔑などしているヒマはないように思っています。