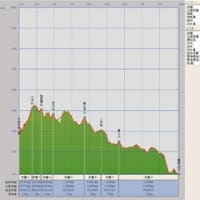大宮八幡宮へ散策
環七経由神田川と善福寺川沿いに大宮八幡宮へ散歩しました。
歩いた軌跡は下の地図赤線です。距離14.5Kmです。
二つの川とも流れはチョロチョロと少なく、かつきれいな流れでしたが、魚は見れませんでした。
下の写真は二つの川の合流点です。
神田川の源流は井之頭池、善福寺川は善福寺池です。二つとも湧水です。
東京の川はみな富士山をはじめとした後背山地の伏流から成っているようです。
所謂、関東ローム層の下をくぐって湧き出した水です。
途中にバカでかい善福寺川取水施設が出来ていました。
大雨の際あふれ出た水を環七沿いの地下貯水池へ取水する施設です。
都市化が進むにつれ、土地がみなコンクリートで固められ自然浄化もままならず、人工的に助ける施設が必要になったようです。
そして、その取水施設のおかげで、沿線の家々は、昔のように、うららかに安心した生活が楽しめるようです。
大宮八幡に行く途中、杉並区立郷土博物館に寄ってみました。
以前から一度訪ねてみたいと思っていました。
入口は昔の家の門です。松の木遺跡復元住居の長屋門です。
もともとは、門番が住んでいた部屋だそうです。
中の記録には、懐かしい地名がたくさんありました。
上井草、下井草、高井戸、荻窪、永福、天沼、高井戸、・・・
私は東京に出てきた初めに荻窪に住み、間もなく兄のいる上井草に住みました。
昭和32年ごろのことです。
西武線を挟んですぐ前に上井草球場がありました。
春一番が吹く頃は球場の砂埃が激しく、畳の上を歩くと足跡がくっきりつくのです。
それも足裏に砂埃が付くためにできる、ほこりの取れた跡です。
不思議な経験でした。
その、上井草球場の記念誌が展示販売されていました。
兄に見せようと思い買いました。
表紙には往年の苅田内野手の写真が載っていました。
確か職業球団・東京セネターズの『百万ドルの内野』手と称えられていた人です。
また、館内裏庭には旧篠崎家といわれる住宅が保存されていました。

三つ間取り広間型といわれる、江戸中期の一般的な間取りだそうです。
ゆっくり見て回ったのち、また善福寺川をさかのぼり、大宮八幡に着きました。
そこでも、また遺跡に遭遇しました。大宮遺跡です。
確か身分のある人の墓地だそうですが・・・。
「・・・大宮遺跡は、都内で初の方形周溝墓が発掘されたことで有名です。
方形周溝墓は『方形の四方を溝で囲んだ土器時代の古代人の墓』で弥生時代末期のものとされます。
昭和四十四年の発掘作業では三基の周溝墓が発見され、そこから土器や勾玉、ガラス玉などが発見されました。
特に壺形土器の配列や底に穴をあけた形状(穿孔土器)からこの遺跡が住居跡でなく、尊貴な者(族長=祖神)の墓域、祭祀遺跡であることが判明しました。
当時、善福寺川沿いの低地では水田耕作が行われていた模様です。
そして対岸の松の木遺跡には、多くの竪穴式居住跡が発見されています。
つまり川や田んぼを挟んで住居と祭りの場を厳密に区分するという観念が当時から存在していたことを示しています。
この遺跡は、大宮八幡宮の旧社殿地ともほとんど重なり、この一帯が聖域とされていた古代からの信仰がのち大宮八幡宮の創建につながったと思われます。・・・」 」
そして最後にその隣の、大宮八幡宮にお参りしました。
梅の花も今を盛りと咲いていました。おだやかないい眺めです。
何時も大勢の人がお詣りしています。今日は平日ですが・・・。
日本全国には大宮八幡宮と名のつくお宮が多いですが、一番古いのは九州博多の宇佐八幡宮で、その次が石清水八幡宮です。それに筥崎宮を加えた三社が日本三大八幡宮(時には鎌倉の八幡宮を加え四大八幡宮といわれますが)とされています。
そうすると、ここの八幡宮の格式は???
帰り道の途中、多少おなかも空いてきたので、蕎麦屋により“ぬる燗”一本と“もりそば”を頂きました。
いい運動になりました。