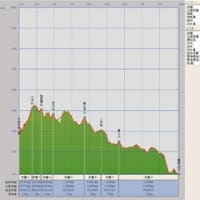佃島を歩く
明治17年測量の5000分一の参謀本部陸軍部測量局の地図があったので、今の佃島と比較したくて出かけました。
旧図は左図です。現在は右図です。
隅田川の砂州も、ずいぶん大きくなったものです。
住吉大社が 昔の位置にありました。
社務所発行の『住之江』によると、今年は
「御祭神の徳川家康公(東照御神命)が元和二年(1616)に没してより四百年、また正保三年(1646)当社がこの佃の地に鎮座してから三百七十年の節目の年となります。・・・」
そうです。
確か、この大社は家康公とともに、大阪の住吉大社が移住してきたものと云われていましたが・・・。
さてと、世の中、いくら科学的に解明されても、いざというときは神仏頼みですね。
若い人達も、神仏にお参りしています。合格祈願、平癒祈願、結婚祈願等々・・・
人間とは弱いものですね。
さて、今日の散歩コースは次の赤線です。
短いようでも、7Kmありました。
先ず、都営大江戸線で勝どき駅に行きました。
地下から出てみると、こんな ‘のっぽビル’ が建っていました。
多分30階ぐらいはあるでしょう。
埋立地にこんなビルを建てても大丈夫なのかな~。
「今後三十年以内に70%の確率で首都圏直下型地震がある」 と、いわれていますが。
私も80年生きてきたのだから、ま~いいか。(他人ごと)
清澄通りを南へ暫く行くと、橋のたもとに東陽院というお寺がありました。
もともと浅草にあったそうですが、関東大震災でこの地に引っ越したそうです。
そして、その際、十辺舎一九の墓も移ってきたそうです。
中央区教育委員会の説明板によると
「十辺舎一九は本姓を重田といい、明和二年(1765)駿河に生まれました。
その後、江戸に出て、日本橋の出版業者、蔦屋重三郎付の作家となり、多くの黄表紙・洒落本を書いた。
なかでも、『東海道中膝栗毛』はよく知られ、
主人公の栃面屋弥次郎兵衛と喜多八が日本橋から東海道を旅し、
伊勢参宮の後、京都へたどりつくという旅行記の形式をとる物語であり、
続編に続編を重ね、一九の代表作となった。(それで一九というのかな~?)
天保二年(1832)に没し、・・・
墓石には次の辞世が刻んである。
此世をば どりゃお暇(おいとま)に 線香の
煙と共に はい左様なら
・・・」
そして、さらに南へ行くと、ビル群がニョキニョキ、
眺めはいいでしょうが、よく住めるもんだな~ と感心します。
レインボウブリッジ、スカイツリー、等々 これが新しい東京かと、暫く驚いて見ていました。
ただ、付近は漁業関係の倉庫や車が多く、魚の生臭い匂いで一杯でした。
暫く佇んだのち、昼時でもあり、郵便局の前の小料理屋へ “まぐろ定食” を食べに入りました。
お昼には少し早かったのか、まだ誰もいませんでした。
店の棚には酒瓶がずらりと並んでいました。
私が我慢できるはずがありません。
ばかでかいコップで焼酎のお湯割りを頂き、マグロ刺身でチビチビやっていました。
それが、お店のお神さん話し上手で、ついつい二杯になりました。
いい気分で、もと来た道を帰り、勝どき交差点で写真撮影。
さらに北へ移動して、月島交差点から佃大橋の方へ廻り、住吉大社へ出ました。
町の案内図も載せます。
この辺りは、元・石川島監獄署で、更生施設がありました。
その建物の様子が、旧図には出ていました。
そして、中央大橋、相生橋を経て、清澄通りへ出ました。
川沿いには、立派な遊歩道が巡らされ、傍らには高層ビルがニョキニョキ・・・。
この辺は、元、石川島の造船所があった所です。
そして、門前仲町駅に出て、ちょっと深川不動様にお参りして、都営大江戸線で帰りました。
今日も、いい一日でした。