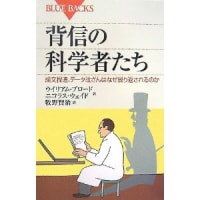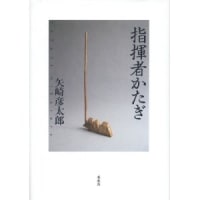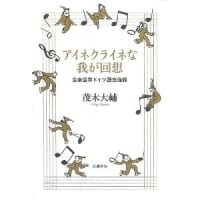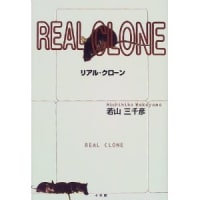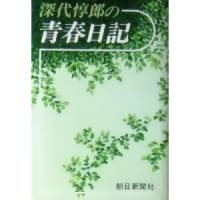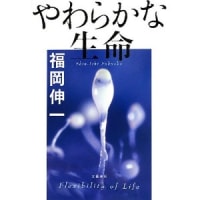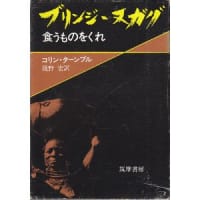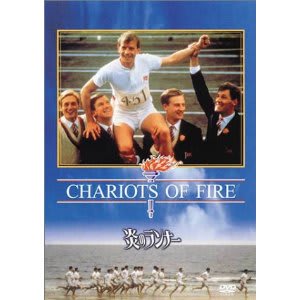 イギリス文学、演劇学、映画論の専門家の狩野良規さんの熱~い大作!「スクリーンの中に英国が見える」という本の最後、”永遠にイギリス的なるものについて”でとりあげられた映画がこの『炎のランナー』である。(もう一作は『日の名残り』)今回この映画を初めて観て、これまで1924年のパリ・オリンピックの陸上競技で金メダルをめざす、ただのスポ根ものと勝手に思い込んで敬遠していたのは、私の失策だったとおおいに反省した次第である。狩野センセイによると、そんな風に勘違いする現象こと、ハリウッド映画に毒されていることになるかもしれないが・・・。
イギリス文学、演劇学、映画論の専門家の狩野良規さんの熱~い大作!「スクリーンの中に英国が見える」という本の最後、”永遠にイギリス的なるものについて”でとりあげられた映画がこの『炎のランナー』である。(もう一作は『日の名残り』)今回この映画を初めて観て、これまで1924年のパリ・オリンピックの陸上競技で金メダルをめざす、ただのスポ根ものと勝手に思い込んで敬遠していたのは、私の失策だったとおおいに反省した次第である。狩野センセイによると、そんな風に勘違いする現象こと、ハリウッド映画に毒されていることになるかもしれないが・・・。映画の冒頭は、「ロンドン 1978年」、ハロルド・エイブラハムズの葬儀ではじまる。早くも、主人がこの名前からわかるようにユダヤ人だと察せられる。そのハロルドとはどういう人物かと言うと、すぐに映像は海辺を走る若者達を映し、クラシックなホテルの窓辺で母親に手紙を書く青年にかわり、、彼の母親にあてた手紙の内容から1924年のオリンピック出場選手の強化合宿だと気がついていく。但し、この青年はハロルドではなく、生涯の親友となる人物オーブリーである。やがて、ホテルでクリケットに興じる青年たちの中で、ひときわ負けず嫌いで判定に文句を言う気性の激しい青年がいるのだが、彼が本作の主人公のハロルドである。そしてもうひとりの重要な人物が、聖職者をめざすスコットランド人のエリック・リデル(イアン・チャールストン)。まずは「ケンブリッジ大学キーズ・カレッジ 1919年」と字幕がでて、ハロルド(ベン・クロス)が入学した日の初日に更に時計の針を戻し、プロローグからいよいよ本編がはじまるのだが。。。
さて、それではどこが英国的なるものか、専門家ではないので、あくまでも16歳の乙女心にきゅんと映った英国を早速見てみたい。
1.1919年10月1日の新入生歓迎の晩餐会
古色蒼然たる歴史的な建築物の中で、タキシードに正装した新入生を歓迎する蝋燭の明かりにゆれる晩餐会の場面が実に美しくも端整である。勿論、女性はひとりもいない。そして学寮長の歓迎スピーチが素晴らしく、英国的エリート教育の仕上げをみるようである。
2.ノーブレス・オブリージュ
その晩餐会が催されたホールには、第一次世界大戦で戦没して犠牲となった多くの卒業生たちの名前が刻まれている。学寮長の歓迎スピーチも彼らの追悼からはじまり、第一次世界大戦では、大卒の上流階級のエリートの多くが出征して亡くなったことが、ノーブレス・オブリージュを果たした戦争とも言える。
3.アングロ・サクソンの国
弁護士をめざすハロルドは、オーブリーに「この国はアングロ・サクソンの国だ。僕は偏見に挑戦して、彼らをひざまづかせてみせる」と意気込む場面がある。随所にユダヤ人であることが、ハロルドの生き方におおいなる影響を与えていることが表現されている。
4.ケンブリッジ大学の伝統
ハロルドは、トリニティ・カレッジの中庭を正午の鐘がなり終わるまでに一周する"カレッジ・ダッシュ"に挑戦して、見事成功する。 この記録は「700年間達成者がいなかった」そうだが、同時に大学の歴史と伝統を感じさせられ、またハロルドとアンドルー・リンゼイの足の速さを説明したよくできた場面である。
5.貴族の国
ハロルドと一緒にカレッジ・ダッシュに挑戦してほんのわずかな差で達成できなかったのが、貴族の御曹司アンドルー。アンドルーは、広大な緑の領地にハードルを並べて、執事にその上に次々とシャンパンを満たしたグラスを置かせるのだった。そして「シャンパンがこぼれたら言ってくれ」と、美しく優雅にハードルをこえて競技の練習をする。彼はイートン校からケンブリッジ大学に進むという典型的なエリート・コースをすすむ、銀のスプーンをくわえて生まれてきた貴族。
6.紳士とアマチュアリズム
エリックに敗退したハロルドは、イタリアとアラブ人の血がまじったマサビーニを金銭を支払ってプロのコーチとして雇うのだが、ケンブリッジのふたりの学寮長から食事に呼び出され、品格に欠けてアマチュアリズムに反すると忠告を受ける。しかし、ハロルドは、こどもの運動会ではないと、忠告を偽善であると一蹴して席を立つのだった。英国では、欧州の上流階級が尊んだ精神のアマチュアリズムにジェントルマンを重ねて考えているが、そもそもアマチュアリズムというのは、労働する必要のない階級がうみだした理屈で、労働者階級をスポーツ競技から締め出そうとした事実がある。
しかし、この映画のポイントは、偏見と差別をはねつけるユダヤ人と神を称えるために走るピューリタンのスコットランド人という、純正イングランド人ではない彼らが、英国を代表してオリンピックに出場し、英国の美徳を体現し母国に栄光をもたらすところにある。そして、もうひとり、忘れてはいけないのが青年貴族のアンドルー。勝利に固執するハロルドや、信仰のために走るエリックとはことなり、走ることを遊びとし、銀メダルに甘んじてエリックに機会をゆずる彼は、”足るを知る”の美徳をもつ余裕がある。物語の展開は早く次々とすすみ、本当に深い意味で理解するには、一度の鑑賞ではなかなか難しい。私はDVDを借りて二晩続けて鑑賞して、ようやくここまでたどりついた。しかし、ハリウッド映画と違いいかにもイギリス映画らしいのは、金メダルをとった後のハロルドの表情である。音楽や映像の力を借りて盛り上げるのではなく、淡々と空しさを感じているハロルドを映す”暗さ”が私には好みである。そして、もうひとつ、地味でめだたない演技ながら過不足なくエリック役を演じたイアン・チャールストン。狩野さんはこの役者を気に入り、英国滞在中に彼が出演する舞台をずいぶんと探したが、すでに亡くなっていたそうだ。端整な青年が、40歳でエイズで他界したというのも悲しくも英国らしい・・・。
ついでながら、”永遠にイギリス的なるものについて”のもう一作が、イシグロ・カズオ原作の「日の名残り」!
原題:CHARIOTS OF FIRE
監督: ヒュー・ハドソン
1981年イギリス製作