関節の「あそび運動」を触診で練習する方法について、以前「ひとりでできる!! 関節あそび検査練習法」としてご紹介しました。
今回からは4回シリーズで、「ひとりでできる!!関節構成運動の触診練習法」をお伝えしたいと思います
まずは、かんたんに知識の整理からはじめましょう

関節構成運動とは、自・他動動運動によって起こる、意識して動きを出すことが出来ない関節包内の運動のことで、「滑り」「転がり」「軸回旋」の3つの運動があります。
「すべり運動」とは、一方の関節面の接触部位は変わらずに、他方の関節面の接触面を変えながら運動が起こることです。
このように書くと難しいのですが、氷の上を滑ったときに、足の裏は地面についたまま変わりませんが、地面の氷はどんどん場所が変わっていきます。
これが「すべり」です
生活感覚では簡単でも、文章で定義づけると何だか難しくなりますね
「転がり運動」とは、関節面相互の接触部位が一対一の割合で変わりながら動くことです。
ちょうど前方へでんぐり返りをしたとき、背中と地面の着く位置は互いに変わりながら回転していきます。
これが「転がり」です
「軸回旋運動」とは、一方の関節面に対して他方の関節面が、ある軸を中心として回転することです。
フィギアスケートで、最後にクルクル回っているアレですね。
関節構成運動のなかでも、機能障害としてよくみられ、症状としても大きな影響を及ぼすのが「すべり運動」の減少・消失です
「すべり運動」が消失すると、どのようになるのでしょうか
「凹凸の法則(concave-convex rule)」に基づいて確認しておきましょう。
凹凸の法則とは、骨運動と関節面の運動との間に起こる一定の法則のことです。
関節は基本的に、凹の関節面と凸の関節面の組み合わせで出来ています。
骨運動が起こる側の関節面が凹か凸かによって、凹の法則と凸の法則に分かれています。
まずは「凹の法則(concave rule)」です。
凸側の関節面を固定し、凹側の関節面が運動する場合、関節面は骨の運動と同じ方向に滑るというものです。
下のイラストのように、頭側へ骨運動が起こると共に、すべり運動も頭側に起こることで、関節面は適合性を保ったまま運動することができます。

では、ここですべり運動が起こらないとどうなるか?
頭側へ骨運動のみが起こると、下のイラストのように、ビンの詮を、栓抜きで空けたときのようなテコの運動になってしまいます。
その結果、関節面の適合性が悪くなって関節同士がぶつかり合うかたちになり、やがては損傷に至ってしまうことになります

つづいて「凸の法則(convex rule)」です。
これは、凹側の関節面を固定し、凸側の関節面が運動する場合、関節面は骨の運動と反対方向に滑るというものです。
ちょうど下のイラストのように、頭側に骨運動が起こるのに対して、すべりは尾側に起こります。

このとき、転がり運動は頭側に起こっていますが、尾側へのすべり運動が起こっているために、関節の位置はズレずに適合性を保ったまま運動できるわけです。
ところが、すべり運動が起こらないと、頭側への転がり運動によって、骨頭の位置が頭方に移動し、関節窩から飛び出そうとする動きになります。
そして、関節面同士がぶつかり合うようになり、やはり損傷するに至ってしまいます

このように、「すべり運動」が確保されているかどうかは、関節の機能にとってとても大切になってきます。
それでは次回から、この「すべり運動」を感じるとるための練習法を紹介します。
 ☆ブログの目次(PDF)を作りました 2014.01.03☆)
☆ブログの目次(PDF)を作りました 2014.01.03☆)
手技療法の寺子屋ブログを始めてから今月でまる6年になり、おかげさまで記事も300を越えました。
これだけの量になると、全体をみたり記事を探すのも手間がかかるかもしれません。
そこで、少しでもタイトルを調べやすくできるように、このお休みを使って目次を作ってみました。
手技療法を学ばれている方、興味を持たれている方にご活用いただき、お役に立てれば幸いです。
手技療法の寺子屋ブログ「目次」
今回からは4回シリーズで、「ひとりでできる!!関節構成運動の触診練習法」をお伝えしたいと思います

まずは、かんたんに知識の整理からはじめましょう


関節構成運動とは、自・他動動運動によって起こる、意識して動きを出すことが出来ない関節包内の運動のことで、「滑り」「転がり」「軸回旋」の3つの運動があります。
「すべり運動」とは、一方の関節面の接触部位は変わらずに、他方の関節面の接触面を変えながら運動が起こることです。
このように書くと難しいのですが、氷の上を滑ったときに、足の裏は地面についたまま変わりませんが、地面の氷はどんどん場所が変わっていきます。
これが「すべり」です

生活感覚では簡単でも、文章で定義づけると何だか難しくなりますね

「転がり運動」とは、関節面相互の接触部位が一対一の割合で変わりながら動くことです。
ちょうど前方へでんぐり返りをしたとき、背中と地面の着く位置は互いに変わりながら回転していきます。
これが「転がり」です

「軸回旋運動」とは、一方の関節面に対して他方の関節面が、ある軸を中心として回転することです。
フィギアスケートで、最後にクルクル回っているアレですね。
関節構成運動のなかでも、機能障害としてよくみられ、症状としても大きな影響を及ぼすのが「すべり運動」の減少・消失です

「すべり運動」が消失すると、どのようになるのでしょうか

「凹凸の法則(concave-convex rule)」に基づいて確認しておきましょう。
凹凸の法則とは、骨運動と関節面の運動との間に起こる一定の法則のことです。
関節は基本的に、凹の関節面と凸の関節面の組み合わせで出来ています。
骨運動が起こる側の関節面が凹か凸かによって、凹の法則と凸の法則に分かれています。
まずは「凹の法則(concave rule)」です。
凸側の関節面を固定し、凹側の関節面が運動する場合、関節面は骨の運動と同じ方向に滑るというものです。
下のイラストのように、頭側へ骨運動が起こると共に、すべり運動も頭側に起こることで、関節面は適合性を保ったまま運動することができます。

では、ここですべり運動が起こらないとどうなるか?

頭側へ骨運動のみが起こると、下のイラストのように、ビンの詮を、栓抜きで空けたときのようなテコの運動になってしまいます。
その結果、関節面の適合性が悪くなって関節同士がぶつかり合うかたちになり、やがては損傷に至ってしまうことになります


つづいて「凸の法則(convex rule)」です。
これは、凹側の関節面を固定し、凸側の関節面が運動する場合、関節面は骨の運動と反対方向に滑るというものです。
ちょうど下のイラストのように、頭側に骨運動が起こるのに対して、すべりは尾側に起こります。

このとき、転がり運動は頭側に起こっていますが、尾側へのすべり運動が起こっているために、関節の位置はズレずに適合性を保ったまま運動できるわけです。
ところが、すべり運動が起こらないと、頭側への転がり運動によって、骨頭の位置が頭方に移動し、関節窩から飛び出そうとする動きになります。
そして、関節面同士がぶつかり合うようになり、やはり損傷するに至ってしまいます


このように、「すべり運動」が確保されているかどうかは、関節の機能にとってとても大切になってきます。
それでは次回から、この「すべり運動」を感じるとるための練習法を紹介します。
 ☆ブログの目次(PDF)を作りました 2014.01.03☆)
☆ブログの目次(PDF)を作りました 2014.01.03☆)
手技療法の寺子屋ブログを始めてから今月でまる6年になり、おかげさまで記事も300を越えました。
これだけの量になると、全体をみたり記事を探すのも手間がかかるかもしれません。
そこで、少しでもタイトルを調べやすくできるように、このお休みを使って目次を作ってみました。
手技療法を学ばれている方、興味を持たれている方にご活用いただき、お役に立てれば幸いです。
手技療法の寺子屋ブログ「目次」

















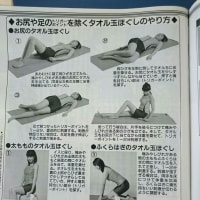


こうやって図に表すと想像しやすいというか分かりやすいですね。さっそく真似してみます。
上肢や下肢を持って操作している時も、この記事のようなことを、イメージしながら動かすと、機能障害を感知する感度が全く違ってきます。
どうぞ、ご参考になさってください。
以前にも質問させてもらった者です。
関節の遊びについて、書籍やネット検索をしても納得した回答が見つからなかったので投稿させていただきました。
骨に変形がない人や、若い人達に関節機能障害があった場合のモビライゼーションを行う時は
これぐらいのリリースが起こればOKかなという感覚があります。
そして、今回の疑問なのですが
骨に変形のある方や、ご年配の方の関節機能障害があった場合のモビライゼーションを行う時は
少しは動きを感じるのですが、
元々が凄い硬いからなのか、なかなか上記のような若くて骨も健康な人のようなリリースの感覚が得られません。
関節の遊びは不動関節で自分で動かすことが出来ず、他者によって動かされるもので2、3ミリしか動かないものだと思うので
年齢や骨の変形など関係なく皆んな同じリリースの感覚を得られるかなと思っていましたが
実際は個人差や、骨の状態や、それともひっとみー関節の部位によって変わるのでしょうか?
もし、個人差がある場合はどのようなアプローチで治療を進めていくべきか教えて頂けないでしょうか?
ご回答頂けるとありがたいです。
よろしくお願い致します。
文章中のひっとみーは誤字です。
すみませんでした。
高齢者は若年者と比べて線維組織が増殖している部位も増えることからも、リリースの感覚を得難いということはあるかもしれません。
また、仙腸関節などは癒合することから関節のリリースということ自体があり得ないことになります。
(感じているとしたら、表面を覆っている軟部組織のリリース)
ただ、動きが残っているところもありますから、身内などで協力していただける方がいるようでしたら脊椎なら上下、四肢なら左右でのあそびを比較して感覚をつかむこともよいかと思います。
必ず個人差はありますから、それを一般論として説明することは難しく、体得するためには場数が必要です。
十分な経験を積むまでは、わからないものを無理にわかろうとせず、わかるところから進めていくという方法も現実問題としてはありだと思います。
仙腸関節は完全に癒合するんですか!
ということは、他の関節も癒合することがあるんですね?!
癒合するということは、遊び自体も無くなるということですよね。
その場合の鑑別は、どのようなやり方があるのでしょうか?
自分は高齢者でも、硬さがある人は
モビライゼーションをして緩みを感じたりするのですが
上の組織のリリースを感じているだけかもしれないということですね。
個人差があるということを意識してやっていきます。
ありがとうございます。