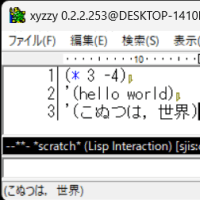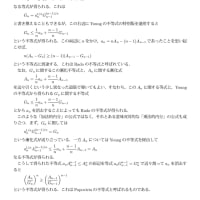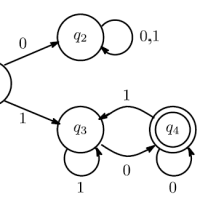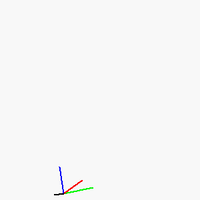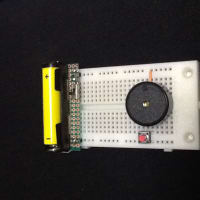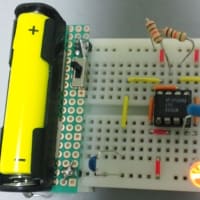今野浩,ヒラノ教授の線形計画法物語,岩波書店,2014.
最適化や数理計画法,線形計画法に興味がわいたので,手当たり次第にいろいろな教科書に当たっている。調べているうちに今野浩氏が日本を代表する数理計画法の専門家の一人であることが分かってきたので,図書館の検索サービスで氏の著作リストを見たところ,この本に行き当たった。線形計画法の優れた入門書は多数あり,いずれか一冊にじっくり取り組めば基礎的な理論は一通り概観できそうであるが,1970年代から現在に至るまでの線形計画法の発展の軌跡を,著者の実体験を織り交ぜながら平易に解説している本書は,それらの本格的な教科書の副読本として,この分野に進もうと思っている方々にぜひとも一読を薦めたい珠玉の一冊である。この分野におけるもっとも重要と思われる基本事項が10ものコラムで簡潔に紹介されているのも,この分野の概要をつかむのに大いに助けになると思われる。
失礼な表現ととられるかもしれないが,むしろ心よりの信愛を込めて言い表せば,「おじいちゃんの昔語り」といった趣の本である。森口繁一,伊理正夫,線形計画法の創始者 Dantzig など,名前は聞いたことがあるが詳しい業績や人物像は一切知らなかったスーパースターたちの逸話が盛りだくさんで,ミーハーな私にはたまらない内容だった。そして線形計画法や関連する分野に関する大まかな概観を得ることができたのは非常にありがたいことである。特に双対定理という重要な定理の由来に関するくだりがあったのは嬉しかった。誰が何をしたか,といった歴史的な側面にも強い関心があるので,こうした記録を書き残してくれているのはとてもありがたいことである。もちろん,本書に登場したさまざまな研究者たちの人物像や評価は,この著者という一個人から見た一面に過ぎないので,すべてを鵜呑みにするのは危険であろうが,貴重な資料であることに変わりはない。
ところで,一松信氏の『偏微分と極値問題』(現代数学社)の第7章に,人間の食事に関して線形計画法で最適解を探したらとんでもない献立が出来上がって大笑いになったといった話が書かれており,具体的にはどんな内容だったのか気になって仕方がなかったのだが,元ネタは本書の第4章で紹介されているエピソードかもしれない。
線形計画法という分野は何度か「線形計画法は終わった」と言われた時期があったそうだが,その度にブレイクスルーが起こり,今に至るまで発展を続けているようである。しかし,本書を最後まで読んで,正直なところ「やはり線形計画法はもう終わったのではないか」という感想を抱いてしまった。これは線形計画法を必要としている応用の現場を全く知らない門外漢が抱いた誤った印象であろう。現場に身を投じれば,今野氏が言う通り,解決すべき難題は山積していることを肌でひしひしと感じるに違いない。とはいえ,私の興味のあり方は氏が随所で批判している経済学者や日本の数学者と同じようなものであって,実務に役立つ具体的な問題には全く興味がないので,既存の理論のごくごく基本的なところを学ぶだけで十分満足できてしまいそうである。
ただ,この本を読むと,若かりし頃の氏にならって Dantzig の分厚いテキストを読破したらどんなに素敵だろうかと夢想してしまうが,あくまでも憧れであって,夢見るだけで終わることだろう。読破したいと夢見た本はこれまでもたくさんあったが,どれ一つとして読破した試しがないからである。
あと,この分野における古典というべき文献をこの本を通じて何冊か知ることができたのもありがたかった。ミーハーなので「定評」に弱いのである。
また,子供の頃に耳にしたことのある「カーマーカー特許」という騒動の一部始終をこの本で初めて知った。そういうわけで,個人的には,前々からうすぼんやりと気になっていた疑問をいくつも解決してくれた,読み応えのある一冊であった。さらには企業で数学の理論がどう活用されているのか,雰囲気をうかがい知ることができたのも収穫であった。実質的に線形代数を必修科目として学ばされる工学系の学生たちにも推薦したい書である。
最適化や数理計画法,線形計画法に興味がわいたので,手当たり次第にいろいろな教科書に当たっている。調べているうちに今野浩氏が日本を代表する数理計画法の専門家の一人であることが分かってきたので,図書館の検索サービスで氏の著作リストを見たところ,この本に行き当たった。線形計画法の優れた入門書は多数あり,いずれか一冊にじっくり取り組めば基礎的な理論は一通り概観できそうであるが,1970年代から現在に至るまでの線形計画法の発展の軌跡を,著者の実体験を織り交ぜながら平易に解説している本書は,それらの本格的な教科書の副読本として,この分野に進もうと思っている方々にぜひとも一読を薦めたい珠玉の一冊である。この分野におけるもっとも重要と思われる基本事項が10ものコラムで簡潔に紹介されているのも,この分野の概要をつかむのに大いに助けになると思われる。
失礼な表現ととられるかもしれないが,むしろ心よりの信愛を込めて言い表せば,「おじいちゃんの昔語り」といった趣の本である。森口繁一,伊理正夫,線形計画法の創始者 Dantzig など,名前は聞いたことがあるが詳しい業績や人物像は一切知らなかったスーパースターたちの逸話が盛りだくさんで,ミーハーな私にはたまらない内容だった。そして線形計画法や関連する分野に関する大まかな概観を得ることができたのは非常にありがたいことである。特に双対定理という重要な定理の由来に関するくだりがあったのは嬉しかった。誰が何をしたか,といった歴史的な側面にも強い関心があるので,こうした記録を書き残してくれているのはとてもありがたいことである。もちろん,本書に登場したさまざまな研究者たちの人物像や評価は,この著者という一個人から見た一面に過ぎないので,すべてを鵜呑みにするのは危険であろうが,貴重な資料であることに変わりはない。
ところで,一松信氏の『偏微分と極値問題』(現代数学社)の第7章に,人間の食事に関して線形計画法で最適解を探したらとんでもない献立が出来上がって大笑いになったといった話が書かれており,具体的にはどんな内容だったのか気になって仕方がなかったのだが,元ネタは本書の第4章で紹介されているエピソードかもしれない。
線形計画法という分野は何度か「線形計画法は終わった」と言われた時期があったそうだが,その度にブレイクスルーが起こり,今に至るまで発展を続けているようである。しかし,本書を最後まで読んで,正直なところ「やはり線形計画法はもう終わったのではないか」という感想を抱いてしまった。これは線形計画法を必要としている応用の現場を全く知らない門外漢が抱いた誤った印象であろう。現場に身を投じれば,今野氏が言う通り,解決すべき難題は山積していることを肌でひしひしと感じるに違いない。とはいえ,私の興味のあり方は氏が随所で批判している経済学者や日本の数学者と同じようなものであって,実務に役立つ具体的な問題には全く興味がないので,既存の理論のごくごく基本的なところを学ぶだけで十分満足できてしまいそうである。
ただ,この本を読むと,若かりし頃の氏にならって Dantzig の分厚いテキストを読破したらどんなに素敵だろうかと夢想してしまうが,あくまでも憧れであって,夢見るだけで終わることだろう。読破したいと夢見た本はこれまでもたくさんあったが,どれ一つとして読破した試しがないからである。
あと,この分野における古典というべき文献をこの本を通じて何冊か知ることができたのもありがたかった。ミーハーなので「定評」に弱いのである。
また,子供の頃に耳にしたことのある「カーマーカー特許」という騒動の一部始終をこの本で初めて知った。そういうわけで,個人的には,前々からうすぼんやりと気になっていた疑問をいくつも解決してくれた,読み応えのある一冊であった。さらには企業で数学の理論がどう活用されているのか,雰囲気をうかがい知ることができたのも収穫であった。実質的に線形代数を必修科目として学ばされる工学系の学生たちにも推薦したい書である。