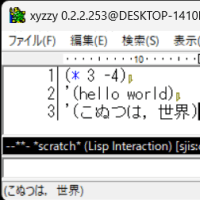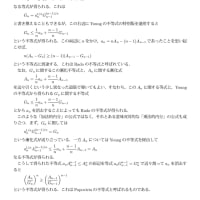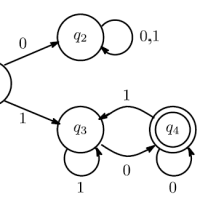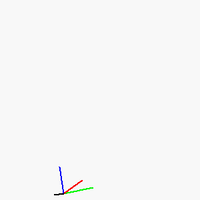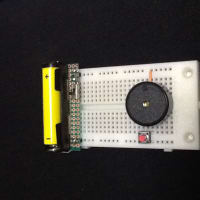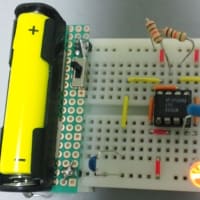新興社啓林館の河合塾・大竹先生による先生方のための徹底入試対策講座は実に 139 回分もの記事が掲載されていて,いろいろと参考になりそうである。
そのサイトは高校数学における複素数の極形式とはどういうものかを確認しようとあれこれ調べていた際にヒットした。
学生の指導の仕方というか,教え方というか,学生に分かってもらえるような話し方などについては,大島利雄先生の大学における数学教育の問題点と工夫という論説も最近見つけた。こちらは冒頭から読み続けるのが辛くなってくるようなエピソードに満ち満ちていて,読んでいて辛くなってくる。だからあまり読み進めていない。最初の部分は大島先生ご自身の学生とのやりとりの例があれこれ出てくるのだが,似たような経験は私もたくさん心当たりがあるので,読んでいて「わかりみ~」と共感しか覚えないのだが,そういった現実をあらためて突きつけられるのが辛くもある。
そういう意味ではファインマンさん本のどれかに書いてあったブラジルの学生の物理の学び方についての感想や,深谷賢治先生の『数学者の視点』で語られているアメリカの大学で教鞭をとった際の体験談(3 クッキングコース)など,ある時代の海外の一大学の実態とはいえ,直視するのが辛い現実の報告の例であり。似た話は現在では枚挙に暇がないであろう。
この記事を書くにあたって大島先生の資料を再検索したところ,相転移 P 氏のアーカイブコンテンツに,彼自身が体験した思い出と共に紹介されているのを見つけた。
彼とはもうかれこれ二十年は会っていないのだが,元気でやっているだろうか。ぜひともそうであって欲しいものだ。
そういえば,肝心の極形式というのは,複素数 z を z=|z|cis(arg(z))
のような形式で書いたものだそうだ。|z| を r,arg(z) を θ のようにおなじみの記号で書けば z=r(cosθ+i sinθ) のことである。この括弧の中身をコンパクトに cisθ と表すのは,私が知らないだけかもしれないが,日本では全く見かけない。19 世紀前半のアイルランドでは Hamilton がその著書だか論文だかで「この頃は cisθ のように書くことがある」みたいなことを述べているそうなので,このセンス抜群の略記法は Hamilton よりも前の世代に遡れるものらしい。19 世紀の前半以前であれば Cajori の本でカバーされているはずなので,機会があったら探してみよう。日本で cis を導入するとしたら高校の「複素数平面」の単元しかない。大学に進学するとたいてい 1 年次の微分積分学の講義で Taylor 展開やら MacLaurin 展開を習った際,Euler の公式も紹介されるであろうから,それ以降は極形式を z=reiθ と書けば済む話となり,cis の出番がなくなってしまう。
電気回路理論においては z=r∠θ のようにも書くそうだ。これは極座標を,2 つの実数の組だということで,数学の正規の記法に従い,(r,θ) と記すより好ましいと思う。ちなみに,角を表す記号 ∠ は日本の初等教育で使われているが,世界標準を謳う ISO やそれを翻訳しただけの JIS では扇形みたいな見かけの記号を使うことになっている。それは Unicode に取り入れられているのだが,こうしてブログで書こうとすると環境依存の記号扱いになってしまう。古いブラウザだったりすると ∢ は表示されないのかもしれない。扇形というよりもヒトの顔を横から見たときの目にそっくりである。目玉のおやじは瞼がないので,目玉のおやじの横顔とは似ても似つかない。
ところで,r∠θ という記法はすぐれていると思うのだが,ISO 流に偏角として負の角である単位円の下半周と,正の角である上半周を合わせた -π<θ≦π の方を採用すると,θ に符号がつくときにどう書くのか,ちょっと気になるところである。√3 ∠ -π/3 なんていう書き方はアリなのかなぁ。電気工学で偏角をどのような一周にとるのか気になるところである。