
竹沢尚一郎先生は『人類学的思考の歴史』(2007年、世界思想社)のなかで、物理学を修め、海水中の色の知覚について博士論文を書いたフランツ・ボアズの関心は、事象を一般法則のなかに還元しようとするものから、個別事象に対する愛着をベースとして、地理学に対してひきつけられていった、というようなことを述べている(211ページ)。20世紀初頭のアメリカにおいて、経験主義的なフィールドデータを重視し、進化主義的な思潮に反対して、文化相対主義を唱えたボアズ。その弟子たちには、ベネディクトやミードがいた。彼女たちは、異文化研究において、「他者」を、肥大化したアメリカ的な「自己」をやしなうための一手段にまで切り下げてしまった(238ページ)。文化人類学は、アメリカの政治状況と結びつくことによって、安っぽい「アメリカ文化論」へと成り下がったのである。ひじょうに興味深い見解である。
ベネディクトやミードがリードした前世紀半ばのアメリカの文化人類学。それは、どこか、わたしたちの時代、特に、日本の文化人類学を取り巻く状況に似ていないだろうか。肥大化した日本の文化の現在をやしなうために、他者は対象化される。結果として、他者は、わたしたちの視界から消えてしまう。紛争状況のなかで生命の危機にさらされ、貧困や飢餓にあえぐ他者たちは、現代日本の若者のヒロイックな自己実現のための対象や道具となっている。地球温暖化問題は、バイオエタノールの生産や削減電力の企業間トレードなどを介して、千載一遇のビジネスチャンスと捉えられて市場化され、気候変動の影響を受ける他者たちは置き去りにされて、どんどんと活動だけが肥大化していく。文化人類学も、基本的には、そういった現代の思潮におもねったかたちで他者に接近している。そのために、悲しいことに、文化人類学は、現在、時代をリードする学問であるという状況にはない。
いったい、なぜ文化人類学は、こんなにも、ダメ学問になってしまったのだろうか。第一に、学問そのものに、ワクワク感がなくなってしまっていることがある。文化人類学をやっている人たちのなかには、ほんとうに楽しいからやっているのか、疑問に思えるようなうような人たちがたくさんいるように思えたりする。それは、文化人類学が、学問の内部に逼塞してしまったことに一因がある。自らの立ち位置をこそ問うという、ワケの分からない学問になってしまったのである。
しかし、本来的には、文化人類学は、けっして、そういった学問ではなかった。他の学問領域に、開かれていた。他の学問領域のいいとこ取りをしてきたのが、文化人類学だった。その意味で、科学や文学の研究や成果から、ヒューと抜け出して、文化人類学にスライドしてきたという、かつての文化人類学者たちの出自のありようを思い起こしてみる価値は、大いにあるのではないだろうか。例えば、ボアズの物理学への関心が、どのようにして、文化人類学の関心を生み出したのだろうか、と。
ボアズの固有の関心はとりあえず傍らにおいて、一般に、物理学は、世界をどう捉えるのか、という問いに支えられている。それは、他者を介して、文化人類学がもっている問いと同様のものである。わたしは、いま、余剰次元に関するリサ・ランドールの本(『ワープする宇宙』2007年、NHK出版)を読んでいる。この本は、門外漢の者にとっては、すんなりと理解できないところがところどころあるが、じつにワクワクする本である。余剰次元の発見の予感に、じつは、著者自身が、一番ワクワクしているのではないかと思える。ワクワク感の点で、いま、文化人類学は、物理学とたたかったなら、対戦成績は2勝13敗くらいで負けるだろう。
線的な移動を可能にする一次元。平面的な移動を可能にする二次元。二次元に上下が加われば三次元となる。わたしたちは、三次元に住んでいるため、四次元、五次元・・・というより高次の次元については、単純なかたちで、想像することができない。逆に、ふつう、三次元より低次のものについては、捉えることができる。影絵の三次元的な人形が壁に射影された場合、二次元的な影となるし、わたしたちは、三次元的な世界にいながらにして、サム・ロイドの「15パズル」をして、文字を並びかえて語=意味をつくり出す。そのことによって、プラスチックの囲いのなかに二次元世界を閉じ込める。遠くに見える山々は三次元のつらなりであるが、夕日に照らし出されて、それらが重なり合ったときに、二次元的に、ひとつのかたまりとして見えることがある。
それとは逆に、わたしたちはどのように、次元を上がることができるのだろうか。ベビーベッドのなかで、幼児は二次元的世界から立ち上がって、上下の方向を知り、三次元世界を自ら体験するようになる。上下だけに二次元的な移動をするエレベータ。「ウォンカベータ」なるものは、想像上で、あらゆる方向に行くことができる三次元的なエレベータである。一次元が巻き上げられて二次元となり、同じように、二次元が巻き上げられて三次元となるという。はたして、三次元を超えた四次元とは、どのようなものなのだろうか。
わたしは、時間の問題を考えているうちに、消化不良ではあるが、余剰次元を含む、物理学の課題へとたどり着いた。中国人とイヌイットが(見た目)よく似ているということは、そもそも、二次元的な空間移動の問題である(イヌイットの祖先が、ベーリング海峡を渡って、アジアから新大陸へたどり着いた)。しかし、そのような空間移動は、移動する時間を内在化させている。その意味で、伝播とは、たんに、二次元的な空間移動だけでなく、時間であり、行動の歴史なのである。
いいかえれば、時間とは、空間的な次元(=三次元)に加えられる、もうひとつの次元でもある。「時空は空間よりも次元の数が一つ多い、『上下』、『左右』、『前後』に加えて、時間を含めたのが時空である」(157ページ)。要は、わたしたちは、じつは、<時空>(=三次元空間+時間)のなかにいる。
そのような<時空>の感覚こそが、時を刻むこと、そのための機械である時計の発生のベースにあるのかもしれない。他方で、時間感覚を身に着けることがなかったような、サラワクのプナンのような人たち。三次元空間における二次元的な移動、遊動のさいに、狩猟採集民は、<時空>の奥深くから突如として立ち昇るかのようにして現れる時間の次元だけを、<時空>から分離して、抽出したいというような衝動に向き合うようなことがなかった。それは、仮説的に述べれば、狩猟採集民が、時だけを飼い慣らし、管理するというような必要がなかったためなのではないだろうか・・・
(写真は、車に載って、狩猟に出かけるプナンの人たち)










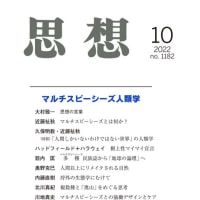

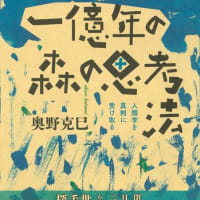
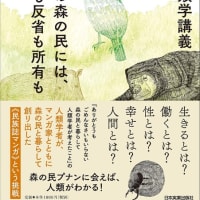



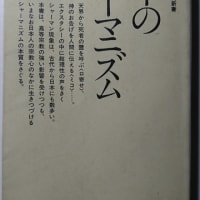


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます