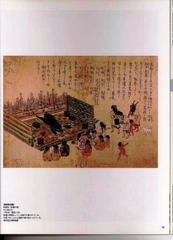
本日の文化人類学の授業で、アイヌのイヨマンテ儀礼を取り上げた。その儀礼は、熊猟において持ち帰られた子熊を人の子以上に丁重に飼い育て、やがて、成長した熊を殺害し、その肉をふるまう儀礼である。つまり、それは、熊の姿で人間の世界にやってきた神を丁重にもてなした後、神を神々の世界に送り返すために行われる。人間にもてなされた熊=神は、神の世界に戻った後に、他の神々に人間の素晴らしさを話し聞かせると、他の神々も、熊となって人間の世界を訪れるとされる。そうした見取り図を示した上で、解説を加え(中沢新一、「映像のエティーク」のなかのイヨマンテをめぐる記述)、ビデオ(1931年、BBC)を見せた。
それは、飼い育てた熊を残酷な方法で殺害し、肉をみなで食べるという内容の儀礼なのであるが、わたしとしては、なぜアイヌの人びとが、そうしたことをしなければならないのか、そういったことを行うことによって、何を表現しようとしているのかを、受講者たちが、真剣に考えているのかどうかを確かめたかった。ビデオを見たすぐ後に、どれほど理解してくれたのかについて<小テスト>を行った(「何が分かったのかについて簡潔に書きなさい)」。全体として、見取り図をなぞるような内容のものが多かったため、わたしとしては、その点において、不満を感じたのであるが、なかには、いろいろと頭を働かせて考えようとしているものもあった。以下、記録として。
【???】
「イヨマンテの儀礼をする時には、本当に多くの人たちが協力し合っているということが分かりました。大人から子供が全員の力を合わせてイヨマンテの儀礼をしていました。熊に対する攻撃をする時でも集団で攻撃をしていました。イヨマンテは、動物に関して独特の考えを持っていて、文明の違いが分かりました」(LA2)という理解が、一応のところ、考えようとしているという点で、ここで取り上げなければならないほどに、表面的に、わたしが解説した見取り図を繰り返すだけのものが多かった。しかし、この学生の理解は、イヨマンテそのものに届いていない。そうした奇妙なやり方を、たんに「文明の違い」に還元してしまっている。
「今の私にとっておかしい所もたくさんあるが、それは文化の違いであり、人間の開き直りではないと信じるしかないと思った」(LA2)というかたちで、彼らのやり方を、けっして、文化の違いに還元してはいけない。
さらに、「ただ自分の意見としては動物を殺す、物を壊すといった行為を神と神の世界に返すなどの理由をつけてやっているにすぎないのだと思いました。人間は神という理由があれば平気で残酷な事をする人だなと思ったのが正直な感想です」(LA2年)。ひぇ~、正直すぎるよ。考えようとしているけど、まったく分かっていないではないか!イヨマンテは、残酷な行為のたんなる宗教的な理由づけという意見。わたしは、教えることがいやになる。いや、もう少し忍耐を持つべきか。
同じような内容のものとして。「どうしても感情論的に見ると、人間の子供以上に大切に育てた熊を殺して食べるなんて、残酷だと思ってしまいました。これはあくまで儀礼なので、アイヌの人々は心を痛めたりしないのでしょうか?儀礼に参加していた人々がみんなが、熊から少しも目をそらさずに、熊を見つめていたのが印象的でした・・・」(LA3)。やはり、残酷だと感じる域をやはり一歩も出ていないですね。「熊から少しも目をそらさずに、熊を見つめていたのが印象的だった」ということの意味を考えてみてほしいのです。なぜ、そうした華やいだ雰囲気のなかで、飼い育てた熊を殺すのでしょうか?残酷かもしれないけど、あえてその残酷さを目にすることによって、彼らは何をしているのでしょうかということを。そうした儀礼でしか表現することができない、人間の実存のあり方が、そこでは表現されているのではないでしょうか。
「アイヌにしてみれば、自分たちがより良く生きるために必要な儀式なのだろう。しかしボクは『逆の立場だったら』と考えてしまってしかたがない。人間が、もし他の星へ行って人間を食す高度な生命体につかまり同じことをされたら・・・どうしてもそんな考えばかり頭にうかぶ。あの映像を見て、それしか考えられなくなってしまった」(総文2)。物事の本質を理解するのに、その空想力は邪魔である。
こうした相対化をまだ体得していない見解の数々から、一歩踏み込んで考えようとしているが、まだまだ足りない意見として。その意味で、イケテナイ理解に属するものとして。「ビデオを見た感じだと、熊がかわいそうにしか見えませんでしたが、話を聞いたり、文章を読んだりして、熊の姿で人間の世界にやってきた神を丁重にもてなし、送りの儀礼(イヨマンテ)を行って神々の世界にお帰り頂くものとして解釈されていたということを知った。資料に書いてあった通り、かわいがっていた熊を殺し、丁寧に解体してあげることは、残酷だと思われるのは、とても分かりました。しかし、生き物に対する慈悲は残酷を否定するというのは、とても難しいことばだなと思いました」 (LA4)。慈悲を実践するだけでは、残酷の先にある事柄の本質を曇らせてしまうということですよ。そこを踏み込んで考えてみなければならないのです。
【○○○】
さて、次に、理解を示してくれたもの。「例えば、身近な所で言えば日本人は魚などを食べる時骨をしゃぶるくらいキレイに食べる。このことについて私は父に『日本人は食べ物(動物)にも神がいて、自分達が生きていく上で殺して食べなくてはいけない。だからこそ敬意を表していただくんだ』と聞いた。動物をペットとして見る事が多い今、とてもショッキングな映像ではあったが、同時に”人間というものは本来どういう動物なのか”を思い知らされた。そして現代人が眼にする事のない動物の”殺し”の現場を見て学ぶアイヌの子供達は、より感謝と生きていくという事を学べるんだと思った」(LA2)。うん、お父さんのことばも助けとなって、イヨマンテ理解のいいところまでイケテイルと思います。
「現在の私たちは動物を殺すこと=残酷として背を向けている。しかし何物も自然からの贈り物であり、それらのおかげで私たちは生きている。イヨマンテは、『自然に感謝する』という当たり前な、しかし現代の私たちには忘れがちなことを思い起こさせてくれるものだった。また、アイヌの人々はイヨマンテを行うことで(自分たちと関わる全てのものに)神として送り出していたことから、それが礼儀(エチケット)だと考えていたことが分かった」(LA3)。そう、私たち現代人は、スーパーで肉を買うから、自然が恵みを与えてくれることに対する感謝の気持ちを忘れてしまっているのです。そのことをイヨマンテが思い起こさせてくれるのですよね。
同様の意見として。「イヨマンテの儀礼というのは、何も知らない人から見れば、ただのむごいだけの儀礼かもしれません。しかしその行為の一つ一つにはとても深い意味があるということを知りました、熊を神の化身として丁重にあつかい、その後神々の世界に返すために盛大な儀礼を行い、その熊を殺す。この儀礼の中で、わたしはアイヌ民族の日々生きていけること、食事をできることへの自然に対する深い感謝の念を感じました。現代に生きる私たちは、食事ができることが当たり前で、生命を殺し作った食べ物を平然と捨てる。私たちとアイヌ民族、本当に野蛮なのはどちらか?深く考えさせられる儀礼でした」(LA3)。しっかりと分かっている。
きちっと理解している答案として。「この儀式は、自分達にめぐみを与えてくれる自然神に対して、アイヌの民族の人達の礼儀、思想の一部なのだという事がわかった。一見残酷に見えるこの儀礼の中には、自分達のために利益を与えてくれる物達へのアイヌの人達の思いやり、感謝を表す一つの方法なのだということが理解できた。なぜ?子熊を自分の子以上に可愛がって育てるのに、最終的に殺してしまうのかという事に対しては、その熊の器を借りてやってきた神に対して、心づくしのおもてなしをして、あちら側の世界(神々が本来あるべき場所)に気持ちよく帰ってもらうための行動なのだと言う事なのだと思った。アイヌの儀式を通して、命を捧げてくれる物達へ、人間は本来どのようにあるべきなのかを教えてくれた」(LA2)。そのとおりだと思います。
「今の私には”神”そのものの存在自体よく理解していないので、生き物を殺すということは、あまりにも残酷だと思ったが、このアイヌの人々の考えにもとづいて行われたイヨマンテは、人間と自然と生物を一つの輪でつなるような、共に生きているみたいな神聖な儀礼と思えた。また、殺すというよりも”神”をまた元の世界に戻すために全てのモノに対してこのイヨマンテを行うアイヌの人々の心もまた清らかなのかなと感じた。”イヨマンテ”を行うことで、礼儀正しさを考えるアイヌの人々はイヨマンテ自体をエチケットとして考えているのだから、全てに対して”はだか”だなあとまぢまぢ感じました」(LA3)。「人間と自然と生物を一つの輪でつなげてような、共に生きているみたいな神聖な儀礼」、ほう~、なるほど、人間が自然(熊・神)によって生かされ、自然(熊・神)に人間が礼儀正しくふるまうということで、すべて共に生きているということを表しているってことですかね。
同様の理解として。「イヨマンテは、人間として自然・動物たちと向き合うことの真実を伝えている。人間はいろいろなものに支えられていて、キレイ言ではなく、そこと人間はどうつながっているのか。今の人間が忘れてしまった、また避けていることをつきつけてくれる。」(LA3)。
「神を送り返す、また来てもらい肉や毛皮を持ってきてもらうという熊送りのイヨマンテ。神を人間に豊かさを与えてくれるという、ある意味都合のいい解釈に感じたが、そこには熊をはじめ全ての自然に人間は生かされているという自然崇拝の形を見た。小熊を育てるという点は、より大きくして肉を得るという利己的な面があるように思えたが、それよりも神をもてなす、感謝する、そして家族の一員として人間も神(自然)も同列にあり、だからこそ礼を尽くすことで対価としての豊かさを得ようという考えもあるように思った。このようなアイヌの自然観、あるいは世界観をイヨマンテから理解することができると私は考えた。」(LA2)。都合のいい解釈をしていたり、利己的な側面に対する疑いを抱きながらも、イヨマンテには、人間と神の交換のなかで、礼を尽くす面もあることを読み取っている。











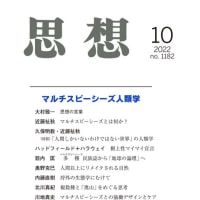

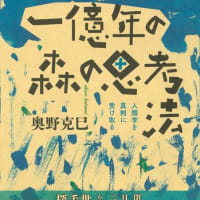
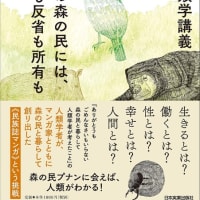



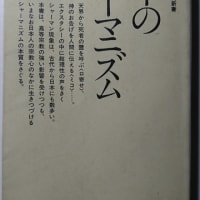

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます