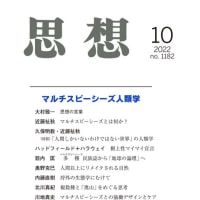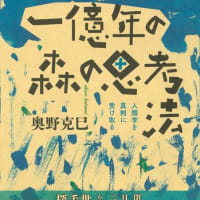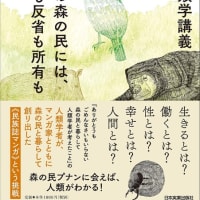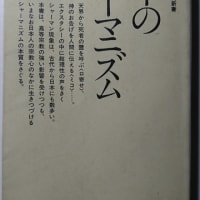内田百間(うちだひゃっけん、間の日は月が正しい)の『冥途・旅順入城式』(岩波文庫)のうち、前半の『冥途』の部分を読んだ。18の短編から構成されている。それぞれ、どこにでもあるような、ありきたりの風景から出発して、主人公とともに不安を煽り立てられ、事の成り行きに翻弄され、夢幻の世界に引き込まれていく。そうした感覚に表現を与えてみたいと思い立って、<わたしたちのなかにある他者や外的存在に対する根源的な不安のようなものが、かたちになって現われる、夢を見ているときに見ているような文学である>と仮につぶやいてみたが、そういう言い方で、事の本質を押さえているかどうかは微妙である。
「波止場」は、湯治場で懇意になった男が、妻が蒸気船に乗るときに手を取って船に入り、妻とともに窓からかわるがわる外を覗いてお出でお出でをしているのが目に入るが、足がすくんだままで、蒸気船に乗りそびれてしまった夫の話。夫は蒸気船を追いかけるために車を走らせる。「車は長い土手を走っている。風のように速い。両側に高い草の生えた間を走りぬけていると、草の中から子供が一人ひょろひょろと出て来て、私の車の下に這入った。私が吃驚して、振り返って見ようとしたら、車屋が、『振り向いて見ちゃ困りますよ』と非常に恐ろしい声をして云ったので、私はどきりとした。矢っ張り死んだのだなと思う」。車は、蒸気船から降りた客が乗り換える駅に着く。妻はすでに男といっしょに汽車に乗り込んでいた。切符を買わずに乗ると駅員に突き飛ばされて、汽車は出てしまい、次の汽車で追いかけることになる。そうした道行きにおいて、彼はときどき妻のことを忘れてしまうのだけれども、着いた駅ではふたたび妻のことを探し始める。「早く早く妻の傍へ行き度いと思う心と裏合わせに、もうどうでもいい様な気がし出した。そう思ってぼんやり見ていると、例の男が私の顔を見て、今までに見せたこともないような美しい顔をした。私は己に帰って、はっとした。そうしてあれが平生ひとごとのように聞いていた間男というものだったかと気がついた」。
本のタイトルにもなっている「冥途」では、一膳飯屋でめしを食べているときに、4,5人の客がやって来て、なにやら話しているのが聞こえてきたという件から始まる。そのうちの一人の年寄りの様子は、見えていながら、どうもはっきりしない。蜂が飛んできた。昔蜂をつかまえてビードロの筒に閉じ込めたという話が聞こえてきたのだが、その話を聞いて、主人公は、自分の記憶に思いあたり、その年寄りが、自分の死んだ父であると思い込む。「『お父様』と私は泣きながら呼んだ。けれども私の声は向こうへ通じなかったらしい。みんなが静かに立ち上がって、外へ出て行った。『そうだ、矢っ張りそうだ』と思って、私はその後を追おうとした。けれどもその一連れは、もうそのあたりには居なかった」。その一膳飯屋は、現世と冥途の境界だったのである。解説のなかで、種村季弘は、この物語を受けて書いている。「生と死はそっくり瓜二つであり、いまにも触れ合い同化しそうでいて、平行線のように交わることなくすれ違い続ける。最終的には、いつかはこの世は滅び、自分はあの世に行くだろう。百間にとっては、それまでの遅延として営まれるのがこの世なのである」。★★★★