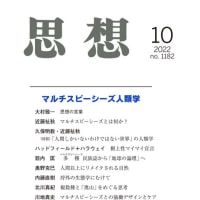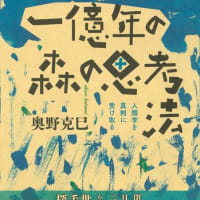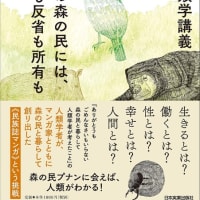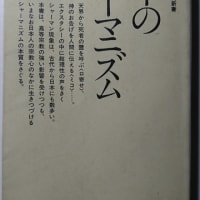ベンドシニスター
このなじみの薄いことば、ナボコフの小説のタイトルは、しばらくわたしの頭から離れなくなった。鐘のように、頭のなかで鳴り響いた。運転中に、ベンドシニスター、授業中に、ベンドシニスタ、ふと、ベンドシニスター・・・ベンドとは、紋章学で、通常、左上から右下にわたる帯状のチャージのこと。他方、ベンドシニスター(左のベンド)とは、右上の角から左下にわたる帯状のチャージだという(下の写真:Wikipediaより)。全然知らなかった。わたしには、いまだに知らないことが、じつに多すぎる!なぜナボコフがこの表題を選んだかというと、「屈折によって乱された輪郭、存在という鏡に映るゆがみ、人生上の誤った進路、左巻きの邪悪な世界というものを暗示するためである」(275ページ)という。
パドックによる警察国家は、妻を失って悲嘆に暮れる友人クルークを利用しようとする。しかし、クルークは、圧力に屈することはない。そのことによって起きる悲劇。やがて、国家は、クルークの息子ダヴィットを人質にとって、クルークを思い通りに操ろうとする。
ナボコフはいう。「『ベンドシニスター』の物語は実際には、グロテスクな警察国家における生と死の物語ではない」(277ページ)と。「『ベンドシニスター』の主要なテーマは、愛に満ちたクルークの心の鼓動、深いやさしさが蒙りやすい苦悩ということになるーそして、ダヴィットとその父親を描くページのためにこそ、この本は書かれたのであり、またそのためにこそ、この本も読まれるべきなのである」(同ページ)。作家自身が導くように、亡き妻への深い情愛、息子ダヴィットへの慈愛、悪意ある友人たちへの悲しみこそが、主題である。
『ベンドシニスター』は、ナボコフが、波瀾のない、活力にあふれる時期であったと回想する、アメリカに来て数年後に、アメリカで書いた最初の小説だったが、後の『ロリータ』での語り口を思わせるような滑稽味の片鱗は、すでに、この小説のなかにも潜在している。
「話している最中で、彼らがクルークをまったく思い出せないでいることがわかった。彼らはクルークの通行証を見た。そして、まるで知識の重荷を振り落とそうとでもするみたいに、肩をすくめた。彼らは頭を掻いてみせさえした。思考細胞の血行を促すというので、この国でおこなわれている奇妙な方法だ」(20ページ)。頭を掻くことが、思考細胞の血行を促す作法?わたしは、そのように考えてみたことなどなかった。なんか可笑しい。
「・・・また、陳腐きわまりない精神構造のカメラマンたちが詰めかけることになっていた。そして、この国唯一の偉大なる思想家が、緋色のローブをまとって(カチャ)国家の象徴たる元首のかたわらに現れ(カチャ、カチャ、カチャ、カチャ、カチャ、カチャ)、朗々たる声で、国家はいかなる個人よりも大きく賢明であると宣言するのだ」(172ページ)。思想家はクルークのこと。括弧内の擬音は、陳腐きわまりない精神構造のカメラマンの写真の音だろう。彼らは、カチャカチャカチャカチャと、元首の写真を写すのだ。こうした表現も滑稽だ。
『ベンドシニスター』は、つかみどころがなく、かなりの難物であるが(一回読んだだけで、その全体を理解できていると言うことは到底できない)、一方で、国家権力の残忍さ、人間の欲望や悲しみに触れ、他方で、そのような問題を、ユーモアを忍ばせながら描き出そうとしている、人間について、なにか途方もなく大きな問題を扱っている小説のようだ。
ウラジミール・ナボコフ著『ベンドシニスター』加藤光也訳、みすず書房(2010-35) ★★★★★