
9月21日(月祝)
2日前に登った北横岳の横にある蓼科山に登ります。
一日往復8時間強 × 二日 のドライブです(笑)
蓼科山は、標高2,530m、八ヶ岳連峰の最北端に位置する孤峰です。
諏訪側から望む美しい円錐形の山容は諏訪富士とも形容されるほどで「日本百名山」の一つです。
19日はのんびり出発して昼過ぎに着いたので、今日は4時に自宅を出発します。

8時10分にすずらん峠駐車場に着きました。
登山口は女乃神茶屋の前から入って行きます。

大きな石が積まれたような登山道です。 
空は青く、白樺の木が信州らしいです。

登って、後ろを振り返ると、「北アルプス」が見えます。
左の方角には・・・
「八ヶ岳連峰」です。ここも北八ヶ岳連峰ですが・・・
しかし連邦軍のモビルスーツは見あたりません。

大きな岩を越えて・・・
まだまだ、石の登山道を登ります。
ピラタスでは近くで見ることが出来なかった縞枯れになった木々の白も美しいです。
空の青と木の白が気持ちいいです。

後ろを振り返ると・・・・・・雲の上なんですねぇ。

岩ばかりになってきました。山頂はもうすぐです。
山頂への案内の印が。。。目立ちすぎ~。
降雪時に迷わないようにポールもたくさん立っています。
「北横岳」が見えます。
2日前はガスで見えなかったから、分からなかったけど、こんなに近くでした。

山頂。 蓼科山 標高2,530m。
山頂部はかつての噴火口跡で、岩石がごろごろしています。
岩石に埋めつくされた山頂は円形で直径約100m。
わずかに噴火口跡がくぼみ、火山であった名残りを感じさせます。
蓼科山頂ヒュッテが見えています。
ヒュッテのほうから沢山の人が上がってきます。子供もいます。
蓼科山は主に三つのコースがあり、北側の七合目からの一番短いコースが整備もされていて人気があるようです。
そこから沢山登ってきているようです。

北アルプスが雲の上に見えます。
女神湖が見えてます。
方位盤。

蓼科神社奥宮の石祠が祀られております。
蓼科山頂ヒュッテは人で混雑しています。

さっきより、多く雲が上がってきます。そろそろ下山します。
下山は、ヒュッテから将軍平へ降り、天祥寺原経由で竜源橋へ出ても良いと思っていたが、ガスがかかってきて眺望も期待できないので、来た道をピストンすることにします。
岩場を下山途中、岩の上に犬がいます。登山者が来ると、見ています。
ガスで周りは白くなってきており寒いです。
次に来た登山者も、犬を心配しています。
けれど、犬はのんびりしています。
主人を待っているのでしょうか。・・・

来た道を戻ります。
また、青空が少し見えてきました。
笹の道を通って・・・ 小鳥が沢山さえずっています。

登山口の女乃神茶屋に出ました。

駐車場に着きました。
帰りは、白樺湖経由で蓼科を後にします。
2日前のリベンジは大成功です。
お天気がよく、素晴らしい景色を見ることができて満足した一日になりました。 今日のルート
今日のルート

駐車地(女乃神茶屋)付近の地図















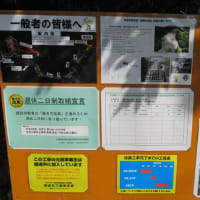





8/8の迷岳以降、更新がないと思ったら一気に5つもアップされていましたね。
さて、北八の最北端の蓼科山には、私も今年5/26に登りましたよ。登山口は同じくすずらん峠からでした。このときは、天気はまずまずでしたが、ちょっと霞んでいたのでイマイチでした。でも、一日天気は崩れることはなかったので、大河原峠から双子山、双子池、亀甲池と周回してきました。
山頂のヒュッテはたくさんの人がいますね。私が登ったときは営業していない時期でしたので、人はあまりいませんでしたね。それでも、団体さんなんかも登ってきていました。北斜面は残雪もありましたよ。
なかなか更新出来ず、やっとアップしました。
kitayama-walkさんみたいに詳細な記事じゃないのに、時間がかかってしまいます。(笑)
蓼科山はお天気が良いと眺望が、最高ですね!
kitayama-walkさんが登った時は、まだ北斜面に残雪があったのですか。2000㍍級の山になると、雪も溶けにくいのかな?
さなりんは蓼科山だけでしたが、kitayama-walkさんは大河原峠から双子山、双子池、亀甲池と周回されたのですね。さすがです!