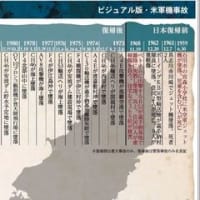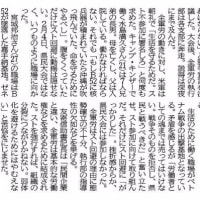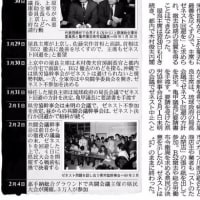美しいゴール 聡明さに興奮/蓮實重彦
決勝戦で私がひきつけられたのは、米国のミッドフィールダー、ラピノーの動きでした。彼女が自陣から前線に上げた長い縦パスにモーガンが素早く反応し、熊谷をかわして先制点を決めた。この意表をついたボールの動きに、「そうか。こんなゴールが見たかったのだ!」と、思わず興奮しました。あのボールの動きの美しさをどうか思い出していただきたい。あれこそがサッカーの爽快さです。
それに比べると、日本の得点は美しくなかった。1点目は宮間がここしかないという場所に走り込み、敵の混乱を突いてボールを冷静に流しこみました。「この選手はただ者でない」と驚嘆したが、爽快さは感じられませんでした。
沢の2点目も、流れるような動きの中でのゴールではなかった。何度も練習した宮間とのサインプレーでしょうが、それを決勝戦で決めた沢はさすがというほかありません。しかし、言葉は悪いかも知れませんが、どさくさ紛れの1点みたいな感じで、二度と起きない奇跡でしょう。
■他国に思いをはせ
私は、4対2ぐらいで米国が勝てた試合だったと思います。逆説的ですが、途中出場の多かったラピノーをあえて先発させたことが、米国の敗因のような気がします。ラピノーはパスの出し手として、今大会で無類の才能を発揮していました。米国が、日本のパスサッカーを潰す刺客として彼女を送りこんだのです。当初はそれが機能して、日本は何度も攻め込まれましたが、米国のシュートはバーやポストにはじかれた。序盤で試合を決めようと焦ったことで、かえってリズムを崩してしまったのです。PK戦での勝敗は、アクシデントのようなもの。日本が勝った試合というより、米国が自滅した試合でした。
一方、日本代表は今大会のどこかで「負ける気がしない」という思い込みを共有したのではないでしょうか。それはまぎれもなく沢と宮間の力です。本来なら悲壮感が漂うはずの岩清水のレッドカード一発退場が、妙に明るくチームを落ちつかせたのもそのためでしょう。ただ、日本代表が突出した強さを持っていたわけではなく、優勝は出来すぎだと思います。
国を挙げて喜ぶのはいい。だが、W杯を「日本の優勝」とだけ捉えると、国際的なイベントが国内問題にすり替わってしまう。参加国の中には北朝鮮も赤道ギニアもいました。仮に彼女らと当たったらどんな戦いになったか。他の国々の選手たちはどんな動きをしたか。そこに思いを致した方が、私たちの世界は豊かさを増すのではないでしょうか。
■騒ぎすぎないで
ここで声を大にして言いたいのは「騒ぎすぎて、彼女らをつぶしてはいけない」ということです。来年はオリンピックを控えているのだから、内外の所属チームに戻って、プレーの質を高めることに専念させるべきなのです。
私がサッカーを見るのは、選手たちの思いがけない動きに驚き、爽快感を覚えたいからです。準々決勝のドイツ戦での丸山のゴールにはしびれました。沢の浮かせたパスを追ってあの勢いで走り込み、難しい角度から右足でゴール左すみに蹴りこむ。誰もが「ああいう形で点を取りたい」と夢見ていながら男子でも失敗するプレーを、あの舞台で実現させた丸山の動きの聡明(そうめい)さには驚きました。
私はNHKで解説をしていた川上直子さんが日本代表だった頃、ちょんまげのように結った髪を揺らして右サイドを駆け上がっていく姿にひかれて女子サッカーを見るようになりました。現代表の川澄のひたむきな走りも、それに劣らぬ魅力です。男子と比べてスピードやパワーは劣りますが、男子の極端なラフプレーやつぶし合いに見られるような陰惨さはありません。「ボールを相手に与えず味方に預け続けることで、見る者を驚かす」というサッカーの理想型は、むしろ女子の方に残っているのではないでしょうか。
敵味方を問わず彼女たちの動きの美しさを味わってほしい。勝利の瞬間に歓喜の輪に加わらず、米国選手たちと健闘をたたえあった宮間の謙虚さにふさわしく、スポーツを語らねばなりません。
私が日本選手で一番期待しているのは決勝戦の終盤、残り数分で出場した18歳の岩渕です。彼女はたぶん、「自分が世界で一番ドリブルがうまいのだから、相手が自分からボールを奪おうとすればファウルをするしかない」と思い込んでプレーしている。その自信にあふれた動きを見ているのは、何ともすがすがしい体験です。沢は人間として最高レベルの選手ですが、岩渕には人間を超えた、動物めいたものを感じる。日本代表の弱点は自信あふれるストライカーの不在ですが、彼女はそうなる可能性を秘めています。
(聞き手・太田啓之、金重秀幸)
------------------------------------------
ナショナリズムと無縁の感動/姜尚中
決勝戦を見ました。感動的な勝利でした。私も、私の家族も跳び上がって喜びました。
これまで一度も米国に勝ったことがない日本が、なぜ勝てたのか。さらにこの勝利がどういう意味を持つのか。私なりに考えてみました。
聞くところによると、「なでしこジャパン」の選手たちは、多くが働きながら競技を続け、経済的に恵まれない境遇で生きてきたそうです。プレーする場を求めて海外に出て、ディアスポラ(流浪の民)的な人生を歩んできた選手も少なくありません。Jリーグで活躍し、海外のクラブから多額の金額を提示される男子サッカーのスターとは、まったく違う環境から飛び出してきたヒロインです。
彼女らは「なでしこ」というエレガントな名称を冠されてはいますが、その名とは裏腹に草の根的なところから出てきました。持たざる者たちが、海外で武者修行を積み、ほとんど誰も注目しない中で、ドイツに集ってきた。あたかも、梁山泊に集結する強者(つわもの)のごとき彼女らが、世界最高の大会の、しかも決勝戦で大番狂わせを演じて世界の頂点に立ったのです。
ついこの間まで、彼女たちのことなど、まったく知らなかった多くの国民が、私も私の家族もまた、彼女らに感動し、熱狂し、最大級の賛辞を贈りました。
■悲壮感なき快挙
日本は、3・11以降、震災、津波、原発、政治の不毛という絶望的な状況に置かれています。そこに彗星(すい・せい)のごとく現れた「なでしこ」には、日本社会の閉塞(へい・そく)感に風穴をあける物語が詰まっていたのです。単に優勝したから素晴らしいのではないのです。
ただ、不思議なことに、国をあげての熱狂にもかかわらず、選手も国民も、ナショナリズム的な高揚感とは無縁だったように思います。
五輪などスポーツの国際大会に臨む選手たちが、一身に国を背負い、国家の大きな物語の中に自己を投影して、悲壮感すら漂わせている姿を見たことがあるでしょう。軽やかに、爽やかにピッチを駆け回る「なでしこ」の姿に、そんなクサさを、まったく感じることがありませんでした。
「なでしこ」は、決して恵まれているとは言えない、それぞれの競技者人生を背負って、この大会に臨んでいたのではないでしょうか。無名の人、不遇の人が、けなげとしか言いようがない姿でもって、みんなができないと思っていた快挙を成し遂げた。
そんな選手たち一人ひとりの小さな物語への共感が感動となって広がったのであって、日本国への愛国心を「なでしこ」に映していたわけではないのです。
今の日本では、国家の大きな物語に感情移入する心境になれなかったのでしょう。日の丸をつけたユニホームを身につけていても、「なでしこ」がナショナリズムと無縁に見えたのは、つまりは、そういうことだと考えています。
■海外でもまれて
決勝で日本に敗れた米国についても、少し考えてみました。
米国において、スポーツは社会の下層にいる人たちが、アメリカンドリームをつかむための手段になっています。その主役は、多くの場合、有色人種です。
しかし今回の代表チームの中心は、白人でした。なぜでしょうか。それは、欧州と違って、米国で女子サッカーは、近ごろは人気があるとはいえ、他のスポーツに比べてお金にならないからです。米国の女子サッカーは、アッパーミドルクラスの、経済的に安定した層がプレーするスポーツであって、アメリカンドリームをつかむためのものではない。
大きな貧富の格差を抱え、多様な民族が織りなす、ある種の混沌(こんとん)が米国の強みです。しかしアッパーミドルの白人を中心に構成された今回の代表チームは、その強みを発揮できなかったと言えるのではないでしょうか。
さらに、米国代表の多くが国内リーグでプレーしています。対する「なでしこ」は、海外リーグでもまれ、はい上がってきた選手たちです。外見は日本人ですが、ドメスティックではない。「グローバル化したメード・イン・ジャパン」とでも呼ぶべき存在です。
最後に、そんな選手たちをまとめ上げた佐々木則夫監督にも賛辞を贈りたいと思います。
決勝のPK戦の前、選手たちが笑顔で佐々木監督を囲んでいる姿を見ました。1964年の東京五輪で優勝したバレーボール女子チーム、いわゆる「東洋の魔女」を率いた大松博文監督は、規律を徹底し、「おれについてこい」という名言のもと、選手を厳しく指導したことで知られています。大松流の指導では、梁山泊の強者の角を矯める結果になっていたでしょう。お見事でした。
(聞き手・秋山惣一郎)
*2011.7.26 朝日朝刊
よろしければ、下のマークをクリックして!

よろしければ、もう一回!

決勝戦で私がひきつけられたのは、米国のミッドフィールダー、ラピノーの動きでした。彼女が自陣から前線に上げた長い縦パスにモーガンが素早く反応し、熊谷をかわして先制点を決めた。この意表をついたボールの動きに、「そうか。こんなゴールが見たかったのだ!」と、思わず興奮しました。あのボールの動きの美しさをどうか思い出していただきたい。あれこそがサッカーの爽快さです。
それに比べると、日本の得点は美しくなかった。1点目は宮間がここしかないという場所に走り込み、敵の混乱を突いてボールを冷静に流しこみました。「この選手はただ者でない」と驚嘆したが、爽快さは感じられませんでした。
沢の2点目も、流れるような動きの中でのゴールではなかった。何度も練習した宮間とのサインプレーでしょうが、それを決勝戦で決めた沢はさすがというほかありません。しかし、言葉は悪いかも知れませんが、どさくさ紛れの1点みたいな感じで、二度と起きない奇跡でしょう。
■他国に思いをはせ
私は、4対2ぐらいで米国が勝てた試合だったと思います。逆説的ですが、途中出場の多かったラピノーをあえて先発させたことが、米国の敗因のような気がします。ラピノーはパスの出し手として、今大会で無類の才能を発揮していました。米国が、日本のパスサッカーを潰す刺客として彼女を送りこんだのです。当初はそれが機能して、日本は何度も攻め込まれましたが、米国のシュートはバーやポストにはじかれた。序盤で試合を決めようと焦ったことで、かえってリズムを崩してしまったのです。PK戦での勝敗は、アクシデントのようなもの。日本が勝った試合というより、米国が自滅した試合でした。
一方、日本代表は今大会のどこかで「負ける気がしない」という思い込みを共有したのではないでしょうか。それはまぎれもなく沢と宮間の力です。本来なら悲壮感が漂うはずの岩清水のレッドカード一発退場が、妙に明るくチームを落ちつかせたのもそのためでしょう。ただ、日本代表が突出した強さを持っていたわけではなく、優勝は出来すぎだと思います。
国を挙げて喜ぶのはいい。だが、W杯を「日本の優勝」とだけ捉えると、国際的なイベントが国内問題にすり替わってしまう。参加国の中には北朝鮮も赤道ギニアもいました。仮に彼女らと当たったらどんな戦いになったか。他の国々の選手たちはどんな動きをしたか。そこに思いを致した方が、私たちの世界は豊かさを増すのではないでしょうか。
■騒ぎすぎないで
ここで声を大にして言いたいのは「騒ぎすぎて、彼女らをつぶしてはいけない」ということです。来年はオリンピックを控えているのだから、内外の所属チームに戻って、プレーの質を高めることに専念させるべきなのです。
私がサッカーを見るのは、選手たちの思いがけない動きに驚き、爽快感を覚えたいからです。準々決勝のドイツ戦での丸山のゴールにはしびれました。沢の浮かせたパスを追ってあの勢いで走り込み、難しい角度から右足でゴール左すみに蹴りこむ。誰もが「ああいう形で点を取りたい」と夢見ていながら男子でも失敗するプレーを、あの舞台で実現させた丸山の動きの聡明(そうめい)さには驚きました。
私はNHKで解説をしていた川上直子さんが日本代表だった頃、ちょんまげのように結った髪を揺らして右サイドを駆け上がっていく姿にひかれて女子サッカーを見るようになりました。現代表の川澄のひたむきな走りも、それに劣らぬ魅力です。男子と比べてスピードやパワーは劣りますが、男子の極端なラフプレーやつぶし合いに見られるような陰惨さはありません。「ボールを相手に与えず味方に預け続けることで、見る者を驚かす」というサッカーの理想型は、むしろ女子の方に残っているのではないでしょうか。
敵味方を問わず彼女たちの動きの美しさを味わってほしい。勝利の瞬間に歓喜の輪に加わらず、米国選手たちと健闘をたたえあった宮間の謙虚さにふさわしく、スポーツを語らねばなりません。
私が日本選手で一番期待しているのは決勝戦の終盤、残り数分で出場した18歳の岩渕です。彼女はたぶん、「自分が世界で一番ドリブルがうまいのだから、相手が自分からボールを奪おうとすればファウルをするしかない」と思い込んでプレーしている。その自信にあふれた動きを見ているのは、何ともすがすがしい体験です。沢は人間として最高レベルの選手ですが、岩渕には人間を超えた、動物めいたものを感じる。日本代表の弱点は自信あふれるストライカーの不在ですが、彼女はそうなる可能性を秘めています。
(聞き手・太田啓之、金重秀幸)
------------------------------------------
ナショナリズムと無縁の感動/姜尚中
決勝戦を見ました。感動的な勝利でした。私も、私の家族も跳び上がって喜びました。
これまで一度も米国に勝ったことがない日本が、なぜ勝てたのか。さらにこの勝利がどういう意味を持つのか。私なりに考えてみました。
聞くところによると、「なでしこジャパン」の選手たちは、多くが働きながら競技を続け、経済的に恵まれない境遇で生きてきたそうです。プレーする場を求めて海外に出て、ディアスポラ(流浪の民)的な人生を歩んできた選手も少なくありません。Jリーグで活躍し、海外のクラブから多額の金額を提示される男子サッカーのスターとは、まったく違う環境から飛び出してきたヒロインです。
彼女らは「なでしこ」というエレガントな名称を冠されてはいますが、その名とは裏腹に草の根的なところから出てきました。持たざる者たちが、海外で武者修行を積み、ほとんど誰も注目しない中で、ドイツに集ってきた。あたかも、梁山泊に集結する強者(つわもの)のごとき彼女らが、世界最高の大会の、しかも決勝戦で大番狂わせを演じて世界の頂点に立ったのです。
ついこの間まで、彼女たちのことなど、まったく知らなかった多くの国民が、私も私の家族もまた、彼女らに感動し、熱狂し、最大級の賛辞を贈りました。
■悲壮感なき快挙
日本は、3・11以降、震災、津波、原発、政治の不毛という絶望的な状況に置かれています。そこに彗星(すい・せい)のごとく現れた「なでしこ」には、日本社会の閉塞(へい・そく)感に風穴をあける物語が詰まっていたのです。単に優勝したから素晴らしいのではないのです。
ただ、不思議なことに、国をあげての熱狂にもかかわらず、選手も国民も、ナショナリズム的な高揚感とは無縁だったように思います。
五輪などスポーツの国際大会に臨む選手たちが、一身に国を背負い、国家の大きな物語の中に自己を投影して、悲壮感すら漂わせている姿を見たことがあるでしょう。軽やかに、爽やかにピッチを駆け回る「なでしこ」の姿に、そんなクサさを、まったく感じることがありませんでした。
「なでしこ」は、決して恵まれているとは言えない、それぞれの競技者人生を背負って、この大会に臨んでいたのではないでしょうか。無名の人、不遇の人が、けなげとしか言いようがない姿でもって、みんなができないと思っていた快挙を成し遂げた。
そんな選手たち一人ひとりの小さな物語への共感が感動となって広がったのであって、日本国への愛国心を「なでしこ」に映していたわけではないのです。
今の日本では、国家の大きな物語に感情移入する心境になれなかったのでしょう。日の丸をつけたユニホームを身につけていても、「なでしこ」がナショナリズムと無縁に見えたのは、つまりは、そういうことだと考えています。
■海外でもまれて
決勝で日本に敗れた米国についても、少し考えてみました。
米国において、スポーツは社会の下層にいる人たちが、アメリカンドリームをつかむための手段になっています。その主役は、多くの場合、有色人種です。
しかし今回の代表チームの中心は、白人でした。なぜでしょうか。それは、欧州と違って、米国で女子サッカーは、近ごろは人気があるとはいえ、他のスポーツに比べてお金にならないからです。米国の女子サッカーは、アッパーミドルクラスの、経済的に安定した層がプレーするスポーツであって、アメリカンドリームをつかむためのものではない。
大きな貧富の格差を抱え、多様な民族が織りなす、ある種の混沌(こんとん)が米国の強みです。しかしアッパーミドルの白人を中心に構成された今回の代表チームは、その強みを発揮できなかったと言えるのではないでしょうか。
さらに、米国代表の多くが国内リーグでプレーしています。対する「なでしこ」は、海外リーグでもまれ、はい上がってきた選手たちです。外見は日本人ですが、ドメスティックではない。「グローバル化したメード・イン・ジャパン」とでも呼ぶべき存在です。
最後に、そんな選手たちをまとめ上げた佐々木則夫監督にも賛辞を贈りたいと思います。
決勝のPK戦の前、選手たちが笑顔で佐々木監督を囲んでいる姿を見ました。1964年の東京五輪で優勝したバレーボール女子チーム、いわゆる「東洋の魔女」を率いた大松博文監督は、規律を徹底し、「おれについてこい」という名言のもと、選手を厳しく指導したことで知られています。大松流の指導では、梁山泊の強者の角を矯める結果になっていたでしょう。お見事でした。
(聞き手・秋山惣一郎)
*2011.7.26 朝日朝刊
よろしければ、下のマークをクリックして!
よろしければ、もう一回!