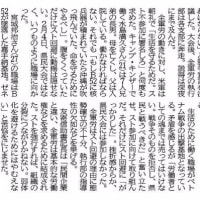ニュースソースの秘匿や守秘義務など様々な制約がある情報(インテリジェンス)の世界を描くには、「ノンフィクション的な小説」と「小説的なノンフィクション」という二つのアプローチの方法があると私は考えています。手嶋さんは前者の手法で『ウルトラ・ダラー』(新潮社刊)をお書きになり、私は後者の手法を取りました。(佐藤 優)
経済大国に求められる「情報力」とは
佐藤 優『自壊する帝国』
手嶋龍一×佐藤 優
--------------------------------------------------------------------------
不気味なほどの共通点
佐藤 ニュースソースの秘匿や守秘義務など様々な制約がある情報(インテリジェンス)の世界を描くには、「ノンフィクション的な小説」と「小説的なノンフィクション」という二つのアプローチの方法があると私は考えています。手嶋さんは前者の手法で『ウルトラ・ダラー』(新潮社刊)をお書きになり、私は後者の手法を取りました。
手嶋 情報源の秘匿、これが問題の核心です。それには確かに、二つの道があると思います。しかしながら、この二つの方法論は意外に近い。そして双方が交錯するところにインテリジェンスの実像が浮かびあがってくる。そういう意味で『自壊する帝国』(新潮社刊)は味わい深い作品でした。
佐藤 なるほど。
手嶋 僕は佐藤優さんという書き手は戦後日本を代表するインテリジェンスオフィサーだと思っているのですが――。
佐藤 それは違いますよ。私はインテリジェンスに関する知識を、少しだけ持った外交官に過ぎません。
手嶋 ご自分では否定されるかもしれません。だからこそ、インテリジェンスオフィサーなのです。希代の情報士官が生まれるまでの過程で何があったのか、これまで佐藤さんについて誤り伝えられていたこともいくつか発見して、ラスプーチン伝説を訂正することができたので、ひじょうに面白く一気に読ませていただきました。
佐藤 ありがとうございます。
手嶋 それで、やや愕然とすることがありました。それは僕はこれまで佐藤さんとは全然似てないと言い募ってきたのですが、この本を読んで、不気味なほど共通点があるということに思い至ったんです。
佐藤 たとえば、どんなところでしょう。
手嶋 佐藤さんは外務省、僕は公共放送とお互い巨大組織にいた。僕は明らかに極端なマイノリティだったのですが、佐藤さんも、マジョリティではないですよね。
佐藤 それはもう明白です。マイノリティの中のマイノリティですよ。
手嶋 それからもうひとつ、佐藤さんは神学というひじょうに奥深い学問を勉強されたという点です。実は僕にはほとんどお師匠さんがいないのですが、あえて挙げさせていただければ、ハーバード大学のブライアン・ヘア教授という方がいます。
カトリックの聖職者で神学部の教授なのですが、一九八○年代、第二次冷戦の頂点といわれた頃に、カトリック教会が来たるべき核戦争に倫理的にも政治的にもどう対応すべきかという事態に直面し、バチカンの見解の筆を執ったのが、「黒衣の国際政治学者」といわれたこの人です。僕は一九九四年にハーバード大学にフェローとして招聘されていたときに、このヘア教授の指導を受けました。
佐藤 そうでしたか。本にも書いたことですが、私はフロマートカというチェコの神学者のことを研究していたことがきっかけとなって、外交の道に入ったんです。
情報の地下水脈へ
手嶋 もう一つだけ共通点を挙げると、本の中にサーシャというとても面白い人物が出てきますね。
佐藤 はい。モスクワ大学で知り合った沿バルト三国の、ラトビア出身の学生です。
手嶋 このサーシャとの出会いが、インテリジェンスオフィサー佐藤優を生むきっかけになったのですね。ここでは、あえてスティーブン・ブラッドレーと申し上げておきますが、僕の場合は東京におけるスティーブンとの出会いが、ひとつの重要なきっかけとなりました。スティーブンに頼まれて、イギリス大使を助けたことがあったんです。その大使は東アジアの外交や安全保障のプロフェッショナルでした。
佐藤 そうそう。イギリス大使には極めて興味深い人がよくいます。
手嶋 ところが、駐日英国大使としては、イギリスのウイスキーに対する関税障壁の問題にも取り組まなければならず、ひじょうに苦労していた。それで、僕が日本政府の税制調査会の攻略に一肌脱いだのです。答申の起草委員のひとりと親しくしていたからです。
その結果、イギリスにとって長年懸案となっていたこの問題で突破口が開けたのでした。それを大使がひじょうに感謝していたとスティーブン経由で聞きました。あの男にはいつの日か借りを返すと言っていたというのですが、そんなことはすぐに忘れてしまいました。
その後、ワシントンに赴任することになって、覚悟はしていたのですが最初の頃は、まったく手も足も出なくて苦労しました。そんなある日、佐藤さんの作品でサーシャに当たるような人物から、突然電話がかかってきた。アクセントから明らかにイギリス人でした。出てこいと言うから会ってみました。向こうはどういう筋に頼まれたなどとは、もちろん何も言いません。だけれども「ああ、そうか」とひざを打ちました。
それは金鉱脈でした。そこから一挙に地下水脈に入っていくことができた。もちろん、ジャーナリストと外交官は違うのでしょうが、同じことが佐藤さんにあったのだと、この本を読んでよく分かりました。ああ、やっぱりラスプーチンにもこんな出会いがあったのかと、ここは感動を持って読ませていただきました。
佐藤 でも、基本的に不思議なもので、このインテリジェンスの核というのは似ているんですね。インテリジェンスは文化で各国別々のものであるということと同時に、インテリジェンス業界自体の文化というものがある。
私も外務省のなかの派閥的なめぐり合わせとか、おつき合いしていた政治家の流れとかで、もちろんこれまでも手嶋さんと重なる部分があり、ときには対立することもありました。そういうなかで私は手嶋さんのことを、優れたジャーナリストであるだけではなく、無視できないプレーヤーの一人だと以前から認識していました。
しかし、『ウルトラ・ダラー』を読み、そしてその後お話をして、少しおつき合いをさせていただいてすぐにわかったのは、この人はほんとうのプロだということです。どうしてかといったら約束は絶対に守る。それと同時に軽々に約束はしない。約束をできないことを約束しない。それが、インテリジェンスというゲームの基本的なルールなんです。日本人はこれを失敗してしまうんです。約束できないことを約束してしまうんですね。
また先ほどのお話では、ワシントンに行ってアプローチしてきたときの人間関係のつくり方がキーですよね。必要のないこと、つまりここより踏み込んで知らないほうがいいことがある。それについてはあえて聞かない。それがインテリジェンスの文化なんです。
手嶋 まったくその通りですね。
『ウルトラ・ダラー』のインパクト
佐藤 ここ数年、私が危惧していたのは、現在の日本では、特に対外インテリジェンスに関して、ほとんど体を為していないような状況に陥ってしまっているということでした。しかし、手嶋さんが登場したことによって、本格的な日本のインテリジェンスの伝統を回復すると同時に、現代イギリス流のインテリジェンスの基礎が、あと五年ぐらいでできるのではないかと思うんです。
その意味で『ウルトラ・ダラー』という作品は、日本にとってインテリジェンスというのはどういうものなのかという大枠を小説という形で提示した上で、その内在論理まできちんと描いた初めての作品だと言えるでしょう。ですから、手嶋さんの提言をここからどうやって活かしていくのかというのは、今後、日本の政府にとって非常に重要なことだと思うんです。
手嶋 同感です。確かに日本には真のインテリジェンスオフィサーが、佐藤優さんのように突然変異的に生まれる以外には、ほとんど出てこないだろうし、そもそも、育てる組織もない。警察にはインテリジェンスに関して組織的にも手法としてもかなりの蓄積はありますが、それはあくまでカウンターインテリジェンス(対敵情報活動)で、対外インテリジェンスとは別のものですからね。
佐藤 本当に警察の能力は高いです。
手嶋 そうですね。
佐藤 しかし、状況によってはカウンターインテリジェンスの文化が対外インテリジェンスのブレーキになる。自発的、積極的に動くというのは潜在的にスパイということになってしまうんです。徹底的に警戒して何もしないのが一番いいということになると、対外インテリジェンスはできないですね。結局、対外インテリジェンスとカウンターインテリジェンスは文化が違うから、切り離さざるを得ない。一緒に動くと必ず軋轢が生じるんです。両者のバランスを為政者がうまくとることが大切です。
手嶋 たしかに、幾つかの問題点を抱えています。ただ、絶望の唄を歌うのはまだ早い。
佐藤 国家は生き残らなければなりません。そのためにはインテリジェンスは不可欠な要素となります。
手嶋 その通りです。世界第二の経済大国である日本は必然的に潜在的にはインテリジェンス大国たり得る――。これは佐藤優さんの立論ですが、僕もなるほどと思います。もちろん、実際にはイギリスやアメリカ、ロシア、イスラエルなどインテリジェンス大国との間には、まだまだ大きな溝があるけれども、諦めてはいけないというのが、佐藤さんの新作の隠されたメッセージではないでしょうか。
佐藤 そこまで読み込んでいただいて、ありがとうございます。
手嶋 僕も外交ジャーナリストの端くれですので、八○年代の終わり頃から、モスクワに佐藤ありと注目していました。それ以来、ずっと佐藤さんのことは気になっていたのです。情報を追いかけていくというのは、獣道を辿って山に分け入って行くようなものです。僕は主としてワシントンから、佐藤さんはモスクワを基盤にして、獣道に分け入っていく。そうすると、思いがけず遭遇したりするわけです。獣道だから暗くて見えない。ところが、頬にちょっと手が触れたように感じる――。
佐藤 すれ違ったりとか。
手嶋 暗いところで、大きな目が僕を見ている。目を凝らすと、そこにラスプーチンという人の姿を見つける。不気味ですよね。
佐藤 こっちも逆に、何回か手嶋さんの歌舞伎役者のような流し目を見たような気がします。テルアビブから成田に帰って来たときに、すっと背中に手嶋さんの視線を感じるとか、そういったことがありましたから。ただ、お互いどこで遭遇したなんて話をしないのが、この世界の文化ですよね(笑)。
手嶋 そうですね。普通はこんな話はしませんが、今日は読者へのサービスということで。
ゾルゲVS.ラスプーチン
手嶋 『自壊する帝国』の著者にひとつ伺いたいのですが、かつて、東京を舞台にした伝説のインテリジェンスオフィサー、リヒャルト・ゾルゲという人がいました。そのゾルゲと佐藤ラスプーチンを比較した人がいるんです。一説によると、僕だということになっているけれども(笑)。
佐藤ラスプーチンに比べると、ゾルゲにはより多くのハンディがあったという指摘です。当時、ゾルゲはクレムリンの中枢や赤軍の中枢部から、何一つ情報をもらっていない。一方、佐藤さんは、もちろん自分でも足で歩いて圧倒的な情報を獲得したのですが、世界第二位の経済大国に流れ込んでくる情報の存在があった。かなりの情報力の恩恵も受けている。だから、ゾルゲよりずっと恵まれていた。こうした批判にどのようにこたえますか。
佐藤 その比較をした方は、リヒャルト・ゾルゲの実像を深くご存じないのかもしれませんね(笑)。ゾルゲは、赤軍本部からは情報をもらっていないですが、実はあるところに蓄積されていた大量の秘密情報にアクセスできた。だから、私が現役の外交官だった頃と同じくらい、情報には恵まれていたんです。
手嶋 そのあるところというのは、ナチス・ドイツですね。
佐藤 その通り、ベルリンからです。要するにインテリジェンスの世界でリヒャルト・ゾルゲをどこのスパイと見るかというと、ソ連とドイツの二重スパイということになる。さらに、国際スタンダードで冷静に見た場合には、ドイツにプライオリティがある。
どうしてかというと、インテリジェンスの世界は二つの要素でできているんです。まず、誰が指令を出して、誰に報告するかです。二番目の要素は、だれがお金を払うかということ。指令を出していたのは駐日ドイツ大使館のオットー大使で、ゾルゲはそれに一○○%こたえています。それから、ドイツ大使館からお金も受け取っている。
手嶋 奥さんは、ロシア系ですよね。
佐藤 ゾルゲのモスクワに残した奥さんはロシア人ですが、他にも何人か奥さんたちがいました。情報を統括する赤軍第四本部は常にゾルゲたちに指令を出していたのですが、途中でソ連からの資金が止まってしまう。そうなると、ゾルゲのスパイグループのなかで通信を担当していたクラウゼンが、かなりいい加減になってくる。お金がとまった瞬間で、スパイとしての関係は終わりなんです。ですから、私はゾルゲはスパイとして、あくまでドイツがメインでロシアはサブだった、と見ているんです。
その先ですけれども、ゾルゲ事件による最大の効果は、日独離反でした。結果から見るならば、これはイギリスの利益に適っていた。ドイツの戦闘機メッサーシュミットや日本の大型潜水艦など、お互いの軍事技術を共有するために提携するようになるのは、昭和十九年になってからです。
手嶋 最新兵器だったV2ロケットや、当時ドイツが研究していた核開発の技術も、日本には入ってこなかったですね。
佐藤 そうですね。日本も持っているデータを出せばよかったんだけれども、結局、当時の日本のカウンターインテリジェンスは、ドイツを友好国と見なしていないんです。在東京のドイツ大使館員はもちろん、ドイツの特派員たちも監視されていた。タス通信のソ連人記者の方が、よほど自由に動けるぐらいだった。
そんな中で、ゾルゲには資金だけではなく、ソースとなるような情報も十二分にドイツ大使館から与えられていた。もし、彼が自前のネットワークだけに頼っていたら、あれだけの活動はできなかったでしょうね。
それでは、日本側は何でゾルゲと接触していたかというと、これはゾルゲの手記にも出てくるのですが、彼を通じてドイツの情報が欲しかったんですね。要するに、当時の日本とドイツはお互いに疑心暗鬼だったというわけです。
スパイの本質とは
手嶋 なるほど。最後に、もう少し『自壊する帝国』の感想を申し上げますと、この作品では、佐藤さんの道案内でソ連邦が崩壊していくプロセスを追っていくわけですが、佐藤さんはロシア人たちから「ミーシャ」という愛称で呼ばれて、共産党官僚や学者、ジャーナリスト、宗教関係者、反体制的な活動家など様々なネットワークに、スーッと溶け込んでいく。そういうミーシャの姿には、まさにゾルゲの活躍を彷彿とさせるものがありました。
読者は、そういう、卓越したインテリジェンスオフィサーの視線で歴史的大事件の顛末を目撃することで、彼の経験をまさに追体験するわけです。時にミーシャこと佐藤さんは、インテリジェンスの対象であるソ連ではなく、日本の外務省内の軋轢や矛盾と戦わなければならない。僕も官僚組織や大組織が嫌いなので、その点は実に痛ましい気がしました。ただ、それもリアリティーなので、読者はミーシャとともに、そのフラストレーションを味わっていただきたい。
それから、究極のところで言うと、インテリジェンスオフィサーというのは、常に本質的に二重スパイであると僕は考えています。『ウルトラ・ダラー』のなかにも、まさにそういう人物が出てくるのですが、これはインテリジェンスの世界の「公理」だと言えるでしょう。
果たして、佐藤ラスプーチン、ミーシャはダブルエージェント、トリプルエージェントたり得るのか、読者にはこの作品から是非そういう部分も読み取ってほしいと思います。
佐藤 私や手嶋さんを含め、どこかとらえどころのないというのが、インテリジェンスの雰囲気を醸し出すのにちょうどよいのでしょう。とても、おもしろいアドバイスをいただき、ありがとうございます。
(てしま・りゅういち ジャーナリスト)
(さとう・まさる 起訴休職外務事務官)
http://book.shinchosha.co.jp/shinkan/nami/shoseki/475202-9.html
経済大国に求められる「情報力」とは
佐藤 優『自壊する帝国』
手嶋龍一×佐藤 優
--------------------------------------------------------------------------
不気味なほどの共通点
佐藤 ニュースソースの秘匿や守秘義務など様々な制約がある情報(インテリジェンス)の世界を描くには、「ノンフィクション的な小説」と「小説的なノンフィクション」という二つのアプローチの方法があると私は考えています。手嶋さんは前者の手法で『ウルトラ・ダラー』(新潮社刊)をお書きになり、私は後者の手法を取りました。
手嶋 情報源の秘匿、これが問題の核心です。それには確かに、二つの道があると思います。しかしながら、この二つの方法論は意外に近い。そして双方が交錯するところにインテリジェンスの実像が浮かびあがってくる。そういう意味で『自壊する帝国』(新潮社刊)は味わい深い作品でした。
佐藤 なるほど。
手嶋 僕は佐藤優さんという書き手は戦後日本を代表するインテリジェンスオフィサーだと思っているのですが――。
佐藤 それは違いますよ。私はインテリジェンスに関する知識を、少しだけ持った外交官に過ぎません。
手嶋 ご自分では否定されるかもしれません。だからこそ、インテリジェンスオフィサーなのです。希代の情報士官が生まれるまでの過程で何があったのか、これまで佐藤さんについて誤り伝えられていたこともいくつか発見して、ラスプーチン伝説を訂正することができたので、ひじょうに面白く一気に読ませていただきました。
佐藤 ありがとうございます。
手嶋 それで、やや愕然とすることがありました。それは僕はこれまで佐藤さんとは全然似てないと言い募ってきたのですが、この本を読んで、不気味なほど共通点があるということに思い至ったんです。
佐藤 たとえば、どんなところでしょう。
手嶋 佐藤さんは外務省、僕は公共放送とお互い巨大組織にいた。僕は明らかに極端なマイノリティだったのですが、佐藤さんも、マジョリティではないですよね。
佐藤 それはもう明白です。マイノリティの中のマイノリティですよ。
手嶋 それからもうひとつ、佐藤さんは神学というひじょうに奥深い学問を勉強されたという点です。実は僕にはほとんどお師匠さんがいないのですが、あえて挙げさせていただければ、ハーバード大学のブライアン・ヘア教授という方がいます。
カトリックの聖職者で神学部の教授なのですが、一九八○年代、第二次冷戦の頂点といわれた頃に、カトリック教会が来たるべき核戦争に倫理的にも政治的にもどう対応すべきかという事態に直面し、バチカンの見解の筆を執ったのが、「黒衣の国際政治学者」といわれたこの人です。僕は一九九四年にハーバード大学にフェローとして招聘されていたときに、このヘア教授の指導を受けました。
佐藤 そうでしたか。本にも書いたことですが、私はフロマートカというチェコの神学者のことを研究していたことがきっかけとなって、外交の道に入ったんです。
情報の地下水脈へ
手嶋 もう一つだけ共通点を挙げると、本の中にサーシャというとても面白い人物が出てきますね。
佐藤 はい。モスクワ大学で知り合った沿バルト三国の、ラトビア出身の学生です。
手嶋 このサーシャとの出会いが、インテリジェンスオフィサー佐藤優を生むきっかけになったのですね。ここでは、あえてスティーブン・ブラッドレーと申し上げておきますが、僕の場合は東京におけるスティーブンとの出会いが、ひとつの重要なきっかけとなりました。スティーブンに頼まれて、イギリス大使を助けたことがあったんです。その大使は東アジアの外交や安全保障のプロフェッショナルでした。
佐藤 そうそう。イギリス大使には極めて興味深い人がよくいます。
手嶋 ところが、駐日英国大使としては、イギリスのウイスキーに対する関税障壁の問題にも取り組まなければならず、ひじょうに苦労していた。それで、僕が日本政府の税制調査会の攻略に一肌脱いだのです。答申の起草委員のひとりと親しくしていたからです。
その結果、イギリスにとって長年懸案となっていたこの問題で突破口が開けたのでした。それを大使がひじょうに感謝していたとスティーブン経由で聞きました。あの男にはいつの日か借りを返すと言っていたというのですが、そんなことはすぐに忘れてしまいました。
その後、ワシントンに赴任することになって、覚悟はしていたのですが最初の頃は、まったく手も足も出なくて苦労しました。そんなある日、佐藤さんの作品でサーシャに当たるような人物から、突然電話がかかってきた。アクセントから明らかにイギリス人でした。出てこいと言うから会ってみました。向こうはどういう筋に頼まれたなどとは、もちろん何も言いません。だけれども「ああ、そうか」とひざを打ちました。
それは金鉱脈でした。そこから一挙に地下水脈に入っていくことができた。もちろん、ジャーナリストと外交官は違うのでしょうが、同じことが佐藤さんにあったのだと、この本を読んでよく分かりました。ああ、やっぱりラスプーチンにもこんな出会いがあったのかと、ここは感動を持って読ませていただきました。
佐藤 でも、基本的に不思議なもので、このインテリジェンスの核というのは似ているんですね。インテリジェンスは文化で各国別々のものであるということと同時に、インテリジェンス業界自体の文化というものがある。
私も外務省のなかの派閥的なめぐり合わせとか、おつき合いしていた政治家の流れとかで、もちろんこれまでも手嶋さんと重なる部分があり、ときには対立することもありました。そういうなかで私は手嶋さんのことを、優れたジャーナリストであるだけではなく、無視できないプレーヤーの一人だと以前から認識していました。
しかし、『ウルトラ・ダラー』を読み、そしてその後お話をして、少しおつき合いをさせていただいてすぐにわかったのは、この人はほんとうのプロだということです。どうしてかといったら約束は絶対に守る。それと同時に軽々に約束はしない。約束をできないことを約束しない。それが、インテリジェンスというゲームの基本的なルールなんです。日本人はこれを失敗してしまうんです。約束できないことを約束してしまうんですね。
また先ほどのお話では、ワシントンに行ってアプローチしてきたときの人間関係のつくり方がキーですよね。必要のないこと、つまりここより踏み込んで知らないほうがいいことがある。それについてはあえて聞かない。それがインテリジェンスの文化なんです。
手嶋 まったくその通りですね。
『ウルトラ・ダラー』のインパクト
佐藤 ここ数年、私が危惧していたのは、現在の日本では、特に対外インテリジェンスに関して、ほとんど体を為していないような状況に陥ってしまっているということでした。しかし、手嶋さんが登場したことによって、本格的な日本のインテリジェンスの伝統を回復すると同時に、現代イギリス流のインテリジェンスの基礎が、あと五年ぐらいでできるのではないかと思うんです。
その意味で『ウルトラ・ダラー』という作品は、日本にとってインテリジェンスというのはどういうものなのかという大枠を小説という形で提示した上で、その内在論理まできちんと描いた初めての作品だと言えるでしょう。ですから、手嶋さんの提言をここからどうやって活かしていくのかというのは、今後、日本の政府にとって非常に重要なことだと思うんです。
手嶋 同感です。確かに日本には真のインテリジェンスオフィサーが、佐藤優さんのように突然変異的に生まれる以外には、ほとんど出てこないだろうし、そもそも、育てる組織もない。警察にはインテリジェンスに関して組織的にも手法としてもかなりの蓄積はありますが、それはあくまでカウンターインテリジェンス(対敵情報活動)で、対外インテリジェンスとは別のものですからね。
佐藤 本当に警察の能力は高いです。
手嶋 そうですね。
佐藤 しかし、状況によってはカウンターインテリジェンスの文化が対外インテリジェンスのブレーキになる。自発的、積極的に動くというのは潜在的にスパイということになってしまうんです。徹底的に警戒して何もしないのが一番いいということになると、対外インテリジェンスはできないですね。結局、対外インテリジェンスとカウンターインテリジェンスは文化が違うから、切り離さざるを得ない。一緒に動くと必ず軋轢が生じるんです。両者のバランスを為政者がうまくとることが大切です。
手嶋 たしかに、幾つかの問題点を抱えています。ただ、絶望の唄を歌うのはまだ早い。
佐藤 国家は生き残らなければなりません。そのためにはインテリジェンスは不可欠な要素となります。
手嶋 その通りです。世界第二の経済大国である日本は必然的に潜在的にはインテリジェンス大国たり得る――。これは佐藤優さんの立論ですが、僕もなるほどと思います。もちろん、実際にはイギリスやアメリカ、ロシア、イスラエルなどインテリジェンス大国との間には、まだまだ大きな溝があるけれども、諦めてはいけないというのが、佐藤さんの新作の隠されたメッセージではないでしょうか。
佐藤 そこまで読み込んでいただいて、ありがとうございます。
手嶋 僕も外交ジャーナリストの端くれですので、八○年代の終わり頃から、モスクワに佐藤ありと注目していました。それ以来、ずっと佐藤さんのことは気になっていたのです。情報を追いかけていくというのは、獣道を辿って山に分け入って行くようなものです。僕は主としてワシントンから、佐藤さんはモスクワを基盤にして、獣道に分け入っていく。そうすると、思いがけず遭遇したりするわけです。獣道だから暗くて見えない。ところが、頬にちょっと手が触れたように感じる――。
佐藤 すれ違ったりとか。
手嶋 暗いところで、大きな目が僕を見ている。目を凝らすと、そこにラスプーチンという人の姿を見つける。不気味ですよね。
佐藤 こっちも逆に、何回か手嶋さんの歌舞伎役者のような流し目を見たような気がします。テルアビブから成田に帰って来たときに、すっと背中に手嶋さんの視線を感じるとか、そういったことがありましたから。ただ、お互いどこで遭遇したなんて話をしないのが、この世界の文化ですよね(笑)。
手嶋 そうですね。普通はこんな話はしませんが、今日は読者へのサービスということで。
ゾルゲVS.ラスプーチン
手嶋 『自壊する帝国』の著者にひとつ伺いたいのですが、かつて、東京を舞台にした伝説のインテリジェンスオフィサー、リヒャルト・ゾルゲという人がいました。そのゾルゲと佐藤ラスプーチンを比較した人がいるんです。一説によると、僕だということになっているけれども(笑)。
佐藤ラスプーチンに比べると、ゾルゲにはより多くのハンディがあったという指摘です。当時、ゾルゲはクレムリンの中枢や赤軍の中枢部から、何一つ情報をもらっていない。一方、佐藤さんは、もちろん自分でも足で歩いて圧倒的な情報を獲得したのですが、世界第二位の経済大国に流れ込んでくる情報の存在があった。かなりの情報力の恩恵も受けている。だから、ゾルゲよりずっと恵まれていた。こうした批判にどのようにこたえますか。
佐藤 その比較をした方は、リヒャルト・ゾルゲの実像を深くご存じないのかもしれませんね(笑)。ゾルゲは、赤軍本部からは情報をもらっていないですが、実はあるところに蓄積されていた大量の秘密情報にアクセスできた。だから、私が現役の外交官だった頃と同じくらい、情報には恵まれていたんです。
手嶋 そのあるところというのは、ナチス・ドイツですね。
佐藤 その通り、ベルリンからです。要するにインテリジェンスの世界でリヒャルト・ゾルゲをどこのスパイと見るかというと、ソ連とドイツの二重スパイということになる。さらに、国際スタンダードで冷静に見た場合には、ドイツにプライオリティがある。
どうしてかというと、インテリジェンスの世界は二つの要素でできているんです。まず、誰が指令を出して、誰に報告するかです。二番目の要素は、だれがお金を払うかということ。指令を出していたのは駐日ドイツ大使館のオットー大使で、ゾルゲはそれに一○○%こたえています。それから、ドイツ大使館からお金も受け取っている。
手嶋 奥さんは、ロシア系ですよね。
佐藤 ゾルゲのモスクワに残した奥さんはロシア人ですが、他にも何人か奥さんたちがいました。情報を統括する赤軍第四本部は常にゾルゲたちに指令を出していたのですが、途中でソ連からの資金が止まってしまう。そうなると、ゾルゲのスパイグループのなかで通信を担当していたクラウゼンが、かなりいい加減になってくる。お金がとまった瞬間で、スパイとしての関係は終わりなんです。ですから、私はゾルゲはスパイとして、あくまでドイツがメインでロシアはサブだった、と見ているんです。
その先ですけれども、ゾルゲ事件による最大の効果は、日独離反でした。結果から見るならば、これはイギリスの利益に適っていた。ドイツの戦闘機メッサーシュミットや日本の大型潜水艦など、お互いの軍事技術を共有するために提携するようになるのは、昭和十九年になってからです。
手嶋 最新兵器だったV2ロケットや、当時ドイツが研究していた核開発の技術も、日本には入ってこなかったですね。
佐藤 そうですね。日本も持っているデータを出せばよかったんだけれども、結局、当時の日本のカウンターインテリジェンスは、ドイツを友好国と見なしていないんです。在東京のドイツ大使館員はもちろん、ドイツの特派員たちも監視されていた。タス通信のソ連人記者の方が、よほど自由に動けるぐらいだった。
そんな中で、ゾルゲには資金だけではなく、ソースとなるような情報も十二分にドイツ大使館から与えられていた。もし、彼が自前のネットワークだけに頼っていたら、あれだけの活動はできなかったでしょうね。
それでは、日本側は何でゾルゲと接触していたかというと、これはゾルゲの手記にも出てくるのですが、彼を通じてドイツの情報が欲しかったんですね。要するに、当時の日本とドイツはお互いに疑心暗鬼だったというわけです。
スパイの本質とは
手嶋 なるほど。最後に、もう少し『自壊する帝国』の感想を申し上げますと、この作品では、佐藤さんの道案内でソ連邦が崩壊していくプロセスを追っていくわけですが、佐藤さんはロシア人たちから「ミーシャ」という愛称で呼ばれて、共産党官僚や学者、ジャーナリスト、宗教関係者、反体制的な活動家など様々なネットワークに、スーッと溶け込んでいく。そういうミーシャの姿には、まさにゾルゲの活躍を彷彿とさせるものがありました。
読者は、そういう、卓越したインテリジェンスオフィサーの視線で歴史的大事件の顛末を目撃することで、彼の経験をまさに追体験するわけです。時にミーシャこと佐藤さんは、インテリジェンスの対象であるソ連ではなく、日本の外務省内の軋轢や矛盾と戦わなければならない。僕も官僚組織や大組織が嫌いなので、その点は実に痛ましい気がしました。ただ、それもリアリティーなので、読者はミーシャとともに、そのフラストレーションを味わっていただきたい。
それから、究極のところで言うと、インテリジェンスオフィサーというのは、常に本質的に二重スパイであると僕は考えています。『ウルトラ・ダラー』のなかにも、まさにそういう人物が出てくるのですが、これはインテリジェンスの世界の「公理」だと言えるでしょう。
果たして、佐藤ラスプーチン、ミーシャはダブルエージェント、トリプルエージェントたり得るのか、読者にはこの作品から是非そういう部分も読み取ってほしいと思います。
佐藤 私や手嶋さんを含め、どこかとらえどころのないというのが、インテリジェンスの雰囲気を醸し出すのにちょうどよいのでしょう。とても、おもしろいアドバイスをいただき、ありがとうございます。
(てしま・りゅういち ジャーナリスト)
(さとう・まさる 起訴休職外務事務官)
http://book.shinchosha.co.jp/shinkan/nami/shoseki/475202-9.html