 採点類に忙殺されている間に古くなってしまったかもしれない話題について、まとまってないのですが、とりあえず書き留めておくことに。
採点類に忙殺されている間に古くなってしまったかもしれない話題について、まとまってないのですが、とりあえず書き留めておくことに。岩波書店が「コネ」を応募条件にしたという話題が駆け巡りました。当該応募条件は、「岩波書店著者の紹介状あるいは岩波書店社員の紹介があること」というものです。私は、これが「コネ」とレッテルを貼られてかなり批判されたということが気にかかりました。
たしかに「親の伝手」とか「役員の口利き」だと、世代間での不平等の再生産が行われていたり、明らかな機会の不平等が生じていたりすると言えるかもしれません。しかし、ここでは、紹介状のもらい先が著者まで広がっています。学術出版という特性を考えた場合、自分が入りたい出版社でよく仕事をしている著者とすでにコネクションがあること、大学や講演会という場を利用して積極的にコネクションをつくる力は、肯定されるべき「職能」と見ることはできないでしょうか。
昨今、「コミュニケーション能力」や「社会関係資本」がもてはやされ、それらや専門技能を早くから身につけさせるような「キャリア教育」が推奨されています。それと比べたとき、それを早くから見につけた証と見ることも可能な、「職業上必要な人脈」があることが、「コネ」として反発されるということは矛盾しているようにも見えます。
もちろん、企業の本当の意図はわかりませんし、中途はまだしも新卒の一介の学生が紹介状を書いてもらうということのハードルの高さを考えれば、やはり相当絞り込んできたという印象はあります。しかし、報道に接して私がとっさに気になったのは、企業の真の意図がどうだったかではなく、これはコネなのかコネでないのかを同定することでもなく、世論が(厚労省も)「これはコネではないか」と強く反応したということ、そして、それと「キャリア教育」などの論調の関係です。
今回の「コネ批判」を「学歴社会批判」と重ね合わせても、どうやら私たちの社会は、規範として、ある段階の選抜において前の段階で手に入れた既得権益がちょっとでも紛れ込むことを不平等だと感じるようです。それが当人の努力の結果(業績)だろうと恵まれた生まれや環境(属性)によるものだろうとそんなことはどっちでもよいのです。(著者に知り合いがいることは、恵まれた生まれによって人脈に恵まれたからかもしれませんし、努力によって人脈をつくりやすい大学に入ったからかもしれませんし、全くの努力で知り合いを広げていったからかもしれません。)
一方で、近年さかんに主張される「キャリア教育」をしようというムードや、「就職力」キャンペーンは、むしろ教育と職業世界をより密につなごうという試みです。職業世界で要求されるものと何ら関係ない学歴で選抜するよりも、そのほうが望ましいと思われているわけです。つまり、教育と職業世界をつなごうとする議論と、(教育に限らず職業世界以前の条件は何でも)切り離そうという議論が同時に主張されていることになります。
とはいえ、これは必ずしも矛盾しているわけではありません。教育の社会的機能は「社会化」と「配分・選抜」であるというのが教育社会学のベーシックな議論ですが、それを踏まえると、現代ではどうも、学校は職業的社会化をしてほしいが、職業的な選抜自体は「無知のベール」をかけて企業が独自にやってほしいという、教育と職業世界の関係性に関する理想像が広まっていると整理できそうです。
それはある種公正な社会とも言えますが、教育現場はなんでもかんでも期待され、企業は企業で高コストの選抜を行わねばならないということも意味します。学歴主義に基づく選抜と新卒一括採用・終身雇用というしくみは、1つの負担回避の形だったわけですが、90年代後半以降それが大きく変わってきています。すでに多くの専門家が指摘しているように、昨今、就職市場が変化し、多くの学生と企業が、リクナビやマイナビなどのかなりオープンな就職市場で、双方多大な負担を追いながらマッチングを行わなくてはならなくなってきています。今回の世論の反応は、この実態と相互に影響し合いながら、教育と職業のつながれ方に関する「職業的社会化はしてほしい、選抜は無知のベールで」という理想論が、従来より強い力を持つようになったということも示唆しているような気がしました。
岩波の出した条件の当初の目的(あくまで公称)は、少数の採用枠に多数の応募者が殺到する事態を避け、採用活動の負担を軽減するためだったようです。それは実態に対する1つのアプローチであり、それはそれで合理的だと思います。もちろん、世論の趨勢を読み違った感は否めないでしょう。ただ、実際のところどういう選抜方式が「まし」かは、まだまだ議論の余地があると思います。














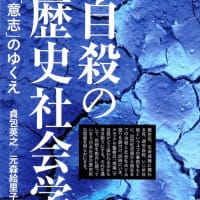






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます