ちなみに、ちょっと前の話に戻りますが、
1回休講にしてしまった補講に、参加できない人も多いのでと、
「クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲」(2001)
を見ました。(あらすじ@wikipediaはこちら)
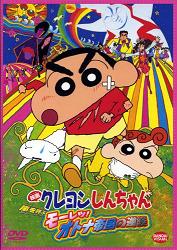
クレヨンしんちゃん自体、教育的子ども観ではないのだけど、
どこかオーソドックスな子ども像・家族像を再生産している面もあり
(だから見せたくないアニメに選ばれつつ教科書に載る)
すごく90年代的なマンガ・アニメだなあと思っているのですが、
映画の、大人=ノスタルジー/子ども=「オラ大人になりたい」という構図は、
大人をやるのが大変な時代・それでも子どもに期待し続ける時代の
ムードを反映しており、授業のテーマとも合うかなと。
(個人的には、シリアスすぎてクレしんである意味が曖昧になった
「戦国大合戦」よりも、好きです。いやアニメ好きでもないので、
クレしん自体全部見たわけでもなんでもないのですが。)
今回、大学生と見て面白かったのは、その反応でした。
私は、まず、「ダメダメのうた」が始まった瞬間「なつかし~~~!!」
という歓声が上がったことにびっくりし(ノスタルジーの対象なんだ!)、
はじめは「一応授業だし、しんちゃんごときに笑ってはいけない」という
固い表情で見ていた大学生が、途中からゲラゲラ笑うようになるのを
見守っておりました。
リアペにはさすが社会学科という分析も多くありました。
・未来に希望が持てない「大人」と未来に前向きな「子ども」と
正反対に描かれている
・親が子ども返りしたらしんちゃんがしっかりしていた
「子ども」は「大人」が保護してくれないとしっかりする
・「ダメダメのうた」からして考察対象になるのではないか
・「このままじゃママがママじゃなくなっちゃう気がする」「ごはんつくれ」など
「子ども」も「大人」に役割を押し付けていることが見えた
・「大人らしさ」と「子どもらしさ」を対照的に描いているのが面白かった
「子ども」は好きなことができて義務も少ないが大人がいなくなると不便
/「大人」は仕事や家事に追われているがやりがいがある
・「子ども」が未来を目指すためには「大人」の手助けがいるということも
描いていると思う
・早くから塾や就活に追い立てられる世代になると、
「過去・子どもの頃に戻りたい」という感覚も無くなるのではないか
・高校生(紅さそり団)も「大人」に入っていて、
「大人」と「子ども」に二極化されて描かれている
などなど(すべて要約)。
しかし、何より、ちょうどしんちゃんを見て育った世代で、
この映画も「子ども」として見ていた人も多いので、
最初からウォッチするつもりで見てしまっていた私には
書けないような感想をいただいたのがおもしろかったです。
・小学生の頃はゲラゲラ笑っていたシーンがシュールに見えた
・小さいとき嫌だと思っていたしんちゃんの下ネタが可愛く感じた
・しんちゃんを見てはいけないと言っていた親に見せてやりたい
・不況の中就活の時期を迎え、「昔に戻りたい」という感覚が
なんだか少しわかった気がする
・平成生まれなのに、昭和のテーマパークに懐かしさを感じるのが
不思議
・映画を見ていて子どもの頃に戻った。それが大人が子ども返りする
話と重なって楽しかった
・昔と全然違って見えた。大人になってもみんな子どもの気持ちを
持っているのだと実感しながら見た
・単純に笑えた自分に、20代になっても子ども心を忘れてないと、安心した
などなど(同じく要約)。
自分は「大人」なんだろうか?でもどうも「子ども」の頃と感覚が違うぞ!
というお年頃の方々のこれらの感想が、どういう意味を持つのか、
まだ私にもよくわからないのですが。
加齢に伴う諸々の感情を伴った過去の想起を、子ども/大人という図式で
解釈させてしまう映画であり授業であり時代であるということに
回収していいのかな?安直か??


1回休講にしてしまった補講に、参加できない人も多いのでと、
「クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲」(2001)
を見ました。(あらすじ@wikipediaはこちら)
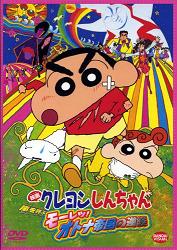
クレヨンしんちゃん自体、教育的子ども観ではないのだけど、
どこかオーソドックスな子ども像・家族像を再生産している面もあり
(だから見せたくないアニメに選ばれつつ教科書に載る)
すごく90年代的なマンガ・アニメだなあと思っているのですが、
映画の、大人=ノスタルジー/子ども=「オラ大人になりたい」という構図は、
大人をやるのが大変な時代・それでも子どもに期待し続ける時代の
ムードを反映しており、授業のテーマとも合うかなと。
(個人的には、シリアスすぎてクレしんである意味が曖昧になった
「戦国大合戦」よりも、好きです。いやアニメ好きでもないので、
クレしん自体全部見たわけでもなんでもないのですが。)
今回、大学生と見て面白かったのは、その反応でした。
私は、まず、「ダメダメのうた」が始まった瞬間「なつかし~~~!!」
という歓声が上がったことにびっくりし(ノスタルジーの対象なんだ!)、
はじめは「一応授業だし、しんちゃんごときに笑ってはいけない」という
固い表情で見ていた大学生が、途中からゲラゲラ笑うようになるのを
見守っておりました。
リアペにはさすが社会学科という分析も多くありました。
・未来に希望が持てない「大人」と未来に前向きな「子ども」と
正反対に描かれている
・親が子ども返りしたらしんちゃんがしっかりしていた
「子ども」は「大人」が保護してくれないとしっかりする
・「ダメダメのうた」からして考察対象になるのではないか
・「このままじゃママがママじゃなくなっちゃう気がする」「ごはんつくれ」など
「子ども」も「大人」に役割を押し付けていることが見えた
・「大人らしさ」と「子どもらしさ」を対照的に描いているのが面白かった
「子ども」は好きなことができて義務も少ないが大人がいなくなると不便
/「大人」は仕事や家事に追われているがやりがいがある
・「子ども」が未来を目指すためには「大人」の手助けがいるということも
描いていると思う
・早くから塾や就活に追い立てられる世代になると、
「過去・子どもの頃に戻りたい」という感覚も無くなるのではないか
・高校生(紅さそり団)も「大人」に入っていて、
「大人」と「子ども」に二極化されて描かれている
などなど(すべて要約)。
しかし、何より、ちょうどしんちゃんを見て育った世代で、
この映画も「子ども」として見ていた人も多いので、
最初からウォッチするつもりで見てしまっていた私には
書けないような感想をいただいたのがおもしろかったです。
・小学生の頃はゲラゲラ笑っていたシーンがシュールに見えた
・小さいとき嫌だと思っていたしんちゃんの下ネタが可愛く感じた
・しんちゃんを見てはいけないと言っていた親に見せてやりたい
・不況の中就活の時期を迎え、「昔に戻りたい」という感覚が
なんだか少しわかった気がする
・平成生まれなのに、昭和のテーマパークに懐かしさを感じるのが
不思議
・映画を見ていて子どもの頃に戻った。それが大人が子ども返りする
話と重なって楽しかった
・昔と全然違って見えた。大人になってもみんな子どもの気持ちを
持っているのだと実感しながら見た
・単純に笑えた自分に、20代になっても子ども心を忘れてないと、安心した
などなど(同じく要約)。
自分は「大人」なんだろうか?でもどうも「子ども」の頃と感覚が違うぞ!
というお年頃の方々のこれらの感想が、どういう意味を持つのか、
まだ私にもよくわからないのですが。
加齢に伴う諸々の感情を伴った過去の想起を、子ども/大人という図式で
解釈させてしまう映画であり授業であり時代であるということに
回収していいのかな?安直か??











