6月11日の午前中は福島大学の中里見先生に誘われて、市内で行われた除染実験を見学させていただいた。中里見さんらは福島大学の教員有志で福島大学原発災害支援フォーラム (FGF)http://fukugenken.e-contents.biz/をたちあげて、放射能汚染に関するとてもよい情報発信や提言をされている。
ただ、文系の教員が多く、放射能についての専門知識があるわけではない。それで中里見さんらはエントロピー学会の場で支援を求めた。それに応じたのが京都精華大学の山田國廣先生らのグループである。
山田氏らは福島市内の詳細な放射線量測定によって「マイクロ・ホットスポット」と呼ぶべき局所的にきわめて高濃度な放射能が蓄積している場所があることを発見した。屋根や駐車場に降下した放射性物質を雨が洗い流した際に、土壌と接するところで、放射性セシウムが吸着濃集しているのである。雨樋から水が流れ出すところ、雨樋がなく屋根から滴が落ちてくるところ、駐車場のわきの草むら、公園の滑り台の下などである。
そういう場所では放射性物質を取り除く除染作業が必要である。県や市にかけあってもまったく動いてくれないため、山田氏らは市民が自前で行える除染作業の方法を開発することが必要と考えた。それで、「剥ぎ取り法」とでも言うべき方法を考案して、この日はじめて実地試験を行うことになっていた。
除染対象となった福島市内の家電量販店の駐車場に到着。さっそく放射線量を測ってみると、たしかに駐車場が側溝に接するところに帯状にある草むらの線量が高い。駐車場の真ん中が1.5マイクロシーベルト/時程度に対して、草むらの周囲では3~6マイクロシーベルト/時程度である。側溝にそって道路があるが、これは小学校の通学路になっている。子どもたちはここを通るたびに余分な被曝をすることになる。
草むらの中で特に線量の高いところを探して、草の上に検出器を直接置いてみた。そうすると数値は88マイクロシーベルト/時を記録した。私が持参した放射線カウンタは針で表示されるメータとデジタル数値の両方の表示があるが、メータの方は最高30マイクロシーベルト/時までしか目盛りがないので振り切れてしまった。もちろん私が今までに見たことのない高い線量率である。私たちはみな上下雨合羽に帽子、マスク、ゴム手袋、長靴の完全装備である。
剥ぎ取り作業はまず草を根こそぎ刈るところからはじまる。次にアスファルトの上に堆積した土壌をスコップでていねいにとる。とったものはすべて土嚢袋に入れる。スコップで取り終えるとアスファルト表面にこびりついている土をさらに布テープで剥ぎ取る。ここまでで放射線量は劇的に下がる。しかし、まだ通常レベルではない。
次はアスファルトのでこぼこの隙間に土とそれに吸着した放射性セシウムがあるので、これをとるために、洗濯用の化学合成のりであるPVA(ホームセンター等で入手可能)をアスファルトの表面に流し、はけで薄くならしていく。その上に不織布(100円ショップで売っている)をかけてさらにはけで押しつける。これでよく乾くまで待つ。そうするとPVAの膜ができて、これを剥ぐことによって、でこぼこの底に溜まっている土まできれいに剥ぎ取ることができるというわけだ。
アスファルトではない土の地面を除染するには、草を刈ったあと、PVAを厚めに流して表面をたたいて浸透させる。それで乾いたところでスコップで剥ぎ取ると、放射性セシウムを含んだ部分はかちかちに固まっているので、飛散することなく回収できるという。
剥ぎ取ったものはすべて土嚢袋に入れて、そこにもPVAを流し込んで袋の上から押さえつける。そうすると水分はにじみ出て体積が減少する。さらに乾けばかちかちになり、埃などを飛散させずに保管することができる。
しばらくは現地で安全な場所に保管する。人が近づかないところに穴を掘って埋めておくなど。そして、最終的には東電に引き取ってもらわなければならない。福島第一原発が「石棺」に閉じこめらる時にいっしょに放り込むということだろうか。
皆さんが作業をしているようすは地元のテレビ局がつきっきりで取材していた。レポーターも個人線量計をポケットに入れている。近所の住民が様子を見にきて取材に応じていた。男性は高校の教員とのこと。放射能の危険性を理解していて、自分の子どもはすでに県外に避難(つまり転校)させている。でも、職場では生徒たちに放射能の危険性について話すことができずに悩んでいるという。福島県の公式的見解は100ミリシーベルト以下の低線量被曝では「何の影響も出ない」というものだからだ。「頭の中は放射能のことでいっぱいです。顔を出して取材に応じてよいのかどうか・・・でも発言しなければいけない時期かもしれません・・・」と苦しい胸の内を語っていた。
この方法の原則はそこにある放射性物質を飛散させたり流したりせず、すべて回収して固めるということにある。地面だけでなく塀や建物などどこにでも適用できる(ただし、垂直な部分ではPVAがたれてしまうので、あらかじめ鍋で煮詰めて粘性を上げておく)。どこでもすぐに手に入る材料で誰でもできる方法である。現時点はもっとも合理的な対応方法といえるだろう。
















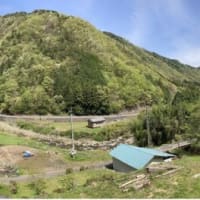


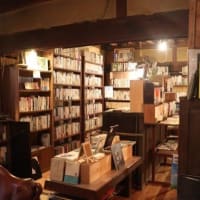
ところで、PVAを土壌に流し込む際は、どの程度薄めて使用されましたか。教えていただければ幸いです。
お手数をおかけ致しますが、よろしくお願いいたします。