今回は、「日本文化のユニークさ」というカテゴリー書くが、内容は前回アップした「マンガ・アニメの発信力の理由03」ともつながる。前回、最後に「宮崎アニメは、充分に意図的に、縄文・ケルト的な森の思想を表現している」と書いた。まず冒頭で、『となりのトトロ』にも、そして宮崎が影響を受けた『ミツバチのささやき [DVD] 』という二つの映画には、ヨーロッパならローマ帝国以前のケルト人の森の文化、日本なら縄文時代やそれ以前の文化への敬愛が底流に流れている。キリスト教や産業文明以前の、自然と人間が一体となった世界への敬愛。森や森の生き物に共感し、生き物と交流できたり、森から異界への入り込む森の人への共感。今回は、縄文文化と比較されるケルト文化に触れながら、日本文化のユニークさを考えてみたい。
』という二つの映画には、ヨーロッパならローマ帝国以前のケルト人の森の文化、日本なら縄文時代やそれ以前の文化への敬愛が底流に流れている。キリスト教や産業文明以前の、自然と人間が一体となった世界への敬愛。森や森の生き物に共感し、生き物と交流できたり、森から異界への入り込む森の人への共感。今回は、縄文文化と比較されるケルト文化に触れながら、日本文化のユニークさを考えてみたい。
世界中の産業文明の国々は、ヨーロッパがケルト文化をほとんど忘れ去ってしまったと同じように、「前農耕的な」時代の文化の精神的な遺産をほとんど残していない。(ケルト人は、牧畜・農耕を営んでいたが、都市は発達せず、森との共生の中に生きていた。)日本の縄文文化は、一部農耕を取り入れながらも、狩猟・漁労・採集中心の豊かな文化で、それが約1万5千年も続いた。しかもその精神的な遺産が、強力な統一国家やそれに伴う、強力な宗教などによって圧殺されずに、現代にまで日本人の精神の中に生き生きと生き続けている。そこに「日本文化のユニークさ」の基盤がある。世界がほとんど忘れ去ってしまった、文明の古層が、現代の日本人および日本文化の中に息づいているのだ。
以下、河合隼雄の『ケルト巡り』を取り上げて、考えてみたい。
◆『ケルト巡り 』(河合隼雄)
』(河合隼雄)
かつてケルト文化は、ヨーロッパからアジアにいたる広大な領域に広がっていた。しかしキリスト教の拡大に伴いそのほとんどが消え去ってしまった。ただオーストリア、スイス、アイルランドなど一部の地域にはその遺跡などがわずかに残っている。とくにアイルランドはケルト文化が他地域に比べて色濃く残る。ローマ帝国の拡大とともにイングランドまではキリスト教が届いたものの、アイルランドに到達したのは遅れたからだ。
この本は河合隼雄が、そのアイルランドにケルト文化の遺産を探して歩いた旅の報告がベースになっている。なぜ今、日本人にとってケルト文化なのか。それはケルト文化が、私たちの深層に横たわる縄文的心性と深く響き合うものがあるからだ。
私たちは、知らず知らずのうちにキリスト教が生み出した、西洋近代の文化を規範にして思考しているが、他面ではそういう規範や思考法では割り切れない日本的なものを基盤にして思考し、生活を営んでいる。一方、ヨーロッパの人々も、日本人よりははるかに自覚しにくいかもしれないが、その深層にケルト的なものをもっているはずだ。
ケルトでは、渦巻き状の文様がよく用いられるが、これはアナザーワールドへの入り口を意味する。そして渦巻きが、古代において大いなる母の子宮の象徴であったことは、ほぼ世界に共通する事実なのだ。それは、生み出すことと飲み込むことという母性の二面性をも表す。また生まれ死に、さらに生まれ死ぬという輪廻の渦でもある。アイルランドに母性を象徴する渦巻き文様が多く見られることは、ケルト文化が母性原理に裏打ちされていたことと無縁ではない。父性原理の宗教であるキリスト教が拡大する以前のヨーロッパには、母性原理の森の文明が広範囲に息づいていたのだ。
日本の縄文土偶の女神には、渦が描かれていることが多い。土偶そのものの存在が、縄文文化が母性原理に根ざしていたことを示唆する。アイルランドに残る昔話は、西洋の昔話は違うパターンのものが多く、むしろ日本の昔話との共通性が多いのに驚く。浦島太郎に類似するオシンの昔話などがそれだ。日本人は、縄文的な心性を色濃く残したまま、近代国家にいちはやく仲間入りした。それはかなり不思議なことでもあり、また重要な意味をもつかも知れない。ケルト文化と日本の古代文化を比較することは、多くの新しい発見をもたらすだろう。
いま、ヨーロッパの人々が、キリスト教を基盤とした近代文明の行きづまりを感じ、ケルト文化の中に自分たちがそのほとんどを失ってしまった、古い根っこを見出そうとしている。これは河合が言っていることではないが、日本のマンガ・アニメがこれだけ人気になるひとつの背景には、彼らがほとんど忘れかけてしまったキリスト教以前の森の文化を、どこかで思い出させる要素が隠されているからかも知れない。
世界中の産業文明の国々は、ヨーロッパがケルト文化をほとんど忘れ去ってしまったと同じように、「前農耕的な」時代の文化の精神的な遺産をほとんど残していない。(ケルト人は、牧畜・農耕を営んでいたが、都市は発達せず、森との共生の中に生きていた。)日本の縄文文化は、一部農耕を取り入れながらも、狩猟・漁労・採集中心の豊かな文化で、それが約1万5千年も続いた。しかもその精神的な遺産が、強力な統一国家やそれに伴う、強力な宗教などによって圧殺されずに、現代にまで日本人の精神の中に生き生きと生き続けている。そこに「日本文化のユニークさ」の基盤がある。世界がほとんど忘れ去ってしまった、文明の古層が、現代の日本人および日本文化の中に息づいているのだ。
以下、河合隼雄の『ケルト巡り』を取り上げて、考えてみたい。
◆『ケルト巡り
かつてケルト文化は、ヨーロッパからアジアにいたる広大な領域に広がっていた。しかしキリスト教の拡大に伴いそのほとんどが消え去ってしまった。ただオーストリア、スイス、アイルランドなど一部の地域にはその遺跡などがわずかに残っている。とくにアイルランドはケルト文化が他地域に比べて色濃く残る。ローマ帝国の拡大とともにイングランドまではキリスト教が届いたものの、アイルランドに到達したのは遅れたからだ。
この本は河合隼雄が、そのアイルランドにケルト文化の遺産を探して歩いた旅の報告がベースになっている。なぜ今、日本人にとってケルト文化なのか。それはケルト文化が、私たちの深層に横たわる縄文的心性と深く響き合うものがあるからだ。
私たちは、知らず知らずのうちにキリスト教が生み出した、西洋近代の文化を規範にして思考しているが、他面ではそういう規範や思考法では割り切れない日本的なものを基盤にして思考し、生活を営んでいる。一方、ヨーロッパの人々も、日本人よりははるかに自覚しにくいかもしれないが、その深層にケルト的なものをもっているはずだ。
ケルトでは、渦巻き状の文様がよく用いられるが、これはアナザーワールドへの入り口を意味する。そして渦巻きが、古代において大いなる母の子宮の象徴であったことは、ほぼ世界に共通する事実なのだ。それは、生み出すことと飲み込むことという母性の二面性をも表す。また生まれ死に、さらに生まれ死ぬという輪廻の渦でもある。アイルランドに母性を象徴する渦巻き文様が多く見られることは、ケルト文化が母性原理に裏打ちされていたことと無縁ではない。父性原理の宗教であるキリスト教が拡大する以前のヨーロッパには、母性原理の森の文明が広範囲に息づいていたのだ。
日本の縄文土偶の女神には、渦が描かれていることが多い。土偶そのものの存在が、縄文文化が母性原理に根ざしていたことを示唆する。アイルランドに残る昔話は、西洋の昔話は違うパターンのものが多く、むしろ日本の昔話との共通性が多いのに驚く。浦島太郎に類似するオシンの昔話などがそれだ。日本人は、縄文的な心性を色濃く残したまま、近代国家にいちはやく仲間入りした。それはかなり不思議なことでもあり、また重要な意味をもつかも知れない。ケルト文化と日本の古代文化を比較することは、多くの新しい発見をもたらすだろう。
いま、ヨーロッパの人々が、キリスト教を基盤とした近代文明の行きづまりを感じ、ケルト文化の中に自分たちがそのほとんどを失ってしまった、古い根っこを見出そうとしている。これは河合が言っていることではないが、日本のマンガ・アニメがこれだけ人気になるひとつの背景には、彼らがほとんど忘れかけてしまったキリスト教以前の森の文化を、どこかで思い出させる要素が隠されているからかも知れない。











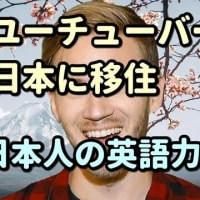



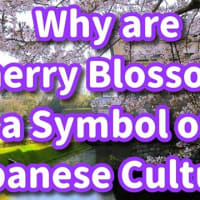
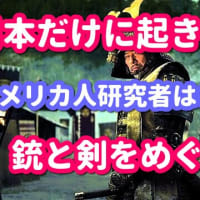

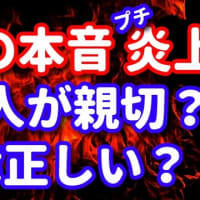







例、人を信じる事、
性悪説の西欧では、人を信じる事などナンセンスで子供じみた事なのですから、
性悪説の文化では、許容されないものが易々と表現されるのが、魅力だという視点、とても参考になりました。性悪説は、おそらく異民族同士の激しい戦いの中で養われたのではないかと思いました。