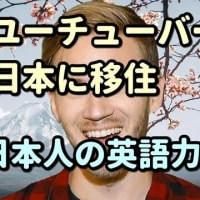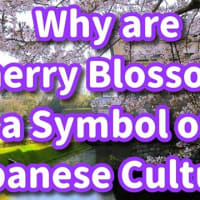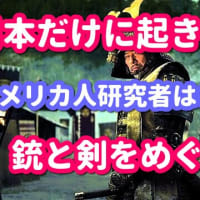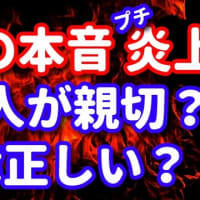日本の文化的・宗教的伝統はどちらかと言えば、父性的な性格よりも母性的な性格が強いのが特徴だ。このテーマについては、「日本文化のユニークさ8項目」のうち、「(2)ユーラシア大陸の父性的な性格の強い文化に対し、縄文時代から現代にいたるまで一貫して母性原理に根ざした社会と文化を存続させてきた」という項目として、様々な観点から論じてきた。
近代化とは、西欧の科学文明の背景にある一神教的な世界観を受け入れ、文化を全体として男性原理的なものに作り替えていくことだともいえる。近代文明を受け入れた国々では、男性原理的なシステムの下に、農耕文明以前の自然崇拝的な文化などはほとんど消え去っている。ところが日本文明だけは、近代化にいち早く成功しながら、その社会・文化の中に縄文以来の太古の層を濃厚に残しているように見える。つまり原初的な母性原理の文明が、現代の社会システムの中に色濃く生残っているのだ。
その事実を、心理学者の河合隼雄は、古事記や日本書紀を読み解きながら『神話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクションIII〉 (岩波現代文庫) 』で、古代日本人の心理として語り、また心理療法家の立場から『母性社会日本の病理 (講談社+α文庫)
』で、古代日本人の心理として語り、また心理療法家の立場から『母性社会日本の病理 (講談社+α文庫) 』で、現代日本人の心理として語っている。また土居健郎は、現代日本人の甘えの心理を『「甘え」の構造 [増補普及版]
』で、現代日本人の心理として語っている。また土居健郎は、現代日本人の甘えの心理を『「甘え」の構造 [増補普及版] 』の中で分析し、日本人論の名著として名高いが、甘えの心理に見られる日本人特有の人間関係のあり方も、きわめて母性原理的な性格を現しているといえよう。
』の中で分析し、日本人論の名著として名高いが、甘えの心理に見られる日本人特有の人間関係のあり方も、きわめて母性原理的な性格を現しているといえよう。
◆『切支丹時代―殉教と棄教の歴史 』(遠藤周作)
』(遠藤周作)
◆「日本人の宗教意識」(遠藤周作)(『英語で話す「日本の文化」 (講談社バイリンガル・ブックス) 』)
』)
今回取り上げるこの本は、いわゆる「かくれキリシタン」のキリスト教信仰の特徴に触れ、日本人の文化的・宗教的伝統の母性的な性格を描き出していて、きわめて興味深い。
作家・遠藤周作は、キリスト教への迫害が絶頂に達した頃のキリスト教に強い興味を示している。宣教師は日本を去り、教会も消え、日本人のごく一部がキリスト教をほそぼそと受け継いでいた時代である。宣教師がいないので、信者はキリスト教を自分たちに納得できるように噛み砕くが、それを是正するものはいない。日本人の宗教意識に合うように自由に変形されていくのだ。それがどのように変形されたのかに、遠藤周作の関心は集中したという。彼らが信じたものもはやキリスト教とは言えず、日本的に変形された彼らのキリスト教になっていた。仏教や神道の要素がごった煮のように混じり合い、キリスト教徒がふつうに信じるGODを本当に信じていたと言えるのか疑わしいと言うのだ。
しかも、彼らが役人の目をかくれていちばん信仰していたのは、GODでもキリストでもなく、実は聖母マリアであった。しかもそのイメージは、キリスト教の聖母マリアというよりも、彼らの母親のイメージが非常に濃かった。宗教画に見る聖母マリアというよりも、野良着を着た日本人のおっかさんのイメージであった。
言うまでもなくヨーロッパにおいてキリスト教は、母親の宗教というより父親の宗教という性格を強くもっていた。教えに外れるものを厳しく叱咤し、裁き、罰するイメージが強いのだ。それが日本では、いつのまにか母親の宗教に変わってしまう。もちろん聖母マリアは、カトリック信仰の中ではきわめて重い意味をもっているが、第一位ではない。その聖母マリアが、「かくれキリシタン」にとっては最重要の信仰の対象となってしまう。しかも日本のおっかさんのイメージに変形されてしまうのだ。父性原理の性格を強くもったキリスト教が、日本ではいつのまにか母性のイメージ中心の信仰に変わってしまう。日本文化の基底に、そうさせてしまう土壌があるからではないのか。
このような変化は、他の宗教での日本人の信仰の場合にも見られるという。たとえば、中国・朝鮮をへて日本に入ってきた仏教の場合も似たような変化が見られる。平安時代から室町時代には、仏教も日本人の歯で噛み砕かれ、次第に母性の宗教に変化していったというのだ。阿弥陀様を拝む日本人のこころには、子供が母親を想うこころの投影があるのではないか。
浄土真宗で「善人なをもて往生を遂ぐ、いわんや悪人をや」といのも、見方によっては悪い子ほど可愛いという母親心理を表していると言えなくもない。ともあれ阿弥陀様には色濃く母親のイメージが漂っている。仏教も日本に流入して日本人に信仰されるうちに、かなり母性的な性格を強くしていったと思われる。
キリスト教にも仏教にも共通に見られる、日本での変化、つまりより母性的な性格のつよい信仰への変化、これは日本人の宗教意識の大きな特徴を表していると言えるだろう。もちろん母親の宗教という面は、キリスト教の中にもある。日本人だけに特有なのではないが、しかし日本の宗教には、この母性的な性格がとくに強く見られるのではないかというのだ。
遠藤周作のこの指摘は、日本人の宗教意識についてのものだが、それは日本の文化や社会の底流に母性原理的なものが色濃くのこっているという捉え方を、一面から強く補強する指摘だろう。
近代化とは、西欧の科学文明の背景にある一神教的な世界観を受け入れ、文化を全体として男性原理的なものに作り替えていくことだともいえる。近代文明を受け入れた国々では、男性原理的なシステムの下に、農耕文明以前の自然崇拝的な文化などはほとんど消え去っている。ところが日本文明だけは、近代化にいち早く成功しながら、その社会・文化の中に縄文以来の太古の層を濃厚に残しているように見える。つまり原初的な母性原理の文明が、現代の社会システムの中に色濃く生残っているのだ。
その事実を、心理学者の河合隼雄は、古事記や日本書紀を読み解きながら『神話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクションIII〉 (岩波現代文庫)
◆『切支丹時代―殉教と棄教の歴史
◆「日本人の宗教意識」(遠藤周作)(『英語で話す「日本の文化」 (講談社バイリンガル・ブックス)
今回取り上げるこの本は、いわゆる「かくれキリシタン」のキリスト教信仰の特徴に触れ、日本人の文化的・宗教的伝統の母性的な性格を描き出していて、きわめて興味深い。
作家・遠藤周作は、キリスト教への迫害が絶頂に達した頃のキリスト教に強い興味を示している。宣教師は日本を去り、教会も消え、日本人のごく一部がキリスト教をほそぼそと受け継いでいた時代である。宣教師がいないので、信者はキリスト教を自分たちに納得できるように噛み砕くが、それを是正するものはいない。日本人の宗教意識に合うように自由に変形されていくのだ。それがどのように変形されたのかに、遠藤周作の関心は集中したという。彼らが信じたものもはやキリスト教とは言えず、日本的に変形された彼らのキリスト教になっていた。仏教や神道の要素がごった煮のように混じり合い、キリスト教徒がふつうに信じるGODを本当に信じていたと言えるのか疑わしいと言うのだ。
しかも、彼らが役人の目をかくれていちばん信仰していたのは、GODでもキリストでもなく、実は聖母マリアであった。しかもそのイメージは、キリスト教の聖母マリアというよりも、彼らの母親のイメージが非常に濃かった。宗教画に見る聖母マリアというよりも、野良着を着た日本人のおっかさんのイメージであった。
言うまでもなくヨーロッパにおいてキリスト教は、母親の宗教というより父親の宗教という性格を強くもっていた。教えに外れるものを厳しく叱咤し、裁き、罰するイメージが強いのだ。それが日本では、いつのまにか母親の宗教に変わってしまう。もちろん聖母マリアは、カトリック信仰の中ではきわめて重い意味をもっているが、第一位ではない。その聖母マリアが、「かくれキリシタン」にとっては最重要の信仰の対象となってしまう。しかも日本のおっかさんのイメージに変形されてしまうのだ。父性原理の性格を強くもったキリスト教が、日本ではいつのまにか母性のイメージ中心の信仰に変わってしまう。日本文化の基底に、そうさせてしまう土壌があるからではないのか。
このような変化は、他の宗教での日本人の信仰の場合にも見られるという。たとえば、中国・朝鮮をへて日本に入ってきた仏教の場合も似たような変化が見られる。平安時代から室町時代には、仏教も日本人の歯で噛み砕かれ、次第に母性の宗教に変化していったというのだ。阿弥陀様を拝む日本人のこころには、子供が母親を想うこころの投影があるのではないか。
浄土真宗で「善人なをもて往生を遂ぐ、いわんや悪人をや」といのも、見方によっては悪い子ほど可愛いという母親心理を表していると言えなくもない。ともあれ阿弥陀様には色濃く母親のイメージが漂っている。仏教も日本に流入して日本人に信仰されるうちに、かなり母性的な性格を強くしていったと思われる。
キリスト教にも仏教にも共通に見られる、日本での変化、つまりより母性的な性格のつよい信仰への変化、これは日本人の宗教意識の大きな特徴を表していると言えるだろう。もちろん母親の宗教という面は、キリスト教の中にもある。日本人だけに特有なのではないが、しかし日本の宗教には、この母性的な性格がとくに強く見られるのではないかというのだ。
遠藤周作のこの指摘は、日本人の宗教意識についてのものだが、それは日本の文化や社会の底流に母性原理的なものが色濃くのこっているという捉え方を、一面から強く補強する指摘だろう。