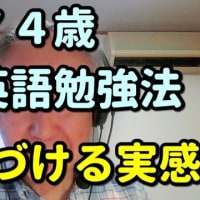《日本神話を読む》
現代人は「科学の知」に圧倒されて「神話の知」の獲得が難しい。現代人の生き方を支えてくれる神話はないのか。結局は各個人が自分の生活に関わりのある神話的な様相を見つけていくほかなく、解決は個人にまかされるのか。集団で神話を共有した時代は、神話による支えが集団として保証されたが、その代償として個人の自由が束縛された。今われわれは、各人にふさわしい「個人神話」を見出さねばならないのであろう。
生きることそのものが神話の探求であり、各人が自分にふさわしい個人神話を見出すことが生きることにつながると言うべきだろう。日本人としては、かつて人類がもった数々の神話、そしてとくに日本の神話を学ぶことは不可欠だろう。
日本の神話は、『古事記』(712)、『日本書紀』(720)によって現在に伝えられている。この時代に神話が記録されたのは、当時の日本が、外国との接触によって統一国家としての存在を示すとともに、その中心としての天皇家の存在を基礎づける必要に迫られていたからだ。
『神話と日本人の心 』の著者の河合隼雄は、日本神話を深層心理学の立場から研究する。つまり、人間にとって神話がいかに必要であり、それが人間の心に極めて深くかかわているか、という観点から、神話のなかに心の深層のあり方を探る。そこに日本人の心のあり方を探り、我々の生き方のヒントを得ようという立場だ。ユング派の分析家として日本人の心の深層にかかわる仕事を続けてきた経験から、日本神話の世界にひたりきることによって得たことを述べるというのである。このブログでは、この河合隼雄の著書を参考にしながら『古事記』を読んでいきたい。
』の著者の河合隼雄は、日本神話を深層心理学の立場から研究する。つまり、人間にとって神話がいかに必要であり、それが人間の心に極めて深くかかわているか、という観点から、神話のなかに心の深層のあり方を探る。そこに日本人の心のあり方を探り、我々の生き方のヒントを得ようという立場だ。ユング派の分析家として日本人の心の深層にかかわる仕事を続けてきた経験から、日本神話の世界にひたりきることによって得たことを述べるというのである。このブログでは、この河合隼雄の著書を参考にしながら『古事記』を読んでいきたい。
前回、アマテラスの話から始まっているので、ここでは上の本の第四章から見ていくつもりである。
第四章「三貴子の誕生」
《父からの出産》
日本神話のなかで三貴子と呼ばれる、アマテラス、ツクヨミ、スサノヲは極めて重要なトライアッドである。その誕生について『古事記』に従って見よう。
イザナキは黄泉の国より逃げ帰り、きたない国に行ってきたので、みそぎをする。このとき、冥界の汚垢(けがれ)によっても神が生まれ、それを「直す」ための神も生まれる。これらの「神」はキリスト教のゴッドとは大いに異なる。これらひとつひとつにヌミノースな感情(超自然現象、聖なるもの、宗教上神聖なものに触れることで沸き起こる感情)が湧き、それを神と名付けたのだろう。
続いて、イザナキが左目を洗うとアマテラスが生まれ、右目を洗うとツクヨミが、鼻を洗うとスサノヲが生まれる。そしてアマテラスには「汝命は、高天の原を知らせ」、ツクヨミには「汝命は、「夜の食国を知らせ」、スサノヲには「汝命は、海原を知らせ」と命じた。
ここで最も貴いとされる三柱の神があえて父から生まれたと語るのはなぜか。
人間がすべて女性から生まれる、その神秘に感動した人々は、まず神として大母神(だいぼしん)を想定したと思われる。ヨーロッパでもキリスト教以前は地母神(ちぼしん)が中心であった。日本の縄文時代の土偶にも地母神は多い。これに対し、父性原理の優位を押し出すユダヤ・キリスト教は、アダムの骨からイヴがつくられる。
日本の神話ではこれに対して、大母神イザナミがつぎつぎと国土も含めて、ほとんどすべてを生み出す。圧倒的な母性優位である。ここで極端な母性の優位性を、父性の強調によってバランスさせる。こうした巧妙なバランスが日本神話の特徴である。
イザナキが三貴子を生んだことで父性の巻き返しがあったが、彼の後継者として高天の原を知らしたのはアマテラスであった。しかしこれで女性優位がすんなり確立するわけではない。
《目と日月》
アマテラスとツクヨミ、つまり日と月はそれぞれ父親の左目、右目から生まれている。日と月が神の目だという主題は世界の神話のなかにかなり広く見られる。しかし、右と太陽、左と月が結びつくのが一般的で、日本神話や中国の盤古の例のように左と太陽、右と月が結びつくのは珍しいようだ。人類は右利きが圧倒的に多いので、一般には右が左に対して優位と考えられる。
西洋の伝統的な象徴性の考え方では、右―太陽―光―男―意識というつながりに対して、
左―月―闇―女―無意識というつながりが対立していて、前者が優位性をもつようだ。
日本の神話では、左―太陽―女という結びつきが見られ、西洋の一般的な象徴パターンとは異なる。強調すべきは、太陽―女性の結びつきという日本の特異性である。(注)
(注)上田篤氏(『縄文人に学ぶ (新潮新書) 』)は、縄文時代が長く続いた理由のひとつを妻問婚に見る。縄文時代の妻問婚が古墳時代へと引き継がれていったというのだ。
』)は、縄文時代が長く続いた理由のひとつを妻問婚に見る。縄文時代の妻問婚が古墳時代へと引き継がれていったというのだ。
妻問婚は、男が女のもとに通うことで婚姻が成立するが、それは一過性のものである。夫婦としての男女の同棲を伴わず、男が通わなくなることも多い。父は、自分の子ども が誰かに頓着しないが、女にとっては、父が誰であれ、産んだ子は等しく自分の子であり、平等に自分のもとで育てる。
子を持つ女たちは、食糧の採集に明け暮れた。いつくるか分からない男たちはあてにならない。そうした社会では母子間の絆は強くなる。そして氏族の先祖は、母から母へとさかのぼり、ついには「一人の仮想上の女性」に至りつくだろう。それが元母(がんぼ:グレートマザー)だ。縄文時代に作られた土偶は、何かしら呪術的な使われ方をしたのだろうが、それは元母の面影をもっている。縄文社会は母系社会だったと思われ、しかも豊かな自然を「母なる自然」として敬う宗教心は、元母への畏敬とも重なっていく。
縄文人の遺跡には、貝塚などの遺跡と並んで石群や木柱群がある。上田氏は、石群と木柱群が「先祖の祭祀」と「太陽の観測」という二つの機能をもつと考える。縄文人は、太陽と先祖の二つを拝んでいた。そして火は、太陽の子であった。ところで太陽と先祖とはどのように結びつくのか。縄文人は、氏族の先祖を遡ったおおもとに元母のイメージをもっていただろう。その元母と太陽の両方の性格をそなえていたのは、女性神アマテラスである。元母の根源にアマテラスを見ると、先祖信仰と太陽信仰は完全につながるというのである。つまり縄文人の宗教心は、母系社会の先祖信仰と「母なる自然」への信仰、その大元としての太陽信仰とが結びついていたのではないか。
父系社会では、力の強い男が多数の女を抱えてたくさんの子どもを産ませ、「血族王国」を作りたがる。その結果、権力をめぐって男同士の争いが始まる。ところが母系社会では、男に子どもがない。女の産む子どもの人数には限りがあり、しかも女は子供を分け隔てなく育てるから争いも起きにくい。母系社会では、母はすべての子とその子孫の安寧を平等に願う傾向があるから、血族集団は争いなく維持され、社会は安定した。ここに縄文時代が一定の文化とともにかくも長く続いた秘密のひとつがあるのではないか。
こうして縄文時代は女性中心の時代であり、その伝統は後の時代に引き継がれた。父系性の結婚制度に移行したあとも、家の中での女性の力が比較的強かったのは、その伝統を受け継いでいるからだろ。「刀自(とじ)」「女房」「奥」「家内」「お袋」「主婦」などの言葉は、多かれ少なかれ家を管理する意味合いを持つ。日本では今でも主婦が一家の家計を預かるケースが多いが、欧米ではそのようなことはないという。
日本列島に生きた人々は、農耕の段階に入っていくのが大陸よりも遅く、それだけ本格的な農耕をともなわない縄文文化を高度に発達させた。世界でもめずらしく高度な土器や竪穴住を伴う漁撈・狩猟・採集文化であった。それが可能だったのは、自然の恵みが豊かだったからだろう。母系社会であり、母なる自然を敬う縄文文化がその後の日本文化の基盤となったのである。しかもやがて大陸から流入した本格的な稲作は、牧畜を伴っていなかった。牧畜は、大地に働きかける農耕よりも、生きた動物を管理し食用にするという意味で、より自覚的な自然への働きかけとなる。つまりより男性原理が強い。そして牧畜は森林を破壊する。
日本では、1万数千年という長きに渡る縄文時代がその後の日本社会を形成する上で、無視できない強固な基盤となった。父性原理の大陸文明を受け入れるにしても、自分たちの体に染みついた縄文の記憶(母性原理に基づく宗教心や生き方)に合わない要素は、拒絶したり変形したりして受け入れていった。こうして中国文明から多くを学んだが、科挙や宦官や纏足は受け入れなかった。西欧文明は受け入れたが、キリスト教信者は今でも極端に少ない。私たちは、たとえ自覚はなくとも、縄文の記憶をいまだに忘れていないようだ。私たちの社会と文化の根底には母性原理が息づいているのである。現代日本の女性も、その遠い記憶に根ざしているから強いのかもしれない。
現代人は「科学の知」に圧倒されて「神話の知」の獲得が難しい。現代人の生き方を支えてくれる神話はないのか。結局は各個人が自分の生活に関わりのある神話的な様相を見つけていくほかなく、解決は個人にまかされるのか。集団で神話を共有した時代は、神話による支えが集団として保証されたが、その代償として個人の自由が束縛された。今われわれは、各人にふさわしい「個人神話」を見出さねばならないのであろう。
生きることそのものが神話の探求であり、各人が自分にふさわしい個人神話を見出すことが生きることにつながると言うべきだろう。日本人としては、かつて人類がもった数々の神話、そしてとくに日本の神話を学ぶことは不可欠だろう。
日本の神話は、『古事記』(712)、『日本書紀』(720)によって現在に伝えられている。この時代に神話が記録されたのは、当時の日本が、外国との接触によって統一国家としての存在を示すとともに、その中心としての天皇家の存在を基礎づける必要に迫られていたからだ。
『神話と日本人の心
前回、アマテラスの話から始まっているので、ここでは上の本の第四章から見ていくつもりである。
第四章「三貴子の誕生」
《父からの出産》
日本神話のなかで三貴子と呼ばれる、アマテラス、ツクヨミ、スサノヲは極めて重要なトライアッドである。その誕生について『古事記』に従って見よう。
イザナキは黄泉の国より逃げ帰り、きたない国に行ってきたので、みそぎをする。このとき、冥界の汚垢(けがれ)によっても神が生まれ、それを「直す」ための神も生まれる。これらの「神」はキリスト教のゴッドとは大いに異なる。これらひとつひとつにヌミノースな感情(超自然現象、聖なるもの、宗教上神聖なものに触れることで沸き起こる感情)が湧き、それを神と名付けたのだろう。
続いて、イザナキが左目を洗うとアマテラスが生まれ、右目を洗うとツクヨミが、鼻を洗うとスサノヲが生まれる。そしてアマテラスには「汝命は、高天の原を知らせ」、ツクヨミには「汝命は、「夜の食国を知らせ」、スサノヲには「汝命は、海原を知らせ」と命じた。
ここで最も貴いとされる三柱の神があえて父から生まれたと語るのはなぜか。
人間がすべて女性から生まれる、その神秘に感動した人々は、まず神として大母神(だいぼしん)を想定したと思われる。ヨーロッパでもキリスト教以前は地母神(ちぼしん)が中心であった。日本の縄文時代の土偶にも地母神は多い。これに対し、父性原理の優位を押し出すユダヤ・キリスト教は、アダムの骨からイヴがつくられる。
日本の神話ではこれに対して、大母神イザナミがつぎつぎと国土も含めて、ほとんどすべてを生み出す。圧倒的な母性優位である。ここで極端な母性の優位性を、父性の強調によってバランスさせる。こうした巧妙なバランスが日本神話の特徴である。
イザナキが三貴子を生んだことで父性の巻き返しがあったが、彼の後継者として高天の原を知らしたのはアマテラスであった。しかしこれで女性優位がすんなり確立するわけではない。
《目と日月》
アマテラスとツクヨミ、つまり日と月はそれぞれ父親の左目、右目から生まれている。日と月が神の目だという主題は世界の神話のなかにかなり広く見られる。しかし、右と太陽、左と月が結びつくのが一般的で、日本神話や中国の盤古の例のように左と太陽、右と月が結びつくのは珍しいようだ。人類は右利きが圧倒的に多いので、一般には右が左に対して優位と考えられる。
西洋の伝統的な象徴性の考え方では、右―太陽―光―男―意識というつながりに対して、
左―月―闇―女―無意識というつながりが対立していて、前者が優位性をもつようだ。
日本の神話では、左―太陽―女という結びつきが見られ、西洋の一般的な象徴パターンとは異なる。強調すべきは、太陽―女性の結びつきという日本の特異性である。(注)
(注)上田篤氏(『縄文人に学ぶ (新潮新書)
妻問婚は、男が女のもとに通うことで婚姻が成立するが、それは一過性のものである。夫婦としての男女の同棲を伴わず、男が通わなくなることも多い。父は、自分の子ども が誰かに頓着しないが、女にとっては、父が誰であれ、産んだ子は等しく自分の子であり、平等に自分のもとで育てる。
子を持つ女たちは、食糧の採集に明け暮れた。いつくるか分からない男たちはあてにならない。そうした社会では母子間の絆は強くなる。そして氏族の先祖は、母から母へとさかのぼり、ついには「一人の仮想上の女性」に至りつくだろう。それが元母(がんぼ:グレートマザー)だ。縄文時代に作られた土偶は、何かしら呪術的な使われ方をしたのだろうが、それは元母の面影をもっている。縄文社会は母系社会だったと思われ、しかも豊かな自然を「母なる自然」として敬う宗教心は、元母への畏敬とも重なっていく。
縄文人の遺跡には、貝塚などの遺跡と並んで石群や木柱群がある。上田氏は、石群と木柱群が「先祖の祭祀」と「太陽の観測」という二つの機能をもつと考える。縄文人は、太陽と先祖の二つを拝んでいた。そして火は、太陽の子であった。ところで太陽と先祖とはどのように結びつくのか。縄文人は、氏族の先祖を遡ったおおもとに元母のイメージをもっていただろう。その元母と太陽の両方の性格をそなえていたのは、女性神アマテラスである。元母の根源にアマテラスを見ると、先祖信仰と太陽信仰は完全につながるというのである。つまり縄文人の宗教心は、母系社会の先祖信仰と「母なる自然」への信仰、その大元としての太陽信仰とが結びついていたのではないか。
父系社会では、力の強い男が多数の女を抱えてたくさんの子どもを産ませ、「血族王国」を作りたがる。その結果、権力をめぐって男同士の争いが始まる。ところが母系社会では、男に子どもがない。女の産む子どもの人数には限りがあり、しかも女は子供を分け隔てなく育てるから争いも起きにくい。母系社会では、母はすべての子とその子孫の安寧を平等に願う傾向があるから、血族集団は争いなく維持され、社会は安定した。ここに縄文時代が一定の文化とともにかくも長く続いた秘密のひとつがあるのではないか。
こうして縄文時代は女性中心の時代であり、その伝統は後の時代に引き継がれた。父系性の結婚制度に移行したあとも、家の中での女性の力が比較的強かったのは、その伝統を受け継いでいるからだろ。「刀自(とじ)」「女房」「奥」「家内」「お袋」「主婦」などの言葉は、多かれ少なかれ家を管理する意味合いを持つ。日本では今でも主婦が一家の家計を預かるケースが多いが、欧米ではそのようなことはないという。
日本列島に生きた人々は、農耕の段階に入っていくのが大陸よりも遅く、それだけ本格的な農耕をともなわない縄文文化を高度に発達させた。世界でもめずらしく高度な土器や竪穴住を伴う漁撈・狩猟・採集文化であった。それが可能だったのは、自然の恵みが豊かだったからだろう。母系社会であり、母なる自然を敬う縄文文化がその後の日本文化の基盤となったのである。しかもやがて大陸から流入した本格的な稲作は、牧畜を伴っていなかった。牧畜は、大地に働きかける農耕よりも、生きた動物を管理し食用にするという意味で、より自覚的な自然への働きかけとなる。つまりより男性原理が強い。そして牧畜は森林を破壊する。
日本では、1万数千年という長きに渡る縄文時代がその後の日本社会を形成する上で、無視できない強固な基盤となった。父性原理の大陸文明を受け入れるにしても、自分たちの体に染みついた縄文の記憶(母性原理に基づく宗教心や生き方)に合わない要素は、拒絶したり変形したりして受け入れていった。こうして中国文明から多くを学んだが、科挙や宦官や纏足は受け入れなかった。西欧文明は受け入れたが、キリスト教信者は今でも極端に少ない。私たちは、たとえ自覚はなくとも、縄文の記憶をいまだに忘れていないようだ。私たちの社会と文化の根底には母性原理が息づいているのである。現代日本の女性も、その遠い記憶に根ざしているから強いのかもしれない。