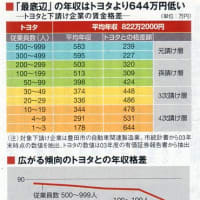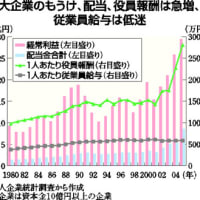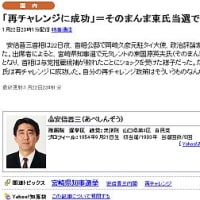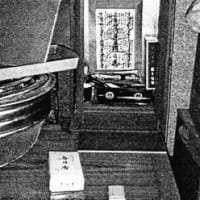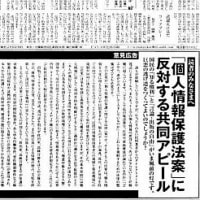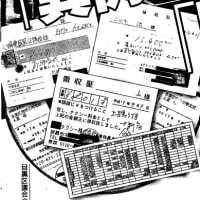携帯電話から警察や消防などにかけたときにその発信場所を自動的に通知させる「緊急通報位置通知」機能を携帯電話にもたせることの要件として、総務省が今年4月以降に発売される第3世代携帯電話(3G)には全てGPSの搭載を義務づけたことは前回に少し書いた。
今日はちょっとその位置情報の精度にまつわること、またその他について書いておきたい。
総務省は自動的に通知される測位の精度は“良好な場合に半径15m程度”と要求している。この”半径15m”というのは、警察官らの人混みにおける視野範囲がおおよそそのくらい、というあたりからきているらしい。しかし、15mも違うと道が通り1つ分違ってきて、都市部などでは交通規制などがあって大回りしないとその目的場所まで到達できないことが頻繁に発生する、だから測位精度は半径5m程度は必要、という意見も出ている。
アメリカでは連邦通信委員会(FCC)が携帯電話からのあらゆる緊急通報(911番通報。日本の警察と消防に相当)時に通報者の位置情報を緊急通報受信センターに自動的に通知する機能(E911=Enhanced 911)を策定していて、その測位精度の目標値が次のようになっている。
■複数基地局測位方式=通知の67%以上が100m以内、95%%以上が300m以内
■GPS測位方式=通知の67%以上が50m以内、95%以上が150m以内
日本では数年前に au のKDDIが東京・青山でGPS衛星が良好に捕捉できる場所の数値として、次の結果を出している。
GPSだけを使用した試験結果
最小誤差=0.7m
最大誤差=31.9m
平均誤差=8.2m
一方でGPS衛星が捕捉できない屋内などでは、基地局だけを使う「複数基地局測位方式」(AFLTと言い、複数の基地局をGPS衛星のように使い測定する方法)で誤差100~200mというのが可能ということだ。
これらの au の位置情報システムを使っているサービスにセコムの「ココセコム」があるが、その精度は「最良の条件下であれば5~10mの誤差」としている。
au 自体は「EZお探しナビ」などで使っている。
ちなみにドコモは複数基地局を使う方式が au とはちょっと違うようだが、「イマドコサーチ」、「いますぐ検索」、「ケータイお探しサービス」などで位置情報システムを使っており、GPS測位の場合はおおむね誤差50m未満、複数基地局の測位の場合はおおむね誤差300m未満と記している。
ウィルコムのPHS通信ネットワークを利用した緊急通報・位置検索システムの「イルカーナ」というサービスをおこなっている加藤電機が興味深い検証をやっている。
実際にビル街や地下街、また公園などでGPSを搭載した携帯との測位の誤差比較をやっているのだ。
1.都心部(新宿ビル街)
2.都心部公園(代々木公園)
3.店舗密集地帯(渋谷のファーストフード店)
4.都心部地下鉄(渋谷駅)
5.郊外(越谷の公園)
総務省は携帯電話にGPSの搭載を義務化し、それを測位方式の基本方式としているが、GPS測位方式以外で半径15mの測位精度が満足できるものができれば携帯電話事業者がそちらを測位の基本方式としてもいいとも考えているようだ。この位置情報システムの研究開発はさまざまなところがおこなっているようで、今月16日には、中国電力、NECなどが共同で「位置検知精度が±30cm程度、方向検知精度が±1度程度」という検知システムを開発したと発表した。このシステムは7m間隔で基地局を設置するというものだが、「中国電力グループでは、電柱、通信ネットワークなどの設備を保有しており、これらの設備やグループ会社の持つノウハウなどを有効活用することで」と記事にはある。
ところで au は人の居場所の情報サービスにおける『セキュリティ・プライバシーの確保』として、次の点をあげている。
では、居場所を検索される人が許可もしていないのに知らないうちに検索され居場所が探られる、ということはないのだろうか。
携帯電話事業者が提供するサービスにはそういうものはもちろんないのだろう。あったら大変だ。お客はすぐ逃げてしまうだろう。
しかし携帯電話や測位サーバ、また携帯と交信をする指令所のプログラム・レベルでみればどうだろうか。
たとえば「ケータイお探しサービス」というものがある。これは所有者が紛失した携帯電話に、携帯電話事業者の指令所からコマンド(命令)が送信されて自動的に携帯電話が応答して位置情報を送ってくるというものである。もちろん、このサービスは事前に所有者がそれを許可する設定をその携帯電話にほどこしていないとできないものである。しかし、その許可の有無という壁さえ消失すれば、プログラム的には携帯電話はいつでも位置情報を送れというコマンドがくれば送れるようになっているということでもある。そして、その「許可の有無を調べる」というのもプログラムの中の単なる一つのルーチン(小単位のプログラム)であり、そのプロセスをスキップさせることは言うまでもなくプログラム的には簡単なことなのだ。つまり、携帯電話というのは「居場所発信機」になりうる可能性を”潜在的”に持っているということなのだ。
もしかしたら緊急用として、設定が不許可になっていても、強制的に位置情報を送らせるようなコマンドも携帯電話にはあるのかもしれない。このへんは事業者のポリシーと、現実に起こりうる所有者の生命や財産が失われる事態の可能性との狭間にある問題であるのだろうが、もしそのような機能があったとしたら、警察が他の用件でもその機能を事業者に強要することもありえない話ではないだろう。
アメリカでは次のようなことも起こっているようだ。
参考:
・創価学会「幹部」が「通話記録」を盗み出した「個人情報」恐怖の実態
今日はちょっとその位置情報の精度にまつわること、またその他について書いておきたい。
総務省は自動的に通知される測位の精度は“良好な場合に半径15m程度”と要求している。この”半径15m”というのは、警察官らの人混みにおける視野範囲がおおよそそのくらい、というあたりからきているらしい。しかし、15mも違うと道が通り1つ分違ってきて、都市部などでは交通規制などがあって大回りしないとその目的場所まで到達できないことが頻繁に発生する、だから測位精度は半径5m程度は必要、という意見も出ている。
アメリカでは連邦通信委員会(FCC)が携帯電話からのあらゆる緊急通報(911番通報。日本の警察と消防に相当)時に通報者の位置情報を緊急通報受信センターに自動的に通知する機能(E911=Enhanced 911)を策定していて、その測位精度の目標値が次のようになっている。
■複数基地局測位方式=通知の67%以上が100m以内、95%%以上が300m以内
■GPS測位方式=通知の67%以上が50m以内、95%以上が150m以内
日本では数年前に au のKDDIが東京・青山でGPS衛星が良好に捕捉できる場所の数値として、次の結果を出している。
GPSだけを使用した試験結果
最小誤差=0.7m
最大誤差=31.9m
平均誤差=8.2m
一方でGPS衛星が捕捉できない屋内などでは、基地局だけを使う「複数基地局測位方式」(AFLTと言い、複数の基地局をGPS衛星のように使い測定する方法)で誤差100~200mというのが可能ということだ。
これらの au の位置情報システムを使っているサービスにセコムの「ココセコム」があるが、その精度は「最良の条件下であれば5~10mの誤差」としている。
au 自体は「EZお探しナビ」などで使っている。
ちなみにドコモは複数基地局を使う方式が au とはちょっと違うようだが、「イマドコサーチ」、「いますぐ検索」、「ケータイお探しサービス」などで位置情報システムを使っており、GPS測位の場合はおおむね誤差50m未満、複数基地局の測位の場合はおおむね誤差300m未満と記している。
ウィルコムのPHS通信ネットワークを利用した緊急通報・位置検索システムの「イルカーナ」というサービスをおこなっている加藤電機が興味深い検証をやっている。
実際にビル街や地下街、また公園などでGPSを搭載した携帯との測位の誤差比較をやっているのだ。
1.都心部(新宿ビル街)
2.都心部公園(代々木公園)
3.店舗密集地帯(渋谷のファーストフード店)
4.都心部地下鉄(渋谷駅)
5.郊外(越谷の公園)
総務省は携帯電話にGPSの搭載を義務化し、それを測位方式の基本方式としているが、GPS測位方式以外で半径15mの測位精度が満足できるものができれば携帯電話事業者がそちらを測位の基本方式としてもいいとも考えているようだ。この位置情報システムの研究開発はさまざまなところがおこなっているようで、今月16日には、中国電力、NECなどが共同で「位置検知精度が±30cm程度、方向検知精度が±1度程度」という検知システムを開発したと発表した。このシステムは7m間隔で基地局を設置するというものだが、「中国電力グループでは、電柱、通信ネットワークなどの設備を保有しており、これらの設備やグループ会社の持つノウハウなどを有効活用することで」と記事にはある。
ところで au は人の居場所の情報サービスにおける『セキュリティ・プライバシーの確保』として、次の点をあげている。
・パスワード設定で本人認証を行います。また、パソコン (PC) での検索用にお客さま固有のURLを設定します。ドコモの場合もこれと似たようなものとなっているようだ。
・検索した履歴・検索された履歴とも最新5件を保持します。
・検索される側で検索拒否の設定が可能です。
・検索保留中、検索される側で検索を中止することが可能です。
・検索された後、検索者の電話番号などが表示されます。
・検索結果を表示する際に、検索結果要求者と表示要求者が同一であるかをチェックしています。このため検索結果に第3者はアクセスできません。
では、居場所を検索される人が許可もしていないのに知らないうちに検索され居場所が探られる、ということはないのだろうか。
携帯電話事業者が提供するサービスにはそういうものはもちろんないのだろう。あったら大変だ。お客はすぐ逃げてしまうだろう。
しかし携帯電話や測位サーバ、また携帯と交信をする指令所のプログラム・レベルでみればどうだろうか。
たとえば「ケータイお探しサービス」というものがある。これは所有者が紛失した携帯電話に、携帯電話事業者の指令所からコマンド(命令)が送信されて自動的に携帯電話が応答して位置情報を送ってくるというものである。もちろん、このサービスは事前に所有者がそれを許可する設定をその携帯電話にほどこしていないとできないものである。しかし、その許可の有無という壁さえ消失すれば、プログラム的には携帯電話はいつでも位置情報を送れというコマンドがくれば送れるようになっているということでもある。そして、その「許可の有無を調べる」というのもプログラムの中の単なる一つのルーチン(小単位のプログラム)であり、そのプロセスをスキップさせることは言うまでもなくプログラム的には簡単なことなのだ。つまり、携帯電話というのは「居場所発信機」になりうる可能性を”潜在的”に持っているということなのだ。
もしかしたら緊急用として、設定が不許可になっていても、強制的に位置情報を送らせるようなコマンドも携帯電話にはあるのかもしれない。このへんは事業者のポリシーと、現実に起こりうる所有者の生命や財産が失われる事態の可能性との狭間にある問題であるのだろうが、もしそのような機能があったとしたら、警察が他の用件でもその機能を事業者に強要することもありえない話ではないだろう。
アメリカでは次のようなことも起こっているようだ。
日本でももうそろそろこのへんの問題を考えなければならないときだろう。
WIRED NEWS
2005年10月27日 11:19am PT
携帯電話の位置情報で個人をリアルタイム追跡
Ryan Singel
携帯電話を追跡に利用しようとした米連邦の法執行当局がこの10月、2度にわたって下級裁判所の裁判官から非難を受けた。政府機関は、相当な理由がない限り、市民の情報をリアルタイムで追跡できないという判断が下されたのだ。
米司法省はこの夏、テキサス州およびニューヨーク州ロングアイランドの裁判官に対し、携帯電話サービス事業者へのある命令を認めるよう求めた。事業者に、2人の個人に関する通話記録と位置情報を――リアルタイムで――提出させようとしたのだ。
2人の裁判官は、位置追跡に関する請求を辛らつな言い回しで却下し、単に情報が捜査に「関連」しそうだと裁判官に申し立てるだけでは、捜査官は携帯電話を追跡装置として使用することはできないと結論付けた。
ニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所のジェイムズ・オレンスタイン連邦治安判事は、10月24日付の覚書および命令(PDFファイル)の中で次のように述べている。「政府機関が携帯電話を当該のユーザーに対する同時性のある位置追跡手段として使う場合には、連邦議会が効果的な法執行と個人のプライバシーのバランスを慎重に勘案した結果、相当な理由が必要とされている」
ロングアイランドのケースで司法省は、携帯電話の「コントロール・チャンネル」の情報によって通話を処理している基地局の場所の記録を求めていた。コントロール・チャンネルは、通話で使われる音声チャンネルとは分離されており、その情報からはユーザーのおおまかな位置と動きのみが分かる。
テキサス州南部地区連邦地方裁判所への請求では、司法省は2ヵ所以上の基地局で計測した携帯電話信号の強度、角度、時間に関する情報を取得しようとした。これらのデータがあれば、捜査官は三角測量によってユーザーの正確な位置を特定できる可能性がある。
オレンスタイン判事が決定を発表した日に、電子プライバシー情報センター(EPIC)は、情報自由法に基づいた訴訟で入手した文書を公開した。この文書によって、米連邦捜査局(FBI)が米国市民の監視において頻繁に局内のルールを破っていることが明らかになった。
司法省はリアルタイムの携帯電話追跡情報の請求と合わせて「ペンレジスター」と「トラップ・アンド・トレース」という装置の設置も申請していた。これらの装置により捜査官は、受発信されるダイヤル情報を即座に知ることが可能になる。
これらの請求は、比較的容易に承認を得やすい。というのも、個人がかける電話番号にはプライバシー侵害の恐れはないと、最高裁判所が判断を下しているためだ。加えて連邦法は、法施行機関がその情報と捜査に関連性がありそうだと断言する限り、裁判官は命令を発行しなければならないと定めている。政府はさらに『保管された通信に関する法律』(Stored Communications Act)の下、これらの装置は位置に特化した情報の取得にも使用し得ると主張している。
電子フロンティア財団(EFF)のケビン・バンクストン弁護士は、ニューヨーク州東部地裁に法廷助言者の意見書(PDFファイル)を提出し、裁判官は通常、そのような命令に対する意見を公に述べないことから、司法省は長期にわたり携帯電話を使用して市民を追跡していた可能性があると指摘している。
「今回の判断は、デジタル時代のプライバシー保護における真の勝利といえる。現在では、ほとんどすべての携帯通信機器が追跡装置として使用できるためだ」と、バンクストン弁護士は声明の中で述べた。「裁判官は、こと監視の問題になると、あまりにも長い間、司法省に欺かれていたと気づき始めている」
取材の中でバンクストン弁護士は、『全令状法』(All Writs Act)という連邦法の下、オレンスタイン治安判事には、携帯電話の追跡に関する命令を出す権限があるとし、司法省が同判事を説得しようとしたと述べた。その際に司法省は、複数の裁判官がこの法律に基づいてクレジットカードによる売買のリアルタイムの追跡を認めてきた事実を明かしたという。同省は、この監視命令を「ホットウォッチ・オーダー」と呼んでいる。
こうした命令が、逃亡者の追跡のみに適用されるのか、それとも一般の犯罪捜査にも適用されるのかは定かでない。
今回、司法省の請求を退けた裁判官2人は、連邦議会が携帯電話の追跡に関する法律について明確にする必要があると結論している。
折りしも米国の上下両院では、『パトリオット法』の更新に関する最終的な形態をめぐって議論が交わされているが、同法によって携帯電話の追跡問題がはっきりすることはなさそうだ。
司法省は、2人の裁判官の決定に対して再審理を要求するとみられる。同省に電話でコメントを求めたが、回答は得られなかった。
参考:
・創価学会「幹部」が「通話記録」を盗み出した「個人情報」恐怖の実態