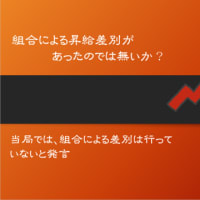おはようございます。
今年の梅雨は、梅雨らしいというのでしょうか?
毎日、曇り空もしくは雨模様が続いています。
現在の仕事は、土日が休みなものですからゆっくりと休ませてもらいました、本日もゆったりとした気分の中でblogなど書かせてもらっています。
今回のお話は、国鉄共済組合と土地の転売問題について語られています。
現在では土地神話は崩壊した感もありますが、当時は「土地は必ず値上がり」するものという神話じみたものがあり、転売転売で大きくなる会社や個人が多数ありました。
そこで国鉄共済組合では、転売禁止条項を設けていたらしいですが、実際には転売されたりすることが後を絶たなかったようでそのようなことから、駅前もしくは将来の駅設置予定地付近への国鉄職員優先分譲地への疑問などが提示されています。
長文ですが、どうぞご覧になってください。
******************************************************************
○委員長(天坊裕彦君) 次に、日本国有鉄道の運営に関する件について調査を行ないます。
質疑のおありの方は、順次御発言を願います。小酒井君。
○小酒井義男君 いわゆる国鉄団地といわれております共済組合の扱っておられる団地の問題で少しお尋ねしたいのですが、質問に入る前に、いつごろからそういう仕事が始められて、どういう手続でやられてきておるか、そういう説明をまずしてほしいと思います。
○説明員(磯崎叡君) 過般来、国鉄共済組合がやっております宅地分譲問題につきまして種々世間で論議されまして、いろいろな疑惑等を受けましたことにつきましては、まことに私としては遺憾に存じます。以下、本問題につきまして率直に事実を申し上げまして、詳細な点は御質問にお答え申し上げたい、こういうふうに思います。
少し詳しくなりますが、お許し願いまして、まず第一に、国鉄共済組合と宅地分譲制度の問題でございますが、国鉄の共済組合は御承知のとおり全国鉄職員で結成しております共済組合でございまして、明治四十年の四月にできたもの、その後、昭和三十一年の公共企業体職員等共済組合法という法律によりまして性格が勅令上の組合から法律上の組合に変わりまして、その仕事の内容といたしましては、御承知のとおり国鉄職員の福祉、厚生をはかり、そうして長期あるいは短期の種々の給付のほかに各種福祉事業を行なうということに相なっております。宅地分譲事業はその福祉事業のうちの組合員の利用に供する財産の取得、管理または貸し付け、こういう規則がございますが、それの一部でございまして、組合員に自分の居住する住宅をつくるための土地を得させる目的で、別途、国鉄共済組合住宅部規程という規程をつくりまして、これによって運営いたしておりまして、国鉄におきましても一般社会におけると同様、職員の住宅事情はきわめて逼迫いたしておりまして、この制度は昭和三十二年からいわゆる宅地分譲制度というものを始めたわけでございます。その後、利用の希望者は年々増加の一途をたどりまして、三十二年から最近までの実績は、全国で三百九十三カ所で、件数といたしまして一万九百二十二件、約一万一千件の宅地分譲をいたしております。そのほかに住宅資金の貸し付けもいたしておりますが、これは非常に数が多いので、また金額も大きくなるので省略いたしますが、国鉄職員の宅地問題につきましては、いわゆる宅地分譲の制度、住宅資金の貸し付けと、この二本立てで職員の老後の安定をはかるという考えでやっておるわけでございます。
次に、現在いろいろ取りざたをされております問題の数点につきまして事実を申し述べたいと思っております。まず国鉄共済組合が購入いたします土地の購入の問題であります。この土地の大きさは大小いろいろございます。たとえば五万坪、三万坪というものもございますれば、また非常に小さい千坪、二千坪というものもございます。非常に大小さまざまでございますが、いずれにいたしましても、購入する場合には、相手方はまず地方自治体すなわち市町村、村はあまりございませんが、市あるいは町あるいはそれらがつくります住宅供給組合というふうなものもございます。いわゆる公社的なもので、市長が大体首長あるいは組合長になっておりますが、そういう場合もございます。そういう公的な機関から買う方法が第一、それから場合によりましては地主から直接購入いたすこともございます。次に、公認と申しますのは、都道府県知事の公認した不動産業者を通じてあっせんしてもらって買う、この三つの方法があるわけでございます。その購入する価格につきましては専門の鑑定士、現在では不動産鑑定士という制度がございますが、その制度前にも専門の鑑定士による評価を受けまして、さらに、問題は、一体うちの組合員がそれを買う能力があるかどうか、いわゆる組合員の経済事情、家庭の経済事情を十分考えませんと、高い土地を買ってみたところで、組合員がそんなに高いものに手が出ないというのでは意味がございませんので、値段と、それから組合員の経済事情と申しますか、家庭の事情、収入状況等も考えました上で、はたして買うべきか、買うべきでないかという決定をしているわけでございます。以上が、購入に至ります手続でございます。
次に、これを取得いたしましたあとに、組合員に分譲する分譲の方法でございます。これも先ほど申しました住宅部の規程に詳しく書いてございますが、原則といたしまして、組合員でなければならない、これはもちろん当然でございますが、単に組合員であっても十年以上の組合員の資格がなければいけない。いわゆる在職年数で押えてあります。
それからその次に、自分の住宅を実際に必要とするかどうか、実際に別に家を持っている人は必要がないわけでありますので、ほんとうに自分の家が必要なのかどうか、これにつきましてはいろいろ認定のむずかしい場合もございます。次男だった場合にどうだこうだという問題などもございまして、必ずしも徹底的に必要性があるかどうかということは究明はむずかしゅうございますが、ともかくまず真に住宅を必要とするかどうかという問題です。さらに、場所によりましては非常に応募者の多いところがございます。これは全部抽せんでいたします。そして原則は一人一区画、大体八十坪ないし百坪でございますが、一人一区画というのが原則でございます。ただ整地等の際にのり面が非常に多いとか、あるいは土地が三角であるとかというふうな場合には、例外的に二口を認めることもございますが、原則としては一人一区画でございます。ただ、応募者が少ない場合には二区画の場合もございますが、これはきわめて例がまれでございます。
しからば、一体いつ国鉄共済組合から各個人の組合員に所有権の移転をするかという次の問題でございますが、これは一応譲渡契約といたしまして、すなわち国鉄共済組合とAならAという職員と、譲渡契約を締結いたしまして、そして土地の引き渡しをいたします。そうするとそのとき直ちに所有権の移転登記をいたします。しかしながら大体原則は即金払いではございません。最高十八年の年賦償還。ただし在職年数の余裕がそれほどない人は退職金でもって払うと、こういう制度になっておりますので、その代金が完済されるまでは国鉄共済組合のために一番抵当の設定をいたしております。これも規則に明らかにいたしております。で、この一番抵当は必ず登記簿上に載せるということに相なっております。
次に問題になりますのは、この国鉄共済組合から譲渡を受けながら、これを転売している、投機目的で転売しているという事実があるというふうに報道された点がございます。で、もちろん住宅部の規則の中に、分譲代金を完済するまでは一切の転売は認めておりませんし、また抵当権が設定されておる以上、売ろうと思ってもそう簡単に売れるものではないわけでございます。すなわち禁止条項といたしまして代金が完済するまでには第三者に使用させたり、あるいは居住以外の用途に使ったり、あるいは住宅の模様がえや、または増築したり、あるいは第三者に権利を譲るということは絶対できないということに相なっております。しかしながら、退職等によりまして、その代金を全部完済いたしますと、先ほどの抵当権は抹消されます。したがいまして、完全に所有権がその本人に移るわけでございます。転売するかどうかはそれからあとの問題に相なるわけでございますが、最近、調査いたしましたところでは、我孫子につくりました団地三百六十八件のうち二十件が転売されております。私どもの局長は四十件と申したように新聞に報道されましたが、これは二十件の誤りでございます。この二十件をまだ一々全部審査はできておりませんが、大体三つ事情があるというふうに考えられます。一つは、本人の死亡による権利の承継でございます。これは登記簿上当然権利が移転いたします。しかし、これは相続いたしますと長子の相続になりますので、名字が同じですから大体これはわかると思っております。次は、主として問題の多いのは、生活設計の変更あるいは貧困という問題でございます。国鉄をやめてからあと、やっと退職金で土地を買って一応家をつくった。その後貧乏になってしまって家を手離さなければならなくなったという事実が実は皆無ではございません。それからもう一つは就職。やめたあと大体この辺に住もうと思って土地を買った。ところがやめたあとの就職口として、この付近にいられなくなった、あるいは急な事情の変更でいなかに帰らなければならなくなったというふうな個人的な生活条件の変更がございます。この場合にはやはり転売をしているようでございます。
それから、我孫子の例で一つ特殊な例といたしましては、いわゆる共有地と申しまして約四、五万坪の団地の中に緑地帯等をつくる意味で、初めからその居住者の自治会の代表の名義でそれを保有しておった部分がございます。その後徐々に家が建ちまして、居住をいたしますにつきましては非常に道路が悪い、団地内の道路が非常に悪いということで、道路整備費をぜひ何とかしなくてはいかぬ。ところが、とてもみんな自分の金で道路を整備するわけにいかないということで、その共有地を転売いたした。これは三件ございますが、いたした事実がございます。この中には、ほんとうに自分で住むつもりで買った人もあれば、一部不動産業者がそれを買ったものもあるようでございまして、不動産業者に転売したというふうに報道されましたのはたぶんこの点ではないかというふうに考えられますが、それにつきましてはいま申しましたとおり、共有地の処分をいたしまして居住者の総意によってきめたことでございますので、これはやむを得ないことだというふうに考えられます。
その他の団地につきましては、目下のところ転売の事実はございませんし、ただ、たいへん遺憾なことは、在職中転売した件が二件ほどいまわかっております。これは本人に確かめましたところ、まあ別にいい場所があったので金を借りて、そのために売ったんだということを率直に申している本人もございます。これはその後いかなる始末をするか等についてはまだ考えておりませんが、そういう事実が絶対なかったとは率直に申しまして申し上げられませんが、大体二十件の転売のうち理由の立つもの、いわゆる投機目的その他利益を得るために売ったというものはまず大体二件ないし三件というふうに考えまして、この点につきましては私どもの非常に監督の不行き届きということで率直にお詫び申し上げます。
それから、さらにもう一つ、団地の中に、いまの譲り受けでなしに初めから不動産業者の名前になっている土地ががあるんじゃないか、こういう問題がございます。これはいろいろ事情がございまして、団地をつくります際にその中に不動産業者がすでに自分の土地を持っているところがございまして、そうしてどうしてもその土地を売らない。しかし、そういう土地をぼつぼつ持っていられたんでは一括した土地造成の工事ができないということで、それではということで、相談いたしまして、造成したあとの土地について、おまえのもと持っておる土地と交換しようということを約束いたしまして、一応こちらに土地を移してもらう、そうしてその土地を移したものをさらに直接もとの所有者である、しかも場所が変わったところの不動産業者に移転登記をした。すなわち不動産業者と申しましてもこのときは地主の一人でございますけれども、地主から国鉄共済組合に一応土地を移転して、国鉄共済組合からさらに違った、同じ団地の中の分筆された違った場所をその不動産業者に移転登録した、こういう例がございます。これが二口か三口ございました。これももとの所有者等が全部はっきりいたしております。登記簿上、国鉄が直接売買――いわゆる売買でもって取得したのでなしに、もと所有者と交換したのだということは、事情から申しましてはっきりしている、こういうふうに私は考えております。
以上が、大体いままでの問題となったところでございますが、その他につきましては、御質問でお答えいたします。
○小酒井義男君 そこで、焦点をしぼって二、三点お尋ねしたいと思いますが、一つは、国鉄団地と新しい駅との関係です。
国鉄共済組合が土地を入手する場合に、何か将来そこに駅ができるというようなことを予想といいますか、考えて、そうして土地の取得をしておるのじゃないか、こういう疑念が持たれるわけなんですが、具体的にいいますと、たとえば根岸線の新大船駅の場合がそうですが、あの周辺に三つほどの団地がすでに買われておったわけでございますが、こういうことについて、まあ偶然の一致ということではなかなか一般は理解しにくいのじゃないかということが言えると思うのです。いまこれは具体的な例なんですが、個々の例でひとつ御説明を願いたい。
○説明員(磯崎叡君) 今回の問題で、駅の設置と国鉄共済組合の団地の造成との関係につきまして、いろいろ疑念がおありであったようでございますが、問題になりました数駅につきまして、具体的な事情を申し上げたいと存じます。
いま小酒井先生の御質問の、根岸線の例は、一番最後に御説明いたしますが、一応たとえば東大宮、これは東北本線でございます。それから高崎線の行田、あるいは、まだできておりませんが、常磐線の我孫子――取手間の駅、こういった駅の設置の問題でございますが、まず原則といたしまして、と申しますか、それは非常に、国鉄は少しむごいと言われるほど絶対に守っております鉄則は、新駅を既設線に設置する場合には、全部全額地元負担であるということであります。一銭も国鉄は出しません。全額地元に持っていただきます。事のよしあしは別といたしまして、新駅設置の場合に国鉄が金を出すということになりますと、これは全国ほうはいとして新駅設置の要望が出てまいりまして、とても国鉄財政でやってまいれませんので、これは戦争前はともかく、戦争後は新駅設置は絶対に国鉄は出しません。非常にむごいといってずいぶんしかられるのでございますが、この鉄則は未だかつて破ったことがございませんが、しかも、いま申しました東北本線あるいは常磐線、高崎線等の駅につきましては、最低七千万円、最高一億三千万円くらいの経費がかかるわけでございます。平均いたしまして大体一億円前後というのが駅設置の費用でございます。これは当然先ほど申しました地元負担に相なりますので、何らかの形で地元民の負担に相なってくるわけでございます。したがって、これだけの大きな負担を地元民がなさる場合に、当然これは市議会あるいは町議会等の議決を経て国鉄にお申し込みがあるのは、これは当然のことでございます。したがいまして、地元住民の方々は応分の負担をする。そうして大体この辺に駅ができるということは、これはすでに御承知なことでございまして、たとえば行田について申しますれば、昭和三十四年にすでに市議会の――この市議会の議決はもっと早いのでございますが、三十四年の四月以降、数回にわたる市長から正式な御陳情を受けております。また東大宮につきましては、これは東北線がまだ単線だった時分に信号場のあったところでございまして、現実に人の乗り降りを多少認めておったところでございます。これは昭和二十七年に市議会の議決をもって、駅を設置してほしい、こういう御要望のあったところでございます。また我孫子――取手間につきましても、昭和三十五年に申請がございまして、これはその後、さっき申しました町の財政事情のためにいま中断されております。そういったように、駅をつくるということは、決して国鉄がつくりたくてつくるというようなものでなしに、地元民がぜひつくってほしい、金は全部おれが出してやる。こういう原則で駅をつくっているわけでございまして、これのよしあしは一応別にいたしまして、現実はそういうやり方をいたしております。したがいまして、地元民の御存じのないままに国鉄が、しかも国鉄共済組合が団地を買ってしまうなどということは考えられないことである、これは全く関係のない点でございます。行田の場合は、行田の市の開発協議会というところから正式にお譲り受けを受ける、また大宮につきましても、大宮市長から正式に譲り受けを受けている。こういうやり方をいたしているわけでございます。根岸線の場合につきましては、これは新線でございますので、ちょっと例が違いますので、後ほど別に御説明申し上げますが、根岸線というのは、御承知のとおり鉄道敷設法では、神奈川県の横浜市桜木町から北鎌倉に至る、こういう敷設法上の予定線に相なっております。で、その線がどこを通るか、北鎌倉というふうに書いてございますので、北鎌倉か、あるいは大船か、北鎌倉というのは行政上鎌倉市でございます。大船駅の半分は神奈川県の鎌倉市、半分は横浜市でございます。で、敷設法上鎌倉に至るというものを、大船に入れることが法律上妥当なりやいなやということについても、ずいぶんこの委員会でも議論されましたが、これは大船駅を通っていけばいいだろうということで法律を改正しないままに、とにかくそれでは横浜市桜木町から大船に入れようということで計画を立てたわけでございますが、大船は御承知のとおり東海道線と横須賀線の分岐点でございます。そうしてその駅をつくる場合には、われわれとして一番考えなければならないことは、輸送の流れでございます。先ほど申し上げましたような既設線の中間に駅をつくる場合においてさえも、私どもは、いま申しました地元負担という問題はもとよりのこと、そのほかに一番大事なことは、土木的に見まして、たとえば線路の勾配あるいはカーブ等が建設規格上合っているかどうか、これは厳格な政令がございまして、建設規格上合っているかどうかという問題が一つ、それから非常に過密化している地域に駅がふえるということは、やはり一ヵ所二分ないし三分も運転時間が延びますので、その線路容量と申します列車の本数に影響を与えるかどうかという運転上の問題ということも十分考えまして、さらにどのくらい利用するか、あるいは逆に国鉄の職員を何人かを置かなければならない。こういう商売上の計算をいたしました上で、先ほど申し上げましたような中間駅をつくるわけでございますが、いまの根岸線の新大船駅につきましては、実はそれどころの問題ではないわけでございまして、いま申し上げましたとおり、大船に入れるにいたしましても、どういうふうに入れるかということが一番大問題でございます。と申しますことは、一体横須賀線から横浜へじかに持っていけるようにすべきか、あるいは湘南地帯から横浜にじかに通えるようにするのか、あるいは根岸線の中間から逆に東京向けに入ったほうがいいか、いわゆるアプローチのつくり方が非常にむずかしい問題でございまして、これは部内でも実は数十回にわたって議論いたしました、いろいろ議論の出た結果、現時点におきましては、最重点の目的は、通勤輸送と貨物輸送であるということで、この貨物輸送の面から一番大事なことは、やはり東海道から横浜に向けて大船を経由してすぐ右に入ってスルーで――と申しますのは、大船駅でもって全然機関車のつけかえをしないでそのまま横須賀のほうに行ける、あるいは横浜からまっすぐ出てきたものはそのまま東海道に流せる、こういう入れ方が一番妥当であろうという結論に落ちついたわけでございます。それまでにいろいろ先ほど申しました議論があったと申しましたが、大体大ざっばに言って三つの案がございました。一つは、いまの最終案でございますが、なるべく北のほうから入ってきて、現在の東海道線と立体交差して大船駅のまん中に入る。そうして東海道の貨物線とつながるようにする、こういうものが最終案でございます。これは立体交差で東海道線をまたいでまいります。それには相当遠くから入ってこないと入らない。大船の駅から約一キロ半ほど北から回って入ってきます。その次は、それを考えないで、旅客輸送だけを考えて、いまの大船の駅の海側と申しますか、大船の撮影所寄りにまっすぐに入れる、こういう案がございました。これでございますと、いまのルートのずっと南に、ほとんど大船の駅に直角ではございませんが、直角に近いような形で入ってまいります。それからもう一つは、逆に南のほうから東京に向けて入ってくるというルートも考えたことがございます。こういったように、実に大船にどういう形で根岸線を入れるかということは、非常に私のほうの輸送プロパーの国鉄自体としての一番重要な問題として私自身参画して議論、検討した問題でございます。で、たまたまこの団地は三つのうちの一つの団地が一つの新しいルートの駅に非常に近いのでありますが、実は大船に笠間というところがございます。これは元海軍の火薬庫かなんかあったところであります。そこに戦争中から実は私のほうが土地を買いまして、約五十戸の宿舎と、それから百数十人入る独身寮とを持っておりました。その他買い上げの官舎等もぼつぼつございますが、笠間地区というのは二十数年前から国鉄職員が多数居住しておった地区でございます。これらの職員からいろいろな情報が入りまして、あの辺で土地が買えそうだ、この辺は土地が買えそうだということで土地をいろいろ物色しておったわけでございます。したがいまして、土地をほしいという考え方、これは大船地区なら大体いいだろう、東京にもそう遠くないし、どうやら通勤圏内でもちろんあるし、まあ、まだそのころは値段も高くないし、大船地区なら一応住宅地として適当だろうということで種々物色いたしました結果、この三つの土地を探したわけでございます。そうして、さっきるる申しました大船に入るルートが決定したのはやっと昨年の秋でございます。もちろんそのルートが決定いたさなければ、新駅はできないわけでございます。したがいまして、この大船の三つの団地はそれぞれ現在の大船駅から十五分ないし二十分、あるいは三十分以上離れております。これと、こういう団地のところにどこに駅をつくるか、あるいはどこを通るかという問題は、先ほどるる申しました大船の駅にどういう姿で根岸線を入れるかという根本問題に比べますれば、全く末梢の問題と言わざるを得ない問題で、このルート決定には、この共済組合がどこの土地を買ったということなどは全く頭に入れないで決定いたしました。その点は私自身が責任者としてこのルートを決定いたしたのでございますので、私自身種々検討いたしました結果、こういうふうにきまりました。この現在の場所の矢部野駅から、逆に申しますと大船から三・三キロの地点でございます。この地点は御承知のPXその他ございまして、わりに付近に人家もある、つくるならこの付近が一番適当だということで、建設公団と大船御当地の方々、国鉄と参画してつくったわけでございます。これは全くたまたまB団地の下にこれがあったということでございます。もしこれが私の申し上げましたとおり、北から東海道線に立体交差で入らないで、大船の撮影所のほうに線路を入れるとすれば、いまの線路からずっと一キロぐらい南を通ったであろうと、これは私の推測であります。北鎌倉から入れるとすれば、十キロぐらい南、北鎌倉の付近のトンネルを出たところぐらいで横須賀線に入るという形になっただろうと思います。したがいまして、私どもとしましてはたいへん申しわけないのですが、職員の団地をどこにするかということなどと全く無関係の国鉄のプロパーの、どうしたら一番輸送がよくて、どうしたら一番この新線の意義があがるかという角度からきめたものでございまして、私自身この問題に参画しましたときに、全く実はうかつなことながら、団地のあることを知らなかったということを、率直に私は申し上げさしていただきたいと思います。
今年の梅雨は、梅雨らしいというのでしょうか?
毎日、曇り空もしくは雨模様が続いています。
現在の仕事は、土日が休みなものですからゆっくりと休ませてもらいました、本日もゆったりとした気分の中でblogなど書かせてもらっています。
今回のお話は、国鉄共済組合と土地の転売問題について語られています。
現在では土地神話は崩壊した感もありますが、当時は「土地は必ず値上がり」するものという神話じみたものがあり、転売転売で大きくなる会社や個人が多数ありました。
そこで国鉄共済組合では、転売禁止条項を設けていたらしいですが、実際には転売されたりすることが後を絶たなかったようでそのようなことから、駅前もしくは将来の駅設置予定地付近への国鉄職員優先分譲地への疑問などが提示されています。
長文ですが、どうぞご覧になってください。
******************************************************************
○委員長(天坊裕彦君) 次に、日本国有鉄道の運営に関する件について調査を行ないます。
質疑のおありの方は、順次御発言を願います。小酒井君。
○小酒井義男君 いわゆる国鉄団地といわれております共済組合の扱っておられる団地の問題で少しお尋ねしたいのですが、質問に入る前に、いつごろからそういう仕事が始められて、どういう手続でやられてきておるか、そういう説明をまずしてほしいと思います。
○説明員(磯崎叡君) 過般来、国鉄共済組合がやっております宅地分譲問題につきまして種々世間で論議されまして、いろいろな疑惑等を受けましたことにつきましては、まことに私としては遺憾に存じます。以下、本問題につきまして率直に事実を申し上げまして、詳細な点は御質問にお答え申し上げたい、こういうふうに思います。
少し詳しくなりますが、お許し願いまして、まず第一に、国鉄共済組合と宅地分譲制度の問題でございますが、国鉄の共済組合は御承知のとおり全国鉄職員で結成しております共済組合でございまして、明治四十年の四月にできたもの、その後、昭和三十一年の公共企業体職員等共済組合法という法律によりまして性格が勅令上の組合から法律上の組合に変わりまして、その仕事の内容といたしましては、御承知のとおり国鉄職員の福祉、厚生をはかり、そうして長期あるいは短期の種々の給付のほかに各種福祉事業を行なうということに相なっております。宅地分譲事業はその福祉事業のうちの組合員の利用に供する財産の取得、管理または貸し付け、こういう規則がございますが、それの一部でございまして、組合員に自分の居住する住宅をつくるための土地を得させる目的で、別途、国鉄共済組合住宅部規程という規程をつくりまして、これによって運営いたしておりまして、国鉄におきましても一般社会におけると同様、職員の住宅事情はきわめて逼迫いたしておりまして、この制度は昭和三十二年からいわゆる宅地分譲制度というものを始めたわけでございます。その後、利用の希望者は年々増加の一途をたどりまして、三十二年から最近までの実績は、全国で三百九十三カ所で、件数といたしまして一万九百二十二件、約一万一千件の宅地分譲をいたしております。そのほかに住宅資金の貸し付けもいたしておりますが、これは非常に数が多いので、また金額も大きくなるので省略いたしますが、国鉄職員の宅地問題につきましては、いわゆる宅地分譲の制度、住宅資金の貸し付けと、この二本立てで職員の老後の安定をはかるという考えでやっておるわけでございます。
次に、現在いろいろ取りざたをされております問題の数点につきまして事実を申し述べたいと思っております。まず国鉄共済組合が購入いたします土地の購入の問題であります。この土地の大きさは大小いろいろございます。たとえば五万坪、三万坪というものもございますれば、また非常に小さい千坪、二千坪というものもございます。非常に大小さまざまでございますが、いずれにいたしましても、購入する場合には、相手方はまず地方自治体すなわち市町村、村はあまりございませんが、市あるいは町あるいはそれらがつくります住宅供給組合というふうなものもございます。いわゆる公社的なもので、市長が大体首長あるいは組合長になっておりますが、そういう場合もございます。そういう公的な機関から買う方法が第一、それから場合によりましては地主から直接購入いたすこともございます。次に、公認と申しますのは、都道府県知事の公認した不動産業者を通じてあっせんしてもらって買う、この三つの方法があるわけでございます。その購入する価格につきましては専門の鑑定士、現在では不動産鑑定士という制度がございますが、その制度前にも専門の鑑定士による評価を受けまして、さらに、問題は、一体うちの組合員がそれを買う能力があるかどうか、いわゆる組合員の経済事情、家庭の経済事情を十分考えませんと、高い土地を買ってみたところで、組合員がそんなに高いものに手が出ないというのでは意味がございませんので、値段と、それから組合員の経済事情と申しますか、家庭の事情、収入状況等も考えました上で、はたして買うべきか、買うべきでないかという決定をしているわけでございます。以上が、購入に至ります手続でございます。
次に、これを取得いたしましたあとに、組合員に分譲する分譲の方法でございます。これも先ほど申しました住宅部の規程に詳しく書いてございますが、原則といたしまして、組合員でなければならない、これはもちろん当然でございますが、単に組合員であっても十年以上の組合員の資格がなければいけない。いわゆる在職年数で押えてあります。
それからその次に、自分の住宅を実際に必要とするかどうか、実際に別に家を持っている人は必要がないわけでありますので、ほんとうに自分の家が必要なのかどうか、これにつきましてはいろいろ認定のむずかしい場合もございます。次男だった場合にどうだこうだという問題などもございまして、必ずしも徹底的に必要性があるかどうかということは究明はむずかしゅうございますが、ともかくまず真に住宅を必要とするかどうかという問題です。さらに、場所によりましては非常に応募者の多いところがございます。これは全部抽せんでいたします。そして原則は一人一区画、大体八十坪ないし百坪でございますが、一人一区画というのが原則でございます。ただ整地等の際にのり面が非常に多いとか、あるいは土地が三角であるとかというふうな場合には、例外的に二口を認めることもございますが、原則としては一人一区画でございます。ただ、応募者が少ない場合には二区画の場合もございますが、これはきわめて例がまれでございます。
しからば、一体いつ国鉄共済組合から各個人の組合員に所有権の移転をするかという次の問題でございますが、これは一応譲渡契約といたしまして、すなわち国鉄共済組合とAならAという職員と、譲渡契約を締結いたしまして、そして土地の引き渡しをいたします。そうするとそのとき直ちに所有権の移転登記をいたします。しかしながら大体原則は即金払いではございません。最高十八年の年賦償還。ただし在職年数の余裕がそれほどない人は退職金でもって払うと、こういう制度になっておりますので、その代金が完済されるまでは国鉄共済組合のために一番抵当の設定をいたしております。これも規則に明らかにいたしております。で、この一番抵当は必ず登記簿上に載せるということに相なっております。
次に問題になりますのは、この国鉄共済組合から譲渡を受けながら、これを転売している、投機目的で転売しているという事実があるというふうに報道された点がございます。で、もちろん住宅部の規則の中に、分譲代金を完済するまでは一切の転売は認めておりませんし、また抵当権が設定されておる以上、売ろうと思ってもそう簡単に売れるものではないわけでございます。すなわち禁止条項といたしまして代金が完済するまでには第三者に使用させたり、あるいは居住以外の用途に使ったり、あるいは住宅の模様がえや、または増築したり、あるいは第三者に権利を譲るということは絶対できないということに相なっております。しかしながら、退職等によりまして、その代金を全部完済いたしますと、先ほどの抵当権は抹消されます。したがいまして、完全に所有権がその本人に移るわけでございます。転売するかどうかはそれからあとの問題に相なるわけでございますが、最近、調査いたしましたところでは、我孫子につくりました団地三百六十八件のうち二十件が転売されております。私どもの局長は四十件と申したように新聞に報道されましたが、これは二十件の誤りでございます。この二十件をまだ一々全部審査はできておりませんが、大体三つ事情があるというふうに考えられます。一つは、本人の死亡による権利の承継でございます。これは登記簿上当然権利が移転いたします。しかし、これは相続いたしますと長子の相続になりますので、名字が同じですから大体これはわかると思っております。次は、主として問題の多いのは、生活設計の変更あるいは貧困という問題でございます。国鉄をやめてからあと、やっと退職金で土地を買って一応家をつくった。その後貧乏になってしまって家を手離さなければならなくなったという事実が実は皆無ではございません。それからもう一つは就職。やめたあと大体この辺に住もうと思って土地を買った。ところがやめたあとの就職口として、この付近にいられなくなった、あるいは急な事情の変更でいなかに帰らなければならなくなったというふうな個人的な生活条件の変更がございます。この場合にはやはり転売をしているようでございます。
それから、我孫子の例で一つ特殊な例といたしましては、いわゆる共有地と申しまして約四、五万坪の団地の中に緑地帯等をつくる意味で、初めからその居住者の自治会の代表の名義でそれを保有しておった部分がございます。その後徐々に家が建ちまして、居住をいたしますにつきましては非常に道路が悪い、団地内の道路が非常に悪いということで、道路整備費をぜひ何とかしなくてはいかぬ。ところが、とてもみんな自分の金で道路を整備するわけにいかないということで、その共有地を転売いたした。これは三件ございますが、いたした事実がございます。この中には、ほんとうに自分で住むつもりで買った人もあれば、一部不動産業者がそれを買ったものもあるようでございまして、不動産業者に転売したというふうに報道されましたのはたぶんこの点ではないかというふうに考えられますが、それにつきましてはいま申しましたとおり、共有地の処分をいたしまして居住者の総意によってきめたことでございますので、これはやむを得ないことだというふうに考えられます。
その他の団地につきましては、目下のところ転売の事実はございませんし、ただ、たいへん遺憾なことは、在職中転売した件が二件ほどいまわかっております。これは本人に確かめましたところ、まあ別にいい場所があったので金を借りて、そのために売ったんだということを率直に申している本人もございます。これはその後いかなる始末をするか等についてはまだ考えておりませんが、そういう事実が絶対なかったとは率直に申しまして申し上げられませんが、大体二十件の転売のうち理由の立つもの、いわゆる投機目的その他利益を得るために売ったというものはまず大体二件ないし三件というふうに考えまして、この点につきましては私どもの非常に監督の不行き届きということで率直にお詫び申し上げます。
それから、さらにもう一つ、団地の中に、いまの譲り受けでなしに初めから不動産業者の名前になっている土地ががあるんじゃないか、こういう問題がございます。これはいろいろ事情がございまして、団地をつくります際にその中に不動産業者がすでに自分の土地を持っているところがございまして、そうしてどうしてもその土地を売らない。しかし、そういう土地をぼつぼつ持っていられたんでは一括した土地造成の工事ができないということで、それではということで、相談いたしまして、造成したあとの土地について、おまえのもと持っておる土地と交換しようということを約束いたしまして、一応こちらに土地を移してもらう、そうしてその土地を移したものをさらに直接もとの所有者である、しかも場所が変わったところの不動産業者に移転登記をした。すなわち不動産業者と申しましてもこのときは地主の一人でございますけれども、地主から国鉄共済組合に一応土地を移転して、国鉄共済組合からさらに違った、同じ団地の中の分筆された違った場所をその不動産業者に移転登録した、こういう例がございます。これが二口か三口ございました。これももとの所有者等が全部はっきりいたしております。登記簿上、国鉄が直接売買――いわゆる売買でもって取得したのでなしに、もと所有者と交換したのだということは、事情から申しましてはっきりしている、こういうふうに私は考えております。
以上が、大体いままでの問題となったところでございますが、その他につきましては、御質問でお答えいたします。
○小酒井義男君 そこで、焦点をしぼって二、三点お尋ねしたいと思いますが、一つは、国鉄団地と新しい駅との関係です。
国鉄共済組合が土地を入手する場合に、何か将来そこに駅ができるというようなことを予想といいますか、考えて、そうして土地の取得をしておるのじゃないか、こういう疑念が持たれるわけなんですが、具体的にいいますと、たとえば根岸線の新大船駅の場合がそうですが、あの周辺に三つほどの団地がすでに買われておったわけでございますが、こういうことについて、まあ偶然の一致ということではなかなか一般は理解しにくいのじゃないかということが言えると思うのです。いまこれは具体的な例なんですが、個々の例でひとつ御説明を願いたい。
○説明員(磯崎叡君) 今回の問題で、駅の設置と国鉄共済組合の団地の造成との関係につきまして、いろいろ疑念がおありであったようでございますが、問題になりました数駅につきまして、具体的な事情を申し上げたいと存じます。
いま小酒井先生の御質問の、根岸線の例は、一番最後に御説明いたしますが、一応たとえば東大宮、これは東北本線でございます。それから高崎線の行田、あるいは、まだできておりませんが、常磐線の我孫子――取手間の駅、こういった駅の設置の問題でございますが、まず原則といたしまして、と申しますか、それは非常に、国鉄は少しむごいと言われるほど絶対に守っております鉄則は、新駅を既設線に設置する場合には、全部全額地元負担であるということであります。一銭も国鉄は出しません。全額地元に持っていただきます。事のよしあしは別といたしまして、新駅設置の場合に国鉄が金を出すということになりますと、これは全国ほうはいとして新駅設置の要望が出てまいりまして、とても国鉄財政でやってまいれませんので、これは戦争前はともかく、戦争後は新駅設置は絶対に国鉄は出しません。非常にむごいといってずいぶんしかられるのでございますが、この鉄則は未だかつて破ったことがございませんが、しかも、いま申しました東北本線あるいは常磐線、高崎線等の駅につきましては、最低七千万円、最高一億三千万円くらいの経費がかかるわけでございます。平均いたしまして大体一億円前後というのが駅設置の費用でございます。これは当然先ほど申しました地元負担に相なりますので、何らかの形で地元民の負担に相なってくるわけでございます。したがって、これだけの大きな負担を地元民がなさる場合に、当然これは市議会あるいは町議会等の議決を経て国鉄にお申し込みがあるのは、これは当然のことでございます。したがいまして、地元住民の方々は応分の負担をする。そうして大体この辺に駅ができるということは、これはすでに御承知なことでございまして、たとえば行田について申しますれば、昭和三十四年にすでに市議会の――この市議会の議決はもっと早いのでございますが、三十四年の四月以降、数回にわたる市長から正式な御陳情を受けております。また東大宮につきましては、これは東北線がまだ単線だった時分に信号場のあったところでございまして、現実に人の乗り降りを多少認めておったところでございます。これは昭和二十七年に市議会の議決をもって、駅を設置してほしい、こういう御要望のあったところでございます。また我孫子――取手間につきましても、昭和三十五年に申請がございまして、これはその後、さっき申しました町の財政事情のためにいま中断されております。そういったように、駅をつくるということは、決して国鉄がつくりたくてつくるというようなものでなしに、地元民がぜひつくってほしい、金は全部おれが出してやる。こういう原則で駅をつくっているわけでございまして、これのよしあしは一応別にいたしまして、現実はそういうやり方をいたしております。したがいまして、地元民の御存じのないままに国鉄が、しかも国鉄共済組合が団地を買ってしまうなどということは考えられないことである、これは全く関係のない点でございます。行田の場合は、行田の市の開発協議会というところから正式にお譲り受けを受ける、また大宮につきましても、大宮市長から正式に譲り受けを受けている。こういうやり方をいたしているわけでございます。根岸線の場合につきましては、これは新線でございますので、ちょっと例が違いますので、後ほど別に御説明申し上げますが、根岸線というのは、御承知のとおり鉄道敷設法では、神奈川県の横浜市桜木町から北鎌倉に至る、こういう敷設法上の予定線に相なっております。で、その線がどこを通るか、北鎌倉というふうに書いてございますので、北鎌倉か、あるいは大船か、北鎌倉というのは行政上鎌倉市でございます。大船駅の半分は神奈川県の鎌倉市、半分は横浜市でございます。で、敷設法上鎌倉に至るというものを、大船に入れることが法律上妥当なりやいなやということについても、ずいぶんこの委員会でも議論されましたが、これは大船駅を通っていけばいいだろうということで法律を改正しないままに、とにかくそれでは横浜市桜木町から大船に入れようということで計画を立てたわけでございますが、大船は御承知のとおり東海道線と横須賀線の分岐点でございます。そうしてその駅をつくる場合には、われわれとして一番考えなければならないことは、輸送の流れでございます。先ほど申し上げましたような既設線の中間に駅をつくる場合においてさえも、私どもは、いま申しました地元負担という問題はもとよりのこと、そのほかに一番大事なことは、土木的に見まして、たとえば線路の勾配あるいはカーブ等が建設規格上合っているかどうか、これは厳格な政令がございまして、建設規格上合っているかどうかという問題が一つ、それから非常に過密化している地域に駅がふえるということは、やはり一ヵ所二分ないし三分も運転時間が延びますので、その線路容量と申します列車の本数に影響を与えるかどうかという運転上の問題ということも十分考えまして、さらにどのくらい利用するか、あるいは逆に国鉄の職員を何人かを置かなければならない。こういう商売上の計算をいたしました上で、先ほど申し上げましたような中間駅をつくるわけでございますが、いまの根岸線の新大船駅につきましては、実はそれどころの問題ではないわけでございまして、いま申し上げましたとおり、大船に入れるにいたしましても、どういうふうに入れるかということが一番大問題でございます。と申しますことは、一体横須賀線から横浜へじかに持っていけるようにすべきか、あるいは湘南地帯から横浜にじかに通えるようにするのか、あるいは根岸線の中間から逆に東京向けに入ったほうがいいか、いわゆるアプローチのつくり方が非常にむずかしい問題でございまして、これは部内でも実は数十回にわたって議論いたしました、いろいろ議論の出た結果、現時点におきましては、最重点の目的は、通勤輸送と貨物輸送であるということで、この貨物輸送の面から一番大事なことは、やはり東海道から横浜に向けて大船を経由してすぐ右に入ってスルーで――と申しますのは、大船駅でもって全然機関車のつけかえをしないでそのまま横須賀のほうに行ける、あるいは横浜からまっすぐ出てきたものはそのまま東海道に流せる、こういう入れ方が一番妥当であろうという結論に落ちついたわけでございます。それまでにいろいろ先ほど申しました議論があったと申しましたが、大体大ざっばに言って三つの案がございました。一つは、いまの最終案でございますが、なるべく北のほうから入ってきて、現在の東海道線と立体交差して大船駅のまん中に入る。そうして東海道の貨物線とつながるようにする、こういうものが最終案でございます。これは立体交差で東海道線をまたいでまいります。それには相当遠くから入ってこないと入らない。大船の駅から約一キロ半ほど北から回って入ってきます。その次は、それを考えないで、旅客輸送だけを考えて、いまの大船の駅の海側と申しますか、大船の撮影所寄りにまっすぐに入れる、こういう案がございました。これでございますと、いまのルートのずっと南に、ほとんど大船の駅に直角ではございませんが、直角に近いような形で入ってまいります。それからもう一つは、逆に南のほうから東京に向けて入ってくるというルートも考えたことがございます。こういったように、実に大船にどういう形で根岸線を入れるかということは、非常に私のほうの輸送プロパーの国鉄自体としての一番重要な問題として私自身参画して議論、検討した問題でございます。で、たまたまこの団地は三つのうちの一つの団地が一つの新しいルートの駅に非常に近いのでありますが、実は大船に笠間というところがございます。これは元海軍の火薬庫かなんかあったところであります。そこに戦争中から実は私のほうが土地を買いまして、約五十戸の宿舎と、それから百数十人入る独身寮とを持っておりました。その他買い上げの官舎等もぼつぼつございますが、笠間地区というのは二十数年前から国鉄職員が多数居住しておった地区でございます。これらの職員からいろいろな情報が入りまして、あの辺で土地が買えそうだ、この辺は土地が買えそうだということで土地をいろいろ物色しておったわけでございます。したがいまして、土地をほしいという考え方、これは大船地区なら大体いいだろう、東京にもそう遠くないし、どうやら通勤圏内でもちろんあるし、まあ、まだそのころは値段も高くないし、大船地区なら一応住宅地として適当だろうということで種々物色いたしました結果、この三つの土地を探したわけでございます。そうして、さっきるる申しました大船に入るルートが決定したのはやっと昨年の秋でございます。もちろんそのルートが決定いたさなければ、新駅はできないわけでございます。したがいまして、この大船の三つの団地はそれぞれ現在の大船駅から十五分ないし二十分、あるいは三十分以上離れております。これと、こういう団地のところにどこに駅をつくるか、あるいはどこを通るかという問題は、先ほどるる申しました大船の駅にどういう姿で根岸線を入れるかという根本問題に比べますれば、全く末梢の問題と言わざるを得ない問題で、このルート決定には、この共済組合がどこの土地を買ったということなどは全く頭に入れないで決定いたしました。その点は私自身が責任者としてこのルートを決定いたしたのでございますので、私自身種々検討いたしました結果、こういうふうにきまりました。この現在の場所の矢部野駅から、逆に申しますと大船から三・三キロの地点でございます。この地点は御承知のPXその他ございまして、わりに付近に人家もある、つくるならこの付近が一番適当だということで、建設公団と大船御当地の方々、国鉄と参画してつくったわけでございます。これは全くたまたまB団地の下にこれがあったということでございます。もしこれが私の申し上げましたとおり、北から東海道線に立体交差で入らないで、大船の撮影所のほうに線路を入れるとすれば、いまの線路からずっと一キロぐらい南を通ったであろうと、これは私の推測であります。北鎌倉から入れるとすれば、十キロぐらい南、北鎌倉の付近のトンネルを出たところぐらいで横須賀線に入るという形になっただろうと思います。したがいまして、私どもとしましてはたいへん申しわけないのですが、職員の団地をどこにするかということなどと全く無関係の国鉄のプロパーの、どうしたら一番輸送がよくて、どうしたら一番この新線の意義があがるかという角度からきめたものでございまして、私自身この問題に参画しましたときに、全く実はうかつなことながら、団地のあることを知らなかったということを、率直に私は申し上げさしていただきたいと思います。