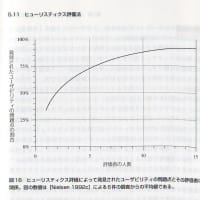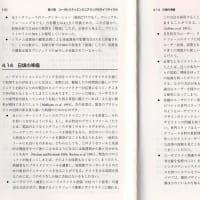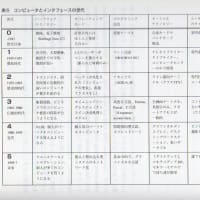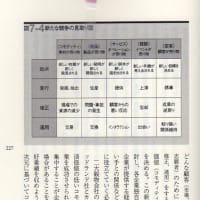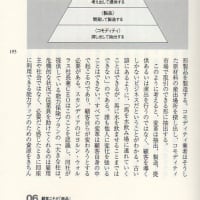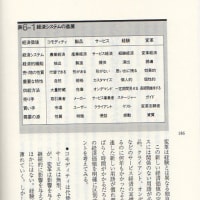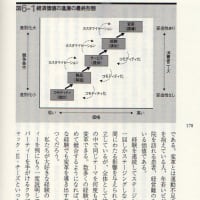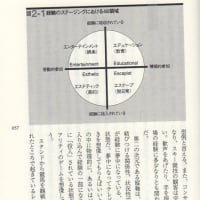ヴィゴツキー入門
http://book.akahoshitakuya.com/b/4901330608
WSDの講義で出てきた「発達の最近接領域」を提唱した、ヴィゴツキーの入門書。ヴィゴツキーの翻訳を多数手掛けているだけあって、訳者がヴィゴツキーの考え方に激しく同意していることが分かります。「発達の最近接領域」の理論 の概念を、ざっくり理解するにはお勧めの本です。
以下、抜粋■
○最初の知能年齢、つまり子どもが一人で解答する問題によって決定される「源下の発達水準」と、他人との協同のなかで問題を解く場合に到達する水準=「明日の発達水準との間の差異が、子どもの<発達の最近接領域>を決定する
・子どもは協同学習の中では、つねに自分一人でするときよりも多くのことをすることができる。
・周囲の子どもたちの考え方ややり方を見て学び、模倣することで、できないことができるようになる。
・「自分一人でもできる」ことから「自分一人ではできない」ことへ移行していく
○教授は、発達の前を進むときにのみよい教授である。そのとき教授は、成熟中の段階にあったり、<発達の最近接領域>にある、一連の機能を呼び起こし、活動させる。ここに、発達における教授の主要な役割がある。
○子どものことばの発達
#ことは=speech
自律的ことば・・・・<乳児期>・・・情動的交わり
↓
話しことば・・・・・<幼児期>・・・事物の性質の習得
↓
自己中心的ことば・・<就学前期>・・ごっこ遊び
↓
書きことば・・・・・<学童期>・・・知識の習得
↓
外国語の学習・・・・<思春期>・・・自分さがし
○ことばの発達
(1)ことばの初歩的・低次の特性の無自覚的習得から、言語の音声的構造や文法形式の自覚的使用へ発達するという法則
(2)「話しことばと書きことば」「生活的概念と科学的概念」「母国語と外国語」とのあいだには、相互関連があり、反対方向へと発達するという法則
○子どもの概念形成は、以下の3段階を経て到達する
第1段階 幼児の行動に見られるように、十分な内的関係なしに統合された「非組織的な未整理の集合」の形成、あるいは印象に基づいていくつかの事物を結びつける「混同性的な結合」の形成
第2段階 具体的事物のあいだに実際に存在する、客観的な結合に基づいて結びつけられた事物の複合による「複合的思考」の形成
第3段階 真の概念形成
○芸術教育の3つの課題
(1)創造性の教育
(2)芸術のあれこれの技術を教える教育
(3)美的鑑賞、すなわち芸術作品を知覚し、味わうことの教育
○障害の構造
「一次的障害(盲ろうなどの生物学的基礎を有する器質的障害)」と「二次的障害(一時的障害を基礎として社会的・集団的生活のなかで生じる障害)」とに分け、教育可能性がもっとも大きいのは、一次的障害への対策ではなくて、二次的障害(集団生活の改善)への対策であることを強調