前川佐美雄賞・ながらみ出版賞の授賞式がお茶の水のガーデンパレスで行われました。
選考委員は三枝昂之・佐々木幹郎・俵万智・加藤治郎・佐佐木幸綱。
「短歌往来」に掲載した小生の選評を採録しておきます。
「前川佐美雄賞」は、黒瀬珂瀾の歌集『蓮食ひ人の日記』に決定しました。サブタイトルに「イギリス歌日記十三ヵ月」とあるように、国際交流基金で二〇一一年二月半ばから十三ヶ月間、英国に滞在した折の歌日記という体裁をとっています。五年前、東日本大震災の年ですね。具体的な滞在地は、アイルランドのダブリン、そしてロンドン。
私は、その二十年ほど前、一九九二年から九三年にかけての一年間、オランダのライデン市隣のフォルスコーテンという町に住み、小学館「本」という雑誌に連載したその間の歌日記を『旅人』という歌集にまとめたことがありました。ですから、なんとなく親しい気持ちで『蓮食ひ人の日記』を読ませてもらいました。はじめて現地の医者に診察してもらうときの緊張感とか、近所の店とだんだんなじみになってゆく感覚とか、「わかるわかる」と思いながら、前書きや短歌を読んでゆきました。
もちろん事情がちがっている点もたくさんありました。私は、大学までの交通が不便だったし、子供の一人が現地校に通っていましたから、毎日、車に乗る生活でした。また、私はあまり日本人とつきあう機会がなかったのですが、この歌集では現地に日本人がかなり多くいるらしく、交流も多かったらしい。ダブリンでは香川ヒサさんが二日前に朗読したという店の前を通ったりもしています。
とくに二十年昔とはっきりちがうのは、ネット環境を含めて、電波事情がこすっかり変わり、日本が断然近くなったその距離感の変化です。
「この教会の鐘が聞こえる範疇で生まれた人を、生粋のロンドンつ子と呼ぶさうだ。」「12/18 エルゴのおんぶ紐を新調。登山リュックのやうなキャリアーで乳児を背負ふ父親は本当によく見かける。」
遠くまで来たのだ金正日の死が一面に配されざる程度には
教会の鐘、ロンドンのイクメン男性、二件を前書きに置いて、日本との心理的距離の近さをうたっているこの一首は印象的です。二十年前とは距離感がちがうなあ、そんな日本との距離のうたい方を楽しませてもらいました。
近現代短歌の外国詠は、最初、日本との大きな差異をうたうことにウェイトが置かれていたわけですが、だんだん近づき、この歌集ではもうその点はごくひかえ目にうたわれているにすぎません。外国詠がとっくに新しい段階に入っていたことを意識的に表に出している点が、この歌集の新しさでしょう。
その意味で、歌集のカバーに引用されている二首は象徴的です。スペースの関係で、前書きは略します。
明日へわれらを送る時間の手を想ふ寝台に児をそつと降ろせば
妻と児があれば吾など誰でもいいひかりを諾ひ生きゆかむかな
二首にはともに「児」が登場します。この歌集で目立つのは子供の歌が断然多い点です。私が最近読んだ歌集では一番多いと思います。大松達知君の「若山牧水賞」受賞歌集『ゆりかごのうた』が、イクメン歌集として話題になりましたが、この歌集の方が数は圧倒的に多い。
英国という場を前面に出すことで、イクメンの歌を新鮮な角度で照らし出した、そんな新しさに注目しました。
「ながらみ出版賞」は小川佳世子歌集『ゆきふる』に決まりました。
この歌集には、「臓器」「内蔵」「はらわた」といったドキッとするような用語がしばしば出てくるのにおどろかされます。たぶん、ぎりぎりのところまでを言葉にしようという並々でない作歌にかける思いが読みとれます。
ただ、歌集として見るとき、上記の用語が出てくるような、現実との接近戦を試みた作よりも、比喩やイメージの意外性で勝負した作に佳作が多いように思いました。
時々は滝もベッドに横たわりたいと思いはしないだろうか
延縄に懸かったような一日をせめて沈んだままで眠ろう




選考委員は三枝昂之・佐々木幹郎・俵万智・加藤治郎・佐佐木幸綱。
「短歌往来」に掲載した小生の選評を採録しておきます。
「前川佐美雄賞」は、黒瀬珂瀾の歌集『蓮食ひ人の日記』に決定しました。サブタイトルに「イギリス歌日記十三ヵ月」とあるように、国際交流基金で二〇一一年二月半ばから十三ヶ月間、英国に滞在した折の歌日記という体裁をとっています。五年前、東日本大震災の年ですね。具体的な滞在地は、アイルランドのダブリン、そしてロンドン。
私は、その二十年ほど前、一九九二年から九三年にかけての一年間、オランダのライデン市隣のフォルスコーテンという町に住み、小学館「本」という雑誌に連載したその間の歌日記を『旅人』という歌集にまとめたことがありました。ですから、なんとなく親しい気持ちで『蓮食ひ人の日記』を読ませてもらいました。はじめて現地の医者に診察してもらうときの緊張感とか、近所の店とだんだんなじみになってゆく感覚とか、「わかるわかる」と思いながら、前書きや短歌を読んでゆきました。
もちろん事情がちがっている点もたくさんありました。私は、大学までの交通が不便だったし、子供の一人が現地校に通っていましたから、毎日、車に乗る生活でした。また、私はあまり日本人とつきあう機会がなかったのですが、この歌集では現地に日本人がかなり多くいるらしく、交流も多かったらしい。ダブリンでは香川ヒサさんが二日前に朗読したという店の前を通ったりもしています。
とくに二十年昔とはっきりちがうのは、ネット環境を含めて、電波事情がこすっかり変わり、日本が断然近くなったその距離感の変化です。
「この教会の鐘が聞こえる範疇で生まれた人を、生粋のロンドンつ子と呼ぶさうだ。」「12/18 エルゴのおんぶ紐を新調。登山リュックのやうなキャリアーで乳児を背負ふ父親は本当によく見かける。」
遠くまで来たのだ金正日の死が一面に配されざる程度には
教会の鐘、ロンドンのイクメン男性、二件を前書きに置いて、日本との心理的距離の近さをうたっているこの一首は印象的です。二十年前とは距離感がちがうなあ、そんな日本との距離のうたい方を楽しませてもらいました。
近現代短歌の外国詠は、最初、日本との大きな差異をうたうことにウェイトが置かれていたわけですが、だんだん近づき、この歌集ではもうその点はごくひかえ目にうたわれているにすぎません。外国詠がとっくに新しい段階に入っていたことを意識的に表に出している点が、この歌集の新しさでしょう。
その意味で、歌集のカバーに引用されている二首は象徴的です。スペースの関係で、前書きは略します。
明日へわれらを送る時間の手を想ふ寝台に児をそつと降ろせば
妻と児があれば吾など誰でもいいひかりを諾ひ生きゆかむかな
二首にはともに「児」が登場します。この歌集で目立つのは子供の歌が断然多い点です。私が最近読んだ歌集では一番多いと思います。大松達知君の「若山牧水賞」受賞歌集『ゆりかごのうた』が、イクメン歌集として話題になりましたが、この歌集の方が数は圧倒的に多い。
英国という場を前面に出すことで、イクメンの歌を新鮮な角度で照らし出した、そんな新しさに注目しました。
「ながらみ出版賞」は小川佳世子歌集『ゆきふる』に決まりました。
この歌集には、「臓器」「内蔵」「はらわた」といったドキッとするような用語がしばしば出てくるのにおどろかされます。たぶん、ぎりぎりのところまでを言葉にしようという並々でない作歌にかける思いが読みとれます。
ただ、歌集として見るとき、上記の用語が出てくるような、現実との接近戦を試みた作よりも、比喩やイメージの意外性で勝負した作に佳作が多いように思いました。
時々は滝もベッドに横たわりたいと思いはしないだろうか
延縄に懸かったような一日をせめて沈んだままで眠ろう




















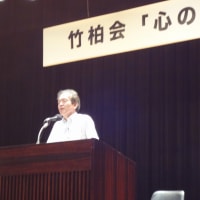


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます