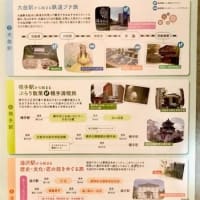駅案内所からこんにちは シズシズです
シズシズです
今日は、後三年合戦歴史探訪ツアーの後編をお届け

後半はいよいよ後三年合戦の最終決戦場である、金沢柵に向います。
と、その前に、ここで後三年合戦について、おさらいをしていきましょう(私のためにも)


事件は、今から900年ほど前、平安時代末期、北東北一帯を支配する清原氏に後継者争いが勃発したことから始まります。
清原氏に養子に入っていた清衡と異父弟の家衡との間で戦いが起こると、清衡には陸奥守源義家、家衡には叔父の武衡が加勢。
家衡は沼の柵・金沢の柵と転戦しますが、義家らの攻撃により武衡とともに討たれ、戦いは終わりました。
これを「後三年の役」と呼びます
さて、その家衡が沼の柵から転戦してこもった金沢柵(金沢城跡)からご紹介しましょう

金沢柵(金沢城跡)は現在、金沢公園内にあり、散歩やハイキングコースとして人気のスポットです
非常に険しい山城で、頂上部の標高は172m、麓との標高差は約90mにも達するそうです


散策を開始すると、見事な杉並木が

しばらく行くと・・・

すっごい大きい杉の幹がありました

これは「兜杉」と呼ばれ、根周り7.45m、樹高26mもあり、樹齢はおよそ900年とも伝えられています
また、義家が凱旋のとき自身の愛用の兜を埋めて、そのそばに記念のために清衡が植えた杉であるともいわれているそうですよ

ちなみに、昭和58年に失火によって焼失するまでは、横手市の天然記念物に指定されていました
そしてもう少し進むと・・・

金沢八幡宮にたどり着きます
こちらは、後三年合戦終了後に義家が清衡に命じて創建させた、歴史のある神社です
そしてこちら、金沢八幡宮の右手側から登っていくとあるのが「本丸」といわれている広場。

昭和39年から46年まで4回にわたり行われた発掘調査において、中央部の地下1.5m付近より、12世紀(平安時代末期・奥州藤原氏の時代)の白磁碗片2点が出土しました。
2点とも現在の中国で焼かれたもので、非常に高価なものであることから、後三年合戦後にも、高価な輸入陶磁器を所有できる勢力が近隣に拠点を構えていたと考えられています
城跡の麓に立地しているこちらは、景正功名塚。

これまた大きい杉の切り株です

合戦時、源義家の軍勢に加わっていた鎌倉権五郎景正が、義家の命を受けて戦死者を弔うために作った塚、という伝説があるところです
こちらも昭和23年に火災にあい、幹だけを残して焼失してしまいました

次に訪れたのは後三年の役金沢資料館です


こちらは、後三年合戦に関する資料館で、明治~昭和初期の画家・戎谷南山(えびすやなんざん)の模写による「後三年合戦絵詞」などを中心に収蔵、展示されています
ちなみに、先ほど金沢柵の本丸で出土した12世紀の白磁碗片2点もこちらで展示されていました

そして、ツアーの最後に訪れたのが蛭藻沼(びるもぬま)

ここは金沢柵陥落の際、逃げ延びた武衡が潜んでいましたが、雁の群れが驚いて飛び立ったことにより、義家軍に発見されたという伝承がある沼です
また、
“江戸時代に目の不自由な法師がこの沼の周辺で武士のような人物に呼び止められ、屋敷のような場所で「奥州後三年記」を語ったが、武衡がこの沼に潜み発見されたくだりで突然怒鳴りつけられ、気を失って翌朝になったらただの野原に倒れていた”
という伝説もあり、「嗤い沼」とも呼ばれているそうです
さて、ちょっと最後は怖い話をご紹介してしまいましたが、これで後三年合戦歴史探訪ツアー後編も終了です

今回、後三年の役という凄惨な戦いを改めて学び、私たちがしっかりと歴史と向き合い語り継ぐことが一番の供養になるのではないか、と思いました。
横手市の観光案内人として、これからももっちと一緒にたくさんのことを学んで行こうと決意を新たにしたシズシズでした
■後三年の役金沢資料館
開 館:時~午後4時30分
休刊日:毎週月曜日(祝日のときは翌日)、年末年始
入館料:大人100円(中学生以下無料)