内田樹著『街場の文体論』(ミシマ社、1600+税、単行本)
何回も読んだので本が汚くなった。丸善のブックカバーは破れてるし、これじゃブクオフも買い取らない。本が限界なのだ。そろそろ、ちょっとした感想をまとめよう。自分の記憶を助けるために。
これは書評じゃない。要約したり、賞賛や批判を与えたりしないのだが、ただ本書のテーマは明確に要約できる。「生成的な言葉とは何か?」である。著者が述べているので間違いない。本書では、このテーマをめぐって、さまざまトピックが語れられているとも。超楽チンw
感激したのは、何と言っても「エクリチュール」を語った部分だ(第7講p115-160)。ロラン・バルトが「ラング」「スティル」とともに提出した言語の概念で、日本のバルト読者は翻訳の少なさもあってか、さまざまに解釈したまま放置してきた印象がある。
バルトの概念のうち「ラング」は母語を、「スティル」は個人に形成された言語の趣向を表わす。「エクリチュール」は、ヤクザ、ヤンキーに典型的にみられる社会的ふるまいに属した言語現象である。お気づきのように、ラングとスティルはほとんど無意識の層に形成される。
一方、エクリテュールは少し複雑である。特定の母語(ラング)による会話や叙述の表面的な特徴は、ふるまいとしてのエクリテュールである。もちろんスティルも現れるが、むしろ選ばれない単語や文の長短、採用されない文体など、もっと控えめに作用する。
スティルとエクリチュールは重なりあう部分もあるが、これは実相の分類一般が抱える困難だろう。スティルは無意識の領域に形成されるため、個人の意識では変質しにくい。一方、エクリチュールは社会的なふるまいであり、かなり意識的に選び取られる違いがある。
ひとつのエクリチュールが個人の性格にくい込み、新しいエクリチュールの下でもスティルの構成要素として作用する場合もあるだろう。また選択されたエクリチュールは、使い慣れるにつれ、次第に無意識化していくだろう。このように、分類は一般に困難を抱える。
内田先生によると、フランス語のエクリチュールは階層社会を強烈に表している。そのため、むしろ階層の限定と固定化に寄与しているという。これは欧米一般の傾向らしい。なので、ロラン・バルト(仏)はゼロ度のエクリチュールを志向して、『異邦人』(カミュ)の「透明な言葉づかい」(p145)を高く評価した。
しかしバルトによる言語の諸相分類は、人類の暗い未来を予言するかのようである。本書をめぐる「生成的な言葉」など、考える意味もないかのように見えてくる。
なぜなら、三層に重なる言語諸相は、どれもこれも現実に生きる人間にたいする牢獄だからだ。人間は言語の操り人形であり、真理や理想に近づくなどは儚い夢。過去のようにいがみ合って殺戮を繰り返し、ただ滅亡へと転落していくのか。うつし世は地獄か。
思い出した。バルトはたしかスティルを楔にたとえ、言語の諸相にたいして垂直に作用すると説明していたはずだ。なおさら言語の相は単一で取り出すわけにはいかない。と、これは分類が困難だという感想の補足。
バルトは、言語の自由をエクリチュールに求めたかも知れない。その企ては成功したといえない。そのためか晩年、あまりエクリチュールについては語らなくなった印象がある。そのかわり、不思議なことを述べた。
彼のテクスト論の中心をなす「作者の死」である。従来のテクスト論は、その中心を「作者」に置いてきた。なにかの意図、思い、考えをもった作者がそのテクストをつくったのであり、したがって読書とは作者の意図を読み取ること、などが従来の結論。
これをバルトは、あたかも作者を神と位置づけ、読者をしもべ扱いする神学だと考え、拒否する。ではテクストと作者の関係は?「テクストは終わることのない絡み合いを通じて、自らを生成し、自らを織り上げていく・・・。この織物・・・のうちに呑み込まれて、主体は解体する(『テクストの快楽』)」(p196-7)。
テクストが果てしなくテクストを生成し、自ら織り上げ、そのなかに作者が占める位置はないと。この織物は書物だけではなく、会話、映画、アニメ、音楽など、さまざまな文化を縦糸、横糸にして織りつづけられるだろう。
神のご意思は理解しにくい。これを理解して万民に聴かせるのは、アブラハムやモーゼのような預言者たち、ザビエルら使徒や宣教師たちである。そして、作者にたいしては批評家と一部の熱心な読者だった。
この感想も、著者の思想を探り当て解説を試みていない。こんな感じの本って紹介が第一の目的で、次にだんだんファンになってきたミシマ社への応援と、自分の記憶補助のつもりだったけど。いまでは部分的な精読をとおして、自分なりに言語を再考するのが目的。
テクストの自動生成と作者の死について、著者は述べる。バルトによれば、作者の意図と読者の読みは、書かれるテクストの「いちばん最後に、テクストの派生物として創りだされる」(p199)。
とりあえず「作者の死」の説明として、著者は読者(聴衆)の感性・直感に訴えようとする。その方法は、昔から「ダイモニオン」(ソクラテス)「詩神(ミューズ)」「霊感」と呼ばれてきた比喩に近い(p203)。ラカンも引用される。「私が語っているときに私が語っているものは他者である」(同上)。
著者の内田樹氏は多作な著述家のお一人だが、書く体験は「誰かが耳に言葉を吹き込んでくる」受動的な体験だとお述べになる(同上)。ますます話は不思議になってきた、ってうかSF。この銀河系で、地球の生物以外に生命が発見されたから不思議なんてないのか。
このダイモニオン(ソクラテス)や詩神(ミューズ)、霊感を論理の文脈に乗せる方法として、著者はふたたびラカンを援用する。言葉の習得段階、とりわけ人間の鏡像段階(ラカン)を振り返る。
詳しくは読んでいただいてからになるが。文字や言葉は、ヘンテコな音声とか謎の記号として、意味不明の中身がない容器として、人間の身体に流れ込んでくる。これに中身を意味を与えるのは、家族や友人、教師etcになるが、その大枠は民族史そのものである。
幼児期から習得される言葉を、パパ・ママなどの単語から文、文脈、著述、文化へと演繹したところに、バルトのテクスト論が見えてくる。ラカンの言葉やミューズの意味が理解される。そっと言葉を吹き込まれる著者の受動的体験を、こちらも追体験できそうになる。
あるとき、ある場所で、文筆家は「糸口」をみつけるのだ。そこから織物に横糸の数本を織り加えるが、誰にも気づかれないまま、1000年後に古文書として発掘される場合もあるだろう。こうした無数の織物が果てもなく生まれ、つながり、色鮮やかな民族史を形づくっていく。
幼児は織りなされる民族史を呼吸し、言葉を習得し、成長して1、2本の横糸を通してみる。こうして果てもなく織りつづけられる民族史のなかで、個々の作家は溶解していく。これが「作者の死」ではないか。
こうしてミューズの正体は暴かれる。言葉をささやかれる体験の受動性が明らかになる。「作家の死」は出版不況やデフレ不況に迎合した「作家不要論」ではない。読者の復権をあおる単純な「読者論」でもない。「私が語っているときに私が語っているものは他者である」。
この言語の織物論には問題が残る。ひとつ目は、エクリチュールのオリジナリティーである。膨大な民族史に糸の一筋として織り加えられるだけなら、次々と新しい面が生まれる理由が説明できない。なぜミューズのささやきは常に新しいのか。
いつごろからか、織物がベルトコンベア化しているかもしれない。つぎつぎ織物は新しく更新されるように見えても、同じ模様が繰り返されるだけって事態もイメージできる。このイメージをどうやって打ち破るか。
この問題の決着は、とくに生成的な言葉をメインテーマとする本書にとって死活的に重要である。これを内田先生は「クリシェ」の問題としてとらえる。クリシェと生成的な言葉の関係は何か。しかし、過激な読者の期待に反して、劇的な関係が語られるわけじゃない。
クリシェは常套句、使い古されたエクリチュールである。私たちはクリシェの監獄にとらえられている。幼児の成長からわかる、言葉は外からやってくる。言葉の音声も意味も適切な反応も、なにもかもが。クリシェは幼児が生き抜くために必要な道具だった。
天空から幼児に吊りさげられた一本の命綱、クリシェが、その後の幼児のすべてを作り上げていったのは驚きだ。その言葉で考え、行動を起こし、やがて彼に見える世界が習熟した言葉によって構成されていく。太古より彩られた民族史に、幼児の全身が染め上げられていく。
「肩が凝る」と言い出してからは、もう日本語は道具じゃない。背中が痛い欧米人とは異なる民族のなかに彼は捕捉されている。こうして、彼は民族的なクリシェの牢獄につながれ、閉じ込められる。
動物の身体ですらDNAによって支配され、人間同士からは人間しか生まれてこないので、私たちはお決まりの定めを生きて死んでいくだけではないか。「生成的な言葉」なんて、あの星がほしいと手をのばした幼児の夢にすぎないのではないか。
こうした人間観をベルトコンベア式人間観とでも呼んでおこう。太古より回転する長大なコンベアのうえで、人間が組み立てられ、雌雄別にラング別に仕分けされ、運ばれ、パッキングされて死の世界へと流れ去っていく。こんなイメージすら太古から繰り返されたクリシェなんだろうか。ところが著者は、異なる次元の考えを述べる。
どうしても逃れられないものからの脱出の方法を著者は考える。まず、十分にクリシェと民族史を利用する。そのうえで破格と逸脱を目論むのだと。なんだ、これが結論かと、お怒りになる読者もいるだろう。だが、これが失敗を避けて進む正攻法であることに異論はないはずだ。
孵化にも共通する方法である。親から与えられる卵を十分に利用して成長し、やがて殻を突き破る孵化の工程。それでも説明不足とお考えの読者は、デリダらの脱構築を思い出せ。本歌取りしつつ、やがて本歌の本質から脱皮する脱構築。脱出不可能にみえる我が民族史から自由を得る方法だ。
話のテーブルを覆すようだが、しかし、どんな言葉を述べればいいのか。日本語を脱臼させるための戯言を並べるか。それもひとつの方法だが、「生成的な言葉」を戯言の騒ぎに貶めるだけなら、世界の先はゾンビの祭典だ。
どんな言葉をという問いにたいして、まず著者は生成的な言葉が生まれる条件を考える。「外に向かう言葉」であると。できるだけ多くの人々に正確に伝えたい、切迫した必死の言葉が前提条件であると。
対して狭い集団内にだけ流通させる、自分の利益のための言葉が「内向きの言葉」である(p284-285)。では、できるだけ多くの人に届けと願う切迫した言葉は、もっと具体的には、どんなミューズのささやきとなって耳に届くのか。
ここで、内田先生は村上春樹氏をとりあげる。もうひとつの言語論ともいうべき村上氏の考えは、イスラエルで行った演説、エルサレム賞の授賞式でのスピーチを通して、国民に広く知られたはずだ。http://ameblo.jp/nattidread/entry-11346558241.html …
上にあげたリンクは優れた翻訳のひとつであり、そこでは奇妙にも、村上氏は自分の父親を語りだす。「私の父は昨年、90歳で亡くなりました。京都の大学院生だったとき、徴兵され、中国の戦場に送られ」た。亡くなると同時に「私が決して知り得ない記憶も一緒に持っていっ」たと。
「しかし、父の周辺に潜んでいた死という存在が記憶に残っています」、これは「最も重要なことの一つです」と書き添える。この点について内田氏は、「言葉や思想を紡いでいく基本にあるものは、かたちあるものではない」と解説する。これが村上氏を代表とする、もうひとつの言語論である。
村上言語論では、意味や修辞法などの表面的な言語の態様から離れ、言語を超えたメタメッセージについて考えられている。フロイトの意識・無意識の二重構造を彷彿とさせるので、考えやすいかも知れない。
著者は「言葉というものは、『言葉にならないもの」をいわば母胎として、そこから生成してくる」。「そこから発してくる言葉だけがほんとうに深いところで人をゆさぶる」と述べている。言葉にならないものを「魂」「ソウル」「生身」とかいうらしい(p292-293)。
自分が幼少期に受けた外傷、立ち直れない衝撃など、言葉にできない経験をトラウマと呼ぶ。しかし、ここでは死者から生者に伝達される経験、生者が経験できなかった記憶、本来的に欠損状態にある記憶について語られている(p293)。一体、そんなものがありえるのか。
死者から生者に伝達された経験の存在を理解するためには、バルトが示した「作者の死」、あるいは文化の織物に戻ってみるのも、多くの読者にとって早道かもしれない。そこには、明らかに膨大な死者から生者への伝達があるのだから。
したがって、私たちの無意識は、死者たちが経験した記憶によっても構成されている。この知識は衝撃的だ。なぜなら、現代社会は生者のために生者が作った社会であると見なされがちだからである。過去の遺物など破壊の対象でしかないとばかりに。
感想の文脈にもどると、生者は死者から「言葉にならない」ものを手渡される。「響きや波動や震えとか、そういうような非言語的な形態」で、死者から手渡された「言葉にならない」魂や生身といわれるものから生成される言葉が、多くの人々に響き届く言葉ではないか、と内田先生は結論的にお述べになる。
「そのような言葉だけが他者に届く」。「それは『言葉を経由しては手渡すことができない』という欠性的な様態で、『どうしてもそれについて直接語ることができない』不能の態様で」他者に伝わる(p293-294)。
「見知らぬ他者の、死者の記憶」がざわめき、「ある種の波動のような形で残」る「死者たちの記憶」が「僕たちの『ソウル』をかたちづく」る。そこから「他者に届く言葉が不断に生成している」のではないかと(p294)。
<了>
何回も読んだので本が汚くなった。丸善のブックカバーは破れてるし、これじゃブクオフも買い取らない。本が限界なのだ。そろそろ、ちょっとした感想をまとめよう。自分の記憶を助けるために。
これは書評じゃない。要約したり、賞賛や批判を与えたりしないのだが、ただ本書のテーマは明確に要約できる。「生成的な言葉とは何か?」である。著者が述べているので間違いない。本書では、このテーマをめぐって、さまざまトピックが語れられているとも。超楽チンw
感激したのは、何と言っても「エクリチュール」を語った部分だ(第7講p115-160)。ロラン・バルトが「ラング」「スティル」とともに提出した言語の概念で、日本のバルト読者は翻訳の少なさもあってか、さまざまに解釈したまま放置してきた印象がある。
バルトの概念のうち「ラング」は母語を、「スティル」は個人に形成された言語の趣向を表わす。「エクリチュール」は、ヤクザ、ヤンキーに典型的にみられる社会的ふるまいに属した言語現象である。お気づきのように、ラングとスティルはほとんど無意識の層に形成される。
一方、エクリテュールは少し複雑である。特定の母語(ラング)による会話や叙述の表面的な特徴は、ふるまいとしてのエクリテュールである。もちろんスティルも現れるが、むしろ選ばれない単語や文の長短、採用されない文体など、もっと控えめに作用する。
スティルとエクリチュールは重なりあう部分もあるが、これは実相の分類一般が抱える困難だろう。スティルは無意識の領域に形成されるため、個人の意識では変質しにくい。一方、エクリチュールは社会的なふるまいであり、かなり意識的に選び取られる違いがある。
ひとつのエクリチュールが個人の性格にくい込み、新しいエクリチュールの下でもスティルの構成要素として作用する場合もあるだろう。また選択されたエクリチュールは、使い慣れるにつれ、次第に無意識化していくだろう。このように、分類は一般に困難を抱える。
内田先生によると、フランス語のエクリチュールは階層社会を強烈に表している。そのため、むしろ階層の限定と固定化に寄与しているという。これは欧米一般の傾向らしい。なので、ロラン・バルト(仏)はゼロ度のエクリチュールを志向して、『異邦人』(カミュ)の「透明な言葉づかい」(p145)を高く評価した。
しかしバルトによる言語の諸相分類は、人類の暗い未来を予言するかのようである。本書をめぐる「生成的な言葉」など、考える意味もないかのように見えてくる。
なぜなら、三層に重なる言語諸相は、どれもこれも現実に生きる人間にたいする牢獄だからだ。人間は言語の操り人形であり、真理や理想に近づくなどは儚い夢。過去のようにいがみ合って殺戮を繰り返し、ただ滅亡へと転落していくのか。うつし世は地獄か。
思い出した。バルトはたしかスティルを楔にたとえ、言語の諸相にたいして垂直に作用すると説明していたはずだ。なおさら言語の相は単一で取り出すわけにはいかない。と、これは分類が困難だという感想の補足。
バルトは、言語の自由をエクリチュールに求めたかも知れない。その企ては成功したといえない。そのためか晩年、あまりエクリチュールについては語らなくなった印象がある。そのかわり、不思議なことを述べた。
彼のテクスト論の中心をなす「作者の死」である。従来のテクスト論は、その中心を「作者」に置いてきた。なにかの意図、思い、考えをもった作者がそのテクストをつくったのであり、したがって読書とは作者の意図を読み取ること、などが従来の結論。
これをバルトは、あたかも作者を神と位置づけ、読者をしもべ扱いする神学だと考え、拒否する。ではテクストと作者の関係は?「テクストは終わることのない絡み合いを通じて、自らを生成し、自らを織り上げていく・・・。この織物・・・のうちに呑み込まれて、主体は解体する(『テクストの快楽』)」(p196-7)。
テクストが果てしなくテクストを生成し、自ら織り上げ、そのなかに作者が占める位置はないと。この織物は書物だけではなく、会話、映画、アニメ、音楽など、さまざまな文化を縦糸、横糸にして織りつづけられるだろう。
神のご意思は理解しにくい。これを理解して万民に聴かせるのは、アブラハムやモーゼのような預言者たち、ザビエルら使徒や宣教師たちである。そして、作者にたいしては批評家と一部の熱心な読者だった。
この感想も、著者の思想を探り当て解説を試みていない。こんな感じの本って紹介が第一の目的で、次にだんだんファンになってきたミシマ社への応援と、自分の記憶補助のつもりだったけど。いまでは部分的な精読をとおして、自分なりに言語を再考するのが目的。
テクストの自動生成と作者の死について、著者は述べる。バルトによれば、作者の意図と読者の読みは、書かれるテクストの「いちばん最後に、テクストの派生物として創りだされる」(p199)。
とりあえず「作者の死」の説明として、著者は読者(聴衆)の感性・直感に訴えようとする。その方法は、昔から「ダイモニオン」(ソクラテス)「詩神(ミューズ)」「霊感」と呼ばれてきた比喩に近い(p203)。ラカンも引用される。「私が語っているときに私が語っているものは他者である」(同上)。
著者の内田樹氏は多作な著述家のお一人だが、書く体験は「誰かが耳に言葉を吹き込んでくる」受動的な体験だとお述べになる(同上)。ますます話は不思議になってきた、ってうかSF。この銀河系で、地球の生物以外に生命が発見されたから不思議なんてないのか。
このダイモニオン(ソクラテス)や詩神(ミューズ)、霊感を論理の文脈に乗せる方法として、著者はふたたびラカンを援用する。言葉の習得段階、とりわけ人間の鏡像段階(ラカン)を振り返る。
詳しくは読んでいただいてからになるが。文字や言葉は、ヘンテコな音声とか謎の記号として、意味不明の中身がない容器として、人間の身体に流れ込んでくる。これに中身を意味を与えるのは、家族や友人、教師etcになるが、その大枠は民族史そのものである。
幼児期から習得される言葉を、パパ・ママなどの単語から文、文脈、著述、文化へと演繹したところに、バルトのテクスト論が見えてくる。ラカンの言葉やミューズの意味が理解される。そっと言葉を吹き込まれる著者の受動的体験を、こちらも追体験できそうになる。
あるとき、ある場所で、文筆家は「糸口」をみつけるのだ。そこから織物に横糸の数本を織り加えるが、誰にも気づかれないまま、1000年後に古文書として発掘される場合もあるだろう。こうした無数の織物が果てもなく生まれ、つながり、色鮮やかな民族史を形づくっていく。
幼児は織りなされる民族史を呼吸し、言葉を習得し、成長して1、2本の横糸を通してみる。こうして果てもなく織りつづけられる民族史のなかで、個々の作家は溶解していく。これが「作者の死」ではないか。
こうしてミューズの正体は暴かれる。言葉をささやかれる体験の受動性が明らかになる。「作家の死」は出版不況やデフレ不況に迎合した「作家不要論」ではない。読者の復権をあおる単純な「読者論」でもない。「私が語っているときに私が語っているものは他者である」。
この言語の織物論には問題が残る。ひとつ目は、エクリチュールのオリジナリティーである。膨大な民族史に糸の一筋として織り加えられるだけなら、次々と新しい面が生まれる理由が説明できない。なぜミューズのささやきは常に新しいのか。
いつごろからか、織物がベルトコンベア化しているかもしれない。つぎつぎ織物は新しく更新されるように見えても、同じ模様が繰り返されるだけって事態もイメージできる。このイメージをどうやって打ち破るか。
この問題の決着は、とくに生成的な言葉をメインテーマとする本書にとって死活的に重要である。これを内田先生は「クリシェ」の問題としてとらえる。クリシェと生成的な言葉の関係は何か。しかし、過激な読者の期待に反して、劇的な関係が語られるわけじゃない。
クリシェは常套句、使い古されたエクリチュールである。私たちはクリシェの監獄にとらえられている。幼児の成長からわかる、言葉は外からやってくる。言葉の音声も意味も適切な反応も、なにもかもが。クリシェは幼児が生き抜くために必要な道具だった。
天空から幼児に吊りさげられた一本の命綱、クリシェが、その後の幼児のすべてを作り上げていったのは驚きだ。その言葉で考え、行動を起こし、やがて彼に見える世界が習熟した言葉によって構成されていく。太古より彩られた民族史に、幼児の全身が染め上げられていく。
「肩が凝る」と言い出してからは、もう日本語は道具じゃない。背中が痛い欧米人とは異なる民族のなかに彼は捕捉されている。こうして、彼は民族的なクリシェの牢獄につながれ、閉じ込められる。
動物の身体ですらDNAによって支配され、人間同士からは人間しか生まれてこないので、私たちはお決まりの定めを生きて死んでいくだけではないか。「生成的な言葉」なんて、あの星がほしいと手をのばした幼児の夢にすぎないのではないか。
こうした人間観をベルトコンベア式人間観とでも呼んでおこう。太古より回転する長大なコンベアのうえで、人間が組み立てられ、雌雄別にラング別に仕分けされ、運ばれ、パッキングされて死の世界へと流れ去っていく。こんなイメージすら太古から繰り返されたクリシェなんだろうか。ところが著者は、異なる次元の考えを述べる。
どうしても逃れられないものからの脱出の方法を著者は考える。まず、十分にクリシェと民族史を利用する。そのうえで破格と逸脱を目論むのだと。なんだ、これが結論かと、お怒りになる読者もいるだろう。だが、これが失敗を避けて進む正攻法であることに異論はないはずだ。
孵化にも共通する方法である。親から与えられる卵を十分に利用して成長し、やがて殻を突き破る孵化の工程。それでも説明不足とお考えの読者は、デリダらの脱構築を思い出せ。本歌取りしつつ、やがて本歌の本質から脱皮する脱構築。脱出不可能にみえる我が民族史から自由を得る方法だ。
話のテーブルを覆すようだが、しかし、どんな言葉を述べればいいのか。日本語を脱臼させるための戯言を並べるか。それもひとつの方法だが、「生成的な言葉」を戯言の騒ぎに貶めるだけなら、世界の先はゾンビの祭典だ。
どんな言葉をという問いにたいして、まず著者は生成的な言葉が生まれる条件を考える。「外に向かう言葉」であると。できるだけ多くの人々に正確に伝えたい、切迫した必死の言葉が前提条件であると。
対して狭い集団内にだけ流通させる、自分の利益のための言葉が「内向きの言葉」である(p284-285)。では、できるだけ多くの人に届けと願う切迫した言葉は、もっと具体的には、どんなミューズのささやきとなって耳に届くのか。
ここで、内田先生は村上春樹氏をとりあげる。もうひとつの言語論ともいうべき村上氏の考えは、イスラエルで行った演説、エルサレム賞の授賞式でのスピーチを通して、国民に広く知られたはずだ。http://ameblo.jp/nattidread/entry-11346558241.html …
上にあげたリンクは優れた翻訳のひとつであり、そこでは奇妙にも、村上氏は自分の父親を語りだす。「私の父は昨年、90歳で亡くなりました。京都の大学院生だったとき、徴兵され、中国の戦場に送られ」た。亡くなると同時に「私が決して知り得ない記憶も一緒に持っていっ」たと。
「しかし、父の周辺に潜んでいた死という存在が記憶に残っています」、これは「最も重要なことの一つです」と書き添える。この点について内田氏は、「言葉や思想を紡いでいく基本にあるものは、かたちあるものではない」と解説する。これが村上氏を代表とする、もうひとつの言語論である。
村上言語論では、意味や修辞法などの表面的な言語の態様から離れ、言語を超えたメタメッセージについて考えられている。フロイトの意識・無意識の二重構造を彷彿とさせるので、考えやすいかも知れない。
著者は「言葉というものは、『言葉にならないもの」をいわば母胎として、そこから生成してくる」。「そこから発してくる言葉だけがほんとうに深いところで人をゆさぶる」と述べている。言葉にならないものを「魂」「ソウル」「生身」とかいうらしい(p292-293)。
自分が幼少期に受けた外傷、立ち直れない衝撃など、言葉にできない経験をトラウマと呼ぶ。しかし、ここでは死者から生者に伝達される経験、生者が経験できなかった記憶、本来的に欠損状態にある記憶について語られている(p293)。一体、そんなものがありえるのか。
死者から生者に伝達された経験の存在を理解するためには、バルトが示した「作者の死」、あるいは文化の織物に戻ってみるのも、多くの読者にとって早道かもしれない。そこには、明らかに膨大な死者から生者への伝達があるのだから。
したがって、私たちの無意識は、死者たちが経験した記憶によっても構成されている。この知識は衝撃的だ。なぜなら、現代社会は生者のために生者が作った社会であると見なされがちだからである。過去の遺物など破壊の対象でしかないとばかりに。
感想の文脈にもどると、生者は死者から「言葉にならない」ものを手渡される。「響きや波動や震えとか、そういうような非言語的な形態」で、死者から手渡された「言葉にならない」魂や生身といわれるものから生成される言葉が、多くの人々に響き届く言葉ではないか、と内田先生は結論的にお述べになる。
「そのような言葉だけが他者に届く」。「それは『言葉を経由しては手渡すことができない』という欠性的な様態で、『どうしてもそれについて直接語ることができない』不能の態様で」他者に伝わる(p293-294)。
「見知らぬ他者の、死者の記憶」がざわめき、「ある種の波動のような形で残」る「死者たちの記憶」が「僕たちの『ソウル』をかたちづく」る。そこから「他者に届く言葉が不断に生成している」のではないかと(p294)。
<了>












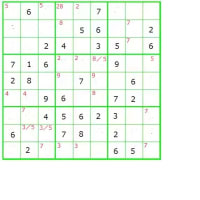
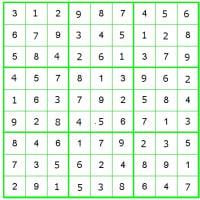
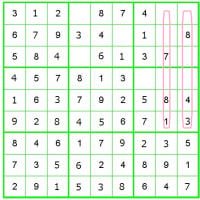
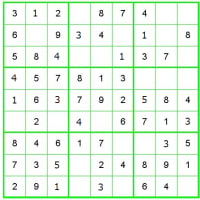
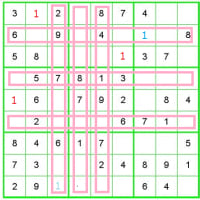
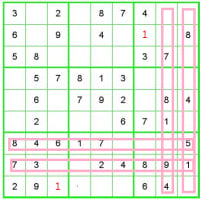
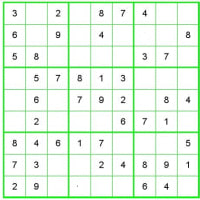

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます