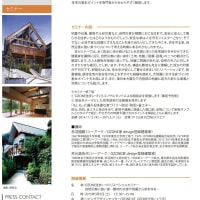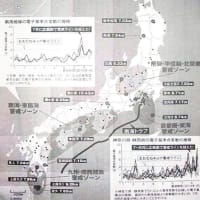子供の皮膚感覚が大人とは違う。こんな意味にとれる記述に出会ったとき、釈然としなかった様々なことが一気に納得いったような気分になり、しばらくの間本当はどうなんだ、実際に自分の子供時代の記憶や人の意見で自分を納得させるための方策にいそしんでいたそれも楽しみつつ、しかもわくわくしながら探求していた。その文章とは中川織江さんの<粘土遊びの心理学 ヒトがつくる、チンパンジーがこねる>(風間書房)
子供は平気で虫(たとえばミミズ)をつかむ、大人はそれができない。こどもは平気で人の顔をさわりにくる、おとなはそれはできない。単純に知識や経験が増えるからできること、できないことを頭で理解して自分の行動を規制しているのか?それにしてはさわるのが気持ち悪いなどの感覚がどうしても納得いかない。五感の中で皮膚感覚についても食感と同様に好き嫌いが様々ではあるし、大人になって変わっていくという点でもよく似ている。しかしその変化の課程は自分の経験ではミミズを何匹も手に持って釣りなどしていたし、蜂の子やトンボなどと何も考えずに一緒に遊んだことも今ではコンポストのミミズですら初めはこわごわ触るというようなことが当たり前のことに対し、食べ物は好き嫌いがもともとなかったせいか、あまり変わってはいない。いったい何で同じヒトにこのようなことが起きるのか?
この本の解説写真の中に子供が粘土に指をつっこんだいたり、粘土にお腹をつけて腹ばいになったり、枕にして寝ていたり、お面のように顔にぴったりつけて遊んでいたりする図をみて大人は滅多にやらないナーという感想を持ちつつ文章を読むと子供は<かたまりのなかに腕や手をつっ込むなど、対象のなかに自分の体をめり込ませるのは「触覚そのもの」世界で><私たちの体は厚みと丸みと暖かさを持ち、三次元の世界のものに触れ、実感して生きています。ヒトの体は{もの}ではなく、{知覚の相対}です。自分の体と外界の境がはっきりしている大人と違って、子どもはまだ自分の体の境界がはっきりしていません、><体の発達が未分化な子どもは、身体感覚を発達させ安定させるために、あらゆる知覚刺激を求めています。>。。。。自分の体の境界がはっきり自覚できないヒト、外見上は体があっても本人の感覚では雲のように自分の境がふわふわしているのだとすれば、虫だろうが何だろうが自分と一体と感じているのだ、つまり、彼らは自然と一体のものなのか。大人はそれにたいして人間圏の中に自分を引き入れてしまうことによって自然とは一線を隔してしまう、こんな感じのことで頭が充満して、半分は納得していたところ、 先日小学生と大学生が一緒に杉並区のニコニコロードの商店街のグリーンマップつくりのワークショップを実施したときはっきり子どもは自然だということが正しいのではないかと思えた。それは小学生が人工的なものしか目立たない商店街の中で大人はめったに気づけない小さな自然を沢山発見していた、大勢の大人の中で四つ葉のクローバーを瞬間に発見して手にしていたのを目撃すして子ども=自然に改めて納得。
先日小学生と大学生が一緒に杉並区のニコニコロードの商店街のグリーンマップつくりのワークショップを実施したときはっきり子どもは自然だということが正しいのではないかと思えた。それは小学生が人工的なものしか目立たない商店街の中で大人はめったに気づけない小さな自然を沢山発見していた、大勢の大人の中で四つ葉のクローバーを瞬間に発見して手にしていたのを目撃すして子ども=自然に改めて納得。
さて、このことはまだまだ研究中のことで、今後も事例を見つけていきたいと考えているのですが、この文を読んで心当たりある方は是非教えてください。
子供は平気で虫(たとえばミミズ)をつかむ、大人はそれができない。こどもは平気で人の顔をさわりにくる、おとなはそれはできない。単純に知識や経験が増えるからできること、できないことを頭で理解して自分の行動を規制しているのか?それにしてはさわるのが気持ち悪いなどの感覚がどうしても納得いかない。五感の中で皮膚感覚についても食感と同様に好き嫌いが様々ではあるし、大人になって変わっていくという点でもよく似ている。しかしその変化の課程は自分の経験ではミミズを何匹も手に持って釣りなどしていたし、蜂の子やトンボなどと何も考えずに一緒に遊んだことも今ではコンポストのミミズですら初めはこわごわ触るというようなことが当たり前のことに対し、食べ物は好き嫌いがもともとなかったせいか、あまり変わってはいない。いったい何で同じヒトにこのようなことが起きるのか?
この本の解説写真の中に子供が粘土に指をつっこんだいたり、粘土にお腹をつけて腹ばいになったり、枕にして寝ていたり、お面のように顔にぴったりつけて遊んでいたりする図をみて大人は滅多にやらないナーという感想を持ちつつ文章を読むと子供は<かたまりのなかに腕や手をつっ込むなど、対象のなかに自分の体をめり込ませるのは「触覚そのもの」世界で><私たちの体は厚みと丸みと暖かさを持ち、三次元の世界のものに触れ、実感して生きています。ヒトの体は{もの}ではなく、{知覚の相対}です。自分の体と外界の境がはっきりしている大人と違って、子どもはまだ自分の体の境界がはっきりしていません、><体の発達が未分化な子どもは、身体感覚を発達させ安定させるために、あらゆる知覚刺激を求めています。>。。。。自分の体の境界がはっきり自覚できないヒト、外見上は体があっても本人の感覚では雲のように自分の境がふわふわしているのだとすれば、虫だろうが何だろうが自分と一体と感じているのだ、つまり、彼らは自然と一体のものなのか。大人はそれにたいして人間圏の中に自分を引き入れてしまうことによって自然とは一線を隔してしまう、こんな感じのことで頭が充満して、半分は納得していたところ、
 先日小学生と大学生が一緒に杉並区のニコニコロードの商店街のグリーンマップつくりのワークショップを実施したときはっきり子どもは自然だということが正しいのではないかと思えた。それは小学生が人工的なものしか目立たない商店街の中で大人はめったに気づけない小さな自然を沢山発見していた、大勢の大人の中で四つ葉のクローバーを瞬間に発見して手にしていたのを目撃すして子ども=自然に改めて納得。
先日小学生と大学生が一緒に杉並区のニコニコロードの商店街のグリーンマップつくりのワークショップを実施したときはっきり子どもは自然だということが正しいのではないかと思えた。それは小学生が人工的なものしか目立たない商店街の中で大人はめったに気づけない小さな自然を沢山発見していた、大勢の大人の中で四つ葉のクローバーを瞬間に発見して手にしていたのを目撃すして子ども=自然に改めて納得。さて、このことはまだまだ研究中のことで、今後も事例を見つけていきたいと考えているのですが、この文を読んで心当たりある方は是非教えてください。










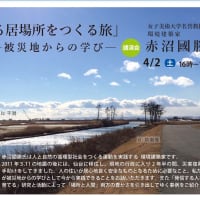

![大地震、天候異変に安心な住まいのために 5 [OZONEすまいつくりスペシャルセミナー]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/39/1d/29021acd591410d2a05f29c9cb71d375.jpg)