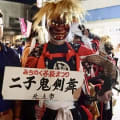清和源氏里見氏流小原氏は、常陸国茨城郡小原郷(現笠間市小原)が発祥の地です。
その小原郷は、1150年頃から里見氏初代の里見義俊の領地となり、五代目の「里見忠義」が本格的に入部し「小原姓」も名乗るようになります。
そして、この小原郷は元々「大茨又は茨」と表記されており、いつの頃からか「小原(おばら)」という郷名に変わったそうです。
実は、「安俵小原氏(狭良城流)系図」に、この里見氏流小原氏と安俵小原氏との繋がりを示唆する記述があります。
その安俵小原氏系図には、狭良城次郎(安俵五郎小原義直)の弟「小原孫次郎義兼(1276年没)」が、里見氏流小原氏の発祥郡と同じ「常陸国茨城郡の中村郷」に居住していたと書かれており(母は中村氏か)、この中村郷は、里見氏流小原氏の発祥地である小原郷とも近かったと思われ、両家は郡内の寄合などで度々会する機会があり、次第に繋がりをもつようになったと考えられます。只、現在、この小原地区周辺には、古くから小原姓を称する系譜の家が一軒も無いそうです。
このことから見えてくる史実は、和田合戦に敗れ刈田郡の領地を失い和賀郡に移った刈田氏や小原家とは違い、茨城郡にいた「小原義兼母子一党(常陸小原氏)」は、和田合戦には参戦せず中村郷の領地を安堵されます。しかしながら、南北朝期に入ると小原義兼の子孫ら(常陸小原氏)は、南北朝の争乱に巻き込まれ、当初は南朝派(宮方)に付き、戦に敗れ茨城郡の領地を失います。
そのため、1340年頃小原義兼の子孫ら(常陸小原氏)は、縁戚である和賀郡の小原家を頼り和賀郡に移住し、和賀小原家の本貫地である和賀郡東部の砂子近隣に領地を与えられます。そして、先に東和に入部していた砂子小原氏と合流又は吸収され、その後、砂子小原氏は出自を源姓里見氏流に改変し、丹内山神社相殿屋根に里見氏一門の家紋である「丸に二つ引き両紋」を寄進しています。
要するに、砂子小原氏は常陸小原氏を吸収することで、出自を源姓里見氏流に改めています。
このことから、
常陸小原氏は和賀郡に入部する前から、既に里見氏流小原氏との婚姻や養子縁組などで出自を源姓里見氏流に改変しており、また、常陸小原氏と共に里見支流小原氏の一部も和賀郡へ入部していた可能性もあります。
そして、砂子小原氏が何故出自を、源姓里見氏流に改変しなければならなかったのか、それは、一族間で相争う南北朝争乱を生き抜くため、武家方の北朝派に付く必要があったからです。
実は、里見氏は北朝派(武家方)の棟梁である「足利尊氏」と先祖が同じで、その先祖は、源頼朝・義経兄弟の先祖でもある「源八幡太郎義家」と言う清和源氏の棟梁だった人物です。
砂子小原氏は、この名門の「清和源氏里見氏流」に出自改変することで、武家方の北朝派に付き、和賀郡内での地位や発言力を獲得します。その後1352年3月に砂子小原氏の「小原四郎右衛門尉義実」が、鬼柳氏系北朝派の代官として登場してきます。そして、この鬼柳氏系北朝派が、後に和賀氏宗家に代わり和賀郡惣領職を得ることとなります。
よって、安俵小原氏は、少なくとも「砂子小原氏、常陸小原氏、秋田物部氏、狭良城小原氏」の四氏で構成されており、順序立てで見ると、「砂子小原氏が常陸小原氏・秋田物部氏を吸収し、その後、倉澤村を経由し安俵に入部して来た狭良城小原氏と安俵小原氏を形成」する流れとなります。