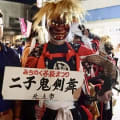肩野物部氏は、 587年7月に起きた丁未の乱(ていびのらん)に敗れ、一族の日下部氏らと共に畿内の河内国から信濃国伊那郡高遠郷に落ち延びました。その後、この地で隠棲していた肩野物部氏一族の日下部氏は、故地に因み「私市」とも名乗る様になり、その子孫らは血脈を守る為、更に東方の地である知知夫(秩父)国や武蔵国方面に移動します。知知夫国や武蔵国には物部氏の親族とも伝わる知知夫国造(ちちぶのくにのみやつこ)や武蔵国造(むさしのくにのみやつこ)らの一族がおり、私市氏らはその一族を頼り武蔵国の山間の地である成木村(現東京都青梅市成木)へ移住します。
そして、共に成木村へ移住した分家筋の中に高遠郷小原(おばら)村出身の者がおり、この一族が「小原」姓を名乗る様になります。
その後、私市氏は東国に定着して行く中で、東国の諸豪族らと友好的な関係を築く為、又、官位を得る為に、出自を物部氏から開化天皇の子孫に改変します。
実は、日下部姓を名乗った一族は物部氏流以外にも複数の系統があり、開化天皇や孝徳天皇の子孫らの中にも日下部姓を名乗る一族がいます。東国の地で血脈を守り官位を得る為には、朝敵となった物部氏の子孫を名乗るのは憚れ、天皇の末裔を装う事で東国の諸豪族らに受け入れられる様になります。
そして、後に子孫の私市家盛(11世紀前期頃の人物)は武蔵権守にまで任ぜられ、武蔵国北部の平野部である大里郡と埼玉郡北部(現埼玉県行田市、羽生市、加須市、鴻巣市、熊谷市の一部)に領地を得、その地に移住します。
その後、私市氏からは、与えられた土地名を名字とし「河原」「久下」「熊谷」「太田」などの諸氏が輩出されます。そして、武蔵権守を賜った私市家盛の六代子孫に、源頼朝に与し鎌倉幕府成立に貢献した私市党の惣領「私市有直」がいます。